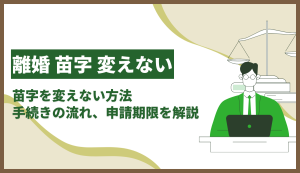シングルマザーが今すぐ申請すべき手当・給付金16選|月10万円の支援も可能
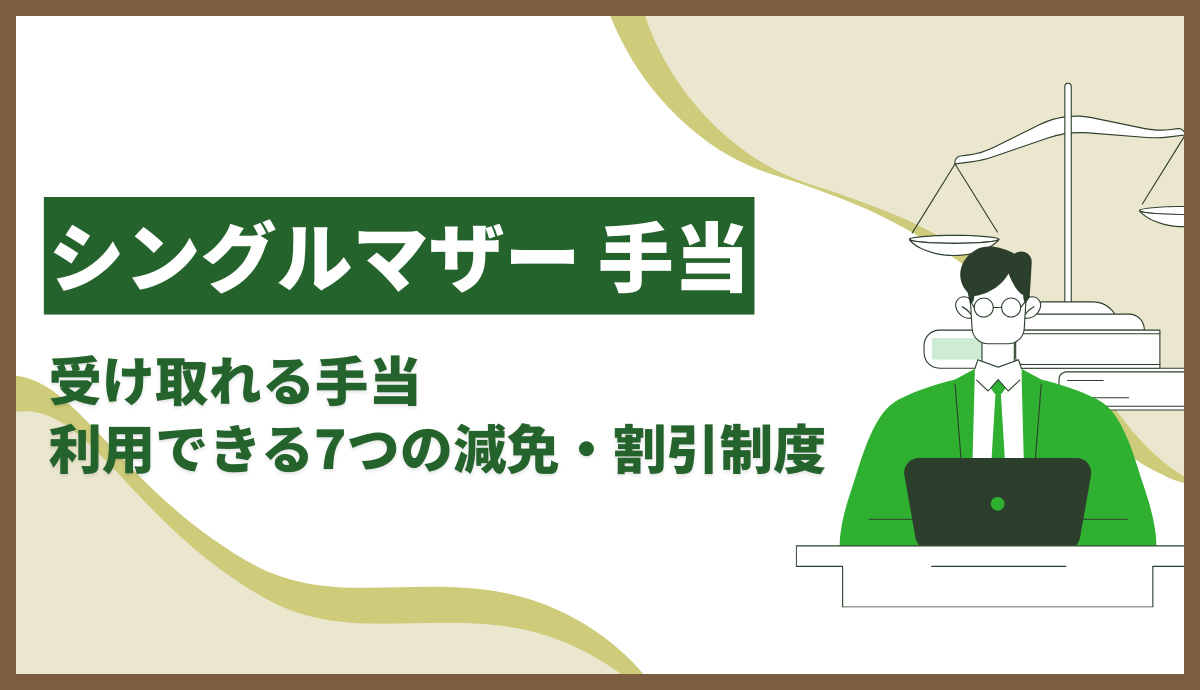
「離婚後の生活、子どもと2人でやっていけるかな…」そんな不安を抱えていませんか?
実は、日本にはシングルマザーを支える16種類以上の手当・給付金制度があり、上手に活用すれば月7〜10万円相当の支援を受けることができます。
例えば、
- 児童扶養手当(最大4.7万円)+児童手当(1万円前後)= 月5〜6万円の基本収入
- 医療費助成で病院代が1回200円程度に
- 国民年金免除で年20万円の家計負担軽減
- 就学援助で給食費・学用品費がほぼ無料
しかし知らないともらえませんし、申請しないと受け取れない。
この記事では、シングルマザーが「もらい忘れゼロ」を実現するために必要な制度を、金額・申請方法・注意点まで分かりやすく解説します。
一人で抱え込まず、利用できる制度はしっかり活用していきましょう。
手当の申請方法や必要書類についても分かりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

シングルマザーが活用できる手当・支援制度16選【年間100万円超も可】
【早見表】主な手当・減免・給付金一覧(支給額は目安)
| 制度名 | 月額/年額の目安 | 申請窓口・タイミング |
|---|---|---|
| 児童扶養手当 | 最大 43,160円/月 | 市区町村 子育て支援課・ 随時 |
| 児童手当 | 5,000〜 15,000円/月 | 市区町村 児童手当係・ 出生15日以内 |
| 児童育成手当 (自治体) | 13,500円/月 | 市区町村 福祉課・ 随時 |
| 住宅手当(自治体) | 上限 10,000〜 20,000円/月 | 市区町村 住宅支援課・ 転居後すぐ |
| ひとり親医療費助成 | 自己負担 0〜 200円/受診 | 市区町村 保険年金課・ 随時 |
| 保育料減免 | 0〜半額 | 市区町村 保育課・ 入園決定後 |
| 就学援助 | 給食費・学用品費 等 | 区市町村 教委・ 年1回 |
| 国民健康保険料 減免 | 約 30,000〜 80,000円/年 | 市区町村 国保年金課・ 随時 |
| 国民年金保険料 免除 | 196,860円/年 | 年金事務所・ 随時 |
| 上下水道料金 減額 | 約 12,000〜 24,000円/年 | 水道局・ 随時 |
| 交通定期割引 | 約3割引 | 自治体・交通事業者・ 利用前 |
| 粗大ごみ手数料 減免 | 最大 無料 | 清掃事務所・ 予約時 |
| 自立支援教育 訓練給付金 | 受講費の60% (上限20万円) | 市区町村 福祉課・ 受講前 |
| 高等職業訓練 促進給付金 | 最大 100,000円/月 | 市区町村 福祉課・ 訓練開始前〜6か月以内 |
| 寡婦控除 | 税額 最大 54,000円/年 | 確定申告・ 年末調整 |
| 資格取得支援金 (自治体) | 上限 数十万円 | 市区町村 雇用支援課・ 公募時 |
- 児童手当 – 全世帯対象、申請忘れ多数
- 児童扶養手当 – ひとり親の基本手当
- ひとり親医療費助成 – 医療費が1回200円程度に
- 就学援助 – 学用品・給食費を補助
- 国民年金保険料免除 – 年約20万円の節約効果
これら5つで年間100万円以上の支援が受けられる場合があります。
毎月もらえる「手当」
毎月もらえる「手当」から紹介。
月最大 約6万円(年約72万円)が受け取れます。
まずチェックすべき基本手当です。
児童扶養手当 (最大46,690円/月)
▶ 支給額:子1人 46,690円(一部支給は所得次第・令和7年4月改定)
- ▶ 申請窓口:市区町村 子育て支援課
- ▶ 申請期限:要件発生から5年以内
注意:所得制限を超えると支給停止。扶養親族・養育費受取額も含まれます。
別居中なら婚姻費用で生活を補填する方法もあります。
▶婚姻費用の請求ガイド
児童手当 (0〜3歳 15,000円/月)
▶ 支給額:0〜3歳15,000円/3歳〜小6 10,000円(第3子以降15,000円)/中学5,000円
- ▶ 申請窓口:市区町村 児童手当係
- ▶ 申請期限:出生・転入の翌日から15日以内
注意:所得上限(扶養2人で年収約960万円)を超えると一律5,000円。
児童育成手当 (月額 13,500円)
▶ 支給額:児童1人あたり 13,500円(東京都例)
- ▶ 申請窓口:市区町村 福祉課
- ▶ 申請期限:要件発生から5年以内
注意:東京都など一部自治体のみ実施。所得制限あり。
住宅手当 (上限 10,000〜20,000円/月)
▶ 支給額:家賃の一部(自治体ごとに上限1〜2万円)
- ▶ 申請窓口:市区町村 住宅支援課
- ▶ 申請期限:転居後すぐ(遡及不可が多い)
注意:所得・家賃上限、賃貸契約者名義など複数条件あり。
教育・医療・保育の補助
教育・医療・保育の補助によって、学費・医療費・保育料をほぼゼロ化できる可能性があります。
ひとり親医療費助成 (自己負担 0〜200円)
▶ 支給内容:保険診療の自己負担額を公費負担(多くの自治体で1回0〜200円)
- ▶ 申請窓口:市区町村 保険年金課
- ▶ 申請期限:随時(受給券交付後適用)
注意:所得制限・対象年齢は自治体差あり。
保育料減免 (0〜全額免除)
▶ 支給内容:保育料が半額〜全額免除(住民税非課税世帯など)
- ▶ 申請窓口:市区町村 保育課
- ▶ 申請期限:入園決定後速やかに
注意:同居親族の所得や兄弟在園状況で減免率が変動。
就学援助 (給食費・学用品費 等)
▶ 支給内容:給食費・学用品費・入学準備金などを一部または全額助成
- ▶ 申請窓口:区市町村 教育委員会
- ▶ 申請期限:毎年度6〜7月頃(自治体により異なる)
注意:年度ごとに申請が必要。生活保護・住民税非課税世帯が基準。
固定費を下げる減免・割引
固定費を下げる減免、割引では、年間10〜30万円の固定費削減が狙えます。
国民健康保険料 減免 (約3〜8万円/年)
▶ 節約額:年額 約3〜8万円(所得階層で変動)
- ▶ 申請窓口:市区町村 国保年金課
- ▶ 申請期限:随時
注意:前年所得が減った場合は減免対象。“申請しないと適用されない”自治体が大半。
国民年金保険料 免除 (最大196,860円/年)
▶ 節約額:全額免除で199,800円(2025年度基準)
- ▶ 申請窓口:年金事務所
- ▶ 申請期限:随時(毎年更新)
注意:免除でも将来受取額は半額納付相当。追納制度を検討。
年金分割など老後資金の備えも重要なポイントです。
▶年金分割制度とは
上下水道料金 減額 (約1.2〜2.4万円/年)
▶ 節約額:基本料金免除などで年約1.2〜2.4万円
- ▶ 申請窓口:市町村 水道局
- ▶ 申請期限:随時
注意:自治体により免除率が異なる。証明書の提出必須。
交通定期割引 (約3割引)
▶ 支援内容:通勤定期約30%割引(母子家庭福祉乗車証 等)
- ▶ 申請窓口:市区町村 福祉課/交通事業者
- ▶ 申請期限:利用開始前までに証明書取得
注意:自治体・事業者限定。医療証などの提示が必要。
粗大ごみ手数料 減免 (最大無料)
▶ 支援内容:粗大ごみ処分手数料が半額〜無料
- ▶ 申請窓口:清掃事務所
- ▶ 申請期限:収集予約時
注意:品目・回数・免除率は自治体差が大きい。
再就職を後押しする給付金
再就職を後押しする給付金では、資格取得中に月10万円+受講費6割補助など、シングルマザーのキャリアアップをサポート。
自立支援教育訓練給付金 (受講費60%補助・上限20万円)
▶ 支給額:講座受講費の60%(上限20万円)
- ▶ 申請窓口:市区町村 福祉課
- ▶ 申請期限:受講前
注意:指定講座のみ対象。雇用保険の一般教育訓練給付金との併用不可。
高等職業訓練促進給付金 (最大10万円/月)
▶ 支給額:訓練期間中月10万円(課税世帯70,500円)/最終年度+4万円、修了後5万円支給
- ▶ 申請窓口:市区町村 福祉課
- ▶ 申請期限:訓練開始前〜6か月以内
注意:看護師・保育士など資格が限定。児童扶養手当受給者か同等所得が対象。
寡婦控除 (税額最大54,000円/年)
▶ 節約額:所得税27,000円+住民税26,000円=54,000円
- ▶ 申請窓口:確定申告(自営)/年末調整(会社員)
- ▶ 申請期限:毎年 2/16〜3/15(確定申告の場合)
注意:前年合計所得金額500万円以下、扶養児童がいる等の要件あり。
資格取得支援金(自治体) (上限数十万円)
▶ 支給額:介護・IT等の指定資格取得費を上限30〜50万円補助(自治体例)
- ▶ 申請窓口:市区町村 雇用支援課
- ▶ 申請期限:募集期間内
注意:公募制。事前相談必須。自治体によっては採択枠が少ない。
母子家庭(シングルマザー)向け自立支援訓練給付金制度について
手当や助成金、減免制度に加えて、シングルマザーの経済的自立を支援するための給付金制度もあります。
特に就業による自立を目指すシングルマザーにとって、これらの制度は新たなスキルを身につけるための大きな助けとなるでしょう。
ここでは母子家庭向けの自立支援訓練給付金制度について詳しく解説します。
- 自立支援給付金の概要
- 自立支援訓練給付金の対象者
自立支援給付金の概要
自立支援給付金制度は、母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するために支給される給付金です。
この制度には「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」の2種類があります。
自立支援教育訓練給付金は、指定された教育訓練講座を受講した場合に、その受講料の一部(最大60%、上限20万円) が支給されます。
たとえば、医療事務やパソコン関連の資格、介護職員初任者研修などの講座が対象となります。
高等職業訓練促進給付金は、看護師や介護福祉士、保育士など就職に有利な資格を取得するために1年以上養成機関で修業する場合に支給される給付金です。
支給額は市町村民税非課税世帯で月額10万円、課税世帯で月額7万500円(2023年4月現在) となっています。
また、修業期間の最後の12か月については月額4万円が加算されます。
さらに、修了後に一時金も支給されるため、長期間の訓練が必要な資格取得にも挑戦しやすくなっています。
自立支援訓練給付金の対象者
自立支援訓練給付金の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
まず、20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父であることが基本条件となります。
児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準にあることも条件の一つです。
さらに、「就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる方」という条件があります。
資格取得によって収入増加や雇用の安定が見込める場合に支給されるため、事前に自治体のひとり親支援窓口で相談することが重要です。
申請前に受講が修了していると対象外となる場合があるので、講座を受講する前に必ず相談しましょう。
申請はお住まいの自治体の母子・父子自立支援窓口で行い、児童扶養手当証書や申請理由書、講座の案内等が必要です。
この制度をうまく活用して、より安定した収入を得られる職業に就くための資格取得を目指しましょう。
日本の母子家庭の現状
シングルマザーに対する支援制度について理解を深めるためには、まず日本の母子家庭の現状を知ることが大切です。
統計データから見える実態を踏まえることで、どのような支援が必要なのかが見えてきます。
ここでは厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査」などのデータをもとに、母子家庭の現状について解説します。
母子家庭数の推移
日本の母子家庭の数は近年増加傾向にあります。
厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査」によると、2016年時点での母子世帯数は約123万世帯と推計されています。
これは1998年の約95万世帯から約30%も増加した数字です。
さらに、18歳未満の子どもがいる世帯のうち、母子世帯の割合は約7.5%となっており、およそ13世帯に1世帯が母子家庭という計算になります。
離婚件数の増加や晩婚化による高齢出産の増加など、社会構造の変化に伴い母子家庭の数は今後も増える可能性があります。
このような統計からも、シングルマザーに対する社会的な支援の重要性が高まっているといえるでしょう。
母子家庭となる主な理由
母子家庭となる理由には様々なものがありますが、最も多いのは離婚です。
厚生労働省の調査によると、母子家庭となった理由として約80%が離婚を挙げています。
次いで多いのが未婚の母(約8%)、死別(約8%) となっており、離婚による母子家庭が圧倒的多数を占めています。
離婚率は1990年代から2000年代にかけて上昇傾向にあり、2002年をピークに若干減少したものの、依然として高い水準を維持しています。
離婚の増加背景には、女性の社会進出や経済的自立の可能性の高まり、家族観の変化などの社会的要因があります。
離婚後の生活設計を考える際には、養育費や各種支援制度についての知識を事前に得ておくことが重要です。

母子家庭の年齢層
母子家庭の母親の年齢層は、30代から40代が中心となっています。
厚生労働省の調査によると、母子家庭の母の平均年齢は約42歳で、30代後半から40代前半が最も多いとされています。
子どもの年齢は、小学生(6〜11歳) が最も多く、次いで中学生(12〜14歳)、高校生(15〜17歳) の順となっています。
年齢層によって直面する課題は異なり、若年層では就労経験の少なさや学歴による就職の壁、中年層では子育てと仕事の両立や再就職の難しさなどがあります。
特に40代以降のシングルマザーは就職や転職が難しくなる傾向があり、安定した雇用と収入の確保が大きな課題となっています。
年齢に応じた支援策や再就職のためのスキルアップ支援が重要と言えるでしょう。
母子家庭の平均収入
母子家庭の経済状況は一般世帯と比較して厳しい状況にあります。
厚生労働省の調査によると、母子世帯の平均年間収入は約243万円で、これは一般世帯の平均年収 (約545万円) の約45%に過ぎません。
収入の内訳は、就労収入が約181万円、養育費が約9万円、児童扶養手当等の社会保障給付が約43万円となっています。
就労状況を見ると、母子家庭の母の就業率は約81%と高いものの、非正規雇用の割合が約52%を占めており、安定した収入を得ることが困難な状況にあります。
収入が少ないにもかかわらず、子育てにかかる費用は変わらないため、多くの母子家庭が経済的な困難を抱えています。
そのため、各種手当や助成金、減免制度などを最大限に活用することが重要です。
児童扶養手当の受給者数
児童扶養手当は母子家庭の重要な経済的支援となっています。
厚生労働省の統計によると、2022年の児童扶養手当の受給者数は約97万人で、そのうち約9割が母子家庭の母となっています。
受給者数は2000年代初頭から増加傾向にありましたが、近年は微減傾向にあります。
ただし、所得制限の影響で受給できない母子家庭も一定数存在しており、実際の母子家庭の数に比べると受給者数は少なくなっています。
児童扶養手当の全部支給と一部支給の割合は約1:2となっており、多くの受給者が所得制限によって一部支給となっています。
所得の増加によって手当が減額されるという制度の仕組みが、就労意欲に影響するという指摘もあります。
養育費の支払い状況
離婚後の養育費の取り決めと支払い状況は、母子家庭の経済状況に大きく影響します。
厚生労働省の調査によると、離婚時に養育費の取り決めをしている割合は約43%にとどまっています。
さらに、養育費を現在も受け取っている母子家庭は約24%と、4世帯に1世帯程度という低い水準です。
取り決めをしているにもかかわらず養育費を受け取れていない世帯が約18%あり、養育費の支払いが途中で止まるケースも少なくありません。
養育費を受け取っている世帯の平均月額は約44,000円で、子どもの教育費や生活費の大きな助けとなっています。
養育費の確保は母子家庭の経済的自立のためにも重要であり、離婚時の公正証書による取り決めや強制執行の手続きなど、制度の利用促進が課題となっています。
離婚後に必ず確保すべき養育費について
母子家庭の経済的な安定を図る上で、養育費の確保は非常に重要です。
しかし、前述のように養育費を受け取っているシングルマザーは約24%にとどまっており、多くの母子家庭が十分な養育費を受け取れていない状況にあります。
ここでは離婚後に必ず確保すべき養育費について詳しく解説します。
養育費に含まれる費用
養育費は子どもの生活全般にかかる費用を指します。
具体的には、衣食住にかかる基本的な生活費、医療費、教育費などが含まれます。
一般的に養育費に含まれる主な費目は以下の通りです。
- 食費(給食費を含む)
- 衣類・靴などの被服費
- 医療費(保険適用外の治療費や薬代も含む)
- 学校教育費(授業料、教材費、制服代など)
- 習い事や塾などの学校外教育費
- 通学・通塾にかかる交通費
- 学校行事や修学旅行の費用
- 携帯電話代などの通信費
- 住居費の一部(子どもの居住スペースに相当する分)
養育費は子どもの年齢が上がるにつれて必要な金額も増えていくため、将来的な教育費なども考慮して取り決めることが重要です。
特に大学進学や専門学校への入学など、高等教育にかかる費用についても明確に取り決めておくとよいでしょう。
養育費とは別に、子どもが進学する際の一時金(入学金や入学準備金など) を「教育費」として別途請求できる場合もあります。
養育費の支払期間とその終了時期
養育費の支払期間は、一般的には子どもが経済的に自立するまでとされています。
具体的な終了時期については当事者間の取り決めによりますが、一般的には以下のようなケースが多いです。
- 子どもが高校を卒業するまで
- 子どもが大学を卒業するまで
- 子どもが20歳になるまで
- 子どもが就職して経済的に自立するまで
最近では大学進学率の上昇を背景に、大学卒業までを養育費の支払期間とする取り決めが増えています。
離婚時の取り決めでは、子どもの成長に伴う養育費の増額や、特定のタイミング (中学進学時や高校進学時など) での見直しについても明記しておくとよいでしょう。
養育費の支払期間や金額について明確な取り決めをしておかないと、後々トラブルの原因になりかねません。
離婚協議書や公正証書などの書面で詳細に取り決めておくことが重要です。
また、養育費の支払いを確実にするために、給与差押え等の強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成しておくことも効果的です。

養育費の平均額
養育費の金額は、支払う側の収入や子どもの年齢、人数などによって大きく異なります。
裁判所が公表している「養育費算定表」によると、収入や子どもの年齢に応じた標準的な養育費の目安が示されています。
例えば、子ども1人(0〜14歳)、父親の年収400万円、母親の年収200万円の場合、月額約4〜5万円が養育費の目安となります。
実際に養育費を受け取っている母子家庭の平均月額は約44,000円ですが、取り決め金額には大きな幅があり、月額1万円程度から10万円以上まで様々なケースがあります。
養育費の金額を決める際は、子どもの年齢や教育環境、特別な事情(障害や持病など)も考慮し、子どもの成長に応じた適切な金額を設定することが大切です。
養育費の取り決めや増額請求については、弁護士や法テラス、各自治体の母子家庭支援窓口などに相談するとよいでしょう。
2021年度からは養育費の不払いに対する「養育費立替払い制度」を導入する自治体も増えており、公的支援の利用も検討する価値があります。
養育費の確保は母子家庭の経済的自立のためにも重要であり、離婚時の公正証書による取り決めや強制執行の手続きなど、制度の利用促進が課題となっています。
養育費の適正額の算定や確実な支払い確保には、法的な専門知識が必要です。
離婚問題に詳しい弁護士なら、あなたの状況に応じた最適な解決策を提案できます。

よくある質問
シングルマザーの手当についてよくある質問をまとめました。
気になる疑問がある方はぜひ参考にしてください。
- シングルマザーが受け取れる手当の総額はいくらですか?
- 子供2人のシングルマザーが受け取れる手当の金額を教えてください。
- シングルマザーの手当には所得制限がありますか?
- 母子家庭の手当一覧を教えてください。
- シングルマザーが手当をもらいすぎると減額されますか?
- 母子家庭に30万円の給付金はありますか?
- シングルマザーに彼氏ができたら手当はどうなりますか?
- シングルマザーが親と同居している場合の手当について教えてください。
- シングルマザーの手当を受け取るための条件は何ですか?
- 会社に勤めながらもらえる母子家庭の支援はありますか?
シングルマザーの手当制度について理解できても、「離婚時の条件設定」や「養育費の確保」で将来の生活が大きく変わります。
特に養育費の取り決めや財産分与、慰謝料などは専門知識が必要な分野です。
離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、より良い条件での離婚成立と、安定したシングルマザー生活を実現できます。
まとめ
この記事では母子家庭 (シングルマザー) が受け取れる手当や助成金、減免制度について詳しく解説しました。
シングルマザーになると経済的な不安を抱えがちですが、様々な支援制度が用意されているので、積極的に活用することが大切です。
児童手当や児童扶養手当といった基本的な手当に加え、住宅手当や医療費助成、各種減免制度など、複数の支援を組み合わせることで家計の負担を軽減できます。
また、将来的な経済的自立のためには、養育費の確保や自立支援訓練給付金などを利用したスキルアップも重要なポイントです。
各制度には所得制限や申請期限があるため、お住まいの自治体の窓口で自分のケースに合った支援について相談することをおすすめします。
一人で子育てと仕事を両立することは決して簡単ではありませんが、利用できる制度をしっかり活用して、少しでも余裕のある生活を目指しましょう。