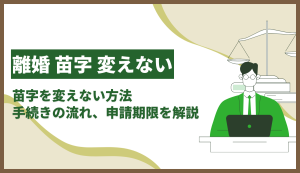離婚したいけどお金がない!経済的に厳しい状況での対策ガイド
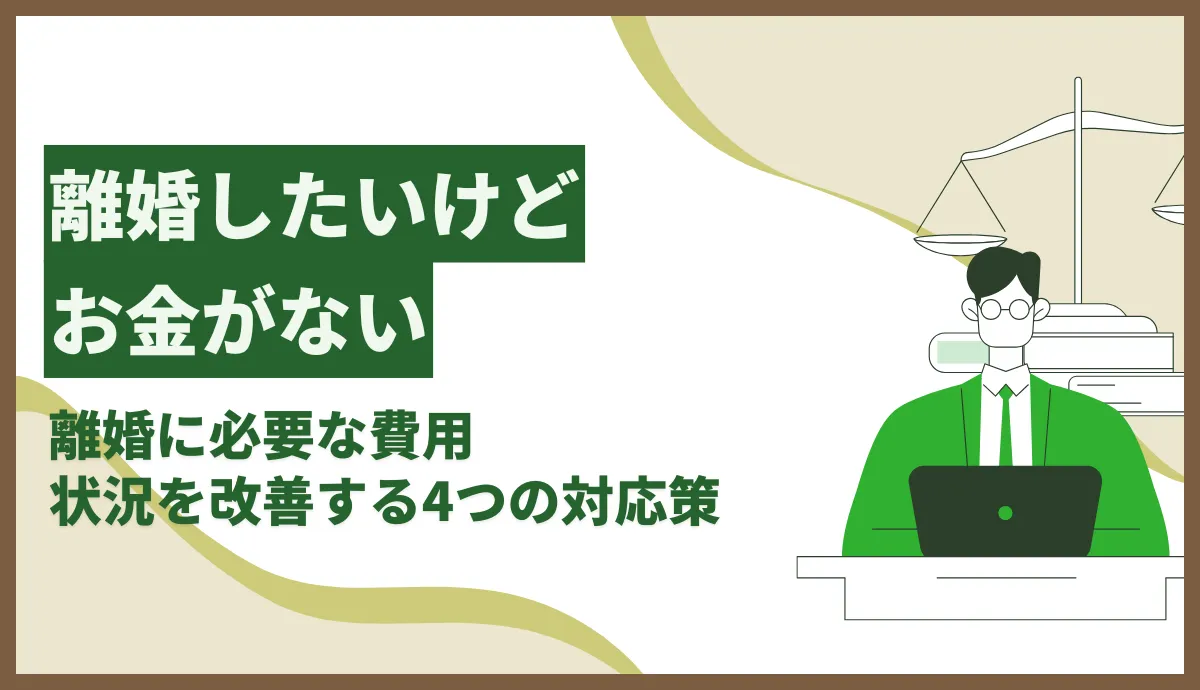
離婚したいのにお金がなくて悩んでいませんか?
経済的な不安から離婚に踏み切れない方は多く、特に専業主婦や収入が少ない方にとって大きな壁となっています。
離婚には別居費用や手続き費用、場合によっては弁護士費用も必要になるため、資金面での準備は欠かせません。
しかし、お金がないからといって離婚を諦める必要はありません。
当記事では、お金がなくても離婚する方法や、離婚に必要な費用、経済的に苦しい状況での具体的な対策を詳しく解説していきます。
どんな状況でも自分らしい選択ができるよう、一つひとつの選択肢をわかりやすく解説していきます。
離婚にかかる費用
離婚を考える際に気になるのが、実際にかかる費用です。
お金がないと離婚できないと思い込んでいる方も多いですが、必要な費用を把握することで対策を立てることができます。
離婚費用は大きく分けて「別居する際の費用」「離婚手続きの費用」「弁護士に依頼する費用」の3つに分類できます。
それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

別居する際の費用
離婚を考える多くの方は、まず別居から始めることが一般的です。
別居するためには、新しい住まいを確保する必要があり、これが最も大きな出費となります。
賃貸物件を借りる場合、初期費用として敷金・礼金・仲介手数料などで家賃の4〜6ヶ月分程度の費用がかかることを覚えておきましょう。
別居時には家賃だけでなく、生活必需品の購入費も考慮する必要があります。
食器や家具、家電などの生活用品を一式揃えるとなると、最低でも10万円程度は見積もっておくとよいでしょう。
また、別居中は二重生活となるため、光熱費や食費などの生活費も二人分必要になります。
| 費用項目 | 概算金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 敷金・礼金等 | 15〜30万円 | 家賃の4〜6ヶ月分 |
| 引越し費用 | 5〜10万円 | 距離や荷物量による |
| 生活必需品 | 10〜20万円 | 家具・家電・日用品など |
| 月々の生活費 | 10〜15万円/月 | 家賃・光熱費・食費など |
収入が少ない場合は、友人宅や実家に一時的に身を寄せる選択肢もあります。
緊急時には女性相談所や母子生活支援施設などの公的支援も検討できます。
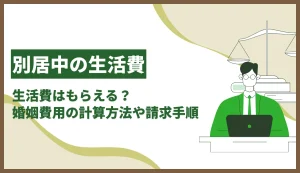
離婚手続きの費用
離婚手続き自体にかかる費用は、離婚の種類によって大きく異なります。
お互いが合意している協議離婚であれば、手続きにかかる費用はほとんどありません。
離婚届は無料で入手でき、提出も無料です。
ただし、戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得するための手数料が数百円から数千円程度必要になります。
調停離婚や裁判離婚になると、申立手数料や印紙代などで数千円から数万円の費用が発生します。
裁判所に提出する書類の作成や証拠集めなどにも費用がかかる場合があります。
| 離婚方法 | 手続き費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 協議離婚 | 数百円〜数千円 | 書類取得費用のみ |
| 調停離婚 | 1,200円程度 | 申立手数料 |
| 審判離婚 | 数千円 | 印紙代など |
| 裁判離婚 | 1〜5万円程度 | 訴状の印紙代など |
経済的に余裕がない場合、裁判所の手続きでは「民事法律扶助制度」を利用できることも覚えておきましょう。
この制度を利用すると、手続き費用の立替えを受けられる場合があります。

弁護士に依頼する費用
離婚問題が複雑な場合や争いがある場合は、弁護士に相談することも検討すべきです。
弁護士費用は一般的に「着手金」と「成功報酬」の2つから構成されます。
着手金は依頼時に支払う費用で、20〜30万円程度が相場です。
成功報酬は、財産分与や慰謝料などの獲得額に応じて発生し、獲得額の10〜20%程度が一般的です。
弁護士に依頼すると費用は高額になりますが、適切な解決につながり結果的に得られる経済的メリットが大きい場合もあります。
特に財産分与や養育費、慰謝料などの金銭的問題で争いがある場合は弁護士のサポートが有効です。
| 費用項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 初回相談料 | 無料〜5,000円 | 無料相談を実施している事務所も多い |
| 着手金 | 20〜30万円 | 事案の複雑さにより変動 |
| 成功報酬 | 獲得額の10〜20% | 財産分与・慰謝料等の獲得に応じて |
経済的に厳しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用すると、弁護士費用の立替えを受けられる場合があります。
また、自治体や弁護士会が実施している無料法律相談も活用すると良いでしょう。
多くの場合、初回相談は無料または低額で利用できるため、まずは相談してみることをおすすめします。

資金不足の場合、貯金をしてから離婚すべきか?
離婚したいけどお金がない場合、多くの方が「貯金をしてから離婚すべきか」と悩みます。
この選択には明確な正解はなく、それぞれの状況によって判断が分かれる部分です。
ここでは、お金が貯まるまで待つメリットとデメリットについて検討してみましょう。
- お金が貯まるまで待つメリット
- お金が貯まるまで待つデメリット
お金が貯まるまで待つメリット
まず、離婚後の生活に備えて資金を確保することには大きなメリットがあります。
十分な資金があれば、離婚後の住居や生活費の心配が少なくなり、精神的な安定につながります。
特に子どもがいる場合は、安定した環境を整えるために一定の貯蓄があると安心できます。
また、弁護士に依頼する資金を確保できれば、より有利な条件で離婚交渉を進められる可能性も高まります。
貯蓄期間中に冷静に将来の計画を立てることができるのも大きな利点です。
離婚後の収入源や住居、子どもの教育費など、具体的な生活設計を考える時間が持てます。
| 待つことのメリット | 内容 |
|---|---|
| 経済的安定 | 離婚後の生活資金や緊急時の備えができる |
| 住居の確保 | 敷金・礼金など新居の初期費用を用意できる |
| 交渉力の向上 | 弁護士費用を確保でき、有利な条件を引き出せる |
| 計画的な準備 | 冷静に将来の生活設計を考えられる |
資金準備のために待つ期間は、同時に心の準備期間にもなります。
貯金額の目安としては、最低でも半年分の生活費(家賃・食費・光熱費など)と別居・引越しの初期費用を合わせた金額が望ましいでしょう。
お金が貯まるまで待つデメリット
一方で、お金が貯まるまで離婚を待つことにはデメリットもあります。
特に深刻なのは、精神的・身体的な負担が長引くことです。
DV(ドメスティックバイオレンス)や著しい精神的苦痛がある場合、貯金のために我慢することで健康を害するリスクがあります。
安全や健康が脅かされている状況では、お金よりも先にまず身を守ることを優先すべきです。
また、貯金しようとしても実際には難しいケースも少なくありません。
家計管理を配偶者が握っていると自由に使えるお金が限られ、貯金が進まないこともあります。
長期間の準備期間中に配偶者に気づかれて対立が激化したり、資産を隠されたりするリスクも考慮する必要があります。
さらに、時間の経過とともに法的な不利益が生じる可能性もあります。
例えば、不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、発覚から長期間経過すると「許した」とみなされるリスクがあります。
| 待つことのデメリット | 内容 |
|---|---|
| 精神的・身体的負担 | 不満や苦痛が長引き、健康を害するリスク |
| 貯金の難しさ | 家計が自由にならず、実際に貯金できない |
| 配偶者との対立激化 | 準備がバレて状況が悪化するリスク |
| 法的な不利益 | 時間経過により証拠が薄れる、時効の問題 |
「お金が貯まったら離婚しよう」と考えていても、実際には離婚に踏み切れずに状況が長期化する可能性もあります。
人生の貴重な時間を不満足な結婚生活に費やすことの機会損失も考慮すべき点です。
結局のところ、「貯金してから離婚すべきか」の判断は、DV等の危険性、精神的苦痛の度合い、経済状況、子どもの有無など総合的に考えて決める必要があります。
次のセクションでは、お金がなくても離婚を進めるための具体的な対策について見ていきましょう。
経済的に厳しい状況で離婚を考える際の4つの対策
お金がないからといって離婚を諦める必要はありません。
経済的に厳しい状況でも離婚を進めるための現実的な対策があります。
ここでは、資金面で苦しい状況でも離婚を実現するための4つの具体的な方法を紹介します。
それぞれの対策について詳しく解説していきます。
婚姻費用の分担を請求する
別居中でも法律上はまだ夫婦関係が続いています。
この期間中、経済力のある配偶者には「婚姻費用」を負担する義務があります。
婚姻費用とは、夫婦とその子どもの生活に必要な費用のことで、食費・住居費・光熱費などの基本的な生活費が含まれます。
別居中の婚姻費用は、収入の差に応じて算定され、裁判所の基準表を参考に決められます。
例えば、子どもがいない場合で、夫の年収が500万円、妻に収入がない場合、月に約10〜12万円程度の支払いが一般的です。
婚姻費用の分担を請求するには、まずは配偶者と話し合いを試みる方法があります。
話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。
調停でも合意に至らない場合は、審判に移行して裁判所が金額を決定します。
婚姻費用の支払いは離婚が成立するまで続くため、離婚準備中の生活を支える大きな助けになります。
| 婚姻費用請求の手順 | ポイント |
|---|---|
| ① 配偶者との話し合い | まずは直接または手紙で金額を提示して交渉 |
| ② 調停の申立て | 話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に申立て |
| ③ 審判への移行 | 調停が不成立なら審判で裁判所が決定 |
| ④ 強制執行 | 支払われない場合は給与差押えなどの手続き |
婚姻費用は支払われるべき権利なので、遠慮せずに請求することが大切です。
離婚時に支払われる金銭を有効に使う
離婚時には、場合によって様々な金銭の支払いを受けられる可能性があります。
これらを適切に請求し、離婚後の生活資金として活用することが重要です。
主な金銭的請求権には、「財産分与」「慰謝料」「養育費」「年金分割」の4つがあります。
財産分与
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築いた財産を分ける制度です。
一般的には夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けることが基本となります。
財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦で協力して形成した財産(住宅、貯金、株式など)です。
結婚前から持っていた財産や相続で得た財産は原則として対象外となります。
ただし、専業主婦であっても家事や育児で貢献したとみなされ、財産分与を受ける権利があります。
財産分与を確実に受けるためには、まず夫婦の財産を把握することが重要です。
通帳のコピーや不動産登記簿などの資料を集めておくとよいでしょう。

慰謝料
相手に離婚の原因がある場合、精神的苦痛に対する賠償として慰謝料を請求できます。
不貞行為(浮気・不倫)、DVや暴言、生活費を渡さないなどが主な請求理由となります。
慰謝料の金額は事案によって異なりますが、不貞行為の場合で100〜300万円が一般的な相場です。
慰謝料を請求するには証拠が重要なので、メールやLINEのやり取り、診断書などを保存しておくことが大切です。
ただし、慰謝料はすべての離婚ケースで認められるわけではなく、相手に責任がない場合は請求できません。

養育費
子どもを引き取る場合、もう一方の親に養育費を請求する権利があります。
養育費は子どもが成人するまで(通常は20歳、大学進学の場合は卒業まで)支払われるのが一般的です。
養育費の金額は、双方の収入や子どもの年齢・人数などを考慮して裁判所の算定表を参考に決められます。
例えば、子ども1人の場合で父親の年収が500万円なら、月に約5〜6万円程度が目安になります。
養育費は公正証書にするなど、法的に強制力のある形で取り決めておくことが重要です。
払われない場合には、給与差押えなどの強制執行の手続きが可能になります。

年金分割
結婚期間中の厚生年金の支給額を、離婚後に分割して受け取れる制度です。
専業主婦や収入が少なかった配偶者にとって、将来の年金を確保する重要な権利となります。
年金分割は原則として結婚期間中の厚生年金保険料納付記録の2分の1を上限に分割可能です。
手続きは離婚から2年以内に行う必要があり、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求するところから始めます。
国民年金のみの期間は分割の対象にならないことに注意が必要です。
| 離婚時の金銭請求 | 概要 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 財産分与 | 夫婦の共有財産を分ける | 共有財産の1/2が基本 |
| 慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償 | 100〜300万円 |
| 養育費 | 子どもの成長に必要な費用 | 子ども1人で月5〜6万円 |
| 年金分割 | 結婚期間中の厚生年金の分割 | 納付記録の1/2まで |
これらの権利をしっかり理解し、適切に請求することで、離婚後の経済的な基盤を作ることができます。

自治体の公的支援を利用する
経済的に厳しい状況での離婚では、各種公的支援制度を活用することも重要な選択肢です。
特にひとり親家庭向けの支援制度は充実しており、積極的に利用すべきでしょう。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の子どもの養育費を補助する制度で、子ども1人の場合、月額約4万3千円〜1万180円(所得に応じて変動)が支給されます。
児童扶養手当は所得制限があり、収入が多いと減額または支給停止となるので注意が必要です。
ひとり親家庭医療費助成制度は、医療費の自己負担分を軽減する制度で、自治体によって内容が異なります。
多くの自治体では、親と子どもの医療費が助成対象になります。
住宅面では、ひとり親家庭は公営住宅の優先入居の対象になる場合が多く、家賃補助制度を設けている自治体もあります。
また、母子生活支援施設は、母子家庭の母と子どもが一緒に生活しながら自立を目指す施設で、緊急時の避難先としても利用できます。
| 公的支援の種類 | 支援内容 | 申請先 |
|---|---|---|
| 児童扶養手当 | 月額4.3万円〜1万円程度の手当 | 市区町村役場 |
| ひとり親医療費助成 | 医療費の自己負担分の軽減 | 市区町村役場 |
| 公営住宅優先入居 | ひとり親家庭の入居優遇 | 各自治体の住宅課 |
| 母子生活支援施設 | 住居と自立支援の提供 | 福祉事務所 |
| 生活保護 | 最低限の生活保障 | 福祉事務所 |
その他にも、就学援助制度(子どもの学用品費などの補助)や高等職業訓練促進給付金(ひとり親の資格取得を支援)など、様々な支援制度があります。
これらの制度は各自治体によって内容や条件が異なるので、お住まいの市区町村役場に相談することをおすすめします。
また、ひとり親家庭支援センターや母子・父子自立支援員に相談すると、適切な支援制度を紹介してもらえます。
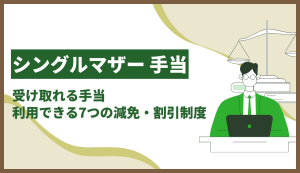
専業主婦が就職して収入を得る
離婚を考える専業主婦にとって、自分で収入を得ることは経済的自立への大きな一歩です。
長期間働いていない場合でも、様々な就職支援や職業訓練制度を活用することで再就職は可能です。
ハローワークは無料の職業紹介や職業訓練、就職支援セミナーなどを提供しており、特にひとり親向けの優先的な支援もあります。
母子家庭等就業・自立支援センターでは、ひとり親向けの就業相談や就職情報の提供、職業訓練などを行っています。
高等職業訓練促進給付金制度は、看護師や介護福祉士などの資格取得のために養成機関で修業する場合、生活費の一部を補助してくれる制度です。
子どもがいる場合は、保育所の利用も検討しましょう。
ひとり親家庭は保育所入所の優先対象になることが多く、保育料も減免される場合があります。
短期間で取得できる資格としては、医療事務、介護職員初任者研修、調剤薬局事務などがあり、比較的就職先も見つけやすいでしょう。
| 就職支援 | 内容 |
|---|---|
| ハローワーク | 無料職業紹介、職業訓練、就職セミナー |
| 母子家庭等就業支援センター | ひとり親向け就業相談・情報提供 |
| 高等職業訓練促進給付金 | 資格取得中の生活費補助 |
| 自立支援教育訓練給付金 | 職業訓練講座の受講料の一部支給 |
正社員だけでなく、パートやアルバイトから始めて徐々にスキルアップしていくことも検討してみましょう。
在宅ワークやフリーランスの仕事も、子育てと両立しやすい働き方として注目されています。
再就職に不安がある場合は、離婚前から少しずつ準備を始めることをおすすめします。
短期バイトやボランティアなどから始めて、社会との接点を増やしていくことが自信につながります。
どのような状況でも、経済的に自立するための道は必ずあります。
公的支援を上手に活用しながら、自分のペースで就職活動を進めていきましょう。
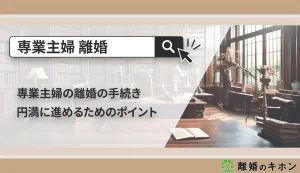
よくある質問
ここでは、離婚したいけどお金がない方からよく寄せられる質問に簡潔にお答えします。
具体的な状況によって対応策は異なりますが、参考にしていただければ幸いです。
- 離婚したいけどお金がない専業主婦はどうすればいいですか?
- 離婚後の住むところがないときはどうすればいいですか?
- 子供がいる場合の離婚にかかる費用について教えてください。
- 50代で離婚したいけどお金がない場合の対処法を教えてください。
- 男性が離婚したいけどお金がない場合はどうすればいいですか?
- 弁護士に相談する費用がない場合はどうすればいいですか?
- 離婚問題の法的支援を受ける方法について教えてください。
まとめ
「離婚したいけどお金がない」という悩みは、多くの方が直面する深刻な問題です。
しかし、この記事で紹介したように、経済的に厳しい状況でも離婚を実現するための方法はいくつもあります。
婚姻費用の分担請求や財産分与・養育費の確保、公的支援の活用、そして就職による経済的自立など、様々な対策を組み合わせることで道は開けるでしょう。
貯金がなくても、安全や健康が脅かされている状況では早めに行動することが重要です。
法テラスや自治体の無料相談窓口、各種支援センターなど、専門家に相談できる場所も多くあります。
まずは一人で抱え込まず、信頼できる人や専門家に相談することから始めてみてください。
お金の問題は確かに大きな壁ですが、適切な情報と支援を得ることで、新しい人生をスタートさせることは可能です。
あなたらしい選択ができることを願っています。