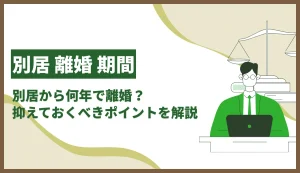離婚を決意する瞬間とは?決断する前に考えておくべき重要事項

「もう限界、離婚したい…」と思っていても、実際に離婚を決意するのは簡単ではありません。
多くの方が「このまま我慢すべきか」「本当に離婚して大丈夫なのか」と迷い続けています。
特に子どもがいる場合や経済的な不安がある場合は、離婚の決意がさらに難しくなるでしょう。
この記事では、多くの夫婦が離婚を決意する瞬間や理由、そして離婚を決意した後に後悔しないためのポイントについて解説していきます。
離婚を考えている方が抱える不安や疑問に丁寧にお答えします。
離婚の決意から実行までの流れを知ることで、より冷静な判断ができるようになりますよ。
夫婦が離婚を決意する主な瞬間と理由
離婚を決意するのは、多くの場合、長い期間の不満や悩みが積み重なった末の決断です。
しかし、その決意を最終的に固める「決定的な瞬間」が存在することが少なくありません。
この章では、多くの夫婦が離婚を決意する主な瞬間と理由について詳しく見ていきましょう。
自分が置かれている状況と照らし合わせながら読んでみてください。
女性(男性)が離婚を決意する瞬間はどのようなとき?
離婚を考え始めるきっかけは人それぞれですが、実際に「もう無理だ」と決意する瞬間には共通点があります。
女性が離婚を決意する場合は、子どもや経済面など様々な要素を考慮した上で、最終的な決断に至ることが多いようです。
統計的に見ると、離婚を申し立てるのは女性が約70%と圧倒的に多く、多くの場合は我慢の限界を超えた時に決意が固まります。
一方で男性の場合は、自尊心が傷つけられたときや、パートナーへの信頼が大きく損なわれたときに離婚を決意するケースが多いでしょう。
どちらにしても、離婚の決意は単なる一時的な感情ではなく、冷静な判断のもとで行われるべき重要な決断です。
以下では、具体的にどのような出来事をきっかけに多くの人が離婚を決意するのかを見ていきましょう。
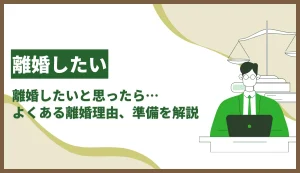
1. 暴力やモラハラを受けたとき
身体的・精神的な暴力は、離婚を決意する最も深刻な理由の一つです。
特に女性の場合、配偶者からの暴力やモラルハラスメントが離婚を決意する大きなきっかけとなっています。
このような状況では、自分や子どもの安全を最優先に考えることが何よりも大切です。

暴力が原因で離婚を決意した事例
Aさん(35歳女性)は、夫の些細な暴力が徐々にエスカレートしたことで離婚を決意しました。
初めは物に当たるだけでしたが、やがて彼女自身に手が出るようになり、子どもの前でも暴力を振るうようになったのです。
「子どもが夫の真似をして、友達に手を出すようになった」という変化を見て、Aさんは子どものためにも離婚するべきだと決断しました。
DVの場合、一時的な謝罪と再発の繰り返しになることが多く、改善を期待して我慢を続けることは危険です。
命の危険を感じる場合は、すぐに警察や配偶者暴力相談支援センターに相談しましょう。

モラハラが原因で離婚を決意した事例
Bさん(40歳女性)は、夫から「何をやってもダメだ」「家事ができていない」などと日常的に否定され続けていました。
徐々に自信を失い、うつ状態に陥りましたが、心療内科の医師から「これはモラルハラスメントです」と指摘されたことで現状を認識。
カウンセリングを受ける中で自分を大切にする気持ちを取り戻し、子どもの将来のためにも離婚を決意しました。
モラハラは目に見える傷が残らないため、周囲に理解されにくい面がありますが、精神的ダメージは深刻です。
自分を責めずに専門家に相談することが重要です。

過度な監視行為も離婚の原因になる
GPSでの位置確認や、スマートフォンのチェック、SNSの監視なども精神的暴力の一種です。
Cさん(28歳女性)は夫から常に行動を監視され、友人との外出も制限されていました。
「帰宅が5分遅れただけで厳しく問い詰められ、スマホの位置情報を常にオンにするよう強要された」というCさん。
このような支配的な関係は次第に悪化する傾向があり、早い段階での対応が必要です。
過度な監視行為は、現代型のDVとして認識されるようになっており、離婚の正当な理由となります。

2. 子どもに悪影響が出始めたとき
多くの夫婦が「子どものため」と言って不幸な結婚生活を続けていますが、子どもの変化をきっかけに離婚を決意するケースも少なくありません。
子どもの健全な成長と幸せを最優先に考えた結果、離婚という選択肢を選ぶことも、親としての責任ある判断といえるでしょう。
子どもの変化をきっかけに離婚を決意した事例
Dさん(42歳女性)は、夫との口論が絶えない家庭環境の中で、小学生の息子が不登校になったことをきっかけに離婚を決意しました。
「息子が学校に行きたくないと言い出した理由を聞いたら、『家に帰るのが怖いから』と答えたんです」と振り返ります。
カウンセラーからも「両親の不仲が子どもに影響している可能性が高い」と言われ、子どものためには別々に暮らす方が良いと判断したのです。
離婚後、息子は徐々に学校に通えるようになり、笑顔も増えたと言います。
家庭環境のストレスで子どもに影響が出ることも
子どもは敏感に家庭の雰囲気を感じ取ります。
以下のような変化が見られる場合は、家庭環境が子どもに悪影響を及ぼしている可能性があります。
- 夜泣きや悪夢が増える
- 急に成績が下がる
- 引きこもりがちになる
- 攻撃的な言動が増える
- 身体的な症状(腹痛、頭痛など)を訴える
- 食欲の急激な減少や増加
「子どものために我慢する」という選択が、実は子どもを苦しめていることもあります。
子どもの様子に変化を感じたら、小児科医やスクールカウンセラーなど専門家に相談することをおすすめします。

3. 配偶者の金銭問題が発覚したとき
お金に関する問題は、離婚の主要な原因の一つです。
特に隠されていた借金が発覚したり、ギャンブルなどの浪費癖が明らかになったりした場合、将来の経済的不安から離婚を決意するケースは少なくありません。
隠れた借金が発覚して離婚を決意した事例
Eさん(38歳女性)は、夫名義のクレジットカードの請求書が届いたことで、夫の多額の借金を知りました。
「カードの明細を見て驚きました。消費者金融からの借り入れが300万円以上あったんです」とEさん。
話し合いを求めると、夫は過去にも何度か借金を作っては親に返済してもらっていたことが判明。
借金は結婚後に作られたものであれば、離婚時に妻にも返済義務が生じる可能性があるため、早急な対応が必要でした。
弁護士に相談した結果、裁判所で夫の浪費を認めてもらえれば、妻に支払い義務はないとのアドバイスを受け、離婚を決意しました。
夫の収入喪失も離婚につながりやすい
Fさん(45歳女性)のケースでは、夫が会社をリストラされた後に再就職の努力をしなかったことが問題になりました。
「最初は『すぐに次の仕事が見つかる』と言っていましたが、半年たっても面接にさえ行かず、貯金を切り崩して生活するようになりました」とFさん。
家計のことを話し合おうとすると怒り出す夫に対し、将来への不安が膨らみ、子どもの教育費も考慮して離婚を決断しました。
収入の問題は単なる経済的な問題だけでなく、将来への責任感や家族への思いやりにも関わる問題です。
金銭問題で離婚を検討する場合は、現在の状況だけでなく将来のリスクも含めて弁護士に相談することをおすすめします。
4. 相手の実家との関係性に問題があるとき
結婚は二人だけの問題ではなく、相手の家族との関係も重要な要素です。
特に義両親との関係が悪化したり、配偶者が実家の問題を優先したりする場合は、夫婦関係よりも親子関係が優先される状況に耐えられず離婚を決意する人も少なくありません。
義両親からの暴言で離婚を決意した事例
Gさん(30歳女性)は、同居する義両親から家事や育児について日常的に批判を受けていました。
「子どもの前で『母親失格だ』と言われ続け、夫も私をかばうどころか『親の言うことを聞け』と責めるばかりでした」と振り返ります。
心療内科でうつ病と診断されても、夫や義両親の態度は変わらず、精神的に追い詰められて離婚を決意しました。
離婚後は実家の支援を受けながら子育てと仕事の両立に励み、徐々に心の健康も回復してきたと言います。
義両親に子どもを連れ去られた事例
Hさん(32歳女性)のケースでは、義両親が「孫の教育のため」と言って子どもを連れ去るという事態が発生しました。
「仕事から帰ると、息子が義両親に連れていかれていて、夫も『親の判断だから』と取り合ってくれませんでした」とHさん。
一時的に子どもと離れ離れになったことで、このまま夫と一緒にいては子どもの親権も危うくなると判断し、離婚を決意しました。
弁護士を通じて調停を行い、最終的に親権と監護権を獲得することができたそうです。
夫のマザコンが原因で離婚を考えた事例
Iさん(36歳女性)は、夫があらゆる決断を母親に相談し、妻の意見よりも母親の意見を優先する状況に悩んでいました。
「家の購入から子どもの名前まで、すべて義母の意見が通り、私の意見は聞き入れてもらえませんでした」とIさん。
カウンセリングを受けるよう夫に提案しても拒否され、「母親と妻のどちらが大切か」と問うと「もちろん母親だ」と即答されたことで離婚を決意しました。
義両親との関係で悩んでいる場合は、まず配偶者と話し合い、それでも改善しない場合は夫婦カウンセリングなどの専門的なサポートを検討しましょう。
5. 配偶者の不倫など信頼を損なう行為があった
信頼関係は夫婦の基盤です。
配偶者の不倫が発覚したり、嘘や裏切りが明らかになったりした場合、一度失われた信頼を回復することは非常に難しく、離婚を決意する大きな要因となります。
夫の不倫が原因で離婚を決意した事例
Jさん(39歳女性)は、夫のスマートフォンに届いたメッセージをたまたま見てしまい、3年以上続いていた不倫関係を知りました。
「最初は一時的な過ちなら許そうと思いましたが、相手の女性には『離婚して一緒になる』と約束していたことを知りました」とJさん。
さらに、家計から相当額のお金が相手の女性に流れていたことも判明し、経済的な裏切りも含めて許せないと感じ、離婚を決断しました。
不倫相手との関係を断ち切る意思がなかったり、反省の姿勢が見られなかったりする場合は、離婚を検討する理由として十分です。
配偶者が自分の味方ではないと感じたとき
Kさん(41歳女性)は、自分が体調を崩して入院した際の夫の態度に深く傷つきました。
「手術が必要だと言われたとき、夫は『仕事が忙しい』という理由で病院に来ず、手術の同意書にさえサインしに来てくれませんでした」とKさん。
最も支えが必要な時に見捨てられたという思いから、「この人は本当に自分の味方ではない」と悟り、回復後に離婚を申し出ました。
困難な状況で配偶者がどう行動するかは、その人の本質を表します。
自分が窮地に立たされた時に助けてくれない相手とは、将来も安心して生活していくことは難しいでしょう。
将来を共に歩めないと感じたとき
Lさん(34歳女性)は、夫との価値観の違いが徐々に大きくなり、将来のビジョンが全く合わなくなったことで離婚を決意しました。
「私は子どもを持ちたかったのに、結婚当初は『いずれは』と言っていた夫が、徐々に子どもを持つ気がないことが明らかになりました」とLさん。
何度も話し合いを重ねましたが、夫の考えは変わらず、残りの人生を子どものいない家庭で過ごすことに納得できず、離婚を選択しました。
子どもの有無、住む場所、仕事のスタイルなど、将来の重要な選択肢について合意できない場合は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
6. 別の人に好意を持ったとき
結婚生活に満足していない状態が続くと、他の人に心惹かれるケースもあります。
配偶者以外の人に好意を持つことが、自分の結婚生活の問題点を浮き彫りにし、離婚を決意するきっかけになることもあるでしょう。
配偶者以外の人に好意を持つリスク
Mさん(37歳女性)は、仕事の同僚に心惹かれ、自分の気持ちに気づいたことで離婚を考え始めました。
「その人と話すと自分の意見を尊重してもらえ、夫との関係ではずっと感じていた『居心地の悪さ』が浮き彫りになりました」とMさん。
不倫関係になることは避け、まずは自分の気持ちと向き合うためにカウンセリングを受けることにしました。
その結果、夫婦間のコミュニケーション不足が根本的な問題だと気づき、夫婦カウンセリングを経て関係の修復を試みる決断をしたそうです。
他の人に好意を持ったからといって、すぐに離婚を決断するのではなく、まずは自分自身の気持ちと夫婦関係を見つめ直すことが重要です。
感情だけで離婚を決断すると、後悔する可能性が高いため、専門家のサポートを受けながら冷静に判断することをおすすめします。
以上のように、離婚を決意する瞬間は人それぞれですが、多くの場合は自分や子どもの幸せ、安全、将来を考えた末の決断です。
目の前の問題から逃げるための一時的な感情ではなく、今後の人生をよりよいものにするための選択として離婚を考えることが大切でしょう。
どのような理由であれ、離婚は人生の大きな転機となるので、専門家のアドバイスを受けながら冷静に判断することをおすすめします。
離婚を決意した後に後悔しないために知っておくべきポイント
離婚を決意することは大きな第一歩ですが、その後に後悔しないためには知っておくべき重要なポイントがあります。
特に離婚を考え始めたばかりの方は、感情に流されやすい状態なので、冷静に事実を確認し、将来を見据えた判断をすることが重要です。
感情的になりすぎず、かといって後悔するほど我慢せず、バランスの取れた判断をするために参考にしてください。
- 離婚を決意するのは妻の方が圧倒的に多い
- 妻が離婚を決断する主な原因
離婚を決意するのは妻の方が圧倒的に多い
統計によると、離婚を申し立てるのは妻側が約70%と圧倒的に多いことが分かっています。
この数字は、女性が我慢強いという側面を表していると言えるでしょう。
多くの場合、妻は何度も夫に改善を求めてきたものの、状況が変わらず限界を感じた末に離婚を決意します。
一方で夫の側は「突然離婚を切り出された」と感じることが多く、認識のずれが生じやすいのが特徴です。
もし離婚を考えているなら、これまで配偶者に対して自分の気持ちをしっかり伝えてきたか振り返ってみましょう。
コミュニケーション不足から生じる問題であれば、まずは夫婦カウンセリングなどの選択肢も検討する価値があります。
妻が離婚を決断する主な原因
妻側から離婚を切り出す際の主な理由として、以下のようなものが挙げられます。
| 理由 | 具体例 |
|---|---|
| 性格の不一致 | 価値観の違い、コミュニケーション不足 |
| 暴力・モラハラ | 身体的暴力、精神的苦痛を与える言動 |
| 生活費の問題 | 家計への無関心、浪費、借金 |
| 不貞行為 | 浮気、不倫関係の発覚 |
| 家事・育児の非協力 | 家庭責任の放棄、育児への無関心 |
| 依存症 | アルコール、ギャンブル、ゲーム依存など |
| 親族との問題 | 義両親との確執、親子関係の優先 |
離婚を決意する前に、上記の問題が本当に解決不可能なものなのか、カウンセリングや専門家の支援を受けることで改善の余地がないか検討することも大切です。
しかし、暴力やモラハラなど、自分や子どもの心身の安全が脅かされる状況では、迷わず専門機関に相談し、安全を最優先に考えるべきです。

女性が行う離婚調停の申立理由ランキング
実際に裁判所に提出される離婚調停の申立書には、具体的な離婚理由が記載されています。
女性側が申し立てる離婚調停では、どのような理由が多いのでしょうか。
統計データを基に女性が離婚を決意して実際に法的手続きに踏み切る際の主な理由をランキング形式で見ていきましょう。
| 順位 | 離婚調停申立理由 | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 性格の不一致 | 約40% |
| 2位 | 暴力、モラハラ | 約25% |
| 3位 | 生活費の問題 | 約15% |
| 4位 | 不貞行為 | 約10% |
| 5位 | 家事、育児への非協力 | 約5% |
| 6位 | 依存症問題 | 約3% |
| 7位 | 親族との問題 | 約2% |
「性格の不一致」が最も多い理由として挙げられていますが、これは様々な問題の総称として使われることが多いようです。
例えば、価値観の違いやコミュニケーション不足、互いを尊重し合えない関係性なども、この「性格の不一致」に含まれます。
次いで多い「暴力・モラハラ」は深刻な問題であり、心身の安全が脅かされる状況では迅速な対応が必要です。
「生活費の問題」は夫が家計に無関心だったり、浪費や借金の問題があったりするケースを指します。
こうした経済的な問題は日常生活に直結するため、将来への不安からも離婚を決意する大きな要因となるでしょう。
「不貞行為」は全体の10%程度ですが、表面化しない不倫も含めるとさらに多いと考えられます。
離婚調停を申し立てる際は、できるだけ具体的な事実に基づいた理由を挙げることが重要です。
特に「性格の不一致」という曖昧な理由ではなく、具体的にどのような言動や行動が問題なのかを明確にしておくと、調停や裁判でも有利に進められる可能性が高まります。

夫との離婚を検討したら、まずは弁護士に相談しよう
離婚を決意しても、実際にどのように進めていけばよいのか迷うことも多いでしょう。
特に女性の場合、経済的な不安や子どもの親権問題など、様々な懸念があるかもしれません。
そんなとき、離婚問題に詳しい弁護士に早めに相談することで、多くのメリットがあるのです。
- 法的な権利や選択肢について正確に知ることができる
- 適切な証拠の収集方法やタイミングをアドバイスしてもらえる
- 感情的にならず冷静に交渉を進められる
- 有利な条件での離婚協議が期待できる
- DV、モラハラがある場合の安全確保策を提案してもらえる
「まだ離婚を決めたわけではないから」と相談を躊躇する方もいますが、むしろ決意が固まる前の段階で相談することで、より冷静な判断ができるようになります。
例えば、「このままだと養育費はいくらもらえるのか」「財産分与の対象はどこまでか」といった具体的な情報を得ることで、現実的な判断材料が増えるでしょう。
また、DVやモラハラの被害を受けている場合は、まず自分と子どもの安全を確保するための方法を優先的に相談することが大切です。
多くの弁護士事務所では初回相談を無料で受け付けていますので、「相談するだけ」という気持ちで利用してみてはいかがでしょうか。
専門家のアドバイスを受けることで、感情に流されず、将来を見据えた冷静な判断ができるようになりますよ。

男性側が離婚を決意する主な理由
男性側の離婚調停申立理由ランキング
女性からの離婚申し立てが多数を占めますが、男性側から離婚を切り出すケースも少なくありません。
男性が離婚調停を申し立てる際の主な理由には、女性とは異なる特徴的なパターンが見られます。
| 順位 | 離婚調停申立理由 | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 性格の不一致 | 約35% |
| 2位 | 妻の不貞行為 | 約20% |
| 3位 | 妻の家事放棄 | 約15% |
| 4位 | 妻の浪費 | 約10% |
| 5位 | 妻の暴言、暴力 | 約8% |
| 6位 | 子どもの非協力的な養育態度 | 約7% |
| 7位 | 妻の親族との問題 | 約5% |
男性が離婚を決意する理由として特徴的なのは、「妻の不貞行為」の割合が女性よりも高いことです。
また、「家事放棄」や「浪費」といった家庭生活の運営に関する不満も上位に挙がっています。
男性の場合、女性と比べて経済的な自立度が高いことが多いため、経済面よりも精神的な信頼関係や家庭の居心地の良さを重視する傾向があるようです。
一方で、「暴言・暴力」を理由とする割合は女性よりも低くなっていますが、これは男性が被害を受けても表に出しにくいという社会的背景も影響しているかもしれません。
また、男性特有の理由として、「子どもを自分になつかせない」「子どもを自分から遠ざける育て方をする」といった、父親としての立場を脅かされる状況も離婚の要因となっています。
男性が離婚を決意する場合でも、感情的な判断ではなく、専門家に相談しながら冷静に判断することが後悔しない選択につながります。
男性が妻との離婚を決意するきっかけとなる瞬間
男性が離婚を決意する瞬間は、女性とは少し異なる特徴があります。
統計的には離婚を切り出すのは女性の方が多いものの、男性が離婚を決意するきっかけには特徴的なパターンが見られます。
ここでは、男性が「もう無理だ」と離婚を決意するきっかけとなる具体的な状況を見ていきましょう。
妻の不貞行為が発覚したとき
男性にとって、妻の不貞行為の発覚は大きな精神的ショックとなります。
特に何の前触れもなく突然発覚した場合、それまでの信頼関係が一瞬で崩れ去ることになります。
Nさん(43歳男性)は、妻のスマートフォンに届いた不審なメッセージをきっかけに、1年以上続いていた不倫関係を知りました。
「最初は信じられなかったけど、証拠を突きつけると認めざるを得なくなった」とNさん。
話し合いの中で妻に反省の様子が見られず、むしろ「あなたにも原因がある」と責められたことで、修復不可能と判断し離婚を決意したそうです。
不貞行為は法的にも離婚理由として認められる「法定離婚原因」の一つです。
ただし、証拠の収集と保全が非常に重要なので、感情的になる前に弁護士に相談することをおすすめします。

妻から評価されないと感じるとき
男性にとって、自分の努力や貢献が認められないことは大きなストレスとなります。
Oさん(38歳男性)は、仕事で成果を上げても家庭での評価がなく、むしろ「もっと稼げるはず」と言われ続けたことで離婚を考え始めました。
「毎日遅くまで働いて家族のために頑張っているのに、『〇〇さんの旦那さんはもっと稼いでいる』と比較され続けた」とOさん。
何をしても評価されず、常に否定的なフィードバックばかりを受け続けると、男性は「この関係を続ける意味があるのか」と疑問を持ち始めます。
家庭内での承認欲求が満たされないことが積み重なり、やがて離婚を決意するきっかけになるのです。
収入に対する不満を言われ続けるとき
男性の多くは「家族を養う」という責任感を持って働いています。
そんな中、妻から常に「お金が足りない」「もっと稼いで」と言われ続けると、大きな精神的プレッシャーを感じます。
Pさん(45歳男性)は、妻からの経済的な不満が増大していくことに耐えられなくなりました。
「転職して収入が上がっても、すぐに『もっと上の会社に行けるはず』『このままじゃ老後が不安』と言われ続けた」とPさん。
最善を尽くしているにもかかわらず、配偶者から理解を得られないと感じることで、男性は「どれだけ頑張っても満足してもらえない」と諦めの気持ちを抱くようになります。
このような状況が続くと、自己評価が下がり、精神的な健康も損なわれるため、離婚を選択肢として考え始めるケースが増えています。

根拠なく疑われ続けるとき
何の根拠もなく不貞や嘘を疑われ続ける状況は、男性にとって大きなストレスとなります。
Qさん(37歳男性)は、帰宅が少し遅れるだけで「誰と会っていた?」と詰問され、スマートフォンのチェックを毎日強要されていました。
「何も悪いことをしていないのに、常に疑われ監視される生活に耐えられなくなった」とQさん。
自分の行動を常に説明しなければならない状況は、プライバシーの侵害であり、互いを信頼し合う夫婦関係の基盤を揺るがすものです。
このような過度な疑いは、モラルハラスメントの一種として認識されることもあり、精神的な健康を害する原因となります。
信頼関係の回復が見込めないと判断した場合、離婚を選択する男性も少なくありません。
妻が夫の悪口を言っているのを知ったとき
妻が友人や家族に自分の悪口を言っているのを知ったとき、男性は深く傷つくことがあります。
Rさん(40歳男性)は、妻の友人の一人から「いつも悪口を聞かされている」と教えられ、ショックを受けました。
「家では普通に接してくれているのに、外では『ダメな夫』として笑い話にされていたと知って、信頼関係が完全に崩れた」とRさん。
特に、収入や性格、家庭での役割などを否定的に話されていると知ると、自尊心が大きく傷つけられます。
妻が自分を尊重していないと感じることで、「このまま一緒にいても幸せになれない」と判断し、離婚を決意するケースもあります。
妻が友人宛のメールを誤送信で夫に送ってしまうケース
誤送信されたメールやメッセージによって、思わぬ真実が明らかになることがあります。
Sさん(36歳男性)は、妻が友人に送るつもりだったメールが誤って自分に届いたことで、妻の本音を知りました。
「『夫とは早く離婚したい』『子どもが中学生になったら別れるつもり』などと書かれていて愕然とした」とSさん。
表面上は円満な家庭を装っていたものの、実は妻は長年離婚を考えていたという事実に、大きな裏切り感を覚えたそうです。
このような形で配偶者の本心を知ると、信頼関係の修復は困難になり、むしろ「先に離婚を切り出そう」と決意するケースも少なくありません。
誤送信されたメッセージは、法的にも証拠として使える可能性があるため、慎重に保存しておくと良いでしょう。
妻の不貞行為が明らかになったとき
先に触れた「妻の不貞行為」とも重なりますが、特に決定的な証拠が見つかった場合、離婚を決意する男性は多いようです。
Tさん(42歳男性)は、妻のスマートフォンに保存されていた不倫相手との親密な写真を見つけたことで、修復不可能と判断しました。
「言い逃れできない証拠を目の当たりにして、一瞬で離婚を決意した」とTさん。
特に長期間続いていた不倫や、複数の相手との不貞行為が発覚した場合、男性の多くは「もう取り返しがつかない」と考えます。
不貞の証拠を押さえた場合は、感情的に相手を責める前に、弁護士に相談して証拠を適切に保全することをおすすめします。
こうした証拠は、離婚調停や裁判、慰謝料請求の際に重要な役割を果たします。

妻の感情的な言動に疲れたとき
日常的に妻の感情的な言動に晒され続けると、精神的に消耗して離婚を検討するケースがあります。
Uさん(39歳男性)は、些細なことで激しく怒鳴られたり、物を投げられたりする状況に長年耐えてきました。
「帰宅するのが怖くなり、子どもも萎縮している様子を見て、このままでは家族全員の精神状態が悪化すると感じた」とUさん。
カウンセリングや夫婦療法を提案しても受け入れてもらえず、状況の改善が見込めないと判断して離婚を決意したそうです。
男性がDVの被害者になるケースも少なくありませんが、社会的な認識の低さから相談しづらい現状があります。
しかし近年は男性向けのDV相談窓口も増えてきているので、一人で抱え込まず専門家に相談することが大切です。
不倫相手へ攻撃的な行動をとるとき
自分が不貞行為をして妻に発覚した場合、その後の妻の行動によっては離婚を決意するケースもあります。
Vさん(44歳男性)は、自らの不倫が発覚した後、妻が不倫相手に対して過剰な嫌がらせを続けたことで離婚を決意しました。
「自分が悪いことをしたのは認めるが、妻が不倫相手の職場に乗り込んだり、SNSで中傷したりする行為は許せなかった」とVさん。
自分の行為は反省しつつも、相手の過剰な報復行動によって「一緒にいられない」と判断するケースは少なくありません。
このような場合、双方の感情が高ぶっているため、第三者である専門家の介入が問題解決には効果的です。
実家との関係に問題が生じたとき
妻と自分の実家との関係が悪化し、修復が難しい状況になると離婚を検討する男性もいます。
Wさん(41歳男性)は、妻が自分の両親を露骨に嫌い、実家への訪問や親との交流を一切拒否するようになったことで悩んでいました。
「親が高齢になり介護が必要になった時に、妻の協力が得られないことが明らかで、将来に大きな不安を感じた」とWさん。
親族関係の問題は、時間が経つにつれて複雑化することが多く、特に親の介護問題は深刻な夫婦間の対立を生むことがあります。
話し合いを重ねても妥協点が見いだせない場合、離婚という選択肢を検討せざるを得ないこともあるでしょう。
離婚を決意する理由は人それぞれですが、どのような場合でも感情だけに流されず、将来を見据えた冷静な判断をすることが大切です。
離婚を考え始めたら、まずは信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
離婚の決意が揺らいでしまう場面とその対処法
離婚を決意しても、実際に行動に移す段階になると気持ちが揺らぐことは珍しくありません。
特に長年連れ添った相手との別れは、大きな決断を伴います。
ここでは、離婚の決意が揺らぎやすい状況とその対処法について解説します。
子どものことを考えて悩むとき
子どもがいる場合、「離婚によって子どもに悪影響が出るのではないか」と心配する方は多いでしょう。
Xさん(36歳女性)は、明らかなモラハラ夫との離婚を決意したものの、小学生の子どもが「パパと離れたくない」と泣くたびに決意が揺らいでいました。
こうした場合、以下のポイントを考慮すると判断の助けになります。
- 不幸な夫婦関係の中で育つことと、離婚後の安定した環境で育つこと、どちらが子どもにとって良いか
- 離婚後も適切な面会交流を確保することで、親子関係を維持できるか
- 子どもの年齢や性格に合わせた説明と心のケアができるか
- 離婚後の養育環境(住居、学校、生活リズムなど)をどう整えるか
専門家によれば、夫婦間の激しい対立や緊張関係の方が、離婚よりも子どもに悪影響を与えることが多いとされています。
子どものためを思うなら、無理に夫婦関係を続けるよりも、離婚後もそれぞれが良き親であり続ける方法を考えることが大切です。

離婚後の生活に不安を感じるとき
経済的な不安や住居の問題など、離婚後の生活への心配から決意が揺らぐことも少なくありません。
Yさん(42歳女性)は、専業主婦として20年近く家庭を支えてきましたが、「離婚後にどうやって生活していけばいいのか」という不安から、離婚を躊躇していました。
このような不安に対処するためには、具体的な生活設計を立てることが重要です。
- 財産分与でどれくらいの資産が手に入るか試算する
- 養育費や婚姻費用の相場を知っておく
- 就職や転職の可能性を探る
- 公的支援制度(児童扶養手当や住宅手当など)を調べる
- 住居の選択肢(実家に戻る、公営住宅を申し込むなど)を検討する
経済的な不安は具体的な数字で把握することで、漠然とした不安から具体的な課題へと変わります。
弁護士や離婚カウンセラーに相談すれば、より正確な情報を得られるでしょう。

周囲の目を気にしてしまうとき
「親や友人、会社の同僚にどう思われるだろう」と周囲の評価を気にして、離婚の決断をためらうケースも多いものです。
Zさん(38歳男性)は、「家族や会社の人に離婚を伝えることが怖くて、踏み出せない」と悩んでいました。
社会的評価の不安に対処するためのポイントは以下の通りです。
- 最も信頼できる人から少しずつ打ち明けていく
- 自分の幸せのために必要な選択であることを伝える
- 詳細な理由を全員に説明する必要はないと割り切る
- 離婚経験者の体験談やアドバイスを聞く
- 必要に応じて転居や転職も視野に入れる
日本でも離婚に対する社会的なスティグマ(負の烙印)は以前より減ってきています。
他人の評価よりも自分自身の幸福を優先することの大切さを認識しましょう。
決意が揺らいだときの考え方
離婚の決意が揺らぐのは自然なことですが、そんなときに冷静に判断するための考え方があります。
まず、「なぜ離婚を考えたのか」という原点に立ち返ることが大切です。
感情に任せた一時的な決断ではなく、長い時間をかけて考えた結論であれば、揺らぎはあっても基本的な方向性は変わらないはずです。
- 離婚を考えるきっかけとなった問題は解決したか、または解決の見込みはあるか
- 今後も同じ問題が繰り返されずに済む保証はあるか
- 離婚せずに問題解決を図る方法(カウンセリングなど)は試したか
- 離婚しない場合と離婚する場合、5年後10年後の自分はどうなっているか
相手の些細な優しさや思い出に心が揺れることもありますが、根本的な問題が解決していないのであれば、同じ苦しみを繰り返す可能性が高いのです。
決断を先送りにすることで問題が解決するわけではないことを認識しましょう。
離婚の決意が揺らいだときこそ弁護士の存在が重要
離婚の決意が揺らぐ時こそ、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
感情的になりがちな時期に、客観的な視点からアドバイスをもらうことで、冷静な判断ができるようになります。
弁護士は法的な側面だけでなく、以下のような点でもサポートしてくれます。
- 離婚後の生活設計の具体的なシミュレーション
- 子どもの親権や面会交流についての現実的な助言
- 財産分与や養育費の適正な金額の試算
- 調停や裁判になった場合の見通し
- 相手との交渉における心構えや戦略
また、弁護士に相談することで、自分の状況を客観的に説明する必要があり、それによって自分自身の考えも整理されるというメリットもあります。
特にDVやモラハラの被害者は、加害者からの謝罪や改善の約束に心が揺れやすいので、第三者の冷静な判断が必要です。
決意が揺らいでも自分を責める必要はありません。
重要なのは、最終的に自分自身が納得できる選択をすることです。
離婚という決断は、新たな人生のスタートでもあります。
不安や迷いを抱えながらも、自分の幸せのために前に進む勇気を持ちましょう。
離婚を決意する前に考えておくべき重要事項
離婚を決意する前に、冷静に考えておくべき重要な事項があります。
感情だけで判断せず、将来の生活を見据えた上で決断することが、後悔のない選択につながります。
ここでは、離婚を決意する前に必ず確認しておきたい7つのポイントについて解説します。
離婚の正当な理由があるか
離婚を考える理由が、一時的な感情によるものなのか、それとも本質的な問題によるものなのかを見極めることが重要です。
法律上、離婚が認められる「法定離婚原因」には以下のようなものがあります。
- 不貞行為(浮気、不倫)
- 悪意の遺棄(正当な理由なく同居や生活費の負担を拒否)
- 3年以上の生死不明
- 重度の精神疾患で回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(DVやモラハラなど)
これらの理由がなくても協議離婚は可能ですが、相手が同意しない場合に調停や裁判で離婚を認めてもらうには、上記のような法定離婚原因が必要です。
「性格の不一致」だけでは裁判で離婚が認められる可能性は低いため、具体的にどのような言動や行為が問題なのかを整理しておきましょう。

相手は離婚に同意してくれるか
相手が離婚に同意するかどうかで、離婚手続きの難易度や期間は大きく変わります。
相手が離婚に同意する場合は「協議離婚」が可能で、比較的スムーズに進みます。
しかし同意が得られない場合は、「調停離婚」や「裁判離婚」という長期化する可能性のある手続きを経る必要があります。
調停では半年〜1年程度、裁判では1年〜3年程度かかることもあるため、心の準備と生活の計画を立てておく必要があるでしょう。
現在の関係性や過去の会話から、相手がどのような反応を示す可能性があるか予測しておきましょう。
特にDVやモラハラがある場合は、離婚を切り出すタイミングや方法によって危険が生じる可能性もあるため、専門家に相談してから行動することが重要です。

経済的に自立した生活が可能か
離婚後の経済的な自立は、特に専業主婦(夫)だった方にとって大きな課題です。
以下の点について具体的に計画を立てておきましょう。
- 現在の貯蓄はいくらあるか
- 就職または転職の可能性はあるか
- 月々の生活費はいくら必要か
- 養育費や婚姻費用をいくら受け取れる見込みか
- 児童手当や児童扶養手当などの公的支援は受けられるか
これらの情報を基に具体的な生活設計を立て、必要に応じて就職活動や資格取得の準備を始めることも検討しましょう。
また、住宅ローンや車のローンなどの債務がある場合、誰がどのように返済していくのかも明確にしておく必要があります。
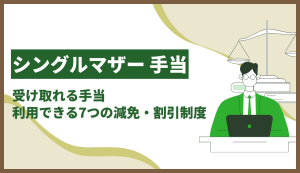
財産分与の見込み額はどれくらいか
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分けることです。
基本的には夫婦の共有財産の2分の1が目安となりますが、具体的にはどのような財産が対象になるのでしょうか。
| 分与対象となる財産の例 | 分与対象とならない財産の例 |
|---|---|
| 預貯金 | 婚姻前から所有していた財産 |
| 不動産(自宅・投資用物件など) | 相続や贈与で得た財産 |
| 車やバイク | 慰謝料として受け取ったお金 |
| 株式・投資信託 | 個人的な賠償金 |
| 退職金(婚姻期間分) | 特別受益(親からの援助など) |
| 保険の解約返戻金 | 婚姻後に受け取った相続財産 |
財産分与の金額を正確に把握するためには、まず夫婦の財産を洗い出す必要があります。
自分名義の口座だけでなく、配偶者名義の口座やローン、クレジットカードの情報なども可能な限り収集しておきましょう。
財産分与の請求権は離婚成立から2年で消滅するため、事前に十分な情報収集と準備が必要です。

慰謝料の支払い義務はあるか
慰謝料とは、配偶者の不法行為(不貞行為やDVなど)によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
自分に慰謝料を請求される可能性があるか、または相手に請求できる可能性があるかを検討しておきましょう。
慰謝料が認められる主な事由には以下のようなものがあります。
- 不貞行為(浮気、不倫)
- 暴力(身体的、精神的)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
- 過度の浪費や借金
- 性生活の拒否
- 重大な侮辱や名誉毀損
慰謝料の相場は状況によって大きく異なりますが、一般的には50万円〜300万円程度と言われています。
不貞行為があった場合は、相手方だけでなく不倫相手にも請求できる可能性があるため、証拠の収集・保全が重要です。
証拠となり得るものには、メールやLINEのやり取り、写真、目撃証言、GPS記録などがあります。

子どもの親権と面会交流はどうするか
子どもがいる場合、親権と監護権をどちらが持つか、そして離婚後の面会交流をどうするかは最も重要な検討事項の一つです。
親権とは子どもの法定代理人として重要な決定を行う権利であり、監護権とは実際に子どもと生活を共にする権利です。
親権者を決める際に裁判所が考慮する主な要素には以下のようなものがあります。
- これまでの養育状況(主に世話をしてきたのは誰か)
- 経済的な安定性(子どもを育てていける環境があるか)
- 子どもとの愛着関係
- 子ども本人の意思(年齢によって考慮される度合いが異なる)
- 親としての適格性(暴力やネグレクトがないか)
- 親族のサポート体制
また、面会交流(親権を持たない親が子どもと会う機会)についても、頻度や方法、費用負担などを具体的に決めておく必要があります。
親権争いは感情的になりやすい問題ですが、常に「子どもの最善の利益」を第一に考えることが重要です。

離婚後の住居はどうするか
離婚後にどこで生活するかも重要な検討事項です。
特に子どもがいる場合は、学校や友人関係への影響も考慮する必要があります。
住居に関する主な選択肢には以下のようなものがあります。
- 現在の住居に住み続ける(相手に退去してもらう)
- 自分が退去して新居を探す
- 実家に戻る
- 公営住宅に申し込む
- 現在の住居を売却して双方が新居を探す
住居費用は生活費の中で大きな割合を占めるため、家賃や住宅ローンの支払いが可能かどうかも検討が必要です。
また、引っ越し費用や敷金・礼金、家具家電の購入費用なども考慮しておきましょう。
住宅ローンがある場合は名義変更や返済計画も重要な検討事項です。
以上のポイントをしっかり検討し、具体的な見通しを立てた上で離婚を決意することで、後悔のない選択ができるでしょう。
不安な点があれば、弁護士や離婚カウンセラーなどの専門家に相談することをおすすめします。
離婚を決意した後に相手を説得する効果的な方法
離婚を決意しても、相手が同意してくれなければ協議離婚はできません。
相手を説得するには段階的なアプローチが効果的です。
ここでは、離婚を決意した後に相手を説得するための効果的な方法を、穏やかな手段から強い手段まで順に解説します。
離婚の意思を明確に伝える
まずは冷静に、しかし明確に離婚の意思を伝えることから始めましょう。
感情的にならず、なぜ離婚を考えるようになったのか、具体的な理由を伝えることが大切です。
話し合いの場を設けるときのポイントは以下の通りです。
- 子どもがいない時間、場所を選ぶ
- 十分な時間を確保する
- 「あなたが悪い」という責める表現は避ける
- 自分の気持ちや考えを「私は~と感じている」と伝える
- 具体的な問題点を挙げる
- 離婚後のイメージ(親権、財産分与など)も伝える
一度の話し合いで相手が納得することは稀です。
何度か話し合いの機会を設け、徐々に理解を求めていくことが大切でしょう。
ただし、DVやモラハラがある場合は、直接対峙することで危険が生じる可能性があるため、弁護士や専門機関に相談してから行動することをおすすめします。
離婚届への署名を求める
何度か話し合いを重ねた後、離婚届への署名を求めてみましょう。
実際に書類を目の前にすることで、相手も離婚の現実味を感じるかもしれません。
離婚届を作成する際のポイントは以下の通りです。
- 役所で入手した正式な離婚届を使用する
- 必要事項を自分の分だけ先に記入しておく
- 離婚条件(財産分与、親権、養育費など)を書面にまとめておく
- 強引に署名を迫るのではなく、時間をかけて検討してもらう
離婚届と一緒に「離婚協議書」も作成しておくと良いでしょう。
離婚協議書には、財産分与の内容、養育費の金額や支払い方法、親権者、面会交流の方法など、具体的な取り決めを記載します。
ただし、「離婚届に署名してもらう」という行為は、相手にとって大きなプレッシャーになる場合もあります。
状況によっては反発を招くこともあるため、相手の性格や関係性を考慮した上で判断しましょう。
家庭内別居の状態を作る
話し合いで進展が見られない場合、同じ家に住みながらも生活を分ける「家庭内別居」という選択肢もあります。
家庭内別居の具体的な方法としては、以下のようなものがあります。
- 寝室を分ける
- 食事は別々にとる
- 家事や育児の分担を明確にする
- 会話を必要最小限にする
- 財布を分ける(生活費の負担方法を決める)
この状態を続けることで、相手にも「このままでは一緒に暮らしていくのは難しい」と実感してもらえるかもしれません。
また、自分自身も離婚後の生活をイメージしやすくなり、本当に離婚すべきかどうかを冷静に考える時間にもなります。
ただし、家庭内別居は子どもにとって理解しにくい状況を作り出すこともあります。
子どもへの影響を考慮し、年齢に応じた適切な説明を心がけましょう。
家庭内別居については「家庭内別居の実態とリスク」の記事が参考になるのでぜひご覧ください。
実際に別居を始める
家庭内別居でも状況が改善しない場合は、実際に別の場所で生活する「別居」を検討しましょう。
別居は離婚の意思をより明確に示すだけでなく、精神的な距離を置くことでお互いの冷静な判断にもつながります。
また、長期間の別居は「婚姻関係の破綻」の証拠にもなり、調停や裁判で離婚を認めてもらいやすくなる場合もあります。

別居中の生活費について決めておく
別居を始める前に、生活費の負担について明確に取り決めておくことが重要です。
特に子どもがいる場合や、経済的に自立していない場合は、「婚姻費用の分担」として相手に生活費を請求できます。
婚姻費用の相場は、収入や子どもの人数などによって変わりますが、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にすることができます。
話し合いで決まらない場合は、「婚姻費用分担請求調停」を家庭裁判所に申し立てることも可能です。
調停で決まった婚姻費用は法的な拘束力を持ち、支払いがない場合は強制執行することもできます。
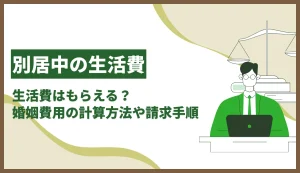
DV・モラハラの場合は別居から始める
DV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント)がある場合は、安全を最優先に考え、まず別居から始めることをおすすめします。
別居の準備を始める前に、以下のような安全対策を検討しましょう。
- 配偶者暴力相談支援センターや警察に相談する
- 信頼できる友人や家族に協力を仰ぐ
- 必要な書類(戸籍謄本、住民票、通帳など)を事前に確保しておく
- 別居先の住所を相手に知られないようにする
- 必要に応じて「保護命令」を申し立てる
特に子どもを連れての別居は「連れ去り」と誤解されるリスクもあるため、事前に弁護士に相談して適切な手順を踏むことが重要です。
DVの証拠(診断書・写真・録音など)があれば、保存しておきましょう。
離婚調停を申し立てる
話し合いや別居によっても相手が離婚に応じない場合は、「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てることを検討しましょう。
調停は裁判所の調停委員を介して話し合いを進める手続きで、直接対面せずに協議できる点がメリットです。
離婚調停の申立方法は以下の通りです。
- 居住地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出する
- 申立費用(収入印紙1,200円と郵便切手数百円分)を支払う
- 離婚の理由や求める条件を記載した申立書を作成する
- 必要に応じて証拠資料を準備する
調停は原則として3週間から1ヶ月に1回のペースで行われ、解決までに半年から1年程度かかることが一般的です。
調停でも合意に至らない場合は「離婚訴訟」に進むことになりますが、調停の段階で弁護士に依頼しておくとスムーズに訴訟に移行できます。
調停は法的な手続きとなるため、相手に「本気で離婚を考えている」という強いメッセージになります。

弁護士から内容証明を送付してもらう
相手に離婚の意思を明確に伝える方法として、弁護士名で内容証明郵便を送ることも効果的です。
弁護士からの文書は心理的なインパクトが大きく、相手に「法的な手続きも辞さない」という姿勢を示すことができます。
内容証明郵便に記載する主な内容は以下の通りです。
- 離婚を希望する意思表示
- 離婚を希望する理由
- 希望する離婚条件(親権、養育費、財産分与など)
- 回答期限(通常は2週間程度)
- 期限内に回答がない場合の対応(調停申立てなど)
内容証明郵便は「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったか」を法的に証明するものです。
後々のトラブルを防ぐためにも、弁護士に依頼して適切な文面を作成してもらうことをおすすめします。
このように、離婚を決意した後の相手への説得方法は段階的に強めていくことで、効果的に進めることができます。
どの段階であっても、感情的にならず冷静に対応することが、スムーズな離婚への近道です。
特に子どもがいる場合は、将来的な親子関係も考慮し、できるだけ円満な形で離婚することを心がけましょう。
離婚を決意したら弁護士が心強い味方!
離婚を決意したとき、誰に相談すれば良いのか悩む方も多いでしょう。
家族や友人に相談することも大切ですが、感情的なアドバイスになりがちです。
そこで頼りになるのが離婚問題に詳しい弁護士の存在です。
弁護士に相談することで得られる具体的なメリットについて見ていきましょう。
- 法的な権利や選択肢について専門的なアドバイスが受けられる
- 離婚後の生活設計を具体的に立てられる
- 財産分与や養育費の適正な金額を把握できる
- 有利な条件での離婚協議を進められる
- 必要な証拠の収集方法を教えてもらえる
- 相手とのやり取りを代行してもらえる
- DVやモラハラがある場合の安全確保策を提案してもらえる
特に、相手が離婚に応じない場合や、DVなどで安全面に不安がある場合、財産が複雑な場合などは、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
多くの弁護士事務所では初回相談を無料または低額で受け付けているため、「まだ決断していない」という段階でも気軽に相談できます。
弁護士に相談する際は、以下の資料を可能な範囲で準備しておくとスムーズです。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 住民票
- 給与明細や確定申告書
- 財産関係の資料(通帳のコピー、不動産の権利書など)
- 離婚の原因となる証拠(メール、LINE、写真など)
- DVがある場合は診断書や被害状況のメモ
これらの資料はすべて揃えなければならないというわけではありません。
手元にある範囲で構いませんので、相談時に持参するとより具体的なアドバイスが受けられるでしょう。
弁護士費用が心配という方も多いと思いますが、離婚問題の解決によって得られる精神的安心や経済的メリット(適正な財産分与や養育費など)を考えると、十分に価値のある投資と言えます。
また、法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、収入が一定基準以下の方は弁護士費用の立替制度を利用することも可能です。
離婚は人生の大きな転機です。
専門家のサポートを受けながら、より良い未来へのステップとしましょう。

よくある質問
離婚の決意に関して、多くの方が抱える疑問や不安にお答えします。
離婚を考えている方だけでなく、パートナーから離婚を切り出された方にも参考になる情報を簡潔にまとめました。
- 離婚するべきか判断するためのチェックポイントはありますか?
- 離婚を決意した妻はどのような行動をとることが多いですか?
- 男性が離婚を決意する瞬間はどんなときですか?
- 女性が離婚を決めるきっかけとなる理由を教えてください。
- 離婚を決意した夫の特徴的な行動パターンはありますか?
- 子持ちの女性が離婚を決める時に考慮すべき点は何ですか?
- 離婚を決意した女性の心理状態はどのように変わりますか?
- 子どもがいない場合でも離婚の決断ができない理由は何ですか?
- 男性が離婚の決断をできない時、その背景にはどんな心理がありますか?
- 一度固まった離婚への決意が揺らぐ原因には何がありますか?
まとめ
離婚を決意することは、人生の大きな転機となる重要な決断です。
この記事では、夫婦が離婚を決意する主な理由や瞬間、後悔しないための重要ポイント、相手を説得する方法など、離婚の決意から実行までのプロセスを詳しく解説してきました。
離婚の決意が揺らぐことは自然なことですが、その根本的な理由をしっかりと見つめ直し、冷静な判断をすることが大切です。
特に子どもがいる場合は、子どもの幸せを第一に考えた決断をしましょう。
どのような状況であっても、一人で悩まず専門家に相談することをおすすめします。
弁護士や離婚カウンセラーなどの専門家のサポートを受けることで、感情に流されず、より良い将来に向けた選択ができるでしょう。
離婚は終わりではなく、新たな人生の始まりです。自分自身と子どもの幸せのために、勇気を持って前に進んでください。