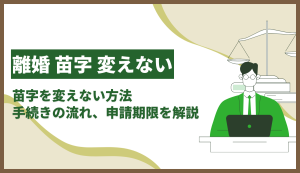離婚時の子ども扶養控除とデメリット|国民健康保険料はいくら?

「離婚したら子どもの健康保険はどうなるの?」
「扶養から外れたら、どれくらい負担が増えるの?」
そんな不安を抱えながら、離婚後の生活を考えていませんか?
離婚による扶養の変更は、年間20万円以上の新たな負担を生む可能性があります。
特に専業主婦だった方にとっては、健康保険料や年金保険料の自己負担が家計を圧迫する大きな要因となります。
でも、決して一人で抱え込む必要はありません。適切な手続きと知識があれば、負担を最小限に抑えることができます。
- 離婚後の健康保険の切り替えはいつまでに?
- 子どもの扶養はどちらの親が持つべき?
- 養育費と扶養控除の関係は?
この記事では、離婚時の扶養に関する手続きから、税金・健康保険の変更、子どもの養育費まで詳しく解説します。
離婚手続きの中でも特に迷いやすい扶養に関する問題を、具体的な事例を交えながら解説しています。
将来のトラブルを避けるためにも、扶養に関する正しい知識を身につけておきましょう。
※ 離婚を検討中・離婚直後の方へ
この記事では扶養に関する手続きを詳しく解説していますが、離婚後14日以内に必要な手続きがあります。緊急を要する場合は専門弁護士への無料相談フォームから今すぐご連絡ください。特に健康保険の切り替えは空白期間を作らないよう早急な対応が必要です。
離婚後の税金はどう変わる? 扶養控除の基本知識
離婚すると税金面でも大きな変化が生じます。
特に扶養関係が変わることで、税金の計算方法も変わってきます。
離婚後の生活設計を考える上で、扶養控除に関する知識は欠かせません。
扶養控除で税金が軽減される
扶養控除とは、生計を共にする家族を養っている場合に受けられる所得控除のひとつです。
この控除を受けることで、課税対象となる所得金額を減らし、結果的に納める税金を少なくすることができます。
例えば、配偶者を扶養に入れている場合、年間で最大38万円の配偶者控除を受けることが可能です。
子どもを扶養に入れている場合も同様に控除を受けられるため、税負担が軽くなります。
しかし離婚すると、前配偶者の扶養から外れることになるため、税金面での優遇がなくなってしまうのです。
特に専業主婦だった方は、離婚後に自分で確定申告をする必要が出てくるケースもあります。
扶養控除を受けるための条件
扶養控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、扶養家族の年間所得が103万円以下であることが基本条件です。
また、生計を同一にしていることも重要なポイントになります。
離婚後に子どもの親権を持つ場合、子どもを扶養に入れることができます。
ただし、離婚協議の中で親権と扶養権は別に考える必要があるため、注意が必要です。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 所得制限 | 年間103万円以下 |
| 同一生計 | 生活費を負担し、生計を一にしていること |
| 年齢制限 | 16歳以上(16歳未満は扶養控除の対象外だが児童手当の対象) |
| 同居の有無 | 別居の場合でも仕送りなど生活費を負担していれば対象 |
扶養控除の申請は、会社員の場合は年末調整で、自営業の方は確定申告時に行います。
離婚によって扶養関係が変わった場合は、速やかに勤務先や税務署に届け出ることが大切です。
扶養控除の金額について
扶養控除の金額は、扶養家族の年齢や状況によって異なります。
一般的な扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)の場合は38万円の控除が受けられます。
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合は63万円と高額な控除が適用されます。
老人扶養親族(70歳以上)の場合は同居か別居かによって48万円または58万円の控除となります。
これらの控除額は課税所得から差し引かれるため、実際の税金軽減額は所得税率によって変わってきます。
| 扶養親族の区分 | 年齢 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上 | 58万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上 | 48万円 |
離婚後に子どもを扶養に入れる場合、これらの控除が受けられるか確認しておくことが大切です。
なお、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが、児童手当などの別の制度で支援が受けられます。
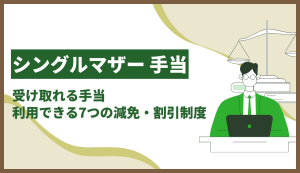
離婚後の健康保険はどうなる?加入保険ごとの手続きまとめ
離婚すると、扶養の関係が変わるため健康保険の加入状況も変更が必要になります。
手続きを怠ると保険料の二重払いや未加入期間が発生する可能性があるので注意が必要です。
健康保険から国民健康保険へ切り替える方法
配偶者の健康保険の扶養に入っていた場合、離婚後は国民健康保険に加入する必要があります。
まず、配偶者の勤務先に「被扶養者異動届」を提出して扶養からの削除手続きを行います。
その際、健康保険資格喪失証明書を必ずもらっておきましょう。
次に、お住まいの市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行います。
離婚の日から14日以内に手続きを完了させることが理想的です。
健康保険の資格喪失日と国民健康保険の資格取得日を合わせることで、保険の空白期間を防げます。
| 必要書類 | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|
| 被扶養者異動届 | 元配偶者の勤務先 | 扶養から外れる手続き |
| 健康保険資格喪失証明書 | もらう書類 | 国保加入時に必要 |
| 国民健康保険加入申請書 | 市区町村役場 | 各自治体で様式が異なる |
| マイナンバーカードまたは通知カード | 市区町村役場 | 本人確認用 |
| 印鑑 | 市区町村役場 | 認印で可 |
| 離婚を証明する書類 | 市区町村役場 | 戸籍謄本など |
なお、国民健康保険は前年の所得に応じて保険料が決まります。
仕事をしていなかった場合でも、最低限の保険料は支払う必要があるため、経済的な準備も忘れずに。
健康保険から別の健康保険へ移行する手続き
あなた自身が会社員で、離婚後も別の健康保険に加入する場合の手続きについて解説します。
この場合は、元の健康保険での脱退手続きと新しい健康保険での加入手続きの両方が必要です。
まず、元の健康保険組合または勤務先の担当部署に「資格喪失届」を提出します。
次に、新たな勤務先で「健康保険資格取得届」を提出して新しい健康保険に加入します。
転職のタイミングで離婚する場合は、健康保険の切り替えを慎重に行いましょう。
手続きのタイミングによっては、一時的に国民健康保険に加入する必要が生じることもあります。
離婚後に同居を続ける場合は、「離婚後の同居について」で解説しているのでご確認ください。
国民健康保険から新しい国民健康保険への変更方法
離婚を機に引越しをする場合、国民健康保険も転出先の自治体で新たに加入する必要があります。
まず、転出前の市区町村役場で「転出届」と「国民健康保険資格喪失届」を提出します。
転居先の市区町村役場では、転入後14日以内に「転入届」と「国民健康保険加入申請書」を提出しましょう。
引越しの予定がある場合は、離婚手続きと一緒に計画的に進めることをおすすめします。
転居を伴う場合の健康保険手続きは次のような流れになります。
| 手続きの流れ | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 1. 転出届・国保資格喪失届の提出 | 転出元市区町村 | 転出前 |
| 2. 転入届の提出 | 転入先市区町村 | 転入後14日以内 |
| 3. 国民健康保険加入申請 | 転入先市区町村 | 転入後14日以内 |
各自治体によって必要書類や手続き方法に若干の違いがあるため、事前に確認することをおすすめします。
国民健康保険から健康保険へ加入し直す流れ
離婚後に就職して国民健康保険から健康保険に切り替える場合の手続きを説明します。
まず勤務先に「健康保険資格取得届」を提出し、健康保険に加入します。
勤務先から「健康保険資格取得証明書」を受け取ったら、市区町村役場で国民健康保険の脱退手続きを行いましょう。
国民健康保険の脱退手続きが遅れると、保険料の二重払いになる可能性があるので注意が必要です。
子どもがいる場合は、あなたの健康保険の扶養に入れることも検討しましょう。
扶養に入れる条件として、子どもの年収が130万円未満であることなどの条件があります。
国民健康保険から健康保険への切り替えで特に注意すべきことは以下の通りです。
- 国民健康保険の脱退手続きを忘れないこと
- 健康保険の扶養に入れる家族がいる場合は扶養追加の手続きも行うこと
- 国民健康保険の保険料に未払いがある場合は精算しておくこと
- 高額療養費の申請中の場合は途中経過を確認しておくこと
健康保険の切替え時は保険証の空白期間が生じないよう、計画的に手続きを進めることが大切です。
子どもの扶養はどう決める?健康保険・養育費の負担は?
離婚後、子どもの扶養に関する取り決めは将来のトラブルを防ぐ重要なポイントです。
健康保険や税金面での扶養と、実際の養育費負担は別の問題として考える必要があります。
子どもの健康保険はどうなるか
子どもの健康保険は、基本的に親権者が加入している保険に入ることが一般的です。
ただし、親権と扶養は法律上別の概念であるため、必ずしも親権者が扶養義務者になるわけではありません。
例えば、母親に親権があっても、父親の健康保険に子どもを入れることは可能なケースがあります。
子どもにとって最も有利な選択をするため、両親の健康保険の条件を比較検討しましょう。
会社員の親の健康保険は保険料負担が少ないケースが多く、医療費助成制度も充実しています。
国民健康保険に比べて付加給付があるなど、子どもにとってのメリットが大きい場合もあります。
| 健康保険の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 会社の健康保険 | ・保険料負担が少ない ・付加給付がある場合が多い | ・扶養条件を満たす必要がある ・手続きが複雑な場合がある |
| 国民健康保険 | ・条件に関わらず加入できる ・手続きがシンプル | ・保険料負担が大きい ・付加給付がない |
健康保険の選択は、子どもの将来的な医療費負担も考慮して決めることが大切です。
なお、子どもが就職するなど経済的に自立するまでは、扶養関係を維持できる場合が多いです。
子どもの養育費の負担方法
養育費は、子どもの食費、教育費、医療費など生活全般にかかる費用を指します。
親権者でない親も、子どもが成人するまで養育費を支払う義務があります。
養育費の金額は、支払う側の収入や子どもの年齢、人数などを考慮して決めるのが一般的です。
裁判所が定めた養育費の算定表を参考にする方法もありますが、あくまで目安です。
養育費は月々の定期支払いが基本ですが、まとめて一括払いする方法もあります。
養育費の取り決めは、公正証書にしておくことで法的な強制力が生まれます。
万が一支払いが滞った場合でも、強制執行などの法的手段を取りやすくなるメリットがあります。
具体的な養育費の相場は以下のような目安があります。
| 子どもの年齢 | 養育費の目安(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 0〜5歳 | 3〜5万円 | 乳幼児期 |
| 6〜11歳 | 4〜6万円 | 小学生 |
| 12〜14歳 | 5〜7万円 | 中学生 |
| 15〜18歳 | 6〜8万円 | 高校生 |
| 19〜22歳 | 7〜10万円 | 大学生など(合意があれば) |
養育費は子どもの成長に伴い増加する傾向にあるため、見直し条項を設けておくと安心です。
また、扶養控除を受ける親と養育費を支払う親が異なる場合もあるため、離婚協議の段階でしっかり話し合いましょう。
親権者が再婚しても、実の親の養育費支払い義務は継続するのが原則です。
養育費の不払いは子どもの権利を侵害する行為であり、法的責任が問われる可能性もあります。

離婚前に決めるべき!子どもの親権と扶養のルール
離婚を考える際、子どもがいる場合は親権と扶養について事前にしっかり話し合っておくことが重要です。
感情的になりがちな離婚協議ですが、子どもの将来のためには冷静な判断が求められます。
子どものために適切な養育費を決めることが重要
養育費は子どもの成長に必要な費用であり、親の義務として適切に定めるべきものです。
養育費の金額は子どもの年齢やライフステージに応じて変動するため、将来的な見直し条項も含めて取り決めましょう。
離婚届だけでは養育費の取り決めに法的効力はないため、公正証書の作成がおすすめです。
公正証書があれば、万が一支払いが滞った場合でも強制執行ができます。
養育費の金額を決める際は、以下のような要素を考慮するとよいでしょう。
- 支払う側の収入と支払い能力
- 子どもの年齢と今後の教育費
- 子どもの人数
- 特別な事情(病気や障害など)
- 親権者の就労状況と収入
親権と養育費は別の問題です。親権を持たない親でも養育費を支払う義務があります。
逆に、親権者が再婚しても、実の親の養育費支払い義務は通常継続します。

養育費以外の扶養に関する取り決めのアドバイスを得る方法
養育費以外にも、扶養に関して決めておくべき事項がいくつかあります。
専門家のアドバイスを得ることで、将来のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
扶養に関する相談は、法律の専門家である弁護士や、家庭問題に詳しい専門家に依頼するのがベストです。
無料で相談できる公的機関もあるので、積極的に活用しましょう。
具体的な相談先としては以下のような選択肢があります。
| 相談先 | 特徴 | サポート内容 |
|---|---|---|
| 法テラス | 法律相談が無料または低額 | 法的アドバイス、弁護士紹介 |
| 弁護士事務所 | 専門的なアドバイス | 公正証書作成、交渉代行 |
| 家庭裁判所 | 調停サービスあり | 養育費の調停、履行勧告 |
| 自治体の相談窓口 | 地域によりサービス内容が異なる | 生活相談、各種手続き案内 |
| 母子支援団体 | 同じ立場の人の経験が聞ける | 生活支援情報、心理的サポート |
養育費以外にも、面会交流の頻度や方法、教育方針、進学時の費用負担なども話し合っておくと安心です。
特に、進学費用やイベント時の特別出費についてはトラブルになりやすいため、事前の取り決めが重要です。
離婚後の税金面でのメリットを最大化するために、扶養控除をどちらが受けるかも検討しましょう。
離婚は大人同士の問題ですが、子どもの権利と利益を最優先に考えることが何より大切です。

離婚で扶養から外れる具体的なデメリット
離婚によって扶養から外れることで、経済的な負担が大幅に増加する可能性があります。
特に専業主婦だった方は、離婚後の生活費を考える上で事前に把握しておくべき重要な要素です。
所得税・住民税の負担増加
配偶者控除(38万円)が受けられなくなるため、元配偶者の税負担が年間で数万円から十数万円増加する可能性があります。
この増税分は間接的に養育費の減額要因となる場合もあるため、離婚協議時に考慮しておくことが大切です。
健康保険料の自己負担
国民健康保険に加入する場合、前年の所得に応じて保険料が決まります。
専業主婦で所得がなかった場合でも、年間2~3万円程度の保険料負担が発生します。
パートなどで収入がある場合は、さらに高額になる可能性があります。
| 年収 | 国民健康保険料の目安(年額) |
|---|---|
| 所得なし | 約2~3万円 |
| 100万円 | 約8~12万円 |
| 150万円 | 約12~18万円 |
| 200万円 | 約18~25万円 |
国民年金保険料の支払い義務
厚生年金の第3号被保険者から第1号被保険者への変更により、月額16,980円(令和6年度)の国民年金保険料を自己負担する必要があります。
年間では約20万円の新たな負担となるため、離婚後の家計に大きな影響を与えます。
会社の福利厚生制度が使えなくなる
元配偶者の勤務先の福利厚生制度(健康診断、保養所、各種割引など)が利用できなくなります。
子どもも含めて、これまで受けていた様々なサービスが受けられなくなる可能性があります。
よくある質問
離婚時の扶養に関して多くの方が疑問を持たれています。ここでは、よくいただく質問についてお答えします。
まとめ
離婚時の扶養の問題は、税金や健康保険、養育費など多岐にわたります。
扶養控除は税金負担を軽減できる重要な制度で、条件を満たせば離婚後も子どもを扶養に入れることが可能です。
健康保険の切り替え手続きは離婚後すみやかに行い、空白期間が生じないよう注意しましょう。
子どもの扶養に関しては、親権と扶養は別の問題であることを理解し、子どもにとって最も有利な選択をすることが大切です。
養育費は親としての義務であり、金額や支払い方法を公正証書にしておくことで将来のトラブルを防げます。
離婚は大人同士の問題ですが、子どもの権利と利益を最優先に考えた判断と取り決めを心がけましょう。
離婚による扶養の変更は、あなたと子どもの生活に大きな影響を与えます。一人で抱え込まず、まずは専門弁護士に状況をご相談ください。適切なアドバイスで、経済的な負担を最小限に抑えることができます。扶養・養育費問題に強い弁護士への無料相談はこちら