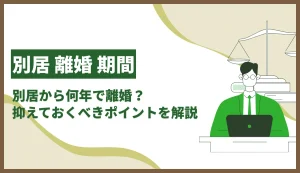「離婚したいけどできない」を完全解決|緊急度別 5つの対処法とは

「離婚したいけどできない」と悩んでいませんか?経済的な不安や子どもへの影響、配偶者の拒否、DVやモラハラの恐怖など、離婚を望んでいても様々な障壁に直面することがあります。
実は離婚したくてもできない理由には、緊急度に応じた適切な対処法があるのです。
緊急度の高い問題(配偶者の拒否、DV・モラハラ)から緊急度の低い問題(有責配偶者の立場)まで、状況に応じた解決策を知ることが重要です。
離婚に踏み切れずに苦しい毎日を過ごしている方や、どうしたら前に進めるのか見当がつかない方のために、段階別の具体的な解決策をご紹介します。
当記事では離婚したいけどできない状況から抜け出すための実践的なアドバイスと、離婚できないまま我慢を続けた場合に起こりうる深刻なリスクについて解説していきます。
一人で抱え込まずに、あなたの状況に合った解決法を見つけていきましょう。
離婚できない5つの理由と緊急度別対処法
結婚生活に行き詰まり、離婚を考えても様々な理由で踏み出せないケースは珍しくありません。多くの方が「離婚したいけどできない」と悩んでいます。
実際に離婚を決意しても、経済的な問題や子どもの存在、相手の反対などによって前に進めないことがあるのです。しかし、どんな状況にも必ず解決策はあります。
まずは離婚を踏み出せない理由を理解し、緊急度に応じた適切な対処法を知ることが重要でしょう。離婚できない理由を緊急度別に分類し、それぞれに最適な解決策をご紹介します。
それでは、離婚したくてもできない理由とその解決策について詳しく見ていきましょう。

【緊急度:高】配偶者が離婚に応じてくれない
離婚を拒む理由は様々です。配偶者に対する愛情の深さから夫婦関係の修復を希望している場合、離婚後に子どもたちと離れて暮らす寂しさを恐れている場合、財産分与や慰謝料などの経済的負担を避けたい場合、そして離婚後の生活が不安定になることを恐れ、現状を維持しようとする場合などがあります。
このような場合、離婚の話し合いが平行線をたどることが多くスムーズな解決が困難になります。
対処法の優先順位
相手が離婚に応じない場合、まずは別居して距離を置くことをおすすめします。別居によって冷静な判断ができるようになり、お互いの関係を見つめ直す機会になります。
別居には以下のメリットがあります。
- 感情的な対立の回避
- 冷静な話し合いの環境づくり
- 婚姻関係破綻の客観的証拠
- 将来の裁判での有利な材料
別居中も生活費や養育費などの取り決めは必要ですので、これらについて書面で合意しておくと良いでしょう。別居について詳しくはこちらをご確認ください。
離婚交渉は弁護士に依頼することで、感情的にならずに進められます。弁護士は法的な観点から適切なアドバイスをしてくれるため、離婚問題の解決が円滑に進むことが多いです。
- 法的根拠に基づいた交渉
- 感情的対立の回避
- 専門的な書面作成
- 相手への心理的プレッシャー
相手が離婚に応じない場合でも、弁護士に依頼すれば調停や裁判など次のステップに進む準備もスムーズに行えます。離婚弁護士の選び方についてはこちらをご参照ください。
協議離婚が難しい場合、次のステップとして家庭裁判所で離婚調停を申し立てることが考えられます。離婚調停では、調停委員が夫婦の間に入って双方の話し合いをサポートしてくれます。
調停委員は中立的な第三者の立場から公正に問題を解決しようと努めるため、感情的な対立を避けながら、冷静な話し合いが進められることが期待されます。相手が強く離婚を拒否している場合でも、調停委員の説得によって解決に至ることも少なくありません。
離婚調停の詳しい流れはこちらでご確認いただけます。
調停でも解決しない場合、最終的には離婚裁判を行うことになります。離婚調停において話し合いを重ねても合意に至らない場合には、離婚調停は不成立となります。
離婚裁判では、離婚原因の有無、財産分与、慰謝料といった法律的な問題を詳細に審理し、その結果、裁判所が判決を出すことで終局的な解決を目指します。
裁判離婚について詳しくはこちらをご覧ください。
解決実績データ
離婚成立までの期間(最高裁判所司法統計より)
- 協議離婚:届出時点で成立(手続き期間:1-3ヶ月)
- 調停離婚:平均6-12ヶ月
- 裁判離婚:平均12-18ヶ月
出典:最高裁判所「司法統計」
離婚件数の推移(厚生労働省統計より)
- 令和4年度の離婚件数:179,096組
- 協議離婚の割合:約88%
- 調停・裁判離婚の割合:約12%
出典:厚生労働省「令和4年人口動態統計月報年計(概数)の概況
【緊急度:高】DVやモラハラで切り出せない
配偶者のDVやモラハラが怖くて離婚の話を切り出せないケースは深刻な問題です。また、離婚を切り出せたとしても、話し合いにならないばかりか、高圧的な説得や暴力を受けて離婚を諦めてしまう人もいます。
安全確保を最優先とした対処法
DVやモラハラの証拠収集は、安全を最優先に行う必要があります:
- 怪我の写真撮影(日付入り)
- 診断書の取得
- 録音・録画(相手に気づかれないよう注意)
- 日記による記録
- 信頼できる人への相談記録
モラハラの証拠収集について詳しくはこちらをご確認ください。
以下の順序で専門機関に相談することをおすすめします:
- 配偶者暴力相談支援センター
- 24時間対応の相談窓口
- 緊急時の一時保護
- 法的手続きのサポート
- 警察への相談
- 生命の危険がある場合は迷わず110番
- 被害届の提出
- 接近禁止命令の申立て支援
- 弁護士への相談
- 法的手続きの代行
- 安全な離婚手続きの実施
- 慰謝料請求のサポート
接近禁止命令について詳しくはこちらをご参照ください
いざという時のために以下の準備をしておきましょう:
- 避難先の確保(実家、友人宅、シェルターなど)
- 必要最小限の荷物をまとめる
- 重要書類のコピー保管
- 緊急時の連絡先リスト作成
- 預金の一部を別口座に移動
DV防止法に基づく保護命令の申立てを検討しましょう:
- 接近禁止命令
- 退去命令
- 子への接近禁止命令
- 親族等への接近禁止命令
このような場合、一人で対応するのは困難なため、警察に相談し、相手との交渉を弁護士に任せることが必要です。
DV離婚の詳しい手続きはこちらでご確認いただけます。
【緊急度:中】経済的不安で踏み切れない
離婚したいけどできない最大の理由として、「経済的な不安」が挙げられます。特に専業主婦や収入の少ない配偶者にとって、経済的自立への不安は大きな障壁になります。
結婚生活では配偶者の収入に依存していた場合、離婚によってその収入源を失うと生活が立ち行かなくなる恐れがあるでしょう。離婚後の生活費や住居費、子どもの養育費などを考えると、経済的な見通しが立たないことが離婚を躊躇する大きな要因になります。
しかし、経済的な問題も適切な準備と対策によって解決できます。離婚を決意したら、まずは自分の経済状況を把握し、具体的な対処法を考えていきましょう。
段階別解決プラン
離婚を考え始めたら、まず最初に行うべきことは情報収集です。
- 児童扶養手当や児童手当などの経済的支援
- 自治体独自の支援制度(住宅支援、就労支援、医療費助成など)
- 母子家庭向けの各種減免制度
離婚を考えている段階から、市区町村の福祉課や相談窓口で利用可能な支援制度について情報収集しておきましょう。シングルマザーの手当について詳しくはこちらをご確認ください。
離婚後の収入シミュレーション
- 就労による収入見込み
- 養育費の受給額
- 各種手当の支給額
- 生活費の詳細な計算
実家サポートの可能性確認 離婚する際、頼れる実家があれば一時的でも迷わず頼りましょう。子どもを実家で預かってくれる場合、再就職する際も有利に動きます。一定のお金がたまるまで、子どもがある程度大きくなるまででもいいので、実家に身を寄せられないかそれとなく確認しておきましょう。
◆就職活動・資格取得
離婚後、女性の生活がうまくまわっていくかどうかは、経済的に自立できるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。そのため、離婚の際定職についていなかった場合は、生計を立てられる仕事を見つけることが重要です。
子どもが幼く保育園にも預けられず、すぐに働くのが難しい場合は、就職に有利になる資格を取ったり、特技があればネットを通じて自分の技術を売ったりセルフプロデュースを行いましょう。
何から始めていいのかわからない場合、ハローワークに相談しましょう。職業訓練所などでは、給付を受けながら就職するための知識を得ることが可能です。
- 保育園の申込み
- 学童保育の確認
- 実家や親族のサポート体制
- 一時保育の利用方法
◆貯金の準備
離婚後には、生活費や住居費、引っ越し費用などが必要になるため、一定の資金を確保することが非常に重要です。家計を見直し、節約できる部分を探して貯金を増やす努力をしましょう。
また、生活費や教育費、将来的な出費を予測し、それに見合った貯金目標を設定しましょう。計画的に貯金を進めることで、離婚後の生活を安定させることができます。
ただし、同居中に貯めた預貯金は財産分与の対象となりますので、その点は留意しましょう。
- 財産分与の内容
- 養育費の金額と支払方法
- 面会交流の取り決め
- 慰謝料の有無と金額
また、養育費の取り決めをしっかり行い、確実に受け取れるようにすることも重要です。公正証書を作成するなど、法的な効力のある形で取り決めを行いましょう。養育費について詳しくはこちらをご確認ください。
◆弁護士相談
経済的に不利にならないよう、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
◆離婚協議の開始
準備が整ったら、配偶者との具体的な話し合いを始めましょう。
母子家庭向け支援制度の活用
子どもがいる場合、離婚後は母子家庭(または父子家庭)として様々な支援制度を利用できます。
- 児童扶養手当:月額最大44,140円(2025年度)
- 児童手当:年齢に応じて月額10,000円〜15,000円
- 医療費助成:18歳まで医療費が無料または減額
- 住宅手当:自治体により月額5,000円〜20,000円
- 就学援助:学用品費や給食費の支援
母子家庭の支援制度について詳しくはこちらをご参照ください。
【緊急度:中】子どもへの影響を心配している
子どもがいる家庭では、「子どものために我慢すべき」という考えから離婚を踏みとどまるケースが少なくありません。子どもの心理的ダメージや成長への影響を心配する気持ちは自然なことです。
特に子どもが小さい場合、親の離婚が与える影響を懸念して離婚を躊躇することがあります。しかし、不幸な夫婦関係の中で育つことも子どもにとって大きなストレスとなり、健全な家族関係のモデルを示せなくなる可能性があります。
夫婦間の緊張や争いが日常的にある家庭環境は、子どもの心理的発達にも悪影響を及ぼすことが研究でも明らかになっています。子どものためを思うなら、問題のある結婚生活を続けるより適切に離婚を進め、子どもにとって安定した環境を整えることも選択肢の一つです。
年齢別対応ガイド
未就学児(0-6歳):環境変化への適応
この年齢の子どもは環境変化への適応力が比較的高い時期です。
- 安定した日常ルーティンの維持
- 面会交流の重要性を理解する
- 保育園・幼稚園との連携強化
- 愛情表現を増やす
未就学児の場合、子どもの前での夫婦喧嘩は絶対に避け、相手の悪口も言わないよう細心の注意が必要です。また、引っ越しなど生活環境の急激な変化は子どもに大きなストレスを与えるため、可能な限り最小限に抑えることが重要です。保育園や幼稚園の先生には状況を適切に伝え、子どもの様子を注意深く見守ってもらいましょう。
小学生(7-12歳):説明責任の重要性
この年齢になると、ある程度の理解力があるため、適切な説明が必要です。
- 年齢に応じたわかりやすい言葉で説明
- 子どもに責任がないことを明確に伝える
- 両親の愛情は変わらないことを強調
- 今後の生活について具体的に説明
学校環境の維持も重要な要素です。転校の必要性については慎重に検討し、やむを得ない場合は担任教師と十分な情報共有を行いましょう。友人関係への配慮も忘れずに、学習環境が安定するよう配慮することが大切です。必要に応じて、スクールカウンセラーや専門のカウンセラーに相談することも検討しましょう。
中高生(13-18歳):本人の意思尊重
思春期の子どもには、より慎重な対応が必要です。
- 本人の意思や感情を尊重する
- 進学への影響を最小限に抑える
- 親権者選択の可能性について説明
- 将来への不安に寄り添う
進学への影響を最小限に抑えるため、受験時期との兼ね合いを十分考慮することが重要です。学費の確保について具体的に説明し、進路選択に悪影響を与えないよう配慮しましょう。この年齢では、子ども自身が親権者を選択できる可能性もあるため、本人の意思を最大限尊重する姿勢が求められます。
離婚が子どもに与える影響について詳しくはこちらをご確認ください。
【緊急度:低】有責配偶者としての立場
離婚原因を自分が作ってしまった「有責配偶者」の場合、離婚請求が認められにくいというハードルがあります。不倫や暴力など婚姻関係を破綻させた原因を作った側からの離婚請求には、裁判所も慎重な判断を下すことがあります。
これは「クリーンハンズの原則」と呼ばれるもので、自分が原因を作っておきながら離婚を請求するのは認められにくいという考え方です。
ただし、婚姻関係が完全に破綻している場合や、長期間の別居がある場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースも増えています。最高裁判所の判例では、5年以上の別居がある場合や、未成熟子がいない場合などは、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性が高くなっています。
3つの要件クリア戦略
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、以下の3つの要件をクリアする必要があります。
要件1:長期別居の実現(5-7年目安)
有責配偶者として離婚を求める場合、まずは別居期間を設けることが重要です。一般的に、3〜5年以上の別居期間があれば、裁判所も婚姻関係の破綻を認めやすくなります。
別居する際は、別居開始日を明確にし、証拠を残しておくことをおすすめします。例えば、転居届や公共料金の契約変更など、客観的に別居の事実が確認できる書類を保管しておきましょう。
別居期間中は感情的な対立を避け、冷静に離婚に向けた準備を進めることが大切です。
要件2:十分な経済的補償の提示
有責配偶者として離婚を求める場合、もう一つ重要なのは、残される配偶者や子どもの生活を保障することです。十分な財産分与や養育費の支払いを提案することで、離婚への同意を得やすくなります。
- 通常よりも多めの財産分与を提案
- 長期間の養育費支払いを約束
- 住居の問題への配慮(住み慣れた家に住み続けられる取り決め)
- 相当額の慰謝料の支払い
ただし、過度な要求には応じる必要はありません。弁護士に相談しながら、適切な範囲での解決策を探ることをおすすめします。
要件3:未成熟の子どもがいない
有責配偶者からの離婚請求が認められるためのもう一つの条件は、未成熟の子どもがいないことです。未成熟の子どもとは、経済的に自立していない未成年の子どものことを指します。
未成熟の子どもがいる場合、離婚による影響が大きいため、有責配偶者による離婚請求が難しくなります。
離婚できない状態で我慢を重ねると発生しうるリスクとは?
「離婚したいけどできない」と悩みながら不幸な結婚生活を続けることは、想像以上に大きなリスクを伴います。
表面的な家庭の平和を保つために我慢を続けることで、心と体に様々な悪影響が生じる可能性があるのです。
離婚できないまま年月が過ぎていくと、後悔や不満が積み重なり、精神的な健康を損なうことも少なくありません。
また、不仲な夫婦関係は子どもの成長にも悪影響を及ぼすため、「子どものため」と我慢を続けることが必ずしも良い選択とは言えないでしょう。
ここでは、離婚したくてもできない状態で我慢を続けた場合に生じるリスクについて詳しく見ていきます。
- 若い時に離婚しておけばと後悔する気持ち
- 不要な出費や介護に伴う課題
- 子どもとの関係悪化につながる可能性
若い時に離婚しておけばと後悔する気持ち
離婚を躊躇しているうちに時間だけが過ぎ、「若いうちに決断しておけば良かった」と後悔するケースは非常に多いです。
年齢を重ねるほど、再出発のハードルは高くなりがちです。
特に30代、40代で離婚を迷っている方は、この先の人生設計を考えると早めの決断が望ましいこともあります。
若いうちに離婚を決断すれば、キャリア形成の時間も十分に確保でき、経済的な自立もしやすくなります。
また、子どもがいる場合も、小さいうちの方が環境の変化に適応しやすいとされています。
「もう少し様子を見よう」と先延ばしにすることで、結果的に貴重な時間を失ってしまうことを認識しましょう。
年齢を重ねるにつれて、就職の選択肢が狭まったり、体力的な問題が出てきたりすることも考慮に入れるべきです。
不要な出費や介護に伴う課題
離婚したいと思いながら生活を続けると、不必要な出費が続くことになります。
愛情がなくなった関係を維持するための費用は、将来の自立のための貯蓄に回せるはずのお金です。
また、年を取るにつれて配偶者の介護問題も視野に入れる必要が出てきます。
愛情がない状態で配偶者の介護を担うことは、想像以上に大きな精神的・肉体的負担となるでしょう。
特に不仲な関係が長く続いている場合、その負担はさらに大きくなります。
「離婚したいけどできない」と悩みながら年月を過ごし、結局は介護の問題に直面するケースも少なくありません。
若いうちに離婚して新たな人生を歩み始めるか、このまま続けて将来の介護も視野に入れるか、長期的な視点で判断することが重要です。
子どもとの関係悪化につながる可能性
多くの親が「子どものために離婚を我慢している」と考えますが、不幸な家庭環境は子どもの心の発達に悪影響を及ぼし、親子関係の悪化を招くことがあります。
子どもは親の不満や緊張関係に敏感です。
表面上は平静を装っていても、子どもは家庭内の雰囲気を敏感に感じ取っています。
親が我慢を重ねている様子を見て育った子どもは、「自分のために親が不幸になっている」と感じ、自己肯定感の低下や罪悪感を抱くことがあります。
また、不健全な夫婦関係を目の当たりにして育つことで、子ども自身の将来の人間関係にも悪影響が及ぶ可能性があります。
子どものためと思って我慢を続けることが、結果的に子どもの心に深い傷を残してしまうこともあるのです。
離婚後も良好な親子関係を維持しながら、子どもが健全に成長できる環境を整えることが大切です。
愛情と尊重に満ちた片親家庭の方が、不和や対立が続く両親がいる家庭よりも、子どもの心の健康に良い影響を与えるという研究結果もあります。

離婚が思い通りに進まないときは弁護士にサポートしてもらおう
「離婚したいけどできない」と悩んでいる状況では、専門家の力を借りることが解決への近道となります。
特に弁護士のサポートは、複雑な離婚問題を解決する上で非常に心強い味方になるでしょう。
弁護士は法律の専門家として、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスを提供してくれます。
また、感情的になりがちな離婚交渉を冷静に進める役割も果たします。
離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、これまで見えていなかった解決策が見つかることも少なくありません。
例えば、相手が離婚に応じない場合の法的手続きや、有責配偶者としての離婚請求の可能性、財産分与や養育費の適正な金額など、専門的な観点からアドバイスを受けられます。
弁護士費用が心配な方は、初回無料相談を実施している法律事務所や、法テラスの民事法律扶助制度の利用も検討してみましょう。
離婚は人生の大きな岐路です。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、より良い未来に向けて進んでいくことをおすすめします。
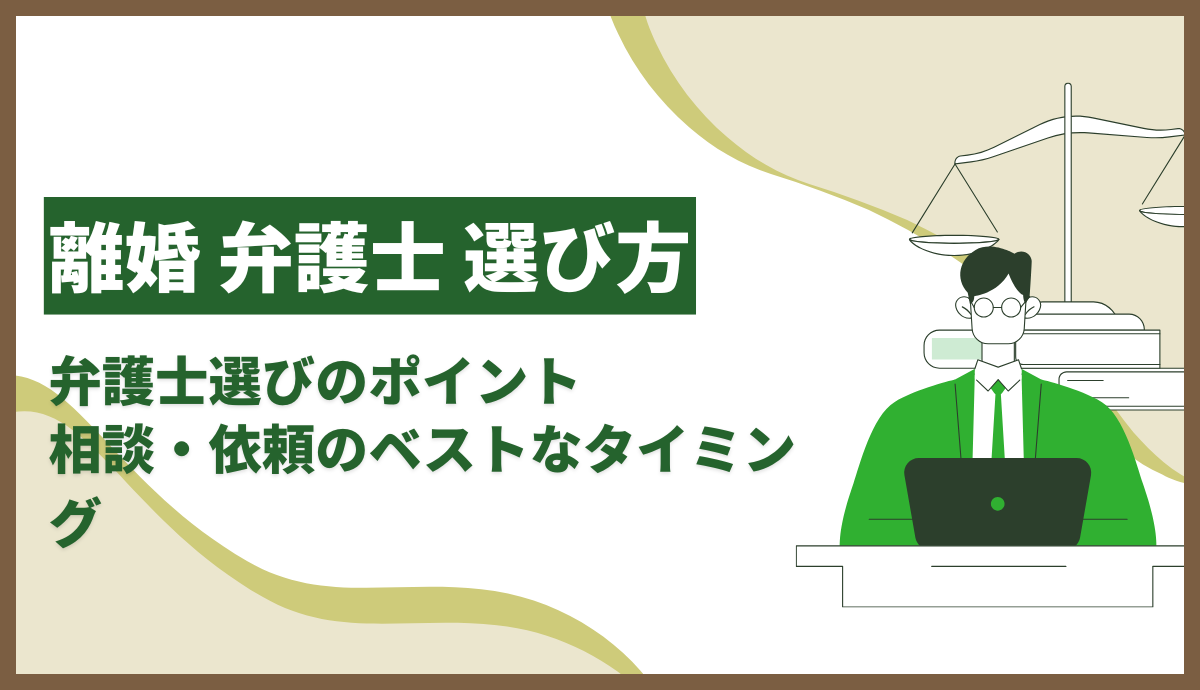
よくある質問
ここでは、「離婚したいけどできない」と悩んでいる方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
同じような悩みを抱えている方の参考になれば幸いです。
- 離婚したいけどできない女性が経済的に自立するにはどうしたらいいですか?
- 子供がいる場合、離婚したいのに離婚できない理由と解決策を教えてください。
- お金がない状況で離婚したい場合の生活保障について教えてください。
- 離婚拒否し続ける妻や旦那に対してどのように協議離婚を進めるべきですか?
- 男性が離婚したいけど踏み切れないケースの特徴はありますか?
- 離婚できないことによるストレスへの対処法を教えてください。
- 日本での離婚したいのに離婚できない人の割合はどのくらいですか?
- 弁護士に相談せずに離婚問題を解決する方法はありますか?
まとめ
「離婚したいけどできない」と悩む状況は、経済的な不安、子どもへの影響、相手の反対、有責配偶者としての立場など、様々な理由から生じます。
しかし、どんな状況にも必ず解決策は存在します。
不幸な結婚生活を我慢し続けることは、精神的な健康を損なうだけでなく、将来的には後悔や不要な出費、子どもとの関係悪化などのリスクも伴います。
離婚を考えている方は、まず自分の状況を客観的に把握し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
一人で抱え込まず、適切なサポートを受けながら、より良い未来に向けて一歩を踏み出しましょう。
どのような困難があっても、あなたらしい人生を取り戻すための選択肢は必ず存在します。
自分自身と大切な人たちのために、勇気を持って前に進むことが大切です。