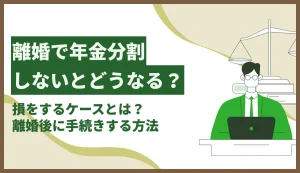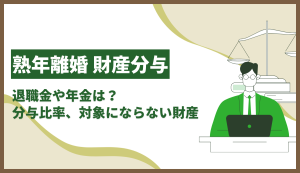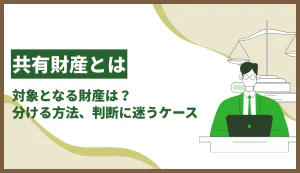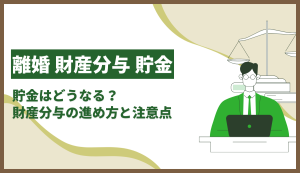離婚時の住宅ローンと財産分与|知っておくべき基本知識と処理方法
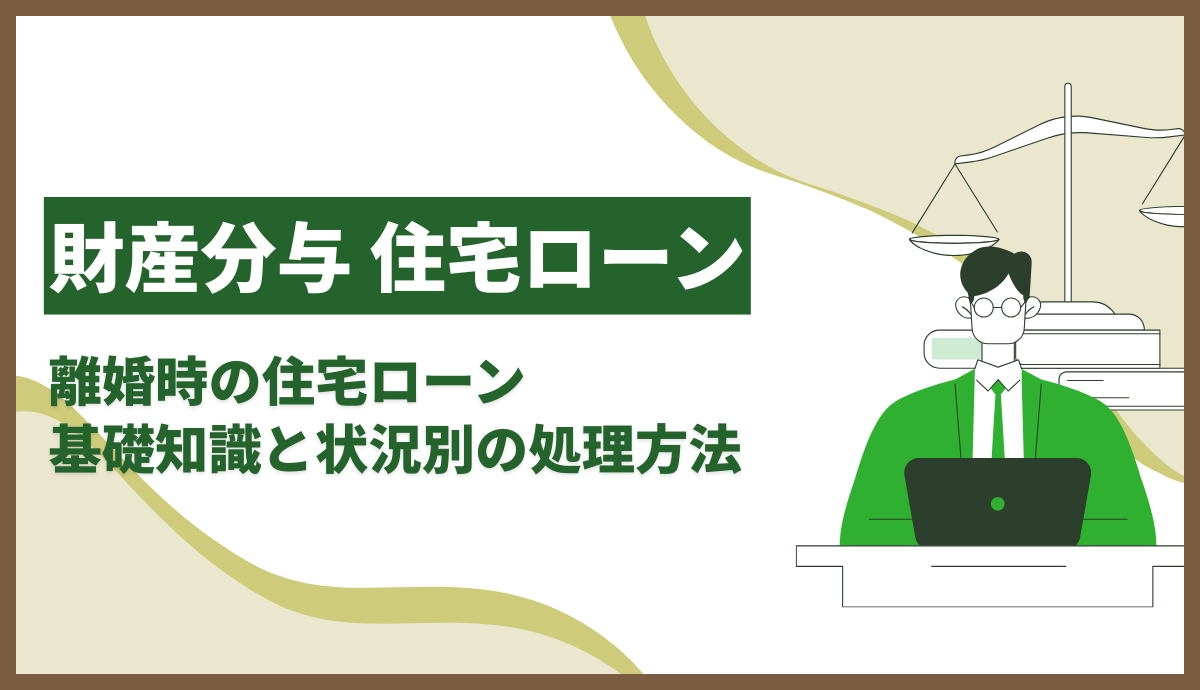
「離婚したいけれど、住宅ローンが残っている」そんな不安を抱えている方は少なくありません。
財産分与において住宅ローンをどう扱うべきか、多くの方が頭を悩ませています。
住宅ローンがある家を売却すべきか、誰が住み続けるのか、ローンの支払い責任は誰にあるのかなど、考えるべき点は数多くあります。
離婚時の住宅ローンの取り扱いは、将来の生活基盤に大きく影響するため、正しい知識を持っておくことが重要です。
この記事では、離婚時の住宅ローンに関する財産分与について、オーバーローンやアンダーローンの違いから、様々な状況における対処法まで詳しく解説していきます。
専門的な知識がなくても理解できるよう、具体例を交えながら分かりやすく説明していきます。
どうぞ最後までお読みいただき、あなたの状況に合った最適な選択肢を見つけてください。
住宅ローンの財産分与に関する基本知識
離婚時の財産分与で最も頭を悩ませるのが、住宅ローンが残っている自宅の取り扱いです。
まずは住宅ローンと財産分与の関係について基本的な知識を押さえておきましょう。
住宅ローンは財産分与に含まれるか?折半する?
住宅ローンそのものは「債務」であり、法律上は財産分与の対象ではありません。
しかし、不動産という「資産」と住宅ローンという「債務」は一体として考える必要があります。
財産分与の対象となるのは、住宅の「正味価値」(資産価値からローン残高を差し引いた金額)です。
例えば、現在の住宅の価値が3,000万円で住宅ローン残高が2,000万円の場合、財産分与の対象となるのは差額の1,000万円となります。
このような「住宅の価値>ローン残高」の状態を「アンダーローン」と呼びます。
反対に「住宅の価値<ローン残高」の状態は「オーバーローン」と呼ばれ、この場合は財産的価値がマイナスになるため、財産分与の対象とはなりません。
ただし、住宅ローンの名義人や連帯債務者の状況によって、離婚後の取り扱いは変わってきます。
住宅の所有権と住宅ローンの返済義務は別の問題なので、どちらも離婚時にしっかり話し合う必要があるでしょう。
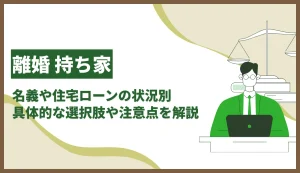
オーバーローンとアンダーローンの定義とその確認方法
住宅ローンの財産分与を考える際に重要なのが、「オーバーローン」と「アンダーローン」の区別です。
この違いによって、財産分与の方法や選択肢が大きく変わってきます。
| アンダーローン | 住宅の価値 > ローン残高 (財産価値がプラス) |
|---|---|
| オーバーローン | 住宅の価値 < ローン残高 (財産価値がマイナス) |
アンダーローンかオーバーローンかを判断するためには、まず現在の住宅の価値(時価)を知る必要があります。
住宅の時価を調べる方法としては、以下のような方法があります。
- 不動産会社に無料査定を依頼する
- 国税庁の「路線価」を参考にする
- 不動産鑑定士に依頼する(費用はかかるが正確)
そして、現在の住宅ローン残高は、ローンの契約先の金融機関に問い合わせれば確認できます。
アンダーローンの場合は住宅に財産的価値があるため、その価値を夫婦で分け合う必要があります。
一方、オーバーローンの場合は住宅に財産的価値がないため、財産分与の対象とはなりません。
しかし、オーバーローンでも住宅ローンの返済義務は残るため、返済をどうするかを決める必要があります。
住宅ローン支払いの責任は名義人にある
住宅ローンの返済責任は、基本的にローンの契約者(名義人)にあります。
離婚したからといって、ローン契約上の義務が自動的に変わることはありません。
住宅ローンの契約形態には主に以下の3つのパターンがあります。
| 単独名義 | 夫または妻のどちらか一方だけがローン契約者 |
|---|---|
| 連帯債務 | 夫婦両方がローン契約者となり、それぞれが返済義務を負う |
| ペアローン | 夫婦がそれぞれ別々にローンを組み、それぞれの収入に応じた金額を返済 |
離婚時に住宅ローンの支払いが滞ると、名義人の信用情報に傷がつき、将来的な借り入れにも影響します。
例えば、夫名義の住宅ローンで離婚後に妻が住み続ける場合でも、ローンの支払いが滞れば夫の責任となります。
また、連帯債務やペアローンの場合は、それぞれが自分の責任部分を支払う必要があるので注意が必要です。
住宅ローンの返済を止めると、最終的には競売にかけられる可能性もあります。
離婚協議の際には、住宅の取り扱いと合わせて、住宅ローンの支払い責任についても明確に決めておきましょう。
住宅を売却する場合の住宅ローンの処理方法
離婚時に住宅を売却するという選択肢は、住宅ローン問題を解決する最もシンプルな方法の一つです。
しかし、オーバーローンとアンダーローンでは売却後の対応が大きく異なります。
オーバーローンの物件売却後、残債は折半になる?
オーバーローンの住宅を売却すると、売却金額だけでは住宅ローンを完済できません。
この場合、残ったローン(残債)をどうするかが問題となります。
基本的に住宅ローンの残債は、ローン契約者が返済する義務を負います。
例えば、住宅が2,000万円で売却できたが、ローン残高が2,500万円だった場合、差額の500万円は残債として残ります。
このローンが夫名義だけなら、原則として夫が返済する義務があります。
連帯債務の場合は、夫婦それぞれの名義の割合に応じて残債の返済義務が生じます。
ただし、離婚協議で「残債を折半する」などの取り決めをすることは可能です。
金融機関はあくまでローン契約者に対して返済を求めるため、離婚協議の内容と関係なく名義人には返済義務が残ります。
そのため、残債の支払いについては公正証書などで明確に取り決めておくことが重要です。
アンダーローン物件の売却益、夫婦で折半する?
アンダーローンの住宅を売却した場合、売却代金からローン残高を差し引いた金額が売却益となります。
この売却益は、財産分与の対象となる夫婦の共有財産です。
法律上は、婚姻期間中に夫婦で協力して得た財産は、原則として平等に分ける「2分の1ルール」が適用されます。
例えば、住宅が3,500万円で売却でき、ローン残高が2,500万円の場合、売却益の1,000万円が財産分与の対象となります。
ただし、頭金や住宅購入資金に片方の親からの贈与や相続財産を充てていた場合など、特別な事情がある場合は別途考慮されます。
また、住宅の購入時期や婚姻期間なども考慮して、分け方が調整されることもあるでしょう。
いずれにしても、住宅の売却益の分け方について夫婦で合意しておくことが大切です。

住宅ローンが払えないときの任意売却
離婚を機に住宅ローンの支払いが困難になるケースは少なくありません。
そのような場合に検討できるのが「任意売却」という方法です。
任意売却とは、ローン滞納などで返済が困難になった場合に、債権者(銀行など)の同意を得て行う住宅の売却方法です。
任意売却には以下のようなメリットがあります。
- 競売よりも高値で売却できる可能性が高い
- 競売のような記録が残らず、信用情報への影響が少ない
- 引越し時期を調整できる
任意売却を検討する場合は、早めに金融機関に相談することが重要です。
また、任意売却を専門に扱う不動産会社や弁護士に相談するのも一つの方法でしょう。
ただし、任意売却しても住宅ローンが完済できない場合は、残債の返済義務が残ることに注意が必要です。
売却後も居住を継続するリースバック
住宅ローンの返済が難しくなったが、今の家に住み続けたいという場合に検討できるのが「リースバック」です。
リースバックとは、自宅を不動産会社などに売却した後、賃貸契約を結んで同じ家に住み続ける方法です。
離婚時の財産分与で特に考慮したいのは、子どもの環境を急に変えたくないというケースです。
例えば、夫婦で住んでいた家を売却し、母子が住み続けるために賃貸契約を結ぶといった方法が考えられます。
リースバックのメリットには以下のようなものがあります。
- 住宅ローンを完済できる
- 引っ越しの必要がない
- 子どもの環境を変えずに済む
ただし、賃料の支払いが必要になること、将来的にオーナーの都合で退去を求められる可能性があることなどのデメリットもあります。
リースバックを検討する場合は、信頼できる不動産会社を選び、契約内容をしっかり確認することが重要です。
名義人が家を出る場合|妻と子供が住み続ける方法は?
離婚後、子どもと妻が今の家に住み続けたいというケースは多いものです。
住宅ローンの名義人(多くの場合は夫)が家を出る場合、いくつかの選択肢があります。
住宅ローンの名義を妻に変更する手続きを行う
理想的な解決策の一つは、住宅ローンの名義を妻に変更することです。
しかし、これは一般的に考えられているより難しい手続きです。
住宅ローンの名義変更は実質的に「借り換え」であり、妻単独で新たなローンを組む必要があります。
つまり、妻が単独で住宅ローンの審査に通る必要があるのです。
住宅ローンの名義変更には、以下の条件をクリアする必要があります。
- 妻に安定した収入がある
- 年収や勤続年数などの審査基準を満たしている
- 返済負担率が基準内に収まる
もし妻が専業主婦だったり、パートタイムでの勤務だったりする場合、単独での住宅ローン審査に通るのは難しいでしょう。
また、名義変更には登記の変更や抵当権の設定などの手続きも必要で、諸費用もかかります。
住宅ローンの名義変更を検討する場合は、まず金融機関に相談し、可能性を確認することが大切です。
住宅ローンは夫名義で妻が返済を継続する
住宅ローンの名義変更が難しい場合、ローンは夫名義のままで妻が返済を続けるという方法もあります。
しかし、この方法には注意点がいくつかあります。
法的には、住宅ローンの支払い義務は名義人である夫にあるため、妻が支払いを滞らせると夫の信用情報に影響します。
また、夫が再婚して新たに住宅ローンを組みたい場合、すでにローンがあることで融資を受けられない可能性もあります。
このような方法を選ぶ場合は、以下のような対策が必要です。
- 妻が確実に返済できる見込みがあることを確認する
- 返済方法や万が一の場合の対応を公正証書で取り決める
- 定期的に返済状況を確認できる仕組みを作る
夫にとっては返済義務が残るリスクがありますが、妻と子供にとっては住み慣れた家に住み続けられるメリットがあります。
将来的なトラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談して適切な取り決めをすることが重要です。
夫は慰謝料や養育費の支払いの代わりとして住宅ローンを負担する
住宅ローンが夫名義のまま、夫が返済を続けるという選択肢もあります。
これは、慰謝料や養育費の一部として住宅ローンを負担するという形で合意するケースです。
住宅ローンの支払いを養育費や慰謝料の代わりとして認めることで、双方にメリットがある場合があります。
夫にとっては、自分名義の資産への支払いを続けることになるため、将来的な資産形成につながる可能性があります。
妻と子どもにとっては、住み慣れた家に住み続けられるという安心感があります。
ただし、この場合も以下のような点に注意が必要です。
- 住宅の所有権が最終的に誰に帰属するのかを明確にする
- ローン完済後の扱いについて取り決めておく
- 修繕費や固定資産税などの諸経費の負担者を決めておく
このような取り決めは、離婚協議書や公正証書にしっかりと明記しておくことが大切です。
住宅ローンを全額返済する
財産状況に余裕がある場合、離婚を機に住宅ローンを一括返済するという選択肢もあります。
これは最もスッキリとした解決方法と言えるでしょう。
住宅ローンを完済することで、住宅に関する金銭的な縛りがなくなり、清算がしやすくなります。
例えば、夫が貯金から住宅ローンを完済し、住宅の所有権を妻に譲渡するといった方法が考えられます。
また、親族からの援助や退職金などを活用して完済するケースもあります。
ローンを完済した後は、以下のような選択肢があります。
- 家を財産分与の対象として、妻の単独所有にする
- 夫の単独所有のままで、妻と子どもに使用させる
- 共有持分のまま維持し、将来的に売却する約束をする
いずれの場合も、所有権の移転には登記手続きや贈与税の問題なども関わってくるため、専門家に相談することをおすすめします。
名義人が居住を継続する場合の住宅ローン取扱い
住宅ローンの名義人が離婚後も家に住み続けるケースも少なくありません。
この場合、財産分与の観点からどのような選択肢があるのでしょうか。
住宅ローンの支払いを続ける
住宅ローンの名義人(多くの場合は夫)が家に住み続ける場合、基本的にはローンの支払いも続けることになります。
この状況では、家を出る配偶者(妻)への財産分与をどうするかが焦点となります。
アンダーローンの場合、住宅の正味価値(住宅の価値からローン残高を引いた金額)の半分を妻に支払うのが一般的です。
例えば、住宅の現在の価値が3,000万円で、ローン残高が2,000万円であれば、正味価値は1,000万円となります。
この場合、財産分与として妻に500万円を支払うことが考えられます。
ただし、一度に大きな金額を支払うのが難しい場合は、分割払いなどの方法も検討できます。
また、他の財産(預貯金や車など)と相殺する方法もあるでしょう。
いずれにしても、公平な財産分与を行うためには、住宅の適正な評価額を知ることが重要です。
住宅ローンの返済を完了する
財産状況に余裕がある場合、離婚を機に住宅ローンを完済するという選択肢もあります。
これによって、住宅に関する財産分与がシンプルになります。
住宅ローンを完済した場合、住宅の価値全体が財産分与の対象となり、その半分を妻に支払うことになります。
例えば、住宅の価値が3,000万円であれば、財産分与として妻に1,500万円を支払う計算になります。
貯金や退職金、親族からの援助などを活用してローンを完済するケースもあります。
ローン完済後は、名義変更や抵当権抹消の手続きも必要になるため、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
住宅ローンを完済することで、将来的な金銭トラブルを避けられるというメリットもあります。
ただし、大きな金額の支払いが必要になるため、資金計画をしっかり立てる必要があるでしょう。
住宅ローンの財産分与に注意すべきポイント
住宅ローンがある家を財産分与する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
これらを事前に理解しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
住宅売却には時間を要する
住宅を売却する場合、思ったより時間がかかることを理解しておく必要があります。
特に不動産市場の状況によっては、売却完了まで数ヶ月、あるいは1年以上かかることもあります。
離婚協議と並行して住宅売却の手続きを進める場合、この時間的なズレを考慮した計画を立てることが重要です。
住宅売却の一般的なスケジュールは以下のようになります。
| 不動産会社との契約 | 1〜2週間 |
|---|---|
| 買い手が見つかるまで | 1〜6ヶ月 |
| 売買契約から決済まで | 1〜2ヶ月 |
| 引き渡し手続き | 1週間程度 |
また、住宅の状態や立地によっては予想以上に売却価格が下がることもあるため、あらかじめ複数の不動産会社に査定を依頼するとよいでしょう。
住宅売却中の住宅ローンの支払いについても取り決めておく必要があります。
住宅ローンの名義変更は容易ではない
住宅ローンの名義変更は、一般的に考えられているよりもハードルが高いものです。
特に、収入の少ない配偶者に名義を変更する場合には注意が必要です。
住宅ローンの名義変更は基本的に「借り換え」の扱いとなり、新たなローン審査を受ける必要があります。
名義変更のためには、以下の条件をクリアしなければなりません。
- 安定した収入があること
- ローン審査基準を満たす信用情報があること
- 年齢や健康状態などの条件を満たすこと
- 返済負担率が一定以下であること
例えば、専業主婦や非正規雇用の場合、単独での審査通過は難しいことが多いです。
また、名義変更には登記費用や保証料など、さまざまな諸費用もかかります。
住宅ローンの名義変更を検討する場合は、まず金融機関に相談し、可能性を確認することが大切です。
住宅の名義を無断で変更することはできない
住宅の所有者名義を変更するためには、共有者全員の同意が必要です。
無断で名義変更をすることはできません。
住宅が共有名義の場合、片方の配偶者だけの意思で所有権を移転することはできないため、必ず協議が必要です。
また、住宅に抵当権が設定されている場合(多くの住宅ローンがこれに該当)、抵当権者(銀行など)の承諾も必要になります。
これは住宅ローン契約で「所有権の変更には銀行の承諾が必要」と定められていることが一般的だからです。
離婚による財産分与で住宅の名義を変更する場合でも、必ず正規の手続きを踏む必要があります。
無断での名義変更は、民事上、刑事上の責任を問われる可能性もあるため、絶対に避けるべきです。
名義変更の手続きは、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
連帯保証人・連帯債務者・ペアローンを維持したままでの離婚を避ける
離婚後も住宅ローンの連帯関係を継続することは、将来的に大きなトラブルの原因となりかねません。
可能な限り、離婚時にはこれらの関係を解消することをおすすめします。
連帯債務者や連帯保証人の立場を維持したまま離婚すると、元配偶者の返済状況によって自分の信用情報に傷がつくリスクがあります。
例えば、夫が連帯債務者、妻が債務者の住宅ローンで離婚した場合、妻が返済を滞らせると夫の信用情報にも影響が出ます。
また、将来的に新たな住宅ローンを組みたい場合にも支障が出る可能性があります。
連帯関係を解消する方法としては、以下のようなものがあります。
- 住宅を売却してローンを完済する
- どちらかが単独で借り換えを行う
- 金融機関と交渉して連帯保証人を外してもらう
ペアローンの場合は、それぞれが別々に借り入れているため、自分の返済分に集中することができますが、物件の共有状態は解消する必要があります。
いずれの場合も、専門家のアドバイスを受けながら進めることが大切です。

よくある質問
住宅ローンの財産分与に関して、多くの方が抱える疑問について簡潔に回答していきます。
離婚を考える中で、住宅ローンについての不安や疑問を解消する手助けとなれば幸いです。
- オーバーローンの住宅は財産分与の対象になりますか?
- 離婚後も妻が住宅ローンのある家に住み続ける方法を教えてください。
- 財産分与における住宅ローンの計算方法はどうなりますか?
- 夫名義の住宅ローンがある自宅に離婚後も住む場合の財産分与はどうなりますか?
- 住宅ローン控除は財産分与でどのように扱われますか?
- アンダーローンの不動産の財産分与に関する判例を教えてください。
- 離婚調停中に住宅ローンの支払いが滞った場合はどうなりますか?
- 住宅ローンのある共有名義の家を売却する時の税金について教えてください。
- 特有財産として取得した家の住宅ローンは財産分与の対象になりますか?
- 住宅がマイナス財産の場合、借金も含めて財産分与されますか?
まとめ
住宅ローンがある家の財産分与は、離婚時の大きな課題の一つです。
アンダーローンかオーバーローンかという状況によって、選択肢や対応方法が大きく異なります。
住宅を売却する、名義人が家を出る、名義人が住み続けるなど、さまざまなパターンに応じた対応方法があることを理解しておきましょう。
特に注意すべき点は、住宅ローンの名義変更の難しさや、連帯債務関係を解消することの重要性です。
将来のトラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら、明確な取り決めを行うことをおすすめします。
住宅ローンの財産分与は一筋縄ではいきませんが、適切な知識を持ち、冷静に話し合うことで、双方が納得できる解決策を見つけることができるでしょう。