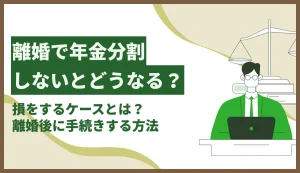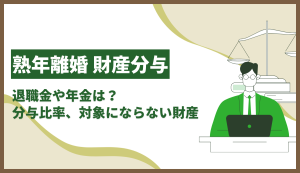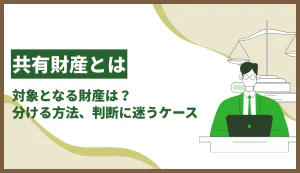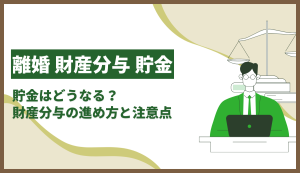財産分与の時効が5年に延長!知っておくべきポイントを詳しく解説

離婚が成立した後、財産分与について気になっていませんか?
特に「財産分与の時効」は、多くの方が知らないうちに請求権を失ってしまう重要なポイントです。
離婚後に財産分与を請求できる期間は法律で定められていて、この期間を過ぎると権利が消滅してしまいます。
「でも、いつまでに請求すればいいの?」「時効が過ぎたらもう何もできないの?」と不安に思う方も多いでしょう。
当記事では、財産分与の時効について詳しく解説し、請求権を守るために知っておくべき情報をお伝えします。
法律の知識がなくても理解できるよう、わかりやすい言葉で説明していきます。
時効に関する正しい知識を身につけて、あなたの権利を守りましょう。
財産分与の基本とは?
離婚するとき、夫婦の財産をどのように分けるかという問題が出てきます。
財産分与とは、結婚中に共同で築き上げた財産を、離婚時にお互いの貢献度に応じて分配する制度です。
例えば、妻が専業主婦だった場合でも、家事や育児で夫の仕事を支えていたという貢献が認められます。
基本的に財産分与の割合は夫婦の貢献度に応じて2:1から5:5の範囲で決められることが多いでしょう。
ただし、この割合は絶対的なものではなく、個々のケースや裁判所の判断によって変わってきます。
財産分与の対象となるのは「婚姻中に夫婦で協力して得た財産」であり、結婚前から持っていた財産や相続で得た財産は原則として対象外です。
共働き夫婦の場合、それぞれの収入や貯蓄が明確になっていても、基本的には婚姻期間中の蓄えは共有財産と見なされます。
「うちは共働きだから財産分与は関係ない」と思っている方もいますが、そういった考えは法的には通用しないケースが多いのです。
財産分与を受け取る権利は法律で定められていますが、この権利にも期限がある点に注意が必要です。

時効の基本とは?
財産分与の請求権にも「時効」という期限があることをご存じでしょうか?
時効とは、一定期間が経過すると権利の行使ができなくなる制度のことを指します。
財産分与の場合、以前は離婚成立後「2年間」という期限が設けられていました。
正確に言うと、この2年間の期限は「時効」ではなく「除斥期間」と呼ばれるものでした。
時効と除斥期間は似ていますが、権利が消滅するタイミングや条件が異なるため、区別して理解する必要があります。
財産分与の請求権については、2018年の民法改正により大きな変更がありました。
現在は離婚成立から「5年間」に延長されており、請求者にとってより有利になっています。
時効と除斥期間の異なる点
時効と除斥期間、どちらも「一定期間が過ぎると権利が消滅する」という点では似ていますが、重要な違いがあります。
時効は「権利を行使できる時から進行し、一定期間の経過で権利が消滅する制度」です。
一方、除斥期間は「権利の発生時から一定期間が経過すると、当然に権利が消滅する制度」になります。
つまり時効は中断や停止が可能ですが、除斥期間はいかなる理由があっても期間の延長ができないのです。
財産分与の請求権について、民法768条2項では「離婚の時から2年間」と規定されていました。
この期間は長らく「除斥期間」として扱われてきましたが、法改正により状況が変わっています。
①除斥期間には猶予や更新の制度が設けられない
時効と除斥期間の大きな違いの一つ目は、期間の延長可能性にあります。
時効には「中断」や「停止」という制度があり、一定の条件下で時効期間をリセットしたり、一時的に進行を止めたりすることができます。
例えば、裁判所に訴えを提起したり、相手が権利を認めたりした場合は時効が中断します。
一方で除斥期間にはこうした猶予制度がなく、期間が過ぎれば絶対的に権利が消滅してしまうという厳しい性質を持っています。
財産分与の場合、以前は除斥期間として扱われていたため、離婚から2年が過ぎると、どんな事情があっても請求できなくなっていました。
しかし現在は状況が変わっているので、後ほど詳しく説明します。
②除斥期間の場合は相手(請求される側)の意思に関わらず権利が失われる
時効と除斥期間の二つ目の違いは、権利消滅の自動性についてです。
時効の場合、期間が経過しても相手が時効を主張しなければ、権利は消滅しない可能性があります。
これを「援用」と呼び、相手が時効を主張することで初めて時効の効果が発生します。
しかし除斥期間の場合は、期間経過により自動的に権利が消滅するため、相手の意思表示は不要なのです。
例えば、除斥期間が過ぎた後に財産分与の請求をしても、裁判所は当然に請求を棄却します。
相手が「時効を主張しない」と言っても意味がなく、法律上当然に権利が消滅しているとみなされるのです。
③期間のスタート時点(起算点)が違う
時効と除斥期間の三つ目の違いは、期間の計算開始時点(起算点)にあります。
時効は「権利を行使できる時」から進行します。
例えば借金の返済期限が来た時や、損害を知った時などからカウントが始まります。
一方、除斥期間は「権利が発生した時」から進行するため、権利者が権利の存在を知らなくても期間は進行し続けるのです。
財産分与の場合、除斥期間とされていた頃は「離婚の時」が起算点となっていました。
つまり、離婚成立の日から2年間という計算になります。
財産分与の期限を定める法的根拠
財産分与の請求権に期限が設けられているのは、法的安定性を確保するためです。
民法第768条第2項では「財産分与の請求権は、離婚の時から2年を経過したときは、消滅する」と規定されていました。
この規定により、離婚後の財産関係を早期に確定させ、元配偶者間の法律関係を安定させる狙いがあります。
しかし2018年の民法改正により、この期間は「5年」に延長されました。
これは国際的な潮流や離婚後の当事者の実情を考慮したもので、より公平な財産分与を実現するための改正でした。
この法改正は2020年4月1日から施行されており、それ以降の離婚に適用されています。
財産分与を求める方法
財産分与を求めるには、主に次の三つの方法があります。
一つ目は、夫婦間の話し合いで財産分与の内容を合意する方法です。
二つ目は、弁護士などの専門家を交えて協議を行う調停という方法です。
三つ目は、話し合いや調停で解決しない場合に裁判所に訴えを起こす方法です。
裁判所に訴える場合、時効期間内に申し立てをしなければ請求権が消滅するので注意が必要です。
離婚時に財産分与について何も決めていなかった場合でも、期間内であれば後から請求することが可能です。
2年が経過した後でも財産分与の請求は成立することがあるのか?
旧法下では、離婚から2年が経過すると財産分与の請求権は原則として消滅していました。
しかし実務上、例外的なケースとして請求が認められることもありました。
例えば、相手が財産を隠していたことが後から発覚した場合や、詐欺的な行為があった場合などです。
民法上の一般原則である信義則や権利濫用の禁止に基づき、2年を過ぎても救済される可能性があるのです。
また、離婚時に「将来財産が見つかった場合は分与する」という合意がある場合も、2年の期間制限を超えて請求できる可能性がありました。
現在は離婚から5年間に延長されていますが、期間内に請求することが望ましいでしょう。
財産分与の期限が5年に延長された
2020年4月1日より施行された改正民法により、財産分与の請求期限は「離婚の時から5年」に延長されました。
これは現代社会の実情に合わせた重要な改正といえるでしょう。
従来の2年間という期限では、離婚直後の精神的・経済的混乱から立ち直る前に期限が過ぎてしまうケースがありました。
特に専業主婦だった方や、DVなどの事情がある場合、2年という期間は短すぎるという指摘が多かったのです。
また、隠し財産の発覚に時間がかかるケースなども考慮され、より公平な財産分与を実現するために期間が延長されました。
この改正は2020年4月1日以降の離婚に適用されるため、それ以前の離婚については旧法の2年間が適用される点に注意が必要です。
離婚から2年以内に確定した財産分与の請求権の時効期間は10年間となる
離婚時に財産分与について合意し、財産分与請求権が確定した場合の時効についても押さえておく必要があります。
離婚から2年以内(現在は5年以内)に財産分与の内容が合意や審判で確定した場合、その履行請求権の時効期間は10年間です。
例えば、離婚時に「1000万円を分割で支払う」と合意した場合、実際の支払いを求める権利は10年間存続します。
この10年の時効期間は、各支払期日から個別に進行する点に注意が必要です。
分割払いの場合、最初の支払日から10年ではなく、各回の支払い期日からそれぞれ10年間の時効が適用されます。
財産分与の内容が確定した後に相手が支払いを怠った場合は、強制執行などの法的手段を取ることも可能です。
ただし、これも時効期間内に行わなければならないため、支払いが滞った場合は早めに対応することをおすすめします。
財産分与を受ける側の注意すべき点
離婚時の財産分与を受ける側は、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。
特に時効を意識した対応が大切なので、具体的に見ていきましょう。
離婚前に財産分与を決める
理想的なのは、離婚協議の段階で財産分与の内容をはっきりと決めておくことです。
離婚前に話し合いをすることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
財産分与の対象となる財産のリストを作成し、それぞれの財産について分与の割合や方法を具体的に決めましょう。
特に不動産や高額な資産については、名義変更の手続きや分割方法まで細かく取り決めておくことが重要です。
離婚届と一緒に「離婚協議書」を作成し、財産分与の内容を書面で残しておくと安心でしょう。
公正証書にすれば、より法的効力が高まります。

離婚後はできるだけ迅速に請求を行う
離婚時に財産分与が決まっていない場合は、できるだけ早く請求手続きを始めることが大切です。
現在は離婚から5年以内という期限がありますが、早めに行動するメリットは多くあります。
時間が経つほど証拠が散逸したり、相手の財産状況が変わったりする可能性があるためです。
特に相手が再婚したり、転職したりすると財産状況が大きく変わることがあるので注意が必要です。
まずは内容証明郵便で財産分与の請求をし、それでも相手が応じない場合は調停や裁判を検討しましょう。
裁判所に申し立てをすれば時効の中断効果もあります。
取り決め通りに財産を渡してもらえない場合は迅速に対応する
財産分与の内容が決まっても、相手が約束を守らないケースは少なくありません。
このような場合は、すぐに法的措置を検討すべきです。
特に財産分与の取り決めが公正証書になっている場合は、強制執行の手続きが比較的簡単です。
裁判所の判決や審判を得ている場合も同様に強制執行が可能なので、履行されないときは迅速に法的手続きを進めるとよいでしょう。
また、履行勧告の制度を利用することもできます。
家庭裁判所に申し立てることで、相手に履行を促す勧告をしてもらえるのです。
財産分与に詳しい弁護士の意見を聞く
財産分与は法律的に複雑な問題を含むことが多いため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
特に資産が多い場合や、隠し財産の疑いがある場合は、弁護士のサポートが必要です。
弁護士は財産の洗い出しから適正な分与割合の算定、請求手続きまでトータルでサポートしてくれます。
離婚問題を扱う弁護士の中でも、特に財産分与に強い弁護士を選ぶことで、より適切なアドバイスを受けられるでしょう。
初回相談が無料の弁護士事務所も多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
弁護士費用は財産分与で取り戻せる金額に比べれば、十分に元が取れる場合が多いです。

財産分与をする側が注意すべき点
財産分与を行う側も、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。
適切に対応することで、後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。
財産隠しを行わないこと
財産分与を少なくしようと考えて財産隠しを行うことは、絶対に避けるべきです。
後から財産隠しが発覚すると、信用を失うだけでなく法的にも不利な立場に立たされます。
財産隠しが発覚すると、裁判所からの評価が下がり、結果的により多くの財産分与を命じられるケースもあります。
場合によっては詐欺罪などの刑事責任を問われる可能性もあるため、正直に財産を申告することが重要です。
特に預貯金や不動産、株式、保険など、主な財産については正確に開示しましょう。
誠実な対応が、最終的には円満な解決につながります。
財産分与の対象や割合に不満があれば、きちんと自分の意見を伝える
相手の要求に対して不満や疑問がある場合は、きちんと意見を伝えることが大切です。
黙って従うだけでは、後で後悔する結果になりかねません。
特に自分が特別に貢献した財産や、相続で得た財産などは、分与対象から外れる可能性があります。
分与割合についても、婚姻期間や夫婦それぞれの収入、貢献度などを考慮して決めるべきで、一方的な要求に応じる必要はないのです。
自分の主張を裏付ける資料を集め、理論的に説明できるよう準備しておくとよいでしょう。
感情的にならず、冷静に話し合うことが重要です。
財産分与に詳しい弁護士の意見を聞く
財産分与をする側も、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
弁護士に相談することで、法的に適切な対応ができます。
特に事業を営んでいる場合や、多額の負債がある場合は、専門家のサポートが必要です。
弁護士は法的に適正な財産分与の範囲を示してくれるだけでなく、分与方法や支払い条件の交渉もサポートしてくれるので心強い味方になるでしょう。
また、離婚後の税金対策なども含めたアドバイスを受けられます。
財産分与は一度決まると変更が難しいため、慎重に進めることが大切です。

よくある質問
財産分与の時効に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
離婚時の状況はそれぞれ異なりますので、参考にしてみてください。
- 離婚前に別居している場合は財産分与の時効はいつから計算されますか?
- 財産分与の対象となる隠し財産がある場合はどうなりますか?
- 財産分与の請求権者が死亡した場合の時効はどうなりますか?
- 財産分与の時効に関する民法改正の内容を教えてください。
- 離婚後2年経過後でも財産分与が認められる具体的な事例を教えてください。
- 財産分与の時効が5年に延長されるケースはどのような場合ですか?
- 不動産を含む財産分与の請求方法について教えてください。
- 離婚時に合意した財産分与が履行されない場合の時効はどうなりますか?
- 親の離婚における子どもの財産分与請求権はありますか?
- 財産分与の時効と除斥期間を区別する法的根拠は何ですか?
まとめ
財産分与の時効について理解を深めることができたでしょうか。
離婚後の財産分与請求権は、現在は離婚成立から5年間有効です。
この期間を過ぎると原則として請求権が消滅するため、早めの対応が重要です。
また、財産分与が確定した後の履行請求権は10年間存続しますが、分割払いの場合は各支払期日から個別に時効が進行します。
財産分与の問題は複雑なケースが多いため、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
正確な情報と適切な対応で、あなたの権利を守りましょう。