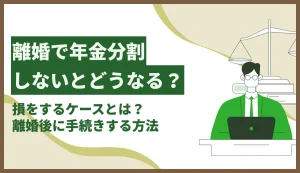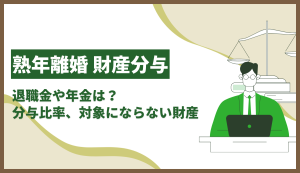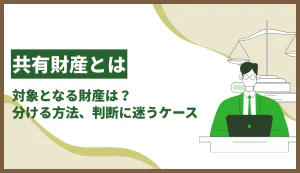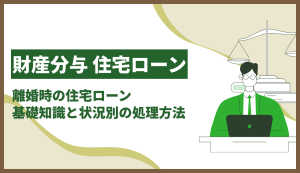離婚時の貯金の扱い|財産分与で知っておくべきポイントと注意点
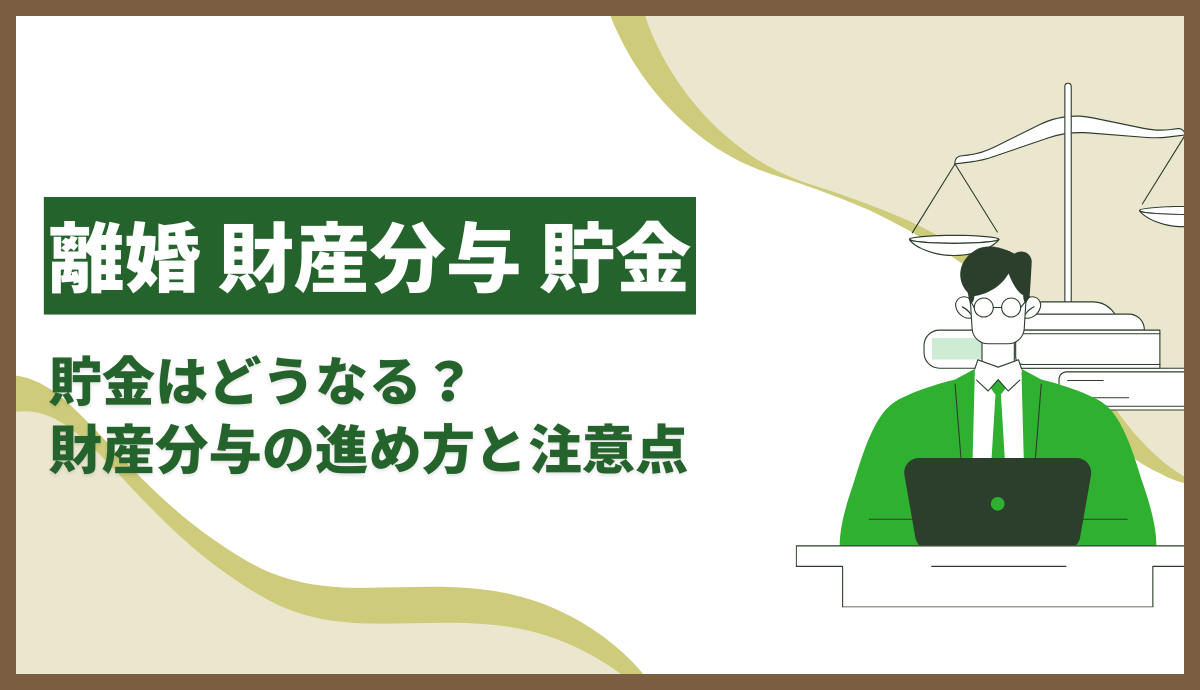
夫婦で貯めた貯金は原則として共有財産として、財産分与の対象です。
しかしすべての貯金が財産分与の対象になるわけではありません。
「結婚前から持っていた貯金」や「別居後に貯めたお金」など、財産分与の対象外となるケースもあるのです。
また、「子ども名義の貯金」や「配偶者が貯金を隠している場合」はどう対処すればよいのでしょうか?
当記事では、離婚における貯金の財産分与について詳しく解説していきます。
離婚時の財産分与に関する不安を少しでも解消できるよう、専門的な内容もわかりやすく説明していきます。
預貯金は財産分与の対象に含まれるか?
離婚時において預貯金は基本的に財産分与の対象になりますが、すべての貯金が必ず対象となるわけではありません。
財産分与の対象となる「共有財産」と対象とならない「特有財産」があり、その区別を正しく理解することが大切です。
それでは、どのような貯金が財産分与の対象になるのか、具体的に見ていきましょう。

財産分与の対象に該当する貯金とは|共有財産になる事例
財産分与の対象となる貯金は、基本的に「婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産」です。
この原則に基づき、結婚後に貯めたお金は原則として共有財産となり、財産分与の対象になります。
名義が夫または妻どちらか一方であっても、結婚中に貯めたものなら基本的に分割することになります。
以下、具体的にどのような貯金が財産分与の対象になるのか見ていきましょう。
夫婦共同で貯めた貯金
夫婦の共同名義口座にある貯金は、最も典型的な財産分与の対象です。
共働き夫婦が生活費を出し合って残ったお金を貯めたケースや、家計費から少しずつ貯金していった場合などが該当します。
このような貯金は夫婦が協力して形成した財産であることが明らかなため、当然ながら財産分与の対象になります。
夫婦間で「このお金は分けない」という約束をしていても、法的には財産分与の対象とみなされるケースが多いので注意しましょう。
子ども名義で保有する貯金
子どもの名義で作った口座の貯金も、原則として財産分与の対象になります。
たとえば教育資金を貯めるために子ども名義の口座を作り、毎月積み立てているケースが当てはまります。
名義が子どもであっても、実質的に夫婦の財産と判断されれば分与対象となるのです。
ただし、親族からの贈与で子ども名義になっている場合や、子どもが自分で稼いだお金の場合は対象外になることもあります。

結婚後に貯めた個人の貯金
夫あるいは妻の個人名義の口座にある貯金でも、結婚後に貯められたものなら基本的に財産分与の対象です。
例えば、妻が専業主婦で夫の収入だけで生活しているケースでも、夫の給料から貯めた貯金は夫婦の共有財産とみなされます。
これは、家事や育児などの家庭内労働も経済的価値があるという考え方に基づいています。
また、共働き夫婦の場合も、それぞれが自分の収入から貯めた個人名義の貯金は、原則として分与対象です。
財産分与の対象に該当しない貯金とは|特有財産になる事例
一方で、すべての貯金が分与対象になるわけではありません。
「特有財産」と呼ばれる、財産分与の対象とならない貯金もあります。
これらは一般的に、結婚前から持っていた財産や、結婚中でも完全に個人的な理由で得た財産などが該当します。
具体的にどのようなケースが特有財産になるのか、見ていきましょう。

結婚前から所有していた貯金
結婚前から持っていた預貯金は、原則として財産分与の対象になりません。
例えば、独身時代に貯めていた貯金や、実家から持ってきた資金などは、特有財産として扱われます。
ただし、結婚前の貯金であることを証明するのは難しい場合があります。
長年の結婚生活の中で、いつの時点で貯めたお金かが不明確になることも少なくありません。
そのため、結婚前の貯金を明確に区別したい場合は、結婚時点での残高を記録しておくなどの対策が大切です。
別居開始後に貯めた貯金
夫婦が別居を始めた後に、各自が貯めた貯金も基本的に財産分与の対象外となります。
別居によって共同生活が終了した後は、夫婦が協力して財産を形成しているとは言えないためです。
ただし、別居後も生活費を送金していた場合や、別居の理由によっては判断が異なることもあります。
また、どの時点を「別居開始」とするかで争いになることも多いため、はっきりと別居開始日を決めておくことが望ましいでしょう。
いずれにしても、貯金が財産分与の対象になるかどうかは、その貯金がいつ、どのように形成されたかによって判断されます。
特に不明確な部分がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
預貯金の財産分与の割合
離婚時の貯金の分け方について、どのような割合で分けるのが一般的なのか気になりますよね。
基本的な分割のルールと、例外的なケースについて解説します。
- 預貯金は原則「2分の1ずつ」の割合で分けられる
- 2分の1ではなく他の割合が適用されるケースもある
預貯金は原則「2分の1ずつ」の割合で分けられる
財産分与の対象となる預貯金は、原則として夫婦で均等に分ける「2分の1ずつ」が基本です。
これは、婚姻生活を夫婦が共同で築き上げたものと考え、その成果である財産も平等に分配するという考え方に基づいています。
例えば、夫婦の共有財産として認められた貯金が1,000万円ある場合、各自500万円ずつ取得するのが原則的な分け方です。
この「2分の1」という割合は、民法上で明確に定められているわけではなく、長年の裁判例によって確立された慣例といえます。
収入の多い少ないにかかわらず、家事や育児などの家庭内労働も経済的価値があるという考え方から、こうした均等分割が一般的になっています。
2分の1ではなく他の割合が適用されるケースもある
すべての離婚ケースで必ず均等に分けられるわけではありません。
2分の1以外の割合が適用される特殊なケースもあるので、知っておくとよいでしょう。
例えば、以下のような事情がある場合は、2分の1の原則から外れることがあります。
| ケース | 財産分与の割合の傾向 |
|---|---|
| 婚姻期間が極めて短い場合 | 貢献度が低いと判断され、2分の1未満になることがある |
| 一方が浪費や借金を重ねていた場合 | 浪費した側の取り分が減ることがある |
| 財産形成への貢献度に大きな差がある場合 | 貢献度の高い側の割合が増えることがある |
| 不貞行為など有責性がある場合 | 有責性のある側の取り分が減ることもある |
具体的な事例を見てみましょう。
結婚期間が1年未満の夫婦の場合、財産形成への貢献度が低いと判断され、均等分割にならないケースがあります。
また、一方が浪費癖があり家計を圧迫していた場合や、ギャンブルなどで貯金を使い込んでいた場合も、貯金の分割割合に影響することがあります。
さらに、共働き夫婦であっても収入差が極端に大きい場合には、高収入だった配偶者の取り分が多くなることもあるでしょう。
財産分与の割合は、最終的には夫婦間の協議で決めることができます。
もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されることになりますが、その際にはこうした個別の事情が考慮されます。
どのような割合になるにせよ、自分の権利を守るためには、まず財産状況を正確に把握しておくことが重要です。
特に貯金額が大きい場合や、分割方法に不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与の進め方と注意点
離婚時の貯金の分け方が分かったところで、実際に財産分与をどのように進めていけばよいのでしょうか。
スムーズに手続きを進めるための流れと、その過程で注意すべきポイントを解説します。
財産分与の進め方
財産分与の手続きは基本的に以下の手順で進めていきます。
まずは夫婦それぞれが所有する財産を洗い出し、その上で協議や調停を通じて分割方法を決定していく流れです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 財産の洗い出し | 夫婦それぞれが持つ預貯金、不動産、証券などの財産を特定 |
| 2. 財産分与の対象の特定 | 共有財産と特有財産を区別 |
| 3. 財産の評価 | 現在価値の算定(必要に応じて専門家に依頼) |
| 4. 分与の方法、割合の協議 | 夫婦間で話し合い |
| 5. 合意形成 | 協議が整えば、内容を書面化 |
| 6. 調停、審判(協議不調の場合) | 家庭裁判所に申し立て |
| 7. 実行 | 合意内容に従って財産を移転 |
特に貯金の財産分与については、次のようなステップで進めるとよいでしょう。
まず、両者がすべての口座情報と残高を開示します。
次に、それらの預貯金がいつ形成されたのかを特定し、財産分与の対象となるか判断します。
その上で、分割の割合を決め、実際に資金を移動させます。
場合によっては、弁護士などの専門家にサポートを依頼すると円滑に進めやすくなります。
財産分与の手続きを行う際の留意点
財産分与を進める際には、いくつかの重要な注意点があります。
特に貯金に関しては、情報の開示拒否や時効の問題が生じることがあるため、事前に知っておくとよいでしょう。
通帳の開示を拒否されるケースへの対応
離婚の話し合いで、配偶者が通帳や口座情報の開示を拒むことは珍しくありません。
こうした状況では、以下の方法で対応することができます。
- 内容証明郵便で通帳の開示を正式に請求する
- 弁護士を通じて請求する
- 調停や審判で裁判所を通じて情報開示を求める
- 財産開示手続きを利用する
特に重要なのは、相手が開示を拒否している場合でも冷静に対応することです。
感情的になって自分で通帳を探したり、無理やり情報を得ようとしたりすると、トラブルの原因になります。
法的な手続きを踏んで対応することが、結果的にスムーズな解決につながるでしょう。
開示拒否に対しては、早めの法的対応が効果的です。
時間が経つほど、資産が移されたり使われたりするリスクが高まります。

財産分与の請求権には5年の時効がある
財産分与の請求権には時効があることを知っておく必要があります。
民法では、財産分与の請求権は「離婚の時から5年間」と定められています。
民法第768条(財産分与)
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
この期間を過ぎると、原則として財産分与を請求できなくなってしまいます。
例えば、離婚後に元配偶者の隠し資産が見つかったとしても、離婚から2年以上経過していれば請求できないケースが多いです。
ただし、この5年の期間内であれば、離婚後でも財産分与の協議や調停を始めることができます。
時効を中断するためには、調停の申立てや裁判所への提訴などの法的手続きを行うことが必要です。
離婚時に財産分与について合意に至らなかった場合でも、時効を意識して早めに行動することが大切です。
財産分与手続きは複雑なケースも多いため、不安な点があれば専門家に相談することをおすすめします。

財産分与で損を避けるため離婚前に理解しておくべき3つのポイント
離婚時の財産分与で不利な立場に立たないためには、事前の準備が欠かせません。
特に貯金に関しては、知識と準備不足のために正当な分け前を受け取れないケースが少なくありません。
ここでは、財産分与で損をしないために離婚前に押さえておくべき3つの重要ポイントを解説します。
財産分与の手続きを行う前に財産状況を把握しておく
財産分与で最も重要なのは、夫婦間のすべての財産を正確に把握することです。
離婚を考え始めたら、できるだけ早い段階で家計の全体像を確認しておくべきでしょう。
具体的には、以下のような情報を集めておくことが大切です。
- 夫婦それぞれの名義の預貯金口座と残高
- 子ども名義の口座情報
- 不動産の名義と評価額
- 証券、株式などの金融資産
- 車やブランド品などの高額な動産
- 生命保険や個人年金の解約返戻金
- ローンや借金などの債務情報
可能であれば、預金通帳や資産証明書などの書類をコピーしておくとよいでしょう。
特に自分が把握していない口座の存在が疑われる場合は、郵便物や家計の出入りをチェックするのも有効です。
離婚話が出た後では情報収集が難しくなることが多いため、早めの行動が鍵となります。
配偶者が貯金を使い込んだ場合には取得する金額が変動する可能性がある
離婚が見えてくると、配偶者が貯金を意図的に使い込むケースがあります。
これは「財産隠し」や「財産減少」と呼ばれ、財産分与の金額に影響する可能性があります。
配偶者による不当な財産減少があった場合、その分を財産分与で調整できる場合があります。
例えば、以下のような行為が確認できた場合は要注意です。
| 不当な財産減少の例 | 考えられる対応 |
|---|---|
| 突然の高額な買い物 | 購入品の価値を財産に含める |
| 親族への不自然な送金 | 贈与と見なし財産に加算 |
| ギャンブルでの浪費 | 浪費分を相手の取り分から差し引く |
| 別居後の共同口座からの引き出し | 不当利得として返還請求 |
不当な財産減少を証明するには、銀行取引履歴やクレジットカードの利用明細などの証拠が必要です。
こうした証拠は、離婚を考え始めた早い段階で集めておくことが重要です。
もし配偶者による使い込みが疑われる場合は、弁護士に相談して適切な対応を検討しましょう。
配偶者が貯金を隠している可能性がある場合は迅速に調査を進める
財産分与において最も厄介なのが、配偶者による「隠し貯金」の問題です。
配偶者が貯金を隠していると感じたら、できるだけ早く調査を開始することが大切です。
隠し貯金の存在を示す可能性がある兆候としては、以下のようなものがあります。
- 収入に比べて家計費が不自然に少ない
- 説明のつかない出費や引き出しがある
- 知らない銀行からの郵便物がある
- 給与明細と入金額が一致しない
- 配偶者が急に財布や携帯電話を隠すようになった
こうした兆候がある場合、自分で調査するよりも専門家に依頼する方が効果的です。
弁護士を通じて銀行口座の調査や預金照会を行うことで、正確な情報を得ることができます。
調査が遅れると、さらに資産が隠される可能性があるため、疑いがある場合は速やかに行動しましょう。
隠し貯金が確認できた場合は、それを財産分与の対象に含めるよう主張することで、公平な分配を実現できます。
いずれにしても、財産分与でトラブルを避けるには、早めの情報収集と適切な専門家のサポートが不可欠です。
夫や妻の隠し貯金を心配している方必見!隠し口座を確認するための3つの方法
「配偶者が貯金を隠しているかも…」という不安を抱えている方は少なくありません。
離婚時の財産分与を公平に行うためには、すべての貯金口座を把握することが重要です。
ここでは、夫や妻の隠し貯金を確認するための具体的な方法を3つご紹介します。
自分で預金通帳やへそくりがないか確認する
まずは自分でできる範囲での調査から始めるのが基本です。
家庭内でできる調査は、専門家に依頼する前の重要なステップになります。
具体的には、以下のような方法で隠し貯金の手がかりを探しましょう。
- 郵便物のチェック(知らない銀行からの郵便物はないか)
- 収入と支出のバランスを確認(説明のつかない金額の差がないか)
- 税金関係の書類を確認(確定申告書などに記載された口座情報)
- キャビネットや引き出しなど、書類を保管する場所の確認
- パソコンやスマホの取引履歴や明細書(閲覧可能な場合)
ただし、無断で配偶者の私物を探ったり、パスワードを解除したりするのはプライバシー侵害になる場合があるので注意しましょう。
あくまでも共有スペースや共有物の中での確認にとどめるべきです。
自分での調査には限界があるため、決定的な証拠が見つからなくても諦める必要はありません。
次のステップとして、専門家の力を借りる方法を検討しましょう。
弁護士を通じて弁護士会への問い合わせを行う
自分での調査に限界を感じたら、弁護士を通じた調査が効果的です。
弁護士会照会制度を利用することで、銀行口座の有無を正式に調査できるというメリットがあります。
弁護士会照会(23条照会)とは、弁護士が弁護士会を通じて金融機関などに情報提供を求める制度です。
この制度を利用すれば、配偶者名義の口座があるかどうかを金融機関に照会することができます。
手続きの流れは以下のようになります。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 弁護士への依頼 | 離婚問題を扱う弁護士に相談し、弁護士会照会を依頼 |
| 2. 申出書の作成 | 弁護士が弁護士会宛に照会申出書を作成 |
| 3. 弁護士会の審査 | 申出内容の適切性を弁護士会が審査 |
| 4. 照会状の発送 | 審査通過後、弁護士会から金融機関へ照会状を送付 |
| 5. 金融機関の回答 | 金融機関が照会に対する回答を弁護士会に送付 |
| 6. 結果の確認 | 弁護士を通じて回答内容を確認 |
ただし、全ての金融機関が必ず回答するわけではありません。
回答は金融機関の任意であり、プライバシー保護などの理由で情報提供を拒否されるケースもあります。
また、弁護士会照会には費用がかかるため、事前に弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょう。

裁判所経由で調査嘱託を申し立てる
最も確実な方法は、裁判所を通じた調査嘱託です。
法的強制力を持つ裁判所からの照会であれば、銀行は原則として回答しなければならないという大きな特徴があります。
調査嘱託とは、裁判所が訴訟や調停の当事者の申立てに基づいて、第三者(金融機関など)に対して情報提供を求める制度です。
この方法は、次のような状況で特に有効です。
- 弁護士会照会で回答が得られなかった場合
- 複数の金融機関に広範囲の照会が必要な場合
- 配偶者が財産開示に非協力的で、確実な調査が必要な場合
調査嘱託は、離婚調停や離婚訴訟の中で申し立てることができます。
ただし、「漠然と全銀行に照会する」といった方法は認められないことが多いので注意が必要です。
口座を持っていると思われる具体的な金融機関を絞り込んだ上で申し立てることが大切です。
調査嘱託は弁護士のサポートを受けながら進めるのが一般的で、申立ての適切な時期や方法について助言を得られます。
隠し貯金の確認は時間と労力がかかることもありますが、公平な財産分与のためには重要なステップです。
状況に応じて上記の方法を組み合わせながら、効果的に調査を進めていくことをおすすめします。
財産分与に不安があれば弁護士に相談した方が良い|弁護士に相談する3つのメリット
離婚時の財産分与、特に貯金の分け方に不安や疑問がある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
専門知識を持つ弁護士のサポートを受けることで、より公平な財産分与を実現できる可能性が高まります。
ここでは、財産分与の問題で弁護士に相談するメリットを3つご紹介します。
財産分与の対象となる財産を正確に判断してくれる
財産分与で最初に直面する難しさは、どの財産が分与対象となるかの判断です。
弁護士は専門的な知識と経験から、共有財産と特有財産を正確に区別できるという強みがあります。
例えば、次のような微妙なケースでも適切な判断が可能です。
- 結婚前からの貯金が結婚後に増えた場合の扱い
- 親族からの贈与や相続で得た財産の位置づけ
- 別居後に形成された財産の取り扱い
- 生命保険や退職金などの特殊な資産の扱い
また、弁護士は裁判例や判例を踏まえた助言ができるため、より確かな根拠に基づいた主張が可能になります。
特に高額な財産や複雑な資産構成を持つ場合、専門家の判断は大きな違いを生み出します。
自分だけでは見落としがちな財産項目も、弁護士の視点から洗い出すことができるでしょう。
離婚後の生活費に不安がある方は、「離婚後の生活費の悩み|受け取れるお金」の記事が参考になるのでぜひご覧ください。
自分だけで対応するより多くの金額を得られる可能性がある
財産分与の交渉は、法的知識と交渉スキルが試される場面です。
弁護士に依頼することで、専門的な交渉テクニックを活かした有利な条件獲得が期待できるのが大きなメリットです。
具体的には、以下のような点で弁護士のサポートが役立ちます。
| メリット | 具体例 |
|---|---|
| 隠し財産の発見 | 弁護士会照会や調査嘱託による口座調査 |
| 適切な財産評価 | 不動産や事業用資産の正確な価値算定 |
| 戦略的な交渉 | 相手の主張への効果的な反論と代替案の提示 |
| 法的手続きの活用 | 調停や審判の効果的な利用 |
特に感情的になりがちな離婚交渉では、冷静な第三者の視点が重要です。
弁護士費用がかかるとしても、最終的に得られる財産分与額の増加で十分にペイする場合が多いといえます。
例えば、隠し財産を発見できただけで数百万円の差が生まれるケースもあります。
自分の権利を適切に主張し、公平な分配を実現するためには、専門家のサポートが大きな力になるでしょう。
配偶者との財産分与に関するやり取りを任せることができる
離婚時の財産分与交渉は精神的な負担が大きいものです。
弁護士に依頼することで、感情的な対立を避け、客観的な立場からの交渉が可能になるというメリットがあります。
具体的には、以下のような負担軽減が期待できます。
- 直接対面せずに交渉を進められる
- 感情的な言い争いを避けられる
- 相手からの圧力や操作に左右されにくくなる
- 必要な書類作成や手続きを任せられる
特に配偶者からのDVや支配的な関係があった場合、弁護士を間に立てることで安全に交渉を進めることが可能です。
また、弁護士は適切なタイミングで妥協点を見出し、スムーズな解決に導く役割も果たします。
離婚後の新生活に向けてエネルギーを温存するためにも、交渉の負担を軽減することは大切です。
財産分与の問題で弁護士に相談する時期は、離婚を考え始めた早い段階が理想的です。
初回相談は無料や低額で受け付けている法律事務所も多いので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。

よくある質問
離婚時の財産分与における貯金の扱いについて、読者からよく寄せられる質問に回答します。
具体的な疑問点を解消し、財産分与に関する理解を深めるお手伝いをしましょう。
- 共働き夫婦の場合、財産分与の割合はどのようになりますか?
- 結婚前に貯めた貯金も財産分与の対象になりますか?
- 離婚時に配偶者が貯金を隠している場合、どう対処すればよいですか?
- 専業主婦(夫)の場合、貯金の分け方に違いはありますか?
- 子供名義の口座にある貯金は財産分与の対象になるのか教えてください。
- 通帳開示を拒否された時の対応策を教えてください。
- 離婚後に財産分与を請求する期限はありますか?
- 自分だけの名義で持っている貯金を渡したくない場合はどうすればよいですか?
- 財産分与で受け取った貯金に税金はかかりますか?
- 生命保険の解約返戻金は財産分与の対象になりますか?
まとめ
離婚時の貯金の財産分与については、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
結婚後に形成された貯金は原則として財産分与の対象となり、基本的には2分の1ずつの分割が目安となります。
ただし、結婚前からの貯金や別居後に貯めた資金は特有財産として扱われることが多く、分与対象外となるケースもあります。
財産分与でトラブルを避けるためには、早い段階で財産状況を把握し、必要に応じて隠し貯金の調査を行うことが大切です。
特に不安がある場合は弁護士に相談することで、専門的なアドバイスを受けられるほか、配偶者との交渉も任せられるメリットがあります。
離婚という人生の大きな転機において、公平な財産分与を実現するためにも、正確な知識と適切な準備が重要です。