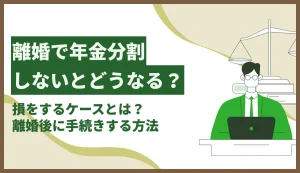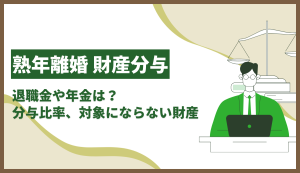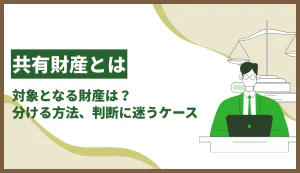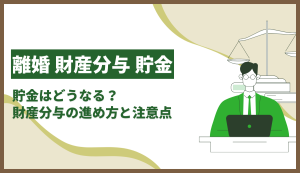離婚の財産分与|対象となるもの・割合・計算方法・進め方を解説
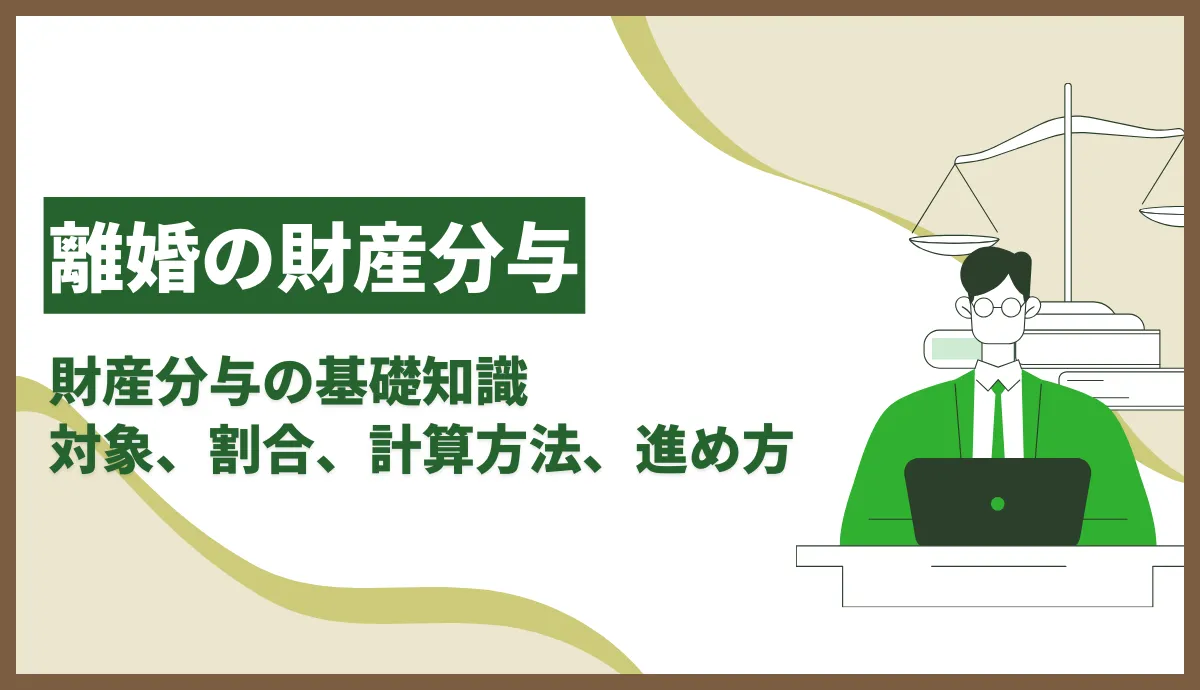
離婚を考えたとき、「財産分与」について悩む方は少なくありません。
「結婚中に貯めたお金はどうなるの?」「家やローンはどう分けるの?」など、不安や疑問が次々と浮かんでくることでしょう。
離婚財産分与は単なるお金の分配ではなく、これからの生活再建の土台となる重要な問題です。
適切な財産分与を受けるためには、どのような財産が対象になるのか、どのような割合で分けられるのかを正確に理解しておく必要があります。
この記事では、離婚財産分与の基本から具体的な計算方法、請求方法まで詳しく解説していきます。
専門用語をできるだけ使わず、わかりやすい言葉で解説していますので、離婚財産分与についての不安を解消するお手伝いができれば幸いです。
財産分与とは何か
離婚するとき、結婚中に夫婦で築いた財産をどう分けるかという問題に直面します。
これが「財産分与」と呼ばれるもので、民法768条に基づく権利として認められています。
財産分与の本質は、二人で協力して形成した財産を離婚時に公平に分配することにあります。
夫婦の貢献度に応じて分けるのが原則ですが、実際には半々で分けるケースが多いでしょう。
離婚時の財産分与の種類
離婚財産分与には大きく分けて3つの種類があります。
それぞれの違いを理解しておくと、自分のケースに当てはめやすくなるでしょう。
| 種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 清算的財産分与 | 結婚中に協力して形成した財産の清算 | 最も一般的な財産分与 |
| 扶養的財産分与 | 離婚後の生活保障を目的とした分与 | 収入差が大きい場合などに検討 |
| 慰謝料的財産分与 | 離婚原因に関する精神的苦痛への賠償 | 有責配偶者からの支払いが基本 |
清算的財産分与
清算的財産分与は、結婚生活中に夫婦で協力して築いた財産を分配する最も基本的な形式です。
例えば、共働きの夫婦が貯めた預貯金や購入した不動産などが対象となります。
専業主婦(主夫)の場合でも、家事や育児による貢献が認められるため、財産分与を受ける権利があります。
裁判例では、婚姻期間が長いほど貢献度が認められやすい傾向があるようです。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚後の生活を支援するための財産分与です。
結婚生活が長く、一方が専業主婦(主夫)だったようなケースで認められやすいでしょう。
高齢で再就職が難しい場合や、病気や障害で働けない場合などに検討される形態です。
扶養的財産分与の金額は、相手の収入や資産状況、自分の年齢や健康状態などから総合的に判断されます。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は、離婚の原因を作った側が相手に支払う性質のものです。
不倫や暴力など、明らかな有責行為がある場合に認められることが多いでしょう。
通常の慰謝料と違い、財産分与として支払われると税金がかからないというメリットがあります。
慰謝料的財産分与の額は、行為の悪質さや婚姻期間、精神的苦痛の程度によって変わります。
ただし、裁判所は清算的財産分与を重視する傾向があり、慰謝料的財産分与のみを認めるケースは少ないようです。
離婚における財産分与の対象となるもの
離婚時の財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産が対象となります。
どの財産が分与の対象になるのか理解しておくことで、離婚後のライフプランを立てやすくなるでしょう。
現金・預貯金
夫婦の給料や賞与などから貯めた預貯金は、財産分与の代表的な対象です。
通帳の名義が夫か妻かにかかわらず、結婚中に貯めたお金は原則として分与の対象になります。
夫婦どちらかの親からもらった現金でも、生活費として使われたり共有の口座に入れられたりしていると、財産分与の対象になるケースがあります。
ただし、明確に個人のために使う目的で受け取ったお金(特有財産)は、分与の対象外となることもあるでしょう。
結婚前から持っていた預貯金も基本的には対象外ですが、婚姻期間中の変動が不明確なら分与対象となる可能性があります。
生命保険
生命保険の解約返戻金も財産分与の対象になるケースが多いです。
特に貯蓄性のある生命保険(終身保険や養老保険など)は、現金と同様に扱われます。
保険料を夫婦の共有財産から支払っていた場合、保険契約者が誰であっても分与対象となるのが一般的です。
実際の分与方法としては、解約して現金化するか、契約をそのまま引き継ぐかを選択できます。
解約返戻金の額や契約状況によって、どちらが有利かは変わってくるでしょう。
株式や出資金
株式、投資信託、社債などの金融商品も財産分与の対象です。
婚姻期間中に購入した金融商品は、購入資金の出所にかかわらず共有財産とみなされることが多いでしょう。
これらの資産は評価額が変動するため、分与の基準時(通常は離婚時)の時価で評価するのが一般的です。
会社の出資金や自営業の事業資産も対象になりますが、評価が難しいケースも少なくありません。
専門家に依頼して適正な評価を受けることで、公平な分与が実現しやすくなるでしょう。
不動産
結婚中に取得した不動産は、名義人が誰であっても財産分与の対象となります。
主な例としては、夫婦の住居として購入したマンションや一戸建て、投資用不動産などがあるでしょう。
不動産の分与では、売却して現金化する方法と、一方が住み続けて他方に代償金を支払う方法があります。
住宅ローンが残っている場合は、ローンの名義変更や借り換えなど、金融機関との調整も必要になります。
特に子どもがいる場合は、住環境の変化を最小限に抑える解決策が検討されることが多いようです。
退職金
退職金も財産分与の対象になりうる重要な資産です。
まだ受け取っていない将来の退職金でも、婚姻期間中の貢献分は分与対象となる可能性があります。
退職金の分与割合は、結婚期間中に積み立てられた分に対して計算されるのが一般的です。
例えば、勤続30年のうち20年が婚姻期間だった場合、退職金の3分の2が分与対象となり、その半分を配偶者が受け取るといった計算方法が採られます。
ただし、退職金がいつ支給されるか未定の場合は、具体的な分与方法を離婚協議書などで明確にしておくことが大切です。
「退職したら支給額の○%を支払う」といった条件を記載しておくと、後々のトラブルを防げるでしょう。
離婚における財産分与の対象とならないもの
財産分与の対象となる財産がある一方で、分与の対象にならない財産もあります。
これらを正しく理解しておくことで、離婚時の財産分与をめぐるトラブルを避けられるでしょう。
特有財産
特有財産とは、婚姻前から個人で所有していた財産や、婚姻中に相続・贈与で得た個人的な財産を指します。
特有財産は原則として財産分与の対象とならず、所有者が離婚後も引き続き保有することができます。
例えば、結婚前から持っていた預貯金や不動産、親から相続した土地や建物などが当てはまります。
ただし、特有財産であっても夫婦の共同生活に組み込まれた場合は、財産分与の対象になることもあります。
相続で得た土地に夫婦で住宅を建てた場合など、一部が共有財産としての性質を持つケースは注意が必要です。
別居後に取得した財産
夫婦が別居を始めた後に取得した財産も、基本的には財産分与の対象外となります。
別居後は夫婦の協力関係が事実上終了しているため、その後に得た収入や資産は個人のものと考えられるからです。
ただし、別居後でも婚姻関係が続いている間の扶養義務は残るため、生活費の支払いなどは必要です。
また、別居の定義や開始時期が不明確な場合は、財産分与の対象となるかどうかで争いになることもあります。
明確な証拠(別居開始日がわかる賃貸契約書など)を残しておくと、後のトラブル防止に役立つでしょう。
借金
離婚財産分与の対象に借金も含まれるのか、気になる方も多いでしょう。
基本的に、夫婦の共同生活のために作った借金は財産分与の対象となり、マイナスの財産として計算されます。
例えば、住宅ローンや生活費のために組んだ借金は夫婦で分担するのが一般的です。
一方で、ギャンブルや浮気など、一方の配偶者が個人的な理由で作った借金は、原則としてその本人が返済責任を負います。
ただし、借金の名義人や契約者が誰であるかにかかわらず、その用途や経緯によって分担の有無が決まる点に注意が必要です。
年金
年金は離婚財産分与の対象とはなりませんが、別の制度で分割が可能です。
「年金分割制度」を利用することで、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦間で分割できます。
分割割合は、原則として2分の1ですが、当事者間の合意や裁判所の決定で変更することも可能です。
年金分割の請求は離婚から2年以内に行う必要があり、この期間を過ぎると分割請求ができなくなります。
年金事務所や年金相談センターで手続きを行いますが、複雑な制度のため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
なお、国民年金は原則として分割対象とならないため、専業主婦(主夫)だった方は注意が必要です。
離婚財産分与の割合について
離婚時の財産分与では、「どのような割合で分けるのか」が大きな関心事となります。
法律上は夫婦の協力によって得た財産を「それぞれの貢献度に応じて」分けると規定されていますが、実際にはどうなるのでしょうか。
一般的には「2分の1ずつ」という考え方が基本となっており、裁判所の判断もこの原則に沿うことが多いです。
ただし、婚姻期間や収入の差、家事・育児への貢献度などによって、この割合が変動することもあります。
例えば、短期間の結婚の場合や、一方が特有財産を元手に資産形成した場合は、均等分割からずれる可能性があるでしょう。
専業主婦(主夫)の場合でも、家事や育児による貢献が評価され、基本的には2分の1の権利が認められます。

離婚財産分与で受け取れる金額の目安
実際に財産分与でどれくらいの金額を受け取れるのか、具体的な目安を知りたい方も多いでしょう。
分与金額は夫婦の資産状況によって大きく異なりますが、一般的な計算方法を紹介します。
| 分与対象となる資産 | 計算方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 残高の2分の1 | 名義を問わず婚姻中の蓄え |
| 不動産 | 時価評価額の2分の1 | ローン残債を引いた純資産価値 |
| 退職金(既受給) | 婚姻期間分の2分の1 | 婚姻期間/勤続年数×退職金×1/2 |
| 株式・投資 | 時価評価額の2分の1 | 評価時点は離婚時が基本 |
| 生命保険 | 解約返戻金の2分の1 | 保険の性質によって変動 |
例えば、結婚10年のカップルで次のような資産がある場合の計算例を見てみましょう。
- 預貯金:500万円
- マイホーム:評価額2,000万円(ローン残高1,000万円)
- 退職金積立:勤続15年中10年が婚姻期間で300万円分
- 株式投資:200万円
この場合の財産分与の対象となる総額は、500万円+1,000万円+200万円+200万円=1,900万円となり、基本的には950万円ずつの分与となります。
ただし、相手に家を引き継いでもらう場合や、子どもの養育費、慰謝料などの要素も加味して最終的な金額が決まることが多いでしょう。
また、離婚時に受け取る財産分与金には税金がかからないという大きなメリットがあります。
ただし、不動産や株式など現物で分与を受ける場合は、将来売却時に譲渡所得税がかかる可能性があるので注意が必要です。
離婚財産分与の計算方法
財産分与の対象や割合について理解したら、次は具体的な計算方法について見ていきましょう。
資産の種類によって計算方法が異なるため、それぞれの特徴を押さえておくことが大切です。
現金と預貯金の計算
現金や預貯金は財産分与の中でも比較的計算がシンプルです。
婚姻中に形成された預貯金の合計額を算出し、原則として2分の1ずつ分けるのが基本的な計算方法です。
例えば、夫名義の口座に300万円、妻名義の口座に200万円ある場合、合計500万円の半分である250万円がそれぞれの取り分となります。
すでに250万円持っている妻は追加でもらう必要がなく、300万円持っている夫は50万円を妻に渡す計算になるでしょう。
ただし、預貯金が一方の特有財産(結婚前からの貯金や相続金など)である場合は、その部分を除外して計算する必要があります。
生命保険の扱い
生命保険は単なる保障だけでなく、貯蓄性を持つ商品も多くあります。
終身保険や養老保険などの貯蓄性のある保険は、解約返戻金が財産分与の対象となります。
具体的な計算方法としては、離婚時点での解約返戻金を確認し、その金額の2分の1を目安に分与額を決めるのが一般的です。
保険料の支払いが一方の特有財産から出ていた場合は、その寄与分を考慮して調整することもあります。
なお、保険を解約せずに名義変更で対応することも可能ですが、保険会社によって手続きが異なりますので確認が必要です。
生命保険の名義人が決まっている場合は解約不要
離婚後に保険契約をどちらが引き継ぐかが決まっている場合は、必ずしも解約する必要はありません。
例えば、夫が契約者の生命保険を夫が継続する場合、解約返戻金相当額の半分を妻に現金で支払うことで対応できます。
反対に妻が引き継ぐ場合は、契約者変更の手続きをした上で、返戻金相当額の半分を夫に支払う形になるでしょう。
保険の名義変更には保険会社所定の手続きが必要ですので、事前に確認しておくことをおすすめします。
不動産の分与方法
不動産は金額が大きく、財産分与の中でも重要な位置を占めます。
不動産の財産分与では、まず現在の時価を不動産会社や鑑定士に評価してもらうことから始めます。
住宅ローンが残っている場合は、その残債を差し引いた純資産価値が分与の対象となります。
例えば、マイホームの評価額が3,000万円で住宅ローンの残債が2,000万円なら、純資産価値は1,000万円となります。
この1,000万円を原則として2分の1ずつ分けることになるため、不動産を引き継ぐ側が相手に500万円の代償金を支払うことになるでしょう。
不動産売却か代償金支払いかの選択
不動産の財産分与には、主に「売却する方法」と「一方が引き継ぐ方法」の2つがあります。
売却する場合は、売却代金からローン残債を清算した後の利益を分け合うシンプルな方法です。
一方が引き継ぐ場合は、引き継ぐ側が相手の取り分を代償金として支払います。
子どもの住環境を守りたい場合や、愛着のある家に住み続けたい場合は、後者を選ぶケースが多いようです。
ただし、代償金の支払いが難しい場合や両者の合意が得られない場合は、売却せざるを得ないこともあります。
特有財産で支払いを負担していた場合
結婚前の貯金(特有財産)を住宅購入などに充てたケースでは、計算方法が少し複雑になります。
特有財産からの支出分は「寄与分」として認められ、財産分与の計算時に考慮されるのが一般的です。
例えば、夫が結婚前の貯金1,000万円を頭金にして住宅を購入した場合、その1,000万円分は夫の特有財産として認められる可能性が高いです。
ただし、婚姻生活が長期に及ぶと、特有財産の区別が曖昧になることもあります。
特有財産であることを主張するには、通帳の記録など客観的な証拠が必要となるでしょう。
5000万円の住宅購入の具体例
より具体的な例で見てみましょう。5,000万円の住宅を次のような資金で購入したケースを考えます。
- 夫の結婚前の貯金(特有財産):1,000万円
- 妻の結婚前の貯金(特有財産):500万円
- 結婚後の共有財産からの支出:500万円
- 住宅ローン:3,000万円
10年後に離婚し、住宅の評価額が4,500万円、ローン残債が2,000万円になったとします。
この場合、純資産価値は4,500万円−2,000万円=2,500万円となります。
ここから特有財産分を考慮すると、分与対象となるのは2,500万円−1,000万円−500万円=1,000万円です。
この1,000万円を2分の1ずつ分けると、それぞれ500万円の取り分となります。
最終的に夫の取り分は1,000万円(特有財産)+500万円(分与分)=1,500万円、妻の取り分は500万円(特有財産)+500万円(分与分)=1,000万円となるでしょう。
住宅ローンがある場合の対応
住宅ローンが残っている場合の財産分与は、特に慎重な対応が必要です。
離婚後にローンの支払いトラブルを避けるためには、可能な限りローンの名義変更や借り換えを行うことが望ましいでしょう。
住宅を引き継ぐ側がローンも引き継ぐのが基本ですが、収入や信用状況によっては金融機関が名義変更に応じないケースもあります。
ローンの名義変更ができない場合は、売却して清算するか、元の名義人が支払いを続ける約束をするといった対応が必要になるでしょう。
特に連帯債務(夫婦両方がローンの債務者)になっている場合は注意が必要です。
相手が支払いを滞納すると自分も責任を問われるため、離婚協議書に支払い条件を明記し、公正証書にしておくことをおすすめします。
離婚時の財産分与の進め方と注意すべきポイント
財産分与を円滑に進めるためには、適切な手順とポイントを押さえておくことが大切です。
ここでは、実際に財産分与を進める際の具体的な方法と注意点を解説します。
財産を売却して現金化する方法
財産分与の最もシンプルな方法は、共有財産をすべて現金化して分ける方法です。
不動産や自動車などの資産を売却し、借金を清算した後の純資産を分け合うことで、明確で公平な分与が実現できます。
この方法のメリットは、分与後のトラブルが少ないことと、新生活をゼロからスタートできる点にあります。
ただし、売却には時間がかかることや、愛着のある財産を手放さなければならない点がデメリットとなるでしょう。
特に不動産の売却は数ヶ月かかることもあるため、その間の生活費や住居について事前に計画しておく必要があります。
夫名義の財産でも分与の対象になる
財産の名義が夫のみになっていても、婚姻中に形成された財産であれば分与の対象となります。
例えば、夫名義の不動産や預貯金、投資商品なども、婚姻中に得たものであれば妻にも分与請求権があるのです。
これは専業主婦(主夫)の場合でも同様で、家事や育児による貢献が経済的価値として認められています。
相手が財産を隠している可能性がある場合は、弁護士に相談して財産開示を求める方法も検討しましょう。
退職金や年金の財産分与における扱い
退職金は受給前でも財産分与の対象となる可能性がありますが、実務上は難しい面もあります。
未受給の退職金を分与する場合は、「退職金を受け取ったら○%を支払う」などの条件を離婚協議書に明記しておくのが一般的です。
年金については前述の通り、財産分与ではなく年金分割制度を利用します。
厚生年金の場合、婚姻期間中の保険料納付実績の2分の1まで分割請求できるので、離婚から2年以内に手続きを行いましょう。

一方が財産を引き継ぐ方法
すべての資産を売却せず、一方が財産を引き継ぐ方法もあります。
この場合、財産を引き継ぐ側が、相手の取り分に相当する金額を代償金として支払うのが一般的です。
例えば、純資産価値が2,000万円の自宅を妻が引き継ぐ場合、夫に1,000万円の代償金を支払うといった形になります。
子どもの環境変化を最小限に抑えたい場合や、愛着のある財産を保持したい場合に選ばれる方法です。
ただし、代償金の支払いが困難なケースや、財産評価で意見が分かれる場合は調停や裁判に発展することもあります。
家屋と土地の分与
不動産の財産分与では、家屋と土地を別々に考えることもあります。
例えば、土地は妻の親から贈与されたもので、家は婚姻中に共同で建てた場合、土地は妻の特有財産として扱い、家の価値のみを分与対象とすることが考えられます。
建物の評価額から算出した代償金を支払うことで、土地と建物をセットで引き継ぐケースが多いでしょう。
ただし、長期間の婚姻関係がある場合は、土地についても部分的に分与対象となる可能性があるので注意が必要です。
自動車の分与
自動車は比較的分与が容易な資産の一つです。
中古車市場での査定額を基準に価値を算定し、引き続き使用する側が相手に半額を支払うか、他の財産と相殺するのが一般的な方法です。
車検証の名義変更や自動車ローンの名義変更も忘れずに行いましょう。
特に自動車ローンが残っている場合は、支払い責任を明確にしておかないとトラブルの原因になります。
生命保険の分与
生命保険の財産分与では、解約返戻金を基準に価値を算定するのが基本です。
解約せずに契約を継続したい場合は、返戻金相当額の半分を相手に支払う方法が考えられます。
保険契約の名義変更が必要な場合は、保険会社に相談して手続きを進めましょう。
なお、掛け捨て型の保険は解約返戻金がほとんどないため、財産分与の対象とならないケースが多いです。
教育保険の分与
子どものための教育保険も財産分与の対象となりますが、扱いが少し異なります。
基本的には子どもの養育を担当する親が引き継ぎ、解約返戻金の半額を相手に支払うのが一般的です。
ただし、「子どもの教育のために使う」という目的が明確な場合は、分与せずにそのまま子どものために継続するという合意をすることも多いでしょう。
この場合、離婚協議書に「教育保険の満期金は子どもの教育費として使用する」などと明記しておくと安心です。
貴金属や美術品の分与
貴金属、美術品、骨董品なども財産分与の対象となります。
これらは査定が難しいため、専門の鑑定士に評価してもらうことが望ましいでしょう。
高額な品物については、売却して現金化するか、評価額の半分を相手に支払って引き継ぐかを選択できます。
ただし、感情的な価値が高いものについては、金銭的価値以上の争いになることもあるので注意が必要です。
財産評価額に基づく平等な分配方法
様々な財産を公平に分けるためには、すべての財産の評価額を一覧表にまとめると良いでしょう。
例えば、以下のような表を作成して総資産を把握します。
| 財産項目 | 評価額 | 帰属先 | 取得者への価値 |
|---|---|---|---|
| 自宅マンション | 2,000万円 | 妻 | 2,000万円 |
| 自家用車 | 150万円 | 夫 | 150万円 |
| 預貯金A | 300万円 | 夫 | 300万円 |
| 預貯金B | 200万円 | 妻 | 200万円 |
| 生命保険 | 250万円 | 夫 | 250万円 |
| 住宅ローン | △1,000万円 | 妻 | △1,000万円 |
| 合計 | 1,900万円 | – | 夫:700万円 妻:1,200万円 |
この例では、妻が1,200万円、夫が700万円の価値を得ているため、平等にするには妻から夫へ250万円の調整金を支払う必要があります。
このように、すべての財産を一覧にして合意を形成することで、公平な分与が実現しやすくなるでしょう。
ローン残債のある資産分与の注意点
住宅ローンや自動車ローンが残っている場合は、債務の引き継ぎについても明確に取り決める必要があります。
ローンの名義変更ができない場合は、「名義人ではない方が実質的に支払う」という約束だけでは不十分です。
元の名義人が支払い義務を負い続けるため、相手が支払いを怠ると自分の信用情報に傷がつくリスクがあります。
このようなトラブルを避けるため、可能な限りローンの借り換えや完済を検討するか、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成して支払いを担保することをおすすめします。
また、連帯保証人になっている場合も注意が必要です。離婚後も保証責任は残るため、保証人解除の手続きについても確認しておきましょう。
離婚財産分与で注意が必要なケース
財産分与には一般的な原則がありますが、状況によっては特別な配慮や対応が必要なケースがあります。
ここでは、通常の財産分与とは異なる対応が求められる典型的なケースについて解説します。
妻の離婚後の生活と財産分与の関係
長期間の専業主婦を経て離婚するケースでは、財産分与に特別な配慮が必要となることがあります。
特に高齢で再就職が難しい場合や、子育てのために就労時間に制限がある場合は、通常より多めの財産分与が認められる可能性があります。
このような状況では、清算的財産分与に加えて扶養的財産分与の要素が考慮されるでしょう。
例えば、婚姻期間が20年以上で高齢の妻の場合、財産の6割程度が分与されるケースもあります。
また、子どもの親権を持つ側には、住居確保のために自宅を優先的に取得させるという配慮がなされることも少なくありません。
ただし、こうした配慮は法的に保証されたものではなく、個々のケースによって判断が異なります。
専業主婦だった方は、財産分与だけでなく、養育費や年金分割なども含めた総合的な生活設計を考える必要があるでしょう。
経営者の配偶者との離婚における生命保険
会社経営者の配偶者と離婚する場合は、会社の資産と個人の資産の区別が難しいケースがあります。
特に法人契約の生命保険は、単なる保障ではなく節税や事業承継の手段として活用されていることが多いため、財産分与の対象となるかどうか判断が難しい場合があります。
例えば、法人名義の生命保険でも、実質的に経営者個人の資産形成目的である場合は、財産分与の対象となる可能性があります。
反対に、明確に事業保障や借入金の担保としての性質が強い保険は、分与対象外となるケースが多いでしょう。
このような複雑なケースでは、税理士や弁護士など専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
会社の決算書や保険証券などの資料を集め、契約の目的や性質を詳しく検討することが必要です。
また、個人事業主の場合は、事業用資産と個人資産の区別が曖昧になりがちですが、原則として事業用資産も財産分与の対象となります。
事業の継続性を考慮して、現金での代償分与が選ばれることが多いでしょう。
離婚財産分与の基準時期
財産分与をめぐるトラブルのひとつに、「いつの時点での財産を分与対象とするか」という問題があります。
特に別居期間が長い場合や、離婚までに時間がかかるケースでは重要な論点となります。
財産分与の基準時は原則として離婚時
財産分与の基準時は、原則として「離婚時」とされています。
つまり、離婚が成立した時点で存在する財産が分与の対象となり、その時点での価値で評価するのが基本です。
この原則に従えば、離婚成立日までに形成された預貯金や資産が分与対象となります。
株式や不動産などの価格変動がある資産も、離婚時の時価で評価するのが一般的です。
ただし、この原則には例外があり、状況によっては別の基準時が採用されることもあります。
別居する夫婦の財産分与の扱い
夫婦が長期間別居している場合は、別居開始時を財産分与の基準時とすることがあります。
別居により共同生活が実質的に終了していると認められる場合、その時点で夫婦の協力関係が終わったと考えるからです。
例えば、5年前から別居していて、その間はお互いの生活費を別々に賄っていた場合などが当てはまります。
このケースでは、別居開始時の財産を対象として分与を行うことが妥当とされることが多いでしょう。
ただし、別居後も生活費の送金や共同での資産運用が続いていた場合は、離婚時を基準とすることもあります。
別居を財産分与の基準時とするには、別居の事実や開始時期を証明できる証拠(賃貸契約書など)が重要です。
さらに、別居後に一方が著しく財産を減らした場合や、浪費・隠匿した場合には、特別な考慮がなされることもあります。
このような不当な財産減少があった場合、減少前の財産状態を基準にしたり、減少分を分与計算に加えたりすることもあるでしょう。
基準時をめぐる争いを避けるためには、別居開始時に財産目録を作成しておくことや、別居の事実を客観的に証明できる資料を保管しておくことが有効です。
離婚財産分与の請求方法
財産分与を実際に受け取るためには、適切な請求方法を知っておく必要があります。
ここでは、離婚財産分与の主な請求方法と、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
話し合いによる解決
財産分与の最も基本的な方法は、夫婦間の話し合いによる解決です。
話し合いで合意できれば、調停や裁判の手間や費用を省くことができ、お互いの意向を反映した柔軟な取り決めが可能になります。
まずはお互いの財産を洗い出し、何が分与対象となるかを確認した上で、分与の方法や金額について話し合いましょう。
感情的にならず、冷静に交渉することが大切です。必要に応じて弁護士や専門家にアドバイスを求めるのも良いでしょう。
合意内容は必ず書面にまとめ、後のトラブル防止のために公正証書にしておくことをおすすめします。
協議離婚が基本的な方法
日本の離婚の約9割は協議離婚であり、財産分与も当事者同士の話し合いで決めるのが基本です。
協議離婚では、離婚届に記入するだけで離婚が成立しますが、財産分与については別途取り決める必要があります。
財産分与の内容は離婚届には記載しないため、口頭だけの約束では後にトラブルになるリスクがあります。
例えば「3か月後に500万円支払う」と約束していても、実際に支払われないケースも少なくありません。
そのため、合意内容は必ず書面化しておくことが重要です。
協議離婚合意書の作成手順
協議離婚で財産分与について合意した場合は、以下の手順で合意書を作成します。
- 財産分与の対象となる財産をリストアップする
- 各財産の評価額を決定する
- 分与の方法と金額を明確に記載する
- 支払いの期日や方法を具体的に記載する
- 両者が署名・捺印する
合意書には、分与する財産の詳細、金額、支払い方法、期限などを明確に記載しましょう。
「自宅マンションは妻が取得し、その代わりに夫に代償金として1,000万円を支払う」といった具体的な内容を盛り込みます。
支払い条件も「2025年3月31日までに一括払い」のように、明確な期日を設定することが大切です。
合意書の公正証書化の重要性
財産分与の合意内容は、できるだけ公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書には「強制執行認諾文言」を入れることができ、相手が支払いを怠った場合に裁判なしで強制執行できるメリットがあります。
公正証書の作成は公証役場で行い、費用は分与額などによって異なりますが、数万円程度が目安です。
必要書類は身分証明書、印鑑、合意内容を記載した書面などで、両当事者が公証人の前で合意内容を確認します。
離婚時の感情的な状況では「書面なんて必要ない」と思うかもしれませんが、将来のトラブル防止のために必ず公正証書を作成しておくべきでしょう。
調停による解決
夫婦間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停を利用することができます。
調停は裁判所が間に入って話し合いをサポートする制度で、専門家の助言を得ながら合意形成を目指せるメリットがあります。
調停では、調停委員が双方の言い分を聞きながら歩み寄りを促し、合理的な解決策を提案してくれます。
また、裁判所から財産開示を求められるため、相手が財産を隠しているケースでも真実が明らかになりやすくなります。
調停で合意に至った場合は「調停調書」が作成され、これは裁判の判決と同等の効力を持ちます。
離婚調停の基本
離婚調停は家庭裁判所に申立てを行い、裁判官と調停委員が関与する公的な話し合いの場です。
調停委員は主に2名で、法律や家庭問題に詳しい方が務めます。調停では、まず別々の部屋で双方の言い分を聞き取ります。
その後、調停委員が間を取り持ち、合意点を探っていきます。場合によっては裁判官が直接アドバイスすることもあります。
調停の費用は申立手数料として1,200円と、相手方への郵便費用数百円程度と比較的安価です。
ただし、弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。
離婚調停の流れ
離婚調停の一般的な流れは以下の通りです。
- 家庭裁判所に調停を申し立てる(申立書を提出)
- 裁判所から相手方に通知が届く
- 第1回調停期日が設定される
- 調停委員が双方の言い分を聞き取る
- 財産の開示や評価を行う
- 妥協点を探りながら合意を目指す
- 合意に至れば調停調書を作成して終了
- 合意に至らなければ調停不成立で終了
調停は通常、数ヶ月から半年程度かかることが多く、月に1回程度のペースで期日が設定されます。
調停が不成立となった場合は、審判や訴訟に移行することになります。
訴訟による解決
話し合いや調停でも解決しない場合は、最終的に裁判所で訴訟を起こすことになります。
訴訟では裁判官が法律に基づいて判断を下すため、公平な解決が期待できますが、時間や費用がかかることがデメリットです。
財産分与を求める訴訟は、相手の住所地を管轄する地方裁判所に提起します。
訴訟では、財産分与の対象となる財産の存在や評価額について証拠を提出し、主張を立証する必要があります。
財産分与請求権は離婚から2年で時効を迎えるため、交渉が長引く場合は注意が必要です。
訴訟では弁護士に依頼することが一般的で、費用は請求額によって異なりますが、着手金と成功報酬を合わせて数十万円から数百万円かかるケースもあります。

離婚訴訟の概要
離婚訴訟は離婚そのものを求める裁判と、財産分与を求める裁判は別々に行われることがあります。
離婚が成立した後に財産分与を求めることもできますし、離婚訴訟の中で財産分与についても判断を求めることも可能です。
訴訟を起こす場合は、分与を求める財産の内容や金額を明確にし、それが夫婦の共有財産であることを証明する資料を用意する必要があります。
例えば、預貯金の通帳、不動産の登記簿謄本、株式の取引報告書などが重要な証拠となります。
裁判所は提出された証拠に基づいて判断するため、証拠収集が訴訟の成否を左右します。
離婚訴訟の進行過程
財産分与を求める訴訟の一般的な流れは以下の通りです。
- 訴状の提出
- 第1回口頭弁論期日
- 答弁書や準備書面の提出
- 証拠調べ(財産評価など)
- 和解協議(裁判所が和解案を提示することも)
- 和解が成立しなければ判決
訴訟は半年から1年以上かかることが一般的で、複雑なケースではさらに長期化することもあります。
訴訟の途中でも和解は可能で、実際には多くのケースが判決前に和解で解決します。
和解内容は「和解調書」として作成され、判決と同等の効力を持ちます。
判決による支払い保証
訴訟で勝訴し、判決を得たとしても、相手が自主的に支払わない場合は強制執行の手続きが必要になります。
判決は公正証書と同様に強制執行の根拠となる債務名義となるため、相手の財産に対して差し押さえを行うことができます。
例えば、相手の給与や預貯金、不動産などを差し押さえて債権回収を図ることが可能です。
ただし、強制執行には別途費用がかかりますし、相手に財産がなければ回収は難しくなります。
そのため、判決を得る前の段階で相手の支払能力を見極めておくことも重要です。
離婚で財産分与が支払われない場合の対処法
財産分与の取り決めをしても、実際に支払いが行われないケースは少なくありません。
そのような場合の対処法について、状況別に解説します。
協議離婚で公正証書がない場合
協議離婚で公正証書を作成せず、書面だけの合意や口頭の約束しかない場合は対応が難しくなります。
この場合、まずは相手に支払いを促す内容証明郵便を送り、それでも支払われなければ訴訟を起こす必要があります。
内容証明郵便では、合意内容と支払期限を明記し、支払いがない場合は法的手段を取る旨を伝えましょう。
合意書があれば証拠として有効ですが、口頭の約束だけだと立証が難しいので注意が必要です。
訴訟を起こす場合は、離婚から2年以内に行う必要があります。2年を過ぎると時効により請求権が消滅してしまいます。
離婚から時間が経っている場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

法的効力のある書類がある場合
公正証書や調停調書、判決など法的効力のある書類がある場合は、強制執行の手続きを取ることができます。
特に強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、裁判なしで直接強制執行の申立てが可能です。
強制執行では、相手の財産(預貯金、給与、不動産など)を差し押さえて債権を回収します。
ただし、相手に差し押さえるべき財産がないと回収は難しくなるため、財産状況の把握も重要です。
差し押さえには費用がかかりますし、手続きも複雑なため、弁護士に依頼するのが一般的でしょう。
強制執行の手続き
強制執行の具体的な手続きは以下の通りです。
- 債務名義(公正証書、調停調書、判決など)を準備する
- 相手の財産情報を収集する
- 地方裁判所に強制執行の申立てを行う
- 差押命令が出た後、第三債務者(銀行など)に通知される
- 差し押さえた財産から債権を回収する
預貯金の差し押さえは比較的スムーズですが、給与の差し押さえは金額に制限があります。
例えば、給与は手取り額の4分の1までしか差し押さえできないという制限があります。
また、不動産の差し押さえは手続きが複雑で時間もかかるため、他に方法がない場合の最終手段と考えるべきでしょう。
強制執行は感情的な問題も生じやすいため、できれば話し合いで解決することが望ましいですが、悪質な場合は毅然とした対応が必要です。
離婚時の財産分与に関する実例
財産分与に関する知識を深めるため、実際にあった事例を見てみましょう。
ここでは、住宅ローン関連のトラブル事例を紹介します。
住宅ローン残債がある家を引き継いだAさんの事例
35歳のAさん(女性)は、10年間の結婚生活の末に離婚しました。
子どもの環境を変えたくないという理由から、住宅ローンが残っている自宅マンションを引き継ぐことになりました。
マンションの評価額は3,000万円、ローン残高は2,000万円で、純資産価値は1,000万円でした。
財産分与として、Aさんは元夫に500万円(1,000万円の半額)を支払う約束をしました。
しかし、住宅ローンは夫婦の連帯債務のままで、名義変更ができていませんでした。
その後、元夫の収入が減り、元夫が負担すると約束していたローン返済が滞るようになりました。
元夫の支払い滞納により競売にかけられた住宅
元夫のローン返済滞納が続いたため、銀行からAさんに支払い請求が来るようになりました。
Aさんは自分の分の返済はしていましたが、元夫分まで支払う余裕はなく、結局マンションは競売にかけられる事態に至りました。
競売価格は市場価格より低く、2,200万円で落札されました。
ローン残高2,000万円を返済しても200万円しか残らず、引っ越し費用やその後の賃貸住宅の敷金などで、ほとんど手元に残りませんでした。
さらに、Aさんが元夫に支払った財産分与の500万円は戻ってくることはありませんでした。
音信不通になった元夫と給与差し押さえの困難
問題を複雑にしたのは、ローン滞納が始まった頃から元夫が音信不通になってしまったことです。
弁護士に相談したところ、元夫の給与を差し押さえる方法があることがわかりました。
しかし、元夫の勤務先が分からないため、差し押さえの手続きを取ることができませんでした。
住民票や戸籍の附票から住所は判明しましたが、実際にはそこに住んでおらず、就労先も確認できませんでした。
結局、Aさんは自己破産を検討する状況に追い込まれました。
ローン残債への対応が不十分だったことの後悔
Aさんは後日、「離婚協議の際に住宅ローンの名義変更をしっかり行うべきだった」と振り返っています。
また、「公正証書に強制執行認諾文言を入れるべきだった」とも話しています。
このケースから学べる教訓は以下の通りです。
- 住宅ローンが残っている物件を引き継ぐ場合は、必ずローンの名義変更も行う
- 名義変更ができない場合は、物件を売却して清算するか、別の安全策を講じる
- 財産分与の合意は必ず公正証書にし、強制執行認諾文言を入れる
- 相手の支払い能力や信頼性も考慮に入れて財産分与の取り決めをする
離婚時には感情的になりがちですが、将来のリスクを想定して、法的に安全な取り決めをすることが重要です。
特に住宅ローンのような大きな債務が絡む場合は、弁護士や専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

よくある質問
離婚財産分与に関して、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。
基本的な疑問から具体的な事例まで、参考にしてください。
専業主婦でも財産分与を受けられますか?
はい、専業主婦(主夫)でも財産分与を受ける権利があります。家事や育児による貢献が経済的価値として認められるため、原則として夫婦の財産は平等に分けられます。
結婚前から持っていた貯金も財産分与の対象になりますか?
結婚前からの貯金(特有財産)は原則として財産分与の対象外です。ただし、婚姻中に使途が不明確になった場合や共同生活に組み込まれた場合は対象となることがあります。
離婚時に家や不動産の財産分与はどうなりますか?
不動産は売却して現金分与するか、一方が引き継いで相手に代償金を支払うかの選択肢があります。住宅ローンが残っている場合は、ローンの名義変更も含めて検討する必要があります。
離婚財産分与で相手の退職金ももらえますか?
婚姻期間中に積み立てられた退職金は財産分与の対象になります。未受給の退職金でも、婚姻期間に対応する部分について分与請求が可能です。
財産分与で受け取ったお金に税金はかかりますか?
財産分与として受け取ったお金には原則として税金はかかりません。ただし、不動産や株式などを現物で分与された場合、将来売却時に譲渡所得税がかかる可能性があります。
離婚時に共有名義の車はどうすればよいですか?
中古車市場での査定額を基準に価値を算出し、一方が引き継ぐ場合は相手に半額を支払うのが一般的です。名義変更の手続きや自動車ローンの扱いも忘れずに取り決めましょう。
相手が財産を隠している場合、通帳開示を求める方法を教えてください。
調停や訴訟を通じて裁判所に文書提出命令を申立てることができます。弁護士に依頼すれば、財産開示を求める内容証明郵便の送付なども効果的です。
住宅ローンが残っている家の財産分与はどうなりますか?
ローン残高を差し引いた純資産価値が分与対象となります。引き継ぐ場合はローンの名義変更も行うのが理想的で、できない場合は売却して清算するのが安全です。
共働きの場合の財産分与の相場はどのくらいですか?
共働き夫婦でも原則として財産は2分の1ずつとされることが多いです。ただし、収入差が大きい場合や一方の貢献度が特に高い場合は割合が変動することもあります。
離婚財産分与の請求に時効はありますか?
はい、財産分与請求権は離婚成立から2年で時効となります。2年を過ぎると請求権が消滅するため、離婚時に合意できなくても、2年以内に調停や訴訟を提起する必要があります。
会社の株式も財産分与の対象になりますか?
婚姻中に取得した株式は財産分与の対象となります。上場企業の株式は時価で評価されますが、非上場企業の場合は専門家による評価が必要になるでしょう。
財産分与の金額に納得がいかない場合はどこに相談すればよいですか?
まずは弁護士に相談することをおすすめします。法律相談センターや自治体の無料相談窓口も利用できます。合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停を申し立てることができます。
まとめ
離婚財産分与は、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を公平に分けるための重要な制度です。
基本的には婚姻期間中に形成された財産が対象となり、原則として2分の1ずつの分割となります。
預貯金や不動産、生命保険の解約返戻金、将来受け取る予定の退職金なども分与対象になる一方、結婚前からの財産や相続・贈与された特有財産は原則として対象外です。
財産分与を円滑に進めるためには、まず対象となる財産を洗い出し、公平な評価額を算定することが大切です。
話し合いで合意できれば協議離婚で解決できますが、合意内容は必ず書面に残し、できれば公正証書にしておくことをおすすめします。
話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟という選択肢もありますが、離婚から2年で請求権が時効となる点に注意が必要です。
特に住宅ローンなどの債務が絡む場合は、将来のトラブルを防ぐためにも専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
離婚は感情的になりがちですが、将来の生活再建の土台となる財産分与については、冷静かつ慎重に対応することが、その後の新生活を安定させる鍵となるでしょう。