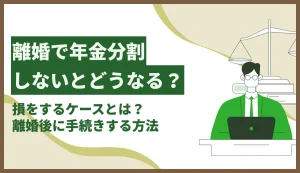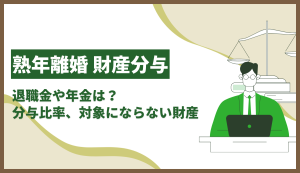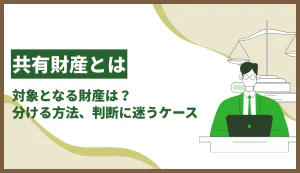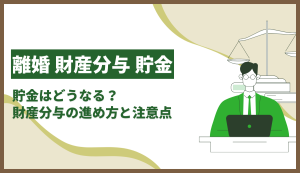「離婚と持ち家」完全ガイド|住宅ローン・財産分与の選択肢
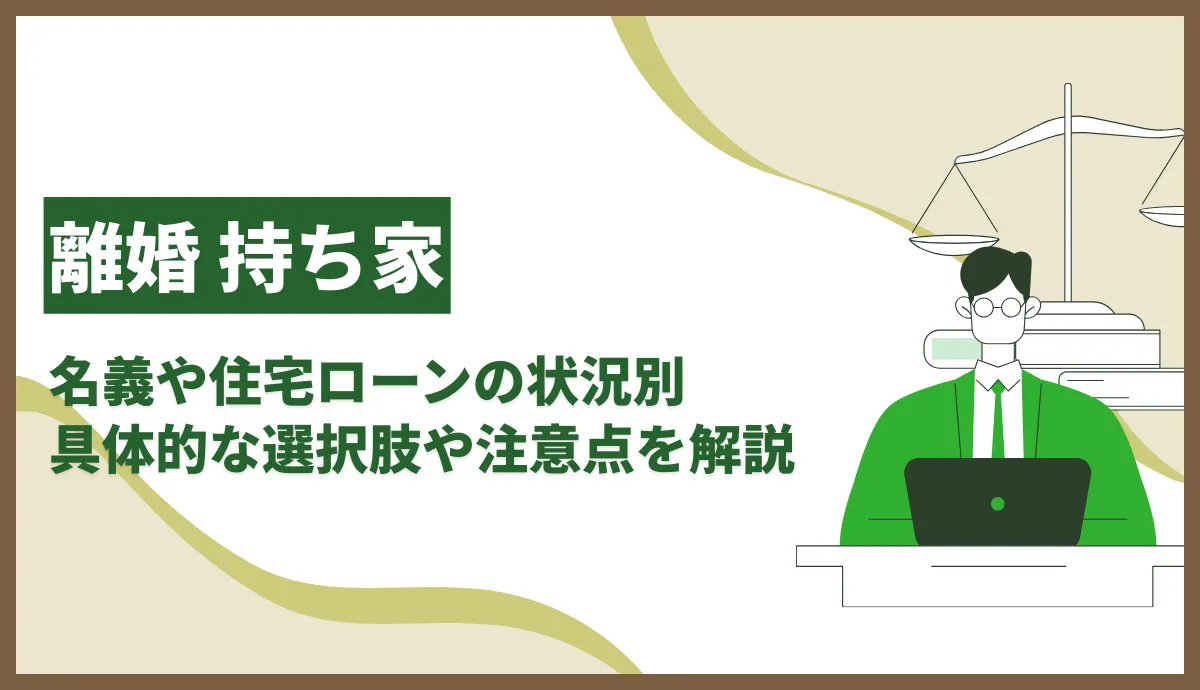
「離婚=家をどうするか?」は、多くの夫婦が最初に直面する“お金の最大級の決断”です。
マイホームは 財産分与の対象 になるため、
- 売却して現金化する
- どちらかが住み続ける
どちらを選ぶかで、住宅ローン残債・名義・固定資産税まで影響が波及します
本記事では、単独名義と共同名義それぞれの場合にどのような判断が必要か、住宅ローンが残っている場合や連帯保証人の問題といった注意点、そしてトラブルを防ぐための公正証書の作成方法についてわかりやすく解説しています。
また、お子さんがいるご家庭では「住居費と養育費」の長期的な見通しも重要なポイントです。
まずは、ご夫婦で「家の現在価値」と「住宅ローンの残高」を数値で把握することから始めましょう。
離婚時の持ち家問題で後悔しないよう、具体的な対処法をわかりやすく説明していきます。

配偶者との離婚で持ち家はどう扱われるのか?
結婚後に取得した持ち家は名義が誰であろうと原則“共有財産”に該当し、離婚時は“家=資産”と“住宅ローン=負債”をセットで精算する必要があります。
まず知っておきたいのは、持ち家が「財産分与」の対象となるという点です。
では具体的に見ていきましょう。
- 持ち家は財産分与の対象に含まれる
- 持ち家は「引き継ぐ」か「売却する」の2つの選択肢がある
持ち家は財産分与の対象に含まれる
離婚時に持ち家は財産分与の対象になります。
民法上、結婚中に夫婦が共同で築いた財産は、離婚時に分けることができると定められています。
持ち家は典型的な「共有財産」であり、たとえ名義が一方にあったとしても、基本的には財産分与の対象です。
財産分与の基本的な割合は「2分の1ずつ」となるケースが一般的です。
ただし、家を購入した時期や資金の出所によって、この割合は変わることがあります。
例えば、結婚前から所有していた家や、親からの贈与で買った物件は「特有財産」として扱われるため、分与の割合が変わってくるでしょう。
また、住宅ローンが残っている場合は、その残債も考慮する必要があります。

持ち家は「引き継ぐ」か「売却する」の2つの選択肢がある
離婚時の持ち家の扱いには、大きく分けて「引き継ぐ」か「売却する」の2つの道があります。
どちらを選ぶかは、住宅ローンの残高や子どもの有無、双方の経済状況などによって決まるでしょう。
「引き継ぐ」とは、夫婦のどちらかがその家に住み続けることを意味します。
特に子どもがいる場合、生活環境の変化を最小限に抑えるために、この選択をするケースが多いようです。
一方、「売却する」場合は、物件を売って得たお金から住宅ローンの残債を清算し、残りを分けることになります。
どちらの選択肢も、双方が納得できる形で話し合うことが重要です。
合意形成が難しい場合は、弁護士や専門家のアドバイスを求めるのも一つの方法でしょう。
次のセクションでは、持ち家が単独名義の場合と共同名義の場合それぞれについて、より詳しく解説していきます。
◆単独名義の場合(例:夫名義)
- 【夫が住み続ける】:妻に持ち家分の金銭を支払う
- 【妻が住み続ける】:名義変更+ローン引き継ぎ(要金融機関の承認)
- 【売却する】:売却代金からローン完済→差額を財産分与
◆共同名義の場合(夫婦2人の名義)
- 【どちらかが住み続ける】:もう一方の持分を買い取って名義を一本化
- 【共有のまま継続保有】:利用方法や売却時期を協議で決定(リスクあり)
- 【売却する】:売却代金を持分に応じて分配(要ローン完済)
離婚時に所有している家が単独名義である場合
持ち家が一方の配偶者の単独名義になっているケースは珍しくありません。
「名義人だから全て自分のもの」と思いがちですが、実際はそう単純ではないのです。
離婚時の持ち家の扱いは、名義の状況や住宅ローンの有無によって対応が変わります。
住宅ローンの名義人が持ち家に住み続ける場合
ローン名義人がそのまま住み続けるのが、最もシンプルな選択肢です。
住宅ローンと所有権の名義が同じ人なので、基本的に手続きは簡単です。
ただし、離婚に伴う財産分与として、家の評価額から住宅ローン残債を差し引いた「実質的な価値」の半分を相手に支払う必要があります。
例えば、家の評価額が3,000万円で住宅ローンの残高が2,000万円の場合、実質的な価値は1,000万円となります。
この場合、相手に支払う財産分与の額は500万円となるでしょう。
この金額を一括で支払えない場合は、分割払いなどで合意することも可能です。
また、子どもの養育費や他の財産と相殺することで、現金での支払いを減らす方法もあります。
住宅ローンの名義人以外の人が持ち家に住み続ける場合
例えば、夫名義の家に妻と子どもが住み続けるケースを考えてみましょう。
この場合、住宅ローンは名義人である夫が支払い続けるか、名義変更手続きを行う必要があります。
名義人が支払い続ける場合、離婚後も経済的な繋がりが残るため、トラブルの原因になりやすいという点に注意が必要です。
名義変更をする場合は、金融機関の審査を通過する必要があります。
金融機関によっては、収入や勤続年数などの条件を満たさないと名義変更が認められないこともあります。
そのため、事前に住宅ローンを組んでいる金融機関に相談し、名義変更が可能かどうか確認することをおすすめします。
また、名義変更は“借り換え審査”と同義で手数料や印紙税などの費用も必要となり、ハードルが高い点も覚えておきましょう。
持ち家を売り出す場合
双方とも住み続けることを望まない場合は、家を売却する選択肢があります。
売却する場合のメリットは、住宅ローンをきれいに清算できることです。
売却で得た利益は、基本的に夫婦で折半することになります。
例えば、3,000万円で売却でき、ローン残高が2,000万円の場合、差額の1,000万円を夫婦で分けることになるでしょう。
ただし、物件の価格が住宅ローン残高を下回る「オーバーローン状態」の場合は注意が必要です。
この場合、売却金だけでは住宅ローンを完済できないため、不足分を夫婦でどう負担するかを話し合う必要があります。
住宅ローンの残債が多い場合は、売却タイミングを慎重に検討することも大切です。
不動産市場の状況によっては、しばらく待つことで良い条件での売却ができる可能性もあります。
売却を検討する際は、複数の不動産会社に査定を依頼して、適正な価格を把握するのがおすすめです。
離婚時に共同名義の持ち家をどうする?
共同名義の持ち家は、より複雑な問題を含んでいます。
所有権が両者にあるため、一方の意思だけで処分することはできません。
ここでは、共同名義の家を離婚時にどう扱うべきか、具体的な選択肢を見ていきましょう。
夫婦両者が承諾しないと売却できない
共同名義の持ち家は文字通り「共同の所有物」です。
そのため、売却するには必ず両者の合意が必要になります。
もし一方が売却に反対している場合、強制的に売ることはできません。
こうした状況では、話し合いによる解決が基本となります。
双方が売却に同意できない場合は、調停や裁判などの法的手段に訴えることもあります。
特に子どもがいる場合や感情的な対立がある場合は、専門家に相談するのがよいでしょう。
また、共同名義の場合は住宅ローンも両者の責任であることが多いため、支払いの分担についても明確に取り決めておく必要があります。
住み続けている夫婦の一人が新しい連帯保証人または連帯債務者を立てる必要性がある
共同名義の住宅ローンがある場合、どちらか一方が住み続けるには金融機関との再交渉が必要です。
一般的に、住み続ける側は新たな連帯保証人か連帯債務者を立てるよう求められます。
これは離婚によって家を出る側のリスクを軽減するためです。
新しい連帯保証人には親族などが選ばれることが多いでしょう。
ただし、連帯保証人になると将来的な支払い義務を負うリスクがあるため、引き受け手を見つけるのは容易ではありません。
場合によっては、金融機関が単独での支払い能力を厳しく審査することもあります。
収入や勤続年数などの条件を満たさないと、住宅ローンの借り換えや名義変更が認められないこともあるため注意が必要です。
住み続ける夫婦の一人が住宅ローンの借り換えを行うことが求められている
住宅ローンが共同名義の場合、住み続ける側が単独名義へ変更する「借り換え」が必要になることが多いです。
借り換えとは、現在の住宅ローンを一旦清算し、新たに単独での住宅ローンを組むことを意味します。
この手続きには、金融機関による新たな審査が必要です。
単独での返済能力や信用情報などが厳しくチェックされます。
収入が不安定だったり、信用情報に問題があったりすると、借り換えが認められないケースもあります。
また、借り換えには手数料や印紙税などの諸費用がかかることも覚えておきましょう。
借り換えの際は、現在よりも良い条件(低金利など)で組み直せる可能性もあるので、複数の金融機関に相談することをおすすめします。
離婚前に住宅ローンの残高や返済計画を確認し、借り換えが可能かどうか事前に検討しておくことが大切です。
離婚前に確認しておきたい3つのチェックポイント
離婚時の持ち家問題をスムーズに解決するためには、事前の準備が欠かせません。
特に重要な3つのチェックポイントを押さえておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
これから紹介するポイントは、離婚協議の段階で必ず確認しておきましょう。
- 持ち家に関する取り決めは公正証書にしておく
- 子どもがいる場合は養育費も考慮に入れるべき
持ち家に関する取り決めは公正証書にしておく
離婚時の持ち家に関する取り決めは、必ず書面に残しておくことが大切です。
特に公正証書にすることで、法的な効力が生まれ、将来のトラブルを防ぐことができます。
公正証書には以下のような内容を明記しておくとよいでしょう。
- 持ち家の所有権の帰属
- 住宅ローンの返済責任
- 固定資産税などの費用負担
- 将来売却する場合の利益配分
公正証書は、裁判所の強制執行認可の申立てができるため、相手が約束を守らない場合の対抗手段になります。
作成には公証人役場に行く必要があり、双方の合意と印鑑証明書などの書類が必要です。
費用は内容によって異なりますが、一般的に数万円程度を見込んでおきましょう。

子どもがいる場合は養育費も考慮に入れるべき
子どもがいる家庭の離婚では、持ち家の問題と養育費を切り離して考えることはできません。
子どもの生活環境を守るという観点から、両者を総合的に検討する必要があります。
例えば、子どもと母親が持ち家に住み続ける場合、住宅ローンの支払いと養育費の負担バランスを考慮することが大切です。
場合によっては、住宅ローンの負担を養育費の一部と見なすケースもあります。
子どもの年齢や教育費の見通しも踏まえて、長期的な視点で取り決めを行いましょう。
特に子どもが小さい場合は、成人するまでの住居費や教育費を含めた長期計画が必要です。
養育費の算定表を参考にしつつ、家庭の事情に合わせた柔軟な取り決めが望ましいでしょう。
離婚後の子どもの生活を安定させるためにも、養育費と住居の問題は慎重に話し合うことをおすすめします。
弁護士や専門家のアドバイスを受けながら、子どもの最善の利益を考えた取り決めをしましょう。

よくある質問
離婚時の持ち家に関して、多くの方が疑問に感じる点を簡潔にまとめました。
具体的な状況によって対応が異なることもありますので、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
- 離婚後、夫名義の持ち家に妻が住み続けることはできますか?
- 持ち家が共同名義の場合、離婚後のローンはどうなりますか?
- 離婚時に持ち家がオーバーローンの場合はどうすればいいですか?
- 離婚後、持ち家に住み続ける場合の名義変更は必要ですか?
- 離婚時の財産分与で持ち家(マンション)はどう扱われますか?
- 離婚後、どちらが持ち家に住むか決められない場合はどうすればいいですか?
まとめ
離婚時の持ち家問題は、夫婦の経済状況や子どもの有無など様々な要素が絡み合う複雑な問題です。
持ち家は財産分与の対象となり、基本的には「引き継ぐ」か「売却する」かの二択になります。
単独名義の場合と共同名義の場合で対応が異なりますが、いずれの場合も金融機関との交渉や名義変更などの手続きが必要になります。
子どもがいる場合は、養育費との兼ね合いも考慮して総合的に判断することが大切です。
離婚前のチェックポイントとして、持ち家に関する取り決めを公正証書にすることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
離婚は人生の大きな岐路ですが、持ち家という重要な財産についてしっかりと話し合い、互いが納得できる形で解決することが望まれます。
難しい問題に直面した際は、弁護士や専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。