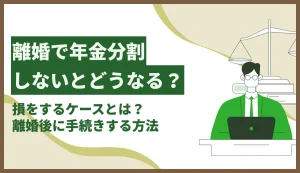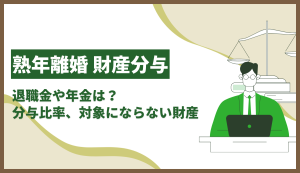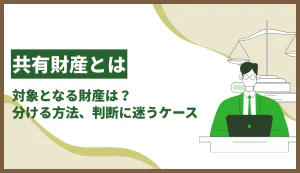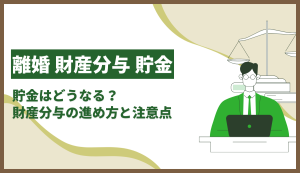財産分与の割合|2分の1の原則とその例外について徹底解説
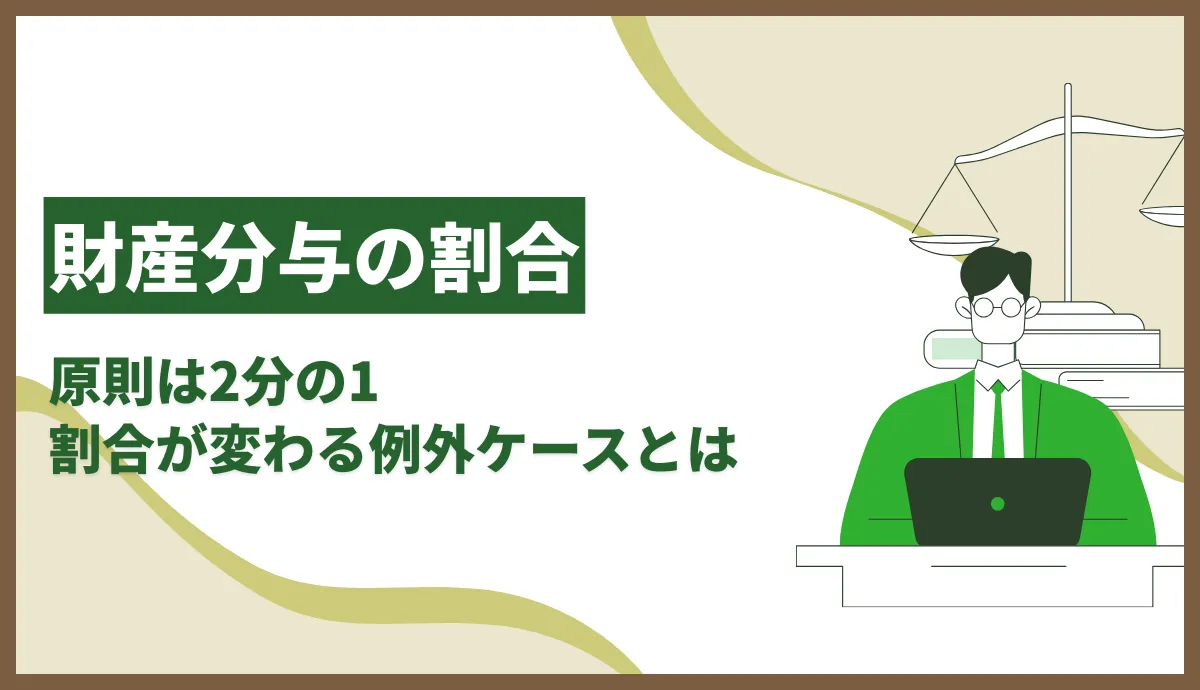
離婚を考えている方にとって、財産分与の割合はとても重要な問題です。
「財産は本当に半分ずつになるの?」「専業主婦だと不利になるの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
実は財産分与の割合は原則2分の1とされていますが、様々な事情によって変動することがあります。
特に共働き家庭や資産が多い場合、財産分与の割合をめぐるトラブルも少なくありません。
この記事では、離婚における財産分与の割合について詳しく解説していきます。
離婚に伴う財産分与の不安を少しでも解消できるよう、具体例を交えながら分かりやすく説明します。
離婚における財産分与の割合は2分の1が原則
日本の民法では、離婚時の財産分与の割合は原則として2分の1と定められています。
離婚を考える多くの方が「本当に財産を半分ずつ分けなければいけないの?」と不安に思うことでしょう。
とはいえ、この「2分の1の原則」はあくまで基本的な考え方であり、様々な要素によって実際の割合が変わることもあります。
この章では財産分与の基本的な考え方から、専業主婦の場合の特殊なケースまで詳しく見ていきましょう。
- 財産分与に関する基本的な考え方
- 専業主婦の場合でも財産分与は2分の1になる?

財産分与に関する基本的な考え方
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を離婚時に分配する制度です。
民法768条には「夫婦が婚姻中に協力して得た財産の清算」という考え方が示されています。
つまり、結婚中に二人で築き上げた財産は夫婦の共同財産であるという前提があるのです。
例えば、結婚してから共働きで住宅ローンを組んで家を購入した場合、その家は夫婦が協力して得た財産になります。
一方で、結婚前から持っていた預金や inherited property(相続財産)などは「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象外となります。
財産分与の割合を決める際には、お互いの貢献度が重要な判断材料となるでしょう。
ただし、最高裁判所の判例では「夫婦の協力によって形成された財産は原則として2分の1ずつ」という基準が示されています。
専業主婦の場合でも財産分与は2分の1になる?
「夫が稼いで妻は家事に専念していた場合、財産分与は不利になるのでは?」と心配される方も多いでしょう。
実は専業主婦(または専業主夫)の場合でも、財産分与の割合は原則として2分の1とされています。
これは、家事・育児・介護といった家庭内労働も、外で働いて収入を得ることと同等の価値があると認められているからです。
つまり、片方が外で働き、もう片方が家庭を守るという役割分担をしていた場合でも、財産形成への貢献度は同等と考えられるのです。
2015年の最高裁判決では「婚姻関係が破綻するまでの間、家事を担当し、夫の稼働環境を整え、子の養育にも協力していた」などを理由に、専業主婦の妻に2分の1の財産分与を認めています。
ただし、専業主婦が何もせず贅沢三昧な生活を送っていたなど、極端なケースでは割合が減ることもあります。
反対に、専業主婦でありながら家業を手伝っていたり、副業で収入を得ていた場合は、2分の1以上の割合が認められることもあるでしょう。
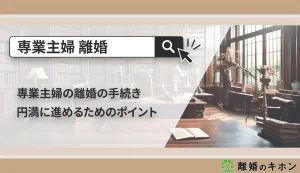
財産分与が必ずしも2分の1にならない場合
財産分与の割合は原則2分の1ですが、様々な事情によって変動することがあります。
「どんな場合に財産分与の割合が変わるの?」と気になる方も多いでしょう。
ここでは、2分の1の原則から外れるケースを具体的に紹介します。
一方が著しく浪費している場合
離婚の原因となった不貞行為や暴力だけでなく、財産形成に悪影響を与えた浪費も財産分与の割合に影響します。
例えば、ギャンブルやブランド品の買いあさりなど、家庭の財産を著しく減らす行為があった場合です。
浪費していた側の財産分与の割合は、相手の寄与度が高かったとみなされ2分の1より少なくなる可能性があります。
実際の裁判例では、夫がパチンコやギャンブルに家計から多額のお金を使っていたケースで、妻の財産分与割合が6割以上認められた事例もあります。
ただし、浪費の程度や期間によって判断は変わるため、明確な基準があるわけではありません。
浪費の事実を証明するためには、銀行の引き出し履歴やクレジットカードの利用明細など、客観的な証拠が必要です。
特別な才能で財産を形成した場合
一方の配偶者が特別な才能や技能によって多額の財産を形成した場合も、財産分与の割合が変わることがあります。
例えば、医師や弁護士などの専門職、芸能人やスポーツ選手、起業家などが該当するでしょう。
特別な才能によって得た収入が大きい場合、その才能を持つ側の寄与度が高いと判断され、財産分与の割合が2分の1よりも多くなることがあります。
ただし、専門的な才能があっても、家庭内での支えがあったからこそ仕事に集中できたという側面もあります。
そのため、相手の内助の功も評価され、完全に才能側に偏った分与になることは少ないようです。
実際の裁判では、才能を持つ側の分与割合が6割から7割程度認められるケースが多いとされています。
特有財産から財産を形成した場合
結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は「特有財産」と呼ばれ、基本的に財産分与の対象外です。
しかし、この特有財産を元手に婚姻中に新たな財産を形成した場合はどうなるのでしょうか。
特有財産を元手に形成された財産は、元手となった特有財産の割合に応じて、財産分与の割合が調整されることがあります。
例えば、夫が結婚前から持っていた1000万円で株式投資を行い、結婚中に2000万円に増えた場合を考えてみましょう。
この場合、元手の1000万円は特有財産として夫のものになりますが、増えた1000万円については夫婦共有の財産と見なされます。
そのため、増えた1000万円のうち500万円が妻の取り分になるという考え方です。
ただし、特有財産と婚姻中の財産の区別が難しいケースも多く、実際の判断は複雑になることが少なくありません。
特に不動産など、価値が変動する資産の場合は専門家の意見が必要になることもあるでしょう。
離婚時の慰謝料と養育費は財産分与の対象とならない
離婚に関連する金銭のやり取りには、財産分与のほかに「慰謝料」と「養育費」があります。
これらは財産分与とは別の制度であり、混同しやすいものの性質が異なるものです。
ここでは、財産分与に含まれない慰謝料と養育費について詳しく見ていきましょう。
- 離婚における慰謝料
- 子どもの養育費
離婚における慰謝料
慰謝料とは、離婚の原因となった精神的苦痛に対する賠償金です。
例えば、不貞行為や暴力・モラハラなどによって精神的苦痛を受けた場合に請求できます。
慰謝料は財産分与とは別物で、過去の精神的な苦痛に対する損害賠償という性質を持っています。
そのため、財産形成への貢献度とは関係なく、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛の程度によって金額が決まります。
実際の慰謝料の相場は、不貞行為の場合で100万円〜300万円程度とされています。
ただし、婚姻期間や不貞行為の回数、子どもの有無などによって金額は変動するでしょう。
慰謝料を請求するためには、相手の不法行為と精神的苦痛の因果関係を証明する必要があります。

子どもの養育費
養育費は、子どもを監護していない親が支払う子どもの成長のための費用です。
これは親としての当然の義務であり、財産分与とは全く別の問題として考える必要があります。
養育費は子どもの権利であり、親の都合で減額や免除になることはありません。
養育費の金額は、子どもの年齢や人数、双方の収入によって算定されます。
「養育費・婚姻費用算定表」という裁判所が作成した表を参考にすることが多いようです。
例えば、父親の年収が500万円、母親の年収が300万円で子ども1人の場合、月額4〜5万円程度が相場とされています。
養育費は子どもが成人するまで(多くの場合は20歳まで)支払い続ける必要があるため、総額では大きな金額になることも少なくありません。
なお、養育費の取り決めは公正証書にしておくと、万が一支払いが滞った場合に強制執行が可能になるので安心です。

財産分与の対象はどの財産が含まれる?
「離婚の際、どの財産が分与の対象になるのか」という疑問を持つ方は多いでしょう。
財産分与の対象となるのは基本的に「夫婦が婚姻中に協力して築いた財産」です。
しかし、具体的にどのような財産が含まれるのか、また対象外となる財産はあるのか知っておく必要があります。
ここでは、財産分与の対象となる財産とならない財産について詳しく解説していきます。
- 婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産
- マイナスの財産(負債)
婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産
財産分与の対象となるのは、結婚してから離婚するまでの間に夫婦で協力して形成した財産です。
これには、給与や事業所得など労働の対価として得た財産だけでなく、様々な資産が含まれます。
婚姻中に取得したものは、たとえ名義が一方にあっても、原則として夫婦の共有財産と見なされます。
以下に、具体的に財産分与の対象となる主な財産を紹介します。
預貯金
夫婦それぞれの名義で持つ預貯金や共同名義の口座にある資金は基本的に分与の対象です。
給与や賞与、ボーナスなどの収入から貯めた預貯金は、名義に関わらず分与対象となります。
ただし、結婚前から持っていた預貯金や相続で得た資金は対象外とされることが多いでしょう。
離婚直前に大量の現金を引き出すなど、財産隠しと思われる行為があった場合は注意が必要です。
そのような場合は、銀行の取引履歴などを証拠として、隠された財産も分与対象に加えるよう主張できます。
保険
生命保険や個人年金保険なども財産分与の対象になることがあります。
特に貯蓄性の高い保険は、解約返戻金という形で現金価値を持つため、分与対象となるケースが多いです。
例えば、保険料を婚姻中の収入から支払っていた場合、その解約返戻金は分与対象になります。
一方、掛け捨てタイプの保険は基本的に財産的価値がないとされるため、分与対象外となることが一般的です。
株式
婚姻中に購入した株式や投資信託などの有価証券も財産分与の対象です。
株式の評価額は、原則として離婚時の時価に基づいて算定されます。
もし結婚前から持っていた株式が婚姻中に値上がりした場合、その値上がり分については分与対象になるケースもあります。
ただし、株価は日々変動するため、財産分与の合意時と実際の分与時で価格差が生じる可能性がある点には注意が必要です。
自動車
結婚中に購入した自動車も財産分与の対象となります。
自動車の評価額は、購入時の価格ではなく離婚時点での時価(中古車価格)に基づいて算定されるのが一般的です。
車両が複数ある場合、それぞれの価値を考慮して分与することになります。
ただ、実務上は車は減価償却が早いため、あまり高額な評価にはならないことが多いでしょう。
不動産
結婚後に購入した土地や家屋などの不動産は、名義人が誰であっても財産分与の対象です。
不動産は一般的に高額であるため、財産分与において最も重要な項目になることが多いでしょう。
評価額は不動産鑑定士による鑑定評価や、路線価などの客観的な指標に基づいて算定されます。
住宅ローンが残っている場合は、不動産の価値からローン残高を差し引いた正味価値が分与の対象となります。
マイナスになる場合は、その不動産に価値はないと判断されることもあるでしょう。
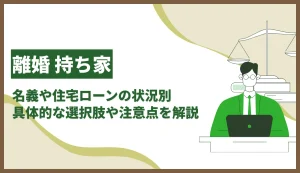
年金
厚生年金や国民年金の「年金分割制度」により、婚姻期間中の年金納付記録を夫婦間で分割することができます。
これは財産分与とは別の制度ですが、離婚時に重要な検討事項となります。
分割割合は原則として2分の1ですが、当事者間の合意により変更することも可能です。
年金分割を希望する場合は、離婚後2年以内に年金事務所への請求が必要になるので注意しましょう。
また、企業年金や個人年金も場合によっては財産分与の対象となることがあります。
マイナスの財産(負債)
財産分与では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も対象となります。
これは「共同で築いた財産」という観点からすると、当然のことと言えるでしょう。
結婚生活のために共同で負担した借金は、夫婦の共有債務として財産分与の対象になります。
例えば、マイホーム購入の住宅ローンや生活費のために組んだ借金などが該当します。
ただし、一方の配偶者が浪費や賭博のために作った借金など、夫婦の共同生活とは関係のない負債は分与対象にならないケースが多いです。
このような場合は、借金を作った本人が全額返済する義務を負うのが一般的でしょう。
なお、負債の名義が誰になっているかは関係なく、その目的や使途によって判断されます。
例えば、夫名義のローンでも家族のための支出であれば共同債務とみなされることが多いでしょう。
離婚時の財産分与割合を決定する4つの方法
財産分与の割合について基本的な考え方を理解したら、次は具体的にどうやって決めるのかを知りたいところでしょう。
離婚時の財産分与割合を決める方法には、主に4つのパターンがあります。
それぞれの方法によって特徴やメリット・デメリットが異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
ここでは、財産分与割合を決める4つの方法について順番に解説していきます。
①当事者の話し合いで決定
財産分与割合を決める最も一般的な方法は、夫婦間の話し合いです。
これは「協議離婚」と呼ばれる日本の離婚制度の基本的な考え方に沿ったものです。
話し合いで決める最大のメリットは、裁判所を通さずに自分たちの意向を最大限反映できる点にあります。
例えば、「家は妻が住み続け、その代わり預貯金は夫が多めに取る」といった柔軟な取り決めが可能です。
話し合いがまとまったら、必ず書面にして残しておくことをおすすめします。
特に「公正証書」にしておくと、万が一相手が約束を破った場合に強制執行ができるため安心です。
ただし、話し合いの際は感情的になりがちなので、冷静な判断ができるよう弁護士などの第三者にアドバイスを求めることも検討しましょう。

②話し合いがまとまらない場合は調停へ
夫婦間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。
調停は裁判官と調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら歩み寄りを促す制度です。
調停のメリットは、専門家の助言を得ながら話し合いができる点と、裁判よりも費用と時間が抑えられる点です。
調停は基本的に月1回程度のペースで行われ、3〜6回程度で終了することが多いようです。
調停で合意に至れば「調停調書」が作成され、これは裁判所の判決と同等の効力を持ちます。
万が一相手が約束を守らない場合は、この調停調書に基づいて強制執行を申し立てることが可能です。
なお、調停を申し立てる際の費用は収入印紙代1,200円と連絡用の郵便切手代のみなので、比較的低コストで利用できます。

③離婚成立後の財産分与調停が不成立なら審判へ移行
すでに離婚が成立した後に財産分与の調停を行い、それでも合意に至らない場合は審判へ移行します。
審判とは、裁判官が法的な判断に基づいて財産分与の割合を決定する制度です。
調停と異なり、審判では当事者の合意は必要なく、裁判官の判断で強制的に決定されます。
審判では、婚姻期間中の財産形成への貢献度や特別な事情などを考慮して判断されます。
一般的には原則の「2分の1」に近い割合になることが多いですが、前述した特別な事情があれば変動することもあります。
審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告を申し立てることで高等裁判所での再審理を求めることができます。
なお、財産分与の請求権は離婚成立後2年間で消滅時効を迎えるため、その点は注意が必要です。
④離婚前の調停が不成立の場合は訴訟を提起
まだ離婚が成立していない状態で財産分与の調停が不成立になった場合は、離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚訴訟では、離婚の成否と財産分与の割合を同時に争うことになります。
訴訟は費用と時間がかかりますが、最終的な解決手段として重要な選択肢です。
訴訟では、当事者が提出した証拠や証言に基づいて判断されるため、しっかりとした準備が必要になります。
特に、財産の評価額や婚姻中の貢献度を証明する資料を集めておくことが重要でしょう。
訴訟の提起には収入印紙代(訴額により異なる)や弁護士費用などがかかりますが、経済的に困難な場合は法律扶助制度の利用も検討できます。
訴訟は1審で終わらない場合、高等裁判所や最高裁判所での審理に進むこともあり、解決までに長期間を要することもあります。

離婚財産分与の割合を弁護士に相談・依頼するメリット
離婚における財産分与は複雑な問題で、専門知識がないと不利な条件で合意してしまうリスクがあります。
特に資産が多い場合や負債がある場合、また相手が非協力的な場合は専門家のサポートが必要かもしれません。
ここでは、財産分与の割合について弁護士に相談・依頼するメリットを詳しく解説します。
- 適正な財産分与割合を決められる
- 相手の所有財産を調査できるから心配がない
- 調停や裁判に移行しても対応してもらえる
適正な財産分与割合を決められる
財産分与に関する法律知識や判例を熟知している弁護士に相談することで、適正な分与割合を知ることができます。
特に財産が多い場合や複雑な資産構成の場合、素人判断ではリスクが高いでしょう。
弁護士は過去の判例や類似ケースの知識に基づいて、あなたの状況に最適な財産分与の割合を提案できます。
例えば「一方の浪費や特別な才能による財産形成」など、2分の1原則の例外に該当するかどうかの判断も的確に行えるでしょう。
また、財産の評価方法についても専門的な知識を持っているため、不動産や事業資産など評価が難しい財産の適切な価値算定ができます。
弁護士に依頼することで感情的になりがちな交渉を客観的に進められるのも大きなメリットと言えるでしょう。
相手の所有財産を調査できるから心配がない
財産分与で最も難しいのは、相手がどんな財産を持っているかを正確に把握することです。
特に別居している場合や、相手が財産を隠していると疑われる場合はなおさらでしょう。
弁護士は法的手段を用いて相手の財産を調査する権限と知識を持っています。
例えば、調停や裁判の場で財産目録の提出を求めたり、金融機関への照会を行ったりすることが可能です。
また、不動産登記簿の調査や年金分割に必要な情報収集なども効率的に行えます。
相手が財産を隠したり、資産価値を過小評価したりする行為を防止できるのは大きな安心材料になるでしょう。
さらに、相手が事業を営んでいる場合など、複雑な財産構成を解析する専門知識も提供してくれます。
調停や裁判に移行しても対応してもらえる
離婚における財産分与は、当事者間の話し合いだけで解決できないケースも多くあります。
そのような場合、調停や裁判へと進むことになるでしょう。
弁護士に依頼していれば、話し合いから調停、さらに裁判へと移行しても一貫して法的サポートを受けられます。
調停や裁判では法的知識や手続きの理解が必要なため、素人が一人で対応するのは非常に困難です。
弁護士は必要な書類の作成や提出期限の管理、適切な証拠の収集など、専門的なサポートを提供します。
また、法廷での主張や反論も的確に行ってくれるため、自分の権利を適切に主張することができるでしょう。
さらに、弁護士が介入することで相手も法的責任を認識し、より真剣に交渉に臨むようになる効果も期待できます。
弁護士費用は決して安くありませんが、適正な財産分与を受けられることを考えれば、将来の経済的安定のための重要な投資と言えるかもしれません。

よくある質問
これまで財産分与の割合について詳しく解説してきましたが、まだ疑問が残っている方もいるでしょう。
ここでは、財産分与の割合に関してよく寄せられる質問に簡潔に回答します。
読者の皆さんが抱きやすい疑問を解消し、より理解を深めるための参考にしてください。
- 財産分与の割合は離婚時の遺産にも適用されますか?
- 離婚時の財産分与の割合はどのように決まるのですか?
- 財産分与の対象にならないものにはどんなものがありますか?
- 子供がいる場合、財産分与の割合に影響はありますか?
- 専業主婦の場合、財産分与の割合は不利になりますか?
- 夫が医師の場合、財産分与の割合はどうなりますか?
- 財産分与の割合を変更することは可能ですか?
- 不貞行為があった場合、財産分与の割合に影響はありますか?
- 財産分与の対象となるものを教えてください。
- 財産分与の割合に関する重要な判例を教えてください。
まとめ
離婚における財産分与の割合は原則として2分の1ですが、様々な要素によって変動することがあります。
専業主婦(夫)の場合でも内助の功が認められ、基本的には2分の1の分与が認められています。
ただし、一方の浪費や特別な才能による財産形成、特有財産からの財産形成などの事情があれば、割合は変わる可能性があるでしょう。
財産分与の対象となるのは基本的に婚姻中に協力して築いた財産で、預貯金や不動産、株式、保険などが含まれます。
また、財産分与の割合を決める方法としては、当事者の話し合い、調停、審判、訴訟という段階があります。
財産分与は複雑な問題なので、専門家である弁護士に相談することで適正な分与割合を知り、相手の財産調査や法的手続きのサポートを受けられるメリットがあります。
離婚は人生の大きな節目ですが、財産分与についての正しい知識を持つことで、将来の経済的な安定を確保する一助となるでしょう。