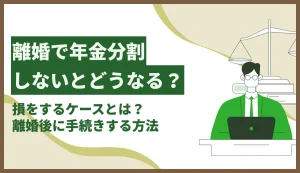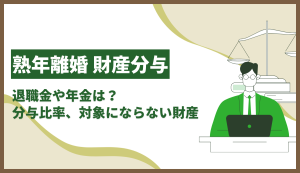共有財産とは?対象になるものの具体例、判断に迷う場合の対処法
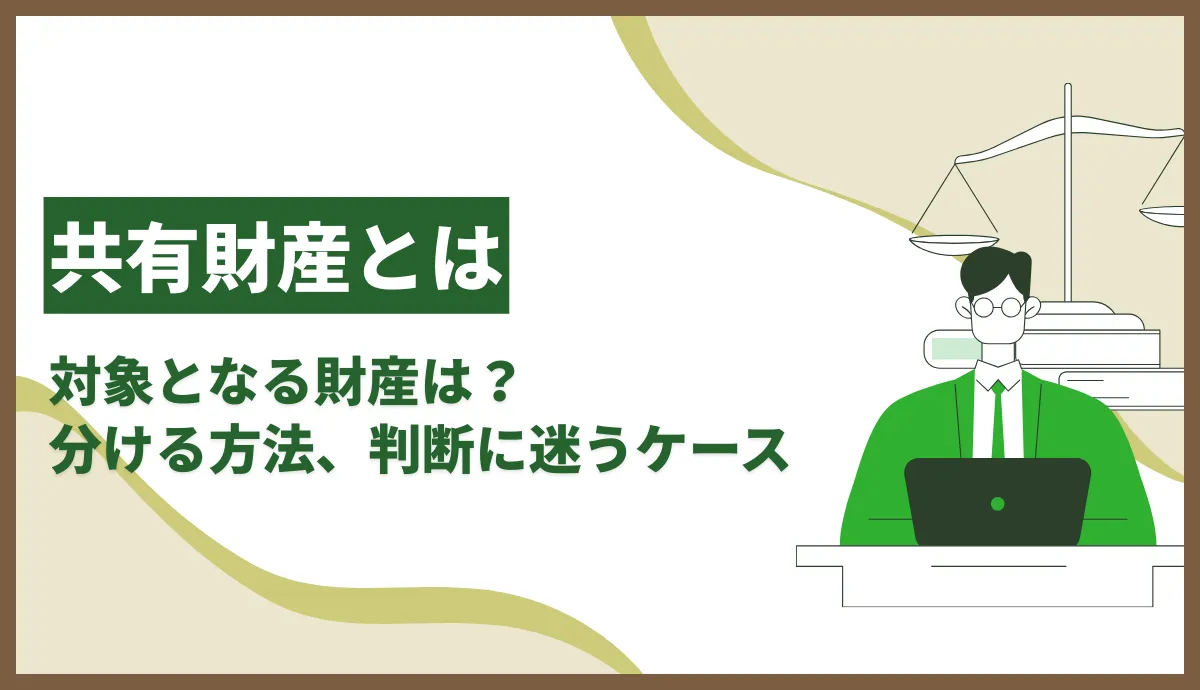
離婚を考えている方や、結婚生活において財産管理に不安を感じている方にとって、「共有財産とは何か」という問いは非常に重要です。
夫婦の間で築いた財産は基本的に共有財産として扱われますが、実際にはどこまでが共有で、何が個人の所有物なのか判断に迷うケースも少なくありません。
財産分与の際には、共有財産と特有財産(個人財産)をきちんと区別することが必要です。
でも、預貯金や不動産、保険、株式など様々な財産について、「これは共有財産に含まれるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
また、離婚となった場合、共有財産はどのような基準で分けられるのかも気になるところでしょう。
この記事では、共有財産について詳しく解説していきます。
法律の専門家ではない方でも理解できるよう、共有財産の基本から実際の分け方まで分かりやすく説明します。
ぜひ最後まで読んで、あなたの財産に関する不安を解消してください。
離婚における財産分与は夫婦の共有財産に限定される
離婚する際に行われる財産分与の対象となるのは、結婚生活中に夫婦で築き上げた「共有財産」のみです。
一方で、個人的に所有していた「特有財産」は原則として財産分与の対象外となります。
共有財産と特有財産の区別がつかないと、離婚時に「これも分けてほしい」と言われても応じる必要がない場合もあります。
逆に、自分が権利を持つ財産を見逃してしまうケースも少なくありません。
このセクションでは、共有財産と特有財産の違いについて詳しく解説していきましょう。
財産分与の対象に該当する「共有財産」
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産のことを指します。
法律上の正式名称は「実質的共有財産」ですが、一般的には「共有財産」と呼ばれています。
共有財産は基本的に夫婦の共同財産とみなされ、離婚時には分配の対象となります。
たとえ片方の名義だけで購入した不動産や預金であっても、結婚中に形成された財産であれば共有財産になるケースがほとんどです。
夫婦の一方が専業主婦(主夫)だった場合でも、家事や育児などの家庭への貢献が認められるため、収入がなくても財産分与の権利があります。
共有財産の代表例としては、婚姻中に購入した家や車、貯蓄した預貯金、株式などの有価証券、退職金の一部などが挙げられます。
| 共有財産の主な例 | 特徴 |
|---|---|
| 給与所得で形成した預貯金 | 婚姻期間中の給与から貯めた資金 |
| 婚姻中に購入した不動産 | たとえ一方の名義でも原則共有財産 |
| 自動車・家財道具 | 婚姻中に購入した生活必需品 |
| 株式・投資信託 | 婚姻中に取得した金融資産 |
| 退職金(婚姻期間分) | 婚姻期間に対応する部分 |

財産分与の対象に該当しない「特有財産」
特有財産とは、結婚前から持っていた財産や婚姻中でも個人的に取得した財産を指します。
こうした財産は原則として財産分与の対象外であり、所有者が単独で権利を持ちます。
特有財産は「個人の固有財産」と考えられるため、離婚時に分ける必要はありません。
例えば結婚前から所有していた不動産や、結婚後に相続や贈与で取得した財産は、通常は特有財産となります。
ただし、特有財産であっても婚姻中に大きく価値が上昇した場合は、その増加分が共有財産とみなされることがあります。
また、特有財産と共有財産が混ざってしまったケースでは、元の区別が難しくなることも少なくありません。
| 特有財産の主な例 | 特徴 |
|---|---|
| 結婚前からの預貯金 | 婚姻前に形成された資金 |
| 相続・贈与で得た財産 | 親族からの相続や贈与で得た資産 |
| 結婚前から所有する不動産 | 婚姻前から所有権がある不動産 |
| 慰謝料・損害賠償金 | 個人的な精神的、身体的損害に対する補償 |
| 個人的な記念品・思い出の品 | 思い出や個人的価値のある物品 |
共有財産と特有財産の区別は離婚時の財産分与において非常に重要です。
どちらに該当するか判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

共有財産に該当するものは何か?
共有財産に何が含まれるのか具体的に知っておくことは、離婚を考える際に非常に重要です。
ここからは、共有財産として認められる代表的な財産を詳しく見ていきましょう。
婚姻期間中に形成された財産には様々な種類がありますが、基本的にはすべて共有財産と考えることができます。
名義が一方の配偶者だけになっていても、それだけで特有財産になるわけではないので注意が必要です。
以下では、共有財産として扱われる主な資産について詳しく解説します。
現金および預貯金
夫婦の預貯金は、結婚期間中に形成されたものであれば基本的に共有財産です。
口座名義が一方の配偶者だけでも、婚姻中の収入から貯めたお金は共有と見なされます。
夫婦のいずれかが働いて得た給料で貯めた預貯金は、名義に関わらず共有財産になります。
例えば、夫名義の銀行口座に貯金されている800万円があった場合、それが婚姻期間中に貯められたものなら、妻にもその一部の権利があるのです。
専業主婦(主夫)の場合でも、家事や育児などの家庭への貢献が認められるため、配偶者の収入から形成された預貯金への権利があります。
ただし、結婚前から持っていた預金や、相続、贈与で得た現金は特有財産に当たるため、分与の対象外となります。
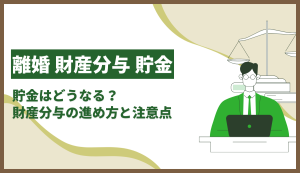
家や土地などの不動産
結婚中に購入した家や土地は、たとえ名義が一方だけであっても、共有財産として扱われます。
住宅ローンの返済も婚姻中の共同生活の一部と考えられるからです。
不動産の名義が夫だけでも、婚姻中に購入したマイホームは共有財産になるのが一般的です。
不動産の購入資金が結婚前からの貯金(特有財産)だった場合は、その部分については特有財産の性質を持ちます。
しかし、婚姻中のローン返済が行われていれば、その分は共有財産としての性質を持つことになります。
また、結婚前から所有していた不動産でも、婚姻中に価値が上昇した場合、その増加分が共有財産とみなされることもあります。
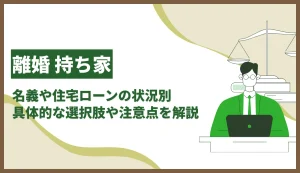
保険に関する権利
婚姻中に加入した生命保険や医療保険も、共有財産に含まれます。
具体的には、保険の解約返戻金や満期保険金などが財産分与の対象となります。
保険料が婚姻中の収入から支払われていれば、その保険は共有財産と見なされます。
例えば、夫が契約者となっている生命保険でも、婚姻中の給与から保険料を支払っていた場合、その解約返戻金は共有財産になります。
ただし、保険金の受取人が指定されている場合、その権利は受取人に帰属するため、必ずしも財産分与の対象にならないケースもあります。
離婚時に保険契約をどうするかは、解約するか継続するかによって対応が異なるので、専門家に相談するのがおすすめです。
株式などの有価証券
婚姻中に購入した株式や投資信託などの有価証券も共有財産に含まれます。
証券口座の名義に関わらず、結婚中の収入で購入したものであれば分与の対象です。
株式投資で得た利益も、婚姻中の共同財産として扱われるのが原則です。
例えば、夫が自分名義の証券口座で株式投資をしていた場合でも、その資金が婚姻中の収入から出ていれば、その株式および利益は共有財産となります。
ただし、結婚前から所有していた株式や、相続、贈与で取得した有価証券は特有財産となり、原則として分与の対象外です。
株式の価値は変動するため、財産分与の際には評価時点の価値が基準となる点に注意が必要です。
車
婚姻中に購入した自動車は、共有財産として扱われます。
車検証の名義が一方だけであっても、婚姻中の収入で購入した場合は共有とみなされます。
通勤や買い物など、夫婦の共同生活で使用されていた車は共有財産です。
例えば、妻名義の軽自動車でも、夫の給料で購入し家族で使っていた場合は共有財産になります。
ただし、自動車は時間の経過とともに価値が下がる資産です。
財産分与の時点での中古車としての評価額が基準となるため、購入時よりも大幅に低い評価になることがほとんどです。
生活に必要な家財道具
冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの家電製品や家具も共有財産に含まれます。
これらは夫婦の共同生活のために購入された物と考えられるからです。
日常生活で使用する家財道具は、購入した時期や金額によらず基本的に共有財産となります。
ただし、家財道具は中古品としての価値が低いため、財産分与においてあまり重視されないことが多いです。
実際の分与では、「使っている方がそのまま使い続ける」という解決方法が一般的です。
高額な家財 (高級家具やブランド家電など) については、その価値を考慮して分与が行われることもあります。
骨董品・美術品・貴金属等
婚姻中に購入した骨董品、美術品、貴金属なども共有財産です。
これらは時に高額な価値を持つため、財産分与では重要な対象となります。
婚姻中に購入した宝飾品や絵画などの価値ある品は、たとえ一方が単独で使用していても共有財産です。
例えば、夫が妻にプレゼントした高級時計やジュエリーも、基本的には共有財産と見なされます。
ただし、明確に贈与の意思が示されていた場合は、受け取った側の特有財産となる可能性もあります。
骨董品や美術品は専門的な評価が必要なため、財産分与の際には専門家による鑑定が行われることもあります。
退職金および年金
退職金は、婚姻期間に対応する部分が共有財産として扱われます。
勤続年数のうち婚姻期間に相当する割合に応じて、共有財産の範囲が決まります。
退職金は夫婦が協力して形成した財産の一部と考えられ、婚姻期間分が共有財産になります。
例えば、勤続20年のうち15年が婚姻期間だった場合、退職金の4分の3(15/20)が共有財産の対象となります。
年金については、厚生年金の被保険者期間が婚姻期間と重なる部分が「年金分割制度」の対象となります。
国民年金の場合は「第3号被保険者期間」に対応する部分が分割の対象です。
退職金や年金の分与は複雑なケースが多いため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

ローンをはじめとする借入
共有財産には資産だけでなく、婚姻中に発生した債務(ローンや借金)も含まれます。
これらも夫婦で分担すべき対象となります。
住宅ローンや車のローンなど、婚姻中の共同生活のために負った債務は共有の負債です。
例えば、夫名義の住宅ローンでも、共同生活のための家を購入したものであれば、残債も共有の負債となります。
ただし、一方の浪費や賭博などによる借金は、共有の負債とはみなされないケースが多いです。
このような場合は、借りた本人が全額返済する責任を負うのが一般的です。
債務の性質や使途によって共有か否かの判断が異なるため、詳細な事情を確認することが大切です。
住宅ローンの場合、離婚後の支払い方法や名義変更など複雑な問題があるため、金融機関や専門家に相談するのがおすすめです。
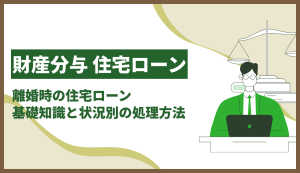
共有財産は離婚時にどのような基準で分けられるか?
共有財産が何かを理解したところで、次は「どのように分けるのか」という点が気になるところです。
共有財産の分け方には明確な法律上のルールがあります。
民法768条では「夫婦が婚姻中に有していた財産の額その他一切の事情を考慮して」分けると規定されています。
一般的に共有財産は2分の1ずつという「平等分割」が基本とされていますが、必ずしもそうとは限りません。
財産分与においては、婚姻期間中の夫婦それぞれの貢献度を考慮して分配割合が決められます。
例えば、長期間の専業主婦が家事や育児で貢献していた場合、家庭外で働いていた配偶者と同等の貢献があったと認められるのが一般的です。
ただし、婚姻期間が短い場合や、一方が浪費や借金を繰り返していた場合などは、平等分割から乖離することもあります。
財産分与の割合に影響を与える要素としては、以下のようなものが挙げられます。
| 考慮される要素 | 具体例 |
|---|---|
| 婚姻期間の長さ | 長期間の婚姻ほど平等分割に近づく傾向 |
| 各配偶者の収入や財産形成への貢献 | 家事育児も経済的貢献と同等に評価 |
| 婚姻中の生活態度 | 浪費、DV、不貞行為などがあった場合は不利に |
| 離婚後の生活への配慮 | 子どもを養育する側への配慮 |
| 年齢や健康状態 | 高齢や病気など働く能力に影響がある場合 |
実際の分割割合は当事者間の話し合いで決めることもできますが、合意できない場合は家庭裁判所での調停や審判によって決定されます。
裁判所では、上記の要素に加えて「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」という3つの観点から分与額を判断することが多いです。
清算的財産分与とは、婚姻中に形成された財産を公平に分けるという観点です。
扶養的財産分与は、離婚後の生活への配慮から、経済力の弱い配偶者への支援を考慮するものです。
慰謝料的財産分与は、離婚の原因を作った配偶者への制裁的な要素を含む分与方法です。
これらの要素を総合的に判断して、最終的な分割割合が決まります。
共有財産の公平な分割を実現するためには、財産の全体像を正確に把握することが何よりも重要です。

共有財産を分ける方法
共有財産を具体的にどのように分けるのかは、離婚時の大きな課題となります。
財産分与の方法には主に3つのパターンがあり、それぞれの状況に応じて選択することが大切です。
共有財産を分ける代表的な方法は「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つです。
1つ目の「現物分割」は、財産をそのままの形で分け合う方法です。
例えば、Aさんは不動産を取得し、Bさんは預貯金を取得するといった形で、財産の種類ごとに分けます。
この方法のメリットは手続きが比較的簡単なことですが、財産の評価が難しいケースもあります。
2つ目の「換価分割」は、財産を売却して現金化した後に分配する方法です。
不動産や自動車などを売却して得た現金を分け合うため、分割が明確になるというメリットがあります。
ただし、売却手続きに時間がかかる点や、売却損が生じる可能性がある点には注意が必要です。
3つ目の「代償分割」は、一方が財産を取得し、他方にその代償として現金などを支払う方法です。
例えば、夫が自宅不動産を取得する代わりに、妻に不動産の評価額の半分を現金で支払うといった形です。
この方法は財産を維持したい場合に有効ですが、支払う側に十分な資金が必要となります。
| 分割方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのままの形で分ける | 手続きが比較的簡単 | 財産評価が難しい場合がある |
| 換価分割 | 財産を売却して得た現金を分ける | 分割が明確になる | 売却手続きに時間がかかる |
| 代償分割 | 一方が財産を取得し、代償を支払う | 財産を維持できる | 支払側に十分な資金が必要 |
実際の財産分与では、これらの方法を組み合わせて行うことが一般的です。
例えば、「不動産は夫が取得して代償金を妻に支払い、預貯金は半分ずつ分ける」といった具合です。
具体的な分け方は夫婦間の協議で自由に決めることができますが、合意に至らない場合は調停や審判で決定されます。
共有財産の分け方を決める際は、税金面での影響も考慮する必要があります。
財産分与として不動産を取得した場合、原則として贈与税はかかりませんが、代償金の支払いなどによっては課税対象となる場合もあります。
財産分与を請求する際に期限は定められているか?
財産分与を請求する権利には期限が設けられています。
民法768条の2により、離婚成立から2年以内に請求しなければなりません。
離婚後2年を過ぎると財産分与請求権は消滅するため、このタイムリミットを意識することが重要です。
離婚協議中から財産分与についても話し合いを進めておくことで、期限切れのリスクを避けることができます。
また、離婚後に隠し財産が発覚した場合でも、基本的には2年の期限内に請求する必要があります。
ただし、相手の詐欺的行為によって財産が隠されていた場合などは、例外的に期限の延長が認められることもあります。
財産分与の請求は口頭でも可能ですが、後のトラブル防止のためには内容証明郵便など証拠が残る形で行うことをおすすめします。
離婚時に財産分与について合意に至らなかった場合でも、とりあえず請求だけしておくことで権利を保全できます。

離婚時に共有財産か否かが不明な財産がある場合
離婚時に財産が共有財産なのか特有財産なのか判断に迷うケースは少なくありません。
特に長年の結婚生活の中で、財産の出所や取得時期が曖昧になっていることも珍しくないでしょう。
財産の区分けが不明確な場合は、「共有財産と推定される」という原則が適用されることが多いです。
つまり、特有財産であることを主張する側が、その証拠を示す必要があります。
例えば、結婚前から所有していた不動産であることを証明するには、取得時の契約書や登記簿謄本などの書類が必要になります。
同様に、相続で得た財産であれば、遺産分割協議書や相続関係の書類が重要な証拠となります。
特に注意が必要なのが、結婚前の預金と結婚後の預金が同じ口座に混在しているケースです。
このような場合、結婚前の残高を明確に証明できる通帳や取引履歴がなければ、全額が共有財産と判断されることもあります。
逆に、結婚後に受け取った相続財産を夫婦の共同口座に入れてしまうと、共有財産化してしまう可能性もあるので注意が必要です。
| 不明確な財産の例 | 判断のポイント | 必要な証拠 |
|---|---|---|
| 結婚前後にまたがる預金 | 結婚時点での残高が明確か | 結婚前の通帳、取引履歴 |
| 相続財産が混合した口座 | 相続時期と金額が証明できるか | 遺産分割協議書、入金記録 |
| 贈与された財産 | 個人に対する贈与かどうか | 贈与契約書、親族からの証明 |
| 婚姻中に名義変更した不動産 | 変更前の取得経緯 | 登記簿謄本、変更前の契約書 |
財産の性質について争いがある場合の解決方法としては、以下のようなものがあります。
- まずは当事者間での話し合い
- 弁護士を交えた協議
- 家庭裁判所での調停
- 最終手段としての審判または訴訟
財産の性質が不明確な場合に備えて、日頃から以下のような対策を取っておくと安心です。
- 結婚前の財産の証拠(通帳、契約書など)を保管しておく
- 相続や贈与で得た財産は別口座で管理する
- 特有財産と共有財産を明確に区別した資産管理を心がける
- 重要な財産については夫婦で話し合い、合意内容を文書化しておく
共有財産か特有財産かの判断が難しいケースでは、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

相手が共有財産を隠している可能性があるので注意が必要
離婚時に共有財産を公平に分けるためには、まず財産の全容を把握することが欠かせません。
しかし残念ながら、配偶者が意図的に財産を隠すケースは少なくありません。
離婚を考え始めた時点で、相手が預金を引き出したり、財産を親族名義に移したりするといった行動に出ることがあります。
特に家計管理を一方が担っていた場合、もう一方は家庭の財産状況を十分に把握できていないことも多いでしょう。
財産隠しの代表的な手口としては、以下のようなものが挙げられます。
- 秘密口座への資金移動
- 親族や友人名義での資産保有
- 退職金や賞与の受け取り隠し
- 架空の借金や支出の捏造
- 高額な現金引き出し
- 投資や保険への資金移動
財産隠しを防ぐためには、日頃から家計の状況を把握しておくことが大切です。
具体的には、通帳や証券口座の残高、不動産の権利書類、生命保険の証券などを確認しておきましょう。
もし離婚協議が始まってから財産隠しの疑いが生じた場合は、以下の方法で調査することが可能です。
| 調査方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 財産開示請求 | 裁判所を通じて相手の財産状況を開示させる | 強制力があるが手続きに時間がかかる |
| 弁護士による調査 | 専門家が法的手段を用いて調査 | 専門的な知識で効率的に調査できる |
| 税務調査の記録確認 | 税務署に開示請求を行う | 税金関連の財産情報が得られる |
| 預金照会 | 裁判所を通じて金融機関に照会 | 隠された口座を発見できる可能性がある |
特に注意すべきは、離婚を考え始めた時期の前後における不自然な資金移動です。
高額な引き出しや送金、名義変更などがあれば、証拠として記録しておきましょう。
隠し財産が見つかった場合は、それも含めて財産分与の対象とすることができます。
財産隠しは法的に認められない行為であり、発覚した場合は裁判所から厳しい判断を受けることがあります。
万が一、相手が財産を隠している疑いがある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けることで、適切な対応策を取ることができ、公正な財産分与の実現につながります。
よくある質問
共有財産に関して読者のみなさんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
離婚時の財産分与に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
- 結婚後に迎え入れたペットは共有財産として財産分与の対象になりますか?
- 配偶者が通帳を見せず共有財産の把握ができません。どう対処すればいいですか?
- 共有財産が一方の夫婦によって使い込まれた場合、財産分与はどうなりますか?
- 結婚前から所有している不動産は財産分与の対象になりますか?
- 専業主婦でも貯金に対する財産分与を請求できますか?
- 夫婦で共有口座を持つメリットと注意点を教えてください。
- 離婚時に財産分与しない方法はありますか?
- 夫婦財産契約とは何か、共有財産との関係を教えてください。
まとめ
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産のことであり、離婚時の財産分与の対象となります。
共有財産には現金や預貯金、不動産、車、株式、保険、家財道具などが含まれ、名義が一方だけであっても夫婦の共同財産と見なされます。
一方、結婚前から所有していた財産や相続、贈与で得た財産は「特有財産」として、基本的に分与の対象外となります。
財産分与は一般的に平等分割が基本ですが、婚姻期間や各自の貢献度などを考慮して割合が調整されることもあります。
分割方法には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類があり、状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
財産分与の請求権には離婚成立から2年の期限があるため、早めに行動することが大切です。
また、財産隠しの可能性も念頭に置き、日頃から家計の状況を把握しておくことをおすすめします。
共有財産に関する正しい知識を持つことで、離婚時の財産分与をスムーズに進め、公平な解決につなげることができるでしょう。