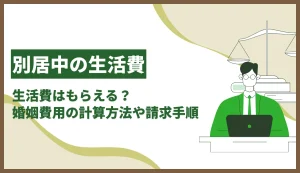婚姻費用が高すぎる!おかしいと感じる代表的なケースと減額対策
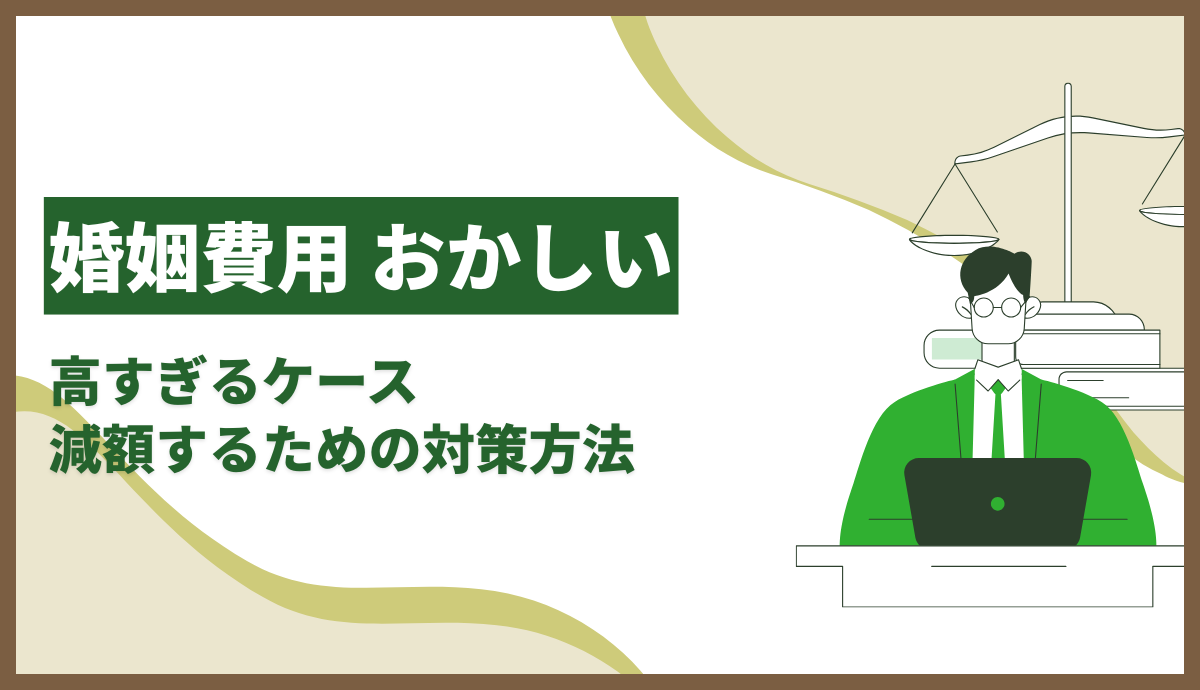
「婚姻費用を払いたくない…」「婚姻費用の金額がおかしい」と感じている方は少なくありません。
別居中の配偶者に支払う婚姻費用が、自分の状況からすると理不尽に思える場合があるでしょう。
特に、妻に不貞行為があった場合や子どもと会わせてもらえないのに支払い義務があるのは納得がいかないものです。
実際のところ、婚姻費用がおかしいと感じるケースは珍しくありません。
婚姻費用の算定方法や、支払いが免除、減額される可能性についても知っておくべきでしょう。
この記事では、婚姻費用がおかしいと感じる代表的なケースと対処法について解説していきます。
婚姻費用で悩んでいる方に向けて、法的な観点から具体的な対応策まで分かりやすく説明します。
婚姻費用の基本概念とは?
婚姻費用とは、夫婦が共同生活を送るために必要な生活費のことです。
家賃や食費、光熱費だけでなく、医療費や教育費など生活全般にかかる費用も含まれます。
通常は夫婦が一緒に暮らしている間は特に意識することなく、各自の収入から分担して支払っているでしょう。
しかし別居状態になると、婚姻費用の分担方法が大きな問題になることがあります。
別居中でも法的に婚姻関係が続いている以上、夫婦の扶養義務は継続します。
そのため、収入が多い配偶者は収入が少ない配偶者に対して婚姻費用を支払う必要があるのです。
婚姻費用が発生する法的根拠
婚姻費用の支払い義務は民法第760条に明確に定められています。
夫婦は互いに協力して生活する義務があり、その一環として生活費を分担することが法律で規定されているのです。
この義務は単なる道徳的なものではなく、法的に強制力を持つ義務です。
もし支払いに応じない場合、裁判所に申し立てをすることで婚姻費用分担請求が可能になります。
婚姻費用の支払いを拒否し続けると、最終的には給与の差し押さえや財産の差し押さえといった強制執行の対象になることもあります。
つまり、「婚姻費用の支払いはおかしい」と感じても、法的には正当な義務なのです。
ただし、後述するように状況によっては減額や免除が認められるケースもあります。
| 法的根拠 | 民法第760条(夫婦の協力義務) |
|---|---|
| 支払い義務者 | 収入が多い配偶者 |
| 支払い対象 | 日常生活に必要な一切の費用 |
| 支払い期間 | 別居開始から離婚成立まで |
| 不払いの場合 | 強制執行の対象になる可能性あり |

婚姻費用がおかしいと感じる代表的なケース
婚姻費用の支払いが「おかしい」と感じるケースは多く、特に男性側からの不満が目立ちます。
なぜそう感じるのか、具体的なケースを見ていきましょう。
妻に不貞行為があったケース
「妻が浮気をしたのに、なぜ私が婚姻費用を払わなければならないのか」という思いは当然でしょう。
不貞行為は離婚原因として認められる重大な事由です。
しかし裁判所は不貞行為の有無と婚姻費用の支払い義務を直接結びつけて判断しないことが多いのが現実です。
法律上、婚姻関係が続いている限り、経済力の差に基づいて婚姻費用の支払い義務は継続します。
とはいえ、不貞行為があった場合には、その事実を婚姻費用の減額理由として主張することは可能です。
裁判所によっては、妻の不貞行為を考慮して婚姻費用を減額する判断をするケースもあります。

妻が勝手に別居を始めたケース
妻の一方的な意思で別居が始まったのに、夫が婚姻費用を支払うことに疑問を感じるのは自然なことです。
特に、夫に非がなく妻が突然家を出て行ったような場合には、不公平感が強くなります。
しかし法律上は、別居の理由や経緯に関わらず、経済力の差があれば婚姻費用の支払い義務が生じるのが原則です。
ただし、妻の別居に合理的な理由がない場合は、その点を裁判所に主張することで減額の可能性があります。
例えば「夫からのDVや暴言などがなかったにもかかわらず、突然別居した」という事実は、減額の材料になるでしょう。
妻が実家で生活に困っていないケース
妻が裕福な実家に身を寄せている場合、「生活に困っていないのになぜ支払う必要があるのか」という疑問が生じることがあります。
確かに、妻の両親が十分な経済力を持ち、娘の生活を全面的に支援しているケースもあるでしょう。
しかし裁判所は基本的に、妻の両親からの援助を婚姻費用の算定において考慮しません。
法的には夫婦間の扶養義務が優先され、第三者(両親など)からの援助は二次的なものと見なされるからです。
ただし、妻の実家暮らしによって住居費などの生活費が大幅に削減されている場合は、その事実を基に減額交渉の材料にすることは可能です。
妻も収入を得ているケース
妻にも一定の収入がある場合、「なぜ自分だけが婚姻費用を負担しなければならないのか」という不満が生じます。
この場合、婚姻費用は夫婦の収入差に基づいて算定されるのが基本です。
妻の収入が増えれば、その分だけ夫が支払うべき婚姻費用は減額されます。
例えば、夫の年収が600万円、妻の年収が200万円の場合、その差額である400万円に基づいて婚姻費用が算定されます。
妻の収入が増えた場合には、婚姻費用の減額請求を検討しましょう。
特に別居当初は専業主婦だったが、その後パートやアルバイトを始めたようなケースでは、婚姻費用の見直しが必要になります。
妻が離婚する意思がないケース
婚姻費用は離婚が成立するまで支払い続ける必要があるため、妻が離婚に応じない状況は特に不満が大きくなります。
「別居してるのに離婚に応じず、婚姻費用だけはしっかり請求してくる」というケースも少なくありません。
離婚に応じないことを理由に婚姻費用の支払いを拒否することはできません。
しかし、別居期間が長期化し、かつ妻が正当な理由なく離婚協議に応じない場合は、裁判所に対して「婚姻関係が破綻している」として離婚調停や離婚訴訟を起こすことを検討すべきでしょう。
また、このようなケースでは早期に弁護士に相談することが非常に重要です。

子供との面会を拒否されているケース
子どもと会わせてもらえないのに養育費を含む婚姻費用を支払うことへの不満は大きいでしょう。
しかし法律上、面会交流の可否と婚姻費用の支払い義務は基本的に別問題として扱われます。
子どもの福祉を最優先する観点から、面会を拒否されていることを理由に養育費の支払いを拒むことはできません。
ただし、面会交流を求める調停や審判を申し立てることは可能です。
裁判所の判断で面会交流が認められれば、定期的に子どもと会う権利が法的に保障されます。
また、婚姻費用の支払いと面会交流をセットで交渉することで、解決の糸口が見つかるケースもあります。

婚姻費用請求が認められないケース
「婚姻費用がおかしい」と感じる状況は多いですが、実際に婚姻費用の支払いが免除されるケースもあります。
どのような場合に婚姻費用請求が認められないのか、確認していきましょう。
婚姻費用の支払いが免除される可能性が高いのは、別居に至った原因が妻側にある場合です。
例えば、妻の不貞行為が明らかで、それが原因で別居状態になった場合は、婚姻費用の減額や免除が認められることがあります。
ただし、単に「妻が浮気した」という事実だけでは免除は難しく、その行為が婚姻関係の破綻の直接原因であることを証明する必要があります。
また、妻が正当な理由なく同居義務を拒否している場合も、婚姻費用が減額、免除されるケースがあります。
さらに、妻側にも十分な収入があり、経済的援助が不要な場合も婚姻費用の支払い義務が認められないことがあります。
特に妻の収入が夫を上回るケースでは、逆に妻から夫への婚姻費用支払いが命じられる可能性もあるでしょう。
| 婚姻費用が認められないケース | 具体例 |
|---|---|
| 妻の不貞行為が原因で別居 | 妻の浮気が明確に証明され、それが別居の直接原因 |
| 正当な理由のない同居拒否 | DVや暴言がないのに妻が一方的に家を出た |
| 妻の収入が十分にある | 夫よりも妻の収入が多い、または同程度 |
| 長期間の音信不通 | 妻が行方不明になり連絡が取れない状態 |
| 婚姻費用の請求権の濫用 | 離婚を引き延ばす目的だけで婚姻費用を請求 |
ただし、これらのケースでも自己判断で婚姻費用の支払いを停止するのは非常にリスクが高いことを覚えておきましょう。
裁判所の判断を経ずに支払いを拒否すると、強制執行の対象となる可能性があります。
婚姻費用の支払いに疑問を感じる場合は、必ず弁護士に相談し、適切な法的手続きを踏むことが重要です。
婚姻費用を減額するための5つの対策方法
婚姻費用の支払いが完全に免除されるケースは限られていますが、減額できる可能性は十分にあります。
ここでは具体的な減額のための対策方法を5つ紹介します。
- 妻の不貞行為の証拠を収集する
- 正しい婚姻費用の金額を確認する
- 支払いが困難な状況を具体的に伝える
- 離婚手続きを迅速に進める
- 婚姻問題に詳しい弁護士に相談する
①妻の不貞行為の証拠を収集する
妻の不貞行為は婚姻費用の減額理由として認められる可能性があります。
ただし、単なる疑いや噂では不十分で、具体的で客観的な証拠が必要になります。
有効な証拠としては、不貞行為の相手とのLINEやメール、ホテルの領収書、デート現場の写真などが挙げられます。
証拠収集の際は、違法な手段(盗聴や無断でのスマホチェックなど)を用いないよう注意しましょう。
こういった証拠は離婚裁判でも有利に働くため、弁護士のアドバイスを受けながら適切に保管することが大切です。

②正しい婚姻費用の金額を確認する
妻側から提示された婚姻費用の金額が適正かどうか、必ず確認しましょう。
特に自分で計算せずに妻の言い値をそのまま支払っている場合、過剰な負担を強いられている可能性があります。
婚姻費用の算定には裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が基準になります。
この表に夫婦それぞれの収入と子どもの人数を当てはめることで、標準的な婚姻費用が算出できます。
また、収入証明書や源泉徴収票など、正確な収入を証明できる書類を用意することも重要です。
適正額の算定方法
婚姻費用の適正額を算定するには、以下の要素を考慮する必要があります。
まず夫婦それぞれの手取り収入を確認します。
次に、婚姻費用算定表に当てはめて基本額を出します。
ここから特別な事情による減額要素(住宅ローンの負担や親の介護費用など)を考慮して調整を行います。
例えば、夫の年収600万円、妻の年収200万円、子ども1人の場合、算定表からの基本額は約8〜10万円程度ですが、特別な事情があれば減額の可能性があります。
自己判断だけで金額を決めず、専門家のチェックを受けることをおすすめします。
③支払いが困難な状況を具体的に伝える
婚姻費用の支払いが経済的に困難な場合は、その状況を具体的に説明することが重要です。
単に「払えない」と主張するだけでは説得力に欠けます。
例えば、「住宅ローンが月々15万円あり、自分の生活費を切り詰めても婚姻費用の全額支払いは困難」といった具体的な説明が必要です。
固定費の内訳や生活費の詳細な収支を書面にまとめ、客観的な数字で示すと効果的でしょう。
また、失業や減収など収入が減少した事情があれば、それを証明する書類も用意しておくと良いでしょう。
交渉の際には感情的にならず、冷静に事実に基づいた主張を心がけることが大切です。
④離婚手続きを迅速に進める
婚姻費用は離婚が成立するまで支払い続ける必要があるため、離婚手続きを迅速に進めることも重要な対策です。
別居期間が長引けば長引くほど、支払う婚姻費用の総額は増えていきます。
まずは話し合いによる協議離婚を目指しましょう。
話し合いが難しい場合は、早めに離婚調停を申し立てることを検討すべきです。
調停でも合意に至らない場合は、離婚訴訟を提起することになります。
特に別居期間が3年以上になると、「婚姻関係が破綻している」として裁判所が離婚を認める可能性が高まります。
離婚手続きを進める際も、感情的にならず冷静な対応を心がけることが肝心です。

⑤婚姻問題に詳しい弁護士に相談する
「婚姻費用がおかしい」と感じたら、早めに専門家に相談することが最も効果的な対策です。
離婚問題に詳しい弁護士は、あなたの状況に最適な解決策を提案してくれます。
弁護士に依頼するメリットは、法的知識に基づいた適切なアドバイスが得られることです。
また、感情的になりがちな交渉を冷静に代行してもらえる点も大きなメリットでしょう。
弁護士費用は一般的に初回相談料が5,000円〜10,000円程度、着手金が20万円〜30万円程度かかります。
しかし、適切な対応によって婚姻費用が減額されれば、長期的には弁護士費用以上のメリットが得られる可能性が高いでしょう。
特に婚姻費用の金額が大きい場合や、複雑な事情がある場合は、弁護士への相談を強くおすすめします。

よくある質問
婚姻費用に関する疑問は多岐にわたります。
ここでは「婚姻費用がおかしい」と感じる方々から寄せられる代表的な質問にお答えします。
- 婚姻費用の支払いを拒否するとどうなりますか?
- 婚姻費用が高すぎる場合の対処法を教えてください。
- 別居中でも婚姻費用の支払い義務はありますか?
- 婚姻費用はいつまで支払う必要がありますか?
- 共働きの場合、婚姻費用はどのように決まりますか?
- 婚姻費用算定表はどのように使われるのですか?
- 婚姻費用と住宅ローンの関係について教えてください。
- 配偶者の収入が多い場合の婚姻費用について教えてください。
まとめ
婚姻費用の支払いが「おかしい」と感じることは珍しくありません。
特に妻の不貞行為があった場合や一方的に別居された場合など、不満を感じる状況は多いでしょう。
しかし、法律上は婚姻関係が続いている限り、収入の多い配偶者には婚姻費用を支払う義務があります。
とはいえ、婚姻費用の減額や免除が認められるケースもあります。
妻の不貞行為の証拠を集める、正しい婚姻費用の金額を確認する、支払いが困難な状況を具体的に説明するなど、できる対策はいくつもあります。
また、離婚手続きを迅速に進めることで、婚姻費用の支払い期間を短縮することも重要な戦略です。
何より大切なのは、「おかしい」と感じたらすぐに行動することでしょう。
感情的にならず、冷静に法的手続きを踏むことが問題解決の近道になります。
婚姻費用で悩んでいる方は、早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けることで、適切な解決策を見つけられるでしょう。