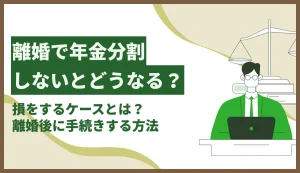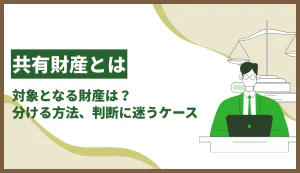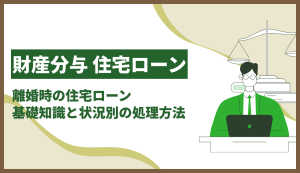熟年離婚の財産分与|退職金や年金は?対象にならない財産とは
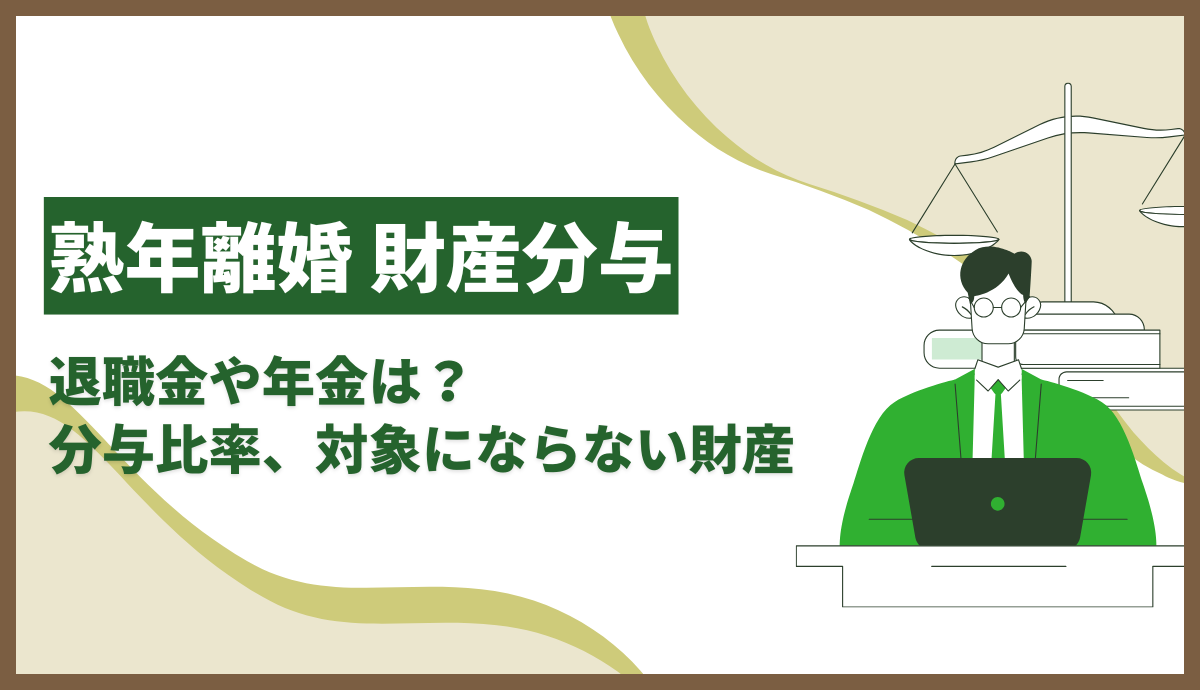
長年連れ添った夫婦が離婚する「熟年離婚」が増加しています。
結婚生活が長ければ長いほど、共有財産も増えるため、財産分与の問題は複雑化していきます。
「退職金はどうなるの?」「年金は分けられるの?」「へそくりも対象になるの?」と不安を抱えている方も多いでしょう。
熟年離婚における財産分与は、婚姻期間が長いからこそ考慮すべき点がたくさんあります。
この記事では、熟年離婚における財産分与の基本から請求方法、実例まで詳しく解説していきます。
熟年離婚を考えている方も、将来に備えて知識を得たい方も、この記事を通して自分の権利を正しく理解し、公平な財産分与を実現するためのヒントを見つけてください。
熟年離婚をする場合財産分与はどうなる?
熟年離婚では、長年の結婚生活で築いた財産をどう分けるかが大きな課題になります。
結婚20年、30年と長く連れ添った夫婦の場合、共有財産も膨大になりがちです。
財産分与の基本的な考え方は「婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を公平に分ける」というものです。
熟年夫婦の場合、退職金や年金といった老後の生活資金も分与の対象になるため、より慎重な話し合いが必要でしょう。
婚姻期間に応じた財産分与の相場
熟年離婚における財産分与の相場は、一般的に婚姻期間が長いほど分与率が高くなる傾向があります。
結婚期間が20年を超えると、財産の分与率は5対5になるケースが多いでしょう。
特に専業主婦(夫)の場合、家事や育児への貢献が評価され、長期間の婚姻では平等な分与が認められやすくなります。
たとえば、結婚30年の夫婦の場合、裁判所は「夫婦が共同で築いた財産」という観点から、ほぼ均等な分割を支持するケースが多いです。
| 婚姻期間 | 一般的な財産分与の割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 5年未満 | 2:8~3:7 | 短期間のため分与率が低め |
| 5~10年 | 3:7~4:6 | 共有財産の形成期間としてはまだ短い |
| 10~20年 | 4:6~4.5:5.5 | 貢献度に応じた分与が増える |
| 20年以上 | 5:5 | 長期の婚姻では平等分与が基本 |
| 30年以上 | 5:5~6:4 | 専業主婦(夫)の場合は優遇される場合も |
ただし、これはあくまで一般的な相場であり、個々の事情によって大きく異なる場合があります。
財産分与の主な3つの種類
財産分与には主に3つの種類があり、熟年離婚の場合はどの種類を選ぶかも重要なポイントです。
それぞれの特徴を理解して、自分の状況に合った方法を選びましょう。
特に熟年離婚では「清算的財産分与」が最も一般的ですが、状況によっては複数の種類を組み合わせることもあります。
| 種類 | 内容 | 熟年離婚での特徴 |
|---|---|---|
| 清算的財産分与 | 婚姻中に形成した財産を分ける | 最も一般的な形態で、退職金や年金も対象 |
| 扶養的財産分与 | 離婚後の生活保障のための分与 | 高齢で再就職が難しい場合に重要 |
| 慰謝料的財産分与 | 離婚の原因を作った側が支払う | 浮気や家庭内暴力など不貞行為があった場合 |
熟年離婚では、特に清算的財産分与と扶養的財産分与の組み合わせが多く見られます。
長年の結婚生活で形成した財産を清算しつつ、高齢による再就職の困難さを考慮して扶養的な要素も加味するのです。
例えば、65歳で離婚する場合、清算的財産分与で退職金の一部を分割しながら、扶養的財産分与として一定期間の生活費を支払うという取り決めをするケースもあります。

熟年離婚における財産分与の割合は?
熟年離婚での財産分与の割合は、婚姻期間の長さや各配偶者の貢献度によって決まります。
長年連れ添った夫婦の場合、一般的に「5対5の平等分割」が基本となるでしょう。
ただし、それぞれの家庭環境や経済状況によって最適な分割比率は変わってきます。
熟年離婚では、単に財産を分けるだけでなく、離婚後の老後生活を見据えた分与が重要です。
特に定年退職後の年金生活を前提とした場合、生活基盤を確保するための公平な分割が求められます。
専業主婦が受け取れる財産分与の割合は?
熟年離婚で専業主婦(夫)が受け取れる財産分与の割合は、近年大きく変化しています。
かつては「稼いだ方が多く取得する」考え方が主流でしたが、現在は家事や育児の貢献も正当に評価されるようになりました。
特に婚姻期間が20年以上の熟年夫婦の場合、専業主婦(夫)でも5対5の平等分割が一般的になっています。
現在の裁判所も「婚姻期間が長期に及ぶ場合、家事労働も経済的貢献と同等」という立場をとることが多いです。
例えば、30年間専業主婦として家庭を支えてきた妻の場合、夫名義の財産であっても半分の権利が認められるケースが多いでしょう。
| 貢献内容 | 評価される点 |
|---|---|
| 家事労働 | 日常の家事全般が配偶者の仕事や生活を支えた |
| 育児・教育 | 子育てに時間を費やし家庭の基盤を作った |
| 親の介護 | 配偶者の親の介護を担当した |
| 社交的活動 | 配偶者の仕事関係の付き合いや接待を支援した |
| 精神的サポート | 家庭の精神的支柱として配偶者を支えた |
ただし、婚姻期間中の浮気や家庭内暴力などがあった場合は、この割合が変わることもあります。

共働きだと財産分与の比率は変わる?
共働き夫婦の熟年離婚では、それぞれの収入差や家事分担の状況によって財産分与の比率が変わってきます。
基本的な考え方は「各自の貢献度に応じた分割」ですが、実際は複雑な要素が絡み合います。
共働きでも収入差が大きい場合、単純な収入比ではなく家事分担も含めた総合的な貢献度で判断されます。
例えば、妻の収入が夫の半分だったとしても、家事の大部分を担っていた場合は5対5に近い分割が認められることが多いです。
また共働き期間と専業主婦(夫)期間が混在している場合は、それぞれの期間の長さも考慮されます。
例えば、結婚40年のうち20年は専業主婦、その後20年は共働きだった場合、その全期間を通じての貢献度が評価されるでしょう。
| ケース | 一般的な財産分与の割合 |
|---|---|
| 収入がほぼ同等の共働き | 5:5の平等分割が基本 |
| 収入差がある共働き | 4:6~5:5(家事分担も考慮) |
| 一方が短時間パート | 4:6~5:5(家事貢献度による) |
| 途中から共働き | 4.5:5.5~5:5(期間による) |
なお、共働き夫婦の場合でも、それぞれが別々に貯蓄していた資産については、「共有財産」と認められないケースもあります。
ただし長期間の婚姻では、たとえ別々の口座で管理していても共有財産と見なされる傾向が強まります。
財産分与の対象となる財産とは?
熟年離婚で財産分与の対象となるのは、基本的に「婚姻期間中に協力して得た財産」です。
この財産は名義が誰であるかに関わらず、夫婦が共同で築き上げたものと見なされます。
特に熟年夫婦の場合、長い結婚生活で積み重ねてきた財産の種類も多岐にわたるでしょう。
熟年離婚特有の財産として、退職金や年金の分割が重要なポイントになります。
これらは老後の生活を支える重要な資金源であるため、慎重な検討が必要です。
不動産(持ち家・土地)
熟年夫婦の多くは持ち家や土地などの不動産を所有しているケースが多いでしょう。
これらは財産分与の中でも最も価値が大きいものの一つです。
不動産の分与方法としては、「現物分与」「換価分与」「代償分与」の3つが一般的です。
現物分与は共有名義に変更する方法ですが、離婚後も関係が続くため避けるケースが多いでしょう。
換価分与は不動産を売却して現金化し分ける方法で、清算がはっきりするメリットがあります。
代償分与は一方が不動産を取得し、相手には他の財産や現金で代償する方法です。
| 分与方法 | 内容 | 熟年離婚での特徴 |
|---|---|---|
| 現物分与 | 不動産を共有名義にする | 関係が続くため避けるケースが多い |
| 換価分与 | 不動産を売却して現金で分配 | 住み替えが必要になる |
| 代償分与 | 一方が住み続け、相手に代償金を支払う | 住み慣れた家に住み続けられる |
熟年離婚の場合、高齢になるほど新たな住居への引っ越しが負担になることも考慮すべきでしょう。
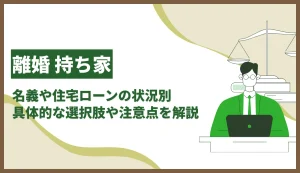
退職金
退職金は熟年離婚における財産分与の大きな争点となることが多いです。
特に定年退職を迎える年齢での離婚では、退職金の扱いが重要になります。
退職金は夫婦が協力して築いた財産と見なされ、婚姻期間中の寄与分に応じて分割の対象となります。
すでに受け取った退職金は通常の財産と同様に分与の対象ですが、まだ受け取っていない将来の退職金も対象になります。
将来受け取る退職金の場合、現時点での推定額を算出し、その中から婚姻期間に対応する部分を分与します。
例えば、会社勤続40年のうち30年が結婚期間だった場合、退職金の4分の3が対象になる計算です。
| 退職金の状況 | 分与の考え方 |
|---|---|
| すでに受け取った退職金 | 通常の財産として分与対象 |
| 将来受け取る退職金 | 婚姻期間分を推定して算出 |
| 一部を運用している退職金 | 運用分も含めて分与対象 |
| 再就職先での退職金 | 婚姻期間中の分は対象 |
退職金の額が大きい場合、一括での支払いが難しいケースもあります。
そのような場合は分割払いや、他の財産との相殺なども検討するとよいでしょう。
年金
熟年離婚では、年金の分割が重要な課題となります。
特に専業主婦(夫)だった場合、離婚後の生活を支える重要な収入源です。
年金分割制度により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割できます。
具体的には、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類の方法があります。
合意分割制度は両者の合意に基づいて分割する方法で、分割割合は自由に決めることができます。
3号分割制度は第3号被保険者期間の分割を請求できる制度で、自動的に2分の1ずつに分割されます。
| 制度 | 対象期間 | 分割割合 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 合意分割制度 | 婚姻期間中すべて | 合意による(上限50%) | 公正証書等の合意書が必要 |
| 3号分割制度 | 第3号被保険者期間のみ | 50%固定 | 合意不要で請求可能 |
年金分割の手続きは離婚成立から2年以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると分割請求ができなくなるので、必ず期限内に手続きを済ませましょう。
年金分割は将来受け取る年金額に大きく影響するため、専門家に相談することをおすすめします。

へそくりも財産分与に含まれるか
「へそくり」と呼ばれる隠し貯金も、基本的には財産分与の対象になります。
婚姻期間中に形成された財産は、その出所や名義に関わらず共有財産と見なされるからです。
ただし、へそくりが相手に知られていない場合、分与の対象になるかは実務上難しい問題です。
へそくりが発覚した場合、それが婚姻期間中の収入から貯めたものであれば共有財産として分与の対象になります。
特に生活費を削って貯めたへそくりは、明らかに婚姻費用からの貯蓄なので分与対象となるでしょう。
一方で、相手の浪費から家計を守るために貯めたへそくりは、状況によっては全額分与にならないケースもあります。
| へそくりの種類 | 財産分与での扱い |
|---|---|
| 生活費から貯めたもの | 共有財産として分与対象 |
| 自分の小遣いから貯めたもの | 原則として分与対象だが、金額によっては特有財産と見なされることも |
| 親からの贈与で貯めたもの | 自分だけへの贈与なら特有財産として分与対象外の可能性 |
| 婚姻前から持っていた貯金 | 特有財産として分与対象外 |
なお、へそくりの存在を疑う場合、預金通帳や税金の申告書などから調査することが可能です。
隠し財産が疑われる場合は、弁護士に相談して適切な調査方法を検討するとよいでしょう。
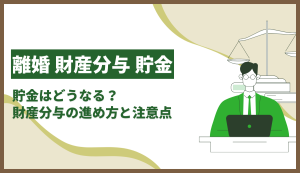
財産分与の対象にならない特有財産
財産分与では夫婦の共有財産が対象となりますが、「特有財産」と呼ばれる個人的な財産は分与の対象外となります。
特に熟年夫婦の場合、長い人生の中で特有財産も増えている可能性があります。
特有財産とは、婚姻前から所有していた財産や婚姻中に特定の個人に対する贈与・相続で得た財産などを指します。
ただし、婚姻期間が長期に及ぶ熟年夫婦の場合、特有財産と共有財産の区別が曖昧になりやすいという特徴があります。
例えば、婚姻前の預金が婚姻後の生活費と混同していたり、相続した不動産を夫婦で改修したりした場合は判断が難しくなります。
| 特有財産の種類 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 婚姻前から所有の財産 | 結婚前の貯金、不動産など | 婚姻中に使われたり混同したりすると区別が難しくなる |
| 相続・遺贈で得た財産 | 親からの相続不動産、遺産など | 夫婦で管理や改修をしていると共有財産化する可能性 |
| 個人的な贈与で得た財産 | 親からのマイホーム資金援助など | 「夫婦への贈与」と見なされると分与対象になる |
| 慰謝料など個人的な補償 | 事故の慰謝料、保険金など | 生活費に使われると共有財産化する可能性 |
| 個人的な賞金・賞品 | 文学賞の賞金、スポーツ賞金など | 家計に組み込まれると共有財産化する可能性 |
長年連れ添った夫婦の場合、特有財産であっても夫婦の共同生活に使われていれば「黙示の合意」によって共有財産になる場合があります。
例えば、相続した不動産を夫婦の住居として20年以上使用していた場合、特有財産としての性質が薄れるとされることがあります。
特有財産を守りたい場合は、口座を分けて管理するなど、共有財産と明確に区別しておくことが重要です。
熟年離婚では「これは特有財産だから分与の対象外」と主張しても、長い婚姻期間により認められにくいケースが多いので注意が必要です。
財産の由来や管理方法について証拠を残しておくと、特有財産としての主張がしやすくなります。

熟年離婚時の財産分与を請求する方法
熟年離婚において財産分与を請求するには、いくつかの方法があります。
基本的な流れとしては「話し合い→調停→裁判」という順序で進みますが、スムーズに解決するためのポイントを押さえておきましょう。
財産分与の請求は離婚成立から2年以内に行う必要があるため、計画的に進めることが大切です。
特に熟年離婚の場合、長年の結婚生活で積み重ねた財産が多く、複雑になりがちなので注意が必要です。
まずは夫婦間での話し合いから始めるのが基本ですが、感情的にならず冷静に進めることがポイントです。
| 請求方法 | 内容 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 夫婦間の話し合い | 双方が納得できる条件を直接交渉 | 費用が少なく済む、プライバシーが守られる/感情的になりやすい |
| 弁護士を介した交渉 | 専門家を通じて条件を交渉 | 冷静な話し合いができる/費用がかかる |
| 調停 | 家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う | 第三者の助言が得られる/時間がかかる場合がある |
| 審判・裁判 | 裁判所が判断を下す | 最終的な解決が得られる/費用と時間がかかる、精神的負担が大きい |
熟年離婚の場合、特に財産リストの作成が重要です。
長年の結婚生活で財産が複雑に絡み合っているため、預金、不動産、自動車、退職金、年金など全ての財産を洗い出しましょう。
可能であれば、最初から弁護士に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、見落としがちな財産の発見や適切な分与額の提案を受けられます。
話し合いが難航する場合は早めに調停を申し立て、2年の時効を迎えないよう注意しましょう。

相手から財産分与を請求された場合は拒否できるか?
配偶者から財産分与を請求された場合、正当な理由なく完全に拒否することはできません。
財産分与は法律で認められた権利であり、相手にも公平な分配を求める権利があるためです。
ただし、全ての財産が無条件で分与対象になるわけではなく、特有財産は原則として分与の対象外となります。
分与を求められた財産が本当に共有財産なのか、特有財産なのかを証明することが重要です。
例えば、婚姻前から所有していた不動産や親から相続した財産が特有財産として認められれば、分与対象から外すことができます。
また、財産分与の割合についても話し合いの余地があり、相手の主張をそのまま受け入れる必要はありません。
| 請求への対応 | 内容 |
|---|---|
| 特有財産の証明 | 婚姻前からの所有や個人的な相続を証明する書類を用意 |
| 適正な分与割合の主張 | それぞれの貢献度を考慮した公平な分配を主張 |
| 代替案の提示 | 一括払いが難しい場合は分割払いなどの代替案を提案 |
| 専門家への相談 | 弁護士に相談して適切な対応策を検討 |
財産分与の請求を完全に無視したり、財産を隠したりすると、後に裁判で不利になる可能性が高いです。
むしろ誠実に対応し、適正な解決を目指す姿勢が重要でしょう。
特に熟年離婚の場合は、長年の結婚生活における両者の貢献を公平に評価することが求められます。
財産分与は離婚成立から2年以内の期限があるため要注意
財産分与を請求できる期間は、離婚成立日から2年間と法律で定められています。
この期限を過ぎると、財産分与を請求する権利が消滅してしまうため注意が必要です。
熟年離婚の場合、財産が多岐にわたるため準備に時間がかかりますが、2年の時効は伸びないので計画的に進めましょう。
特に重要なのは、離婚前から財産分与について考え始めることです。
離婚が成立した後に初めて財産分与を考え始めると、調査や交渉に時間がかかり、期限が迫ってしまう恐れがあります。
| 状況 | 対応策 |
|---|---|
| 離婚前 | 事前に財産リストを作成し、分与方針を検討しておく |
| 離婚成立直後 | 速やかに財産分与の話し合いを始める |
| 話し合いが難航 | 1年以内を目安に調停申立てを検討 |
| 調停不成立 | 残り期間を考慮し、すぐに審判・裁判へ移行 |
| 期限が迫っている | とりあえず調停申立てで時効を中断させる |
財産分与の時効は「裁判上の請求」をすることで中断させることができます。
具体的には、調停や審判の申立て、訴訟の提起などが裁判上の請求に当たります。
話し合いがまとまらない場合でも、期限が迫っているなら「とりあえず調停申立て」という選択肢も検討する価値があります。
また、年金分割の手続きも2年以内に行う必要があるため、財産分与と併せて計画的に進めましょう。
熟年離婚では退職金や年金など老後の生活に直結する財産が多く、2年の期限を逃すと大きな不利益を被る可能性があります。
期限が近づいてから慌てないよう、早めの準備と行動を心がけることが大切です。

実例:弁護士に依頼した結果、短期間で財産分与として800万円を獲得できた
ここでは、実際のケースを基に熟年離婚における財産分与の成功例を紹介します。
Aさん(62歳、専業主婦)は結婚35年目で夫(65歳、会社員)との離婚を考えていました。
最初は自分たちだけで話し合いを進めようとしましたが、金額面で折り合いがつかず、弁護士に相談したことで状況が大きく変わりました。
Aさんの夫は「自分が稼いだ財産だから」と主張し、退職金や預金をほとんど分けようとしませんでした。
そこでAさんは弁護士に依頼し、まず夫婦の全財産を洗い出すところから始めました。
| 把握した財産 | 金額 | 名義 |
|---|---|---|
| 自宅マンション | 3,500万円 | 夫 |
| 退職金 | 2,200万円 | 夫 |
| 預貯金 | 1,800万円 | 夫 |
| 投資信託 | 600万円 | 夫 |
| 預貯金 | 300万円 | 妻 |
| 合計 | 8,400万円 | – |
弁護士は「35年間の専業主婦としての家事、育児の貢献」を強調し、財産の半分を請求する方針を立てました。
また、夫が隠していた預金口座についても調査し、さらに600万円の預金が見つかりました。
弁護士を通じた交渉の結果、当初夫が提示していた200万円から大幅アップの800万円での合意に至ったのです。
さらに、年金分割についても手続きを進め、将来の年金受給額も増額することができました。
このケースから学べる重要なポイントは以下の通りです。
- 専門家に依頼することで隠れた財産が見つかることがある
- 長年の結婚生活における家事、育児の貢献は正当に評価される
- 法的知識を持った専門家の交渉力で結果が大きく変わる
- 年金分割の手続きも並行して進めることが重要
熟年離婚の財産分与は老後の生活に直結する重要な問題です。
少しでも不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問
熟年離婚における財産分与に関して読者からよく寄せられる質問をまとめました。
実際の状況に応じた対応を考える際の参考にしてください。
- 結納金で購入した家具は財産分与でどう扱われますか?
- 別居中に取得したマンションは財産分与の対象になりますか?
- 相手の隠し財産を調査する方法はありますか?
- 長年支払われなかった生活費を財産分与として請求できますか?
- 熟年離婚の場合、退職金はどのように分配されますか?
- 専業主婦の財産分与の相場について教えてください。
- 結婚25年以上の熟年夫婦の財産分与割合はどうなりますか?
- 共働き夫婦の年金分割の方法について教えてください。
- 財産分与に関するローンがある持ち家の扱いを教えてください。
- 60代での離婚と40代での離婚で財産分与の違いはありますか?
まとめ
熟年離婚における財産分与は、長年の結婚生活で築いた財産をどう公平に分けるかという重要な問題です。
基本的には婚姻期間が長いほど5対5の平等分割に近づき、特に20年以上の結婚では平等分割が一般的になります。
財産分与の対象には不動産や預貯金だけでなく、退職金や年金も含まれるため、老後の生活設計に大きく影響します。
財産分与を請求できる期間は離婚成立から2年間と限られているため、計画的に行動することが大切です。
熟年離婚での財産分与は専門的な知識が必要なケースが多いため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
それぞれの状況に応じた適切な財産分与を実現し、離婚後も安定した生活を送れるよう、十分な情報収集と準備をしておきましょう。