養育費は公正証書で残すべき!費用の目安、手続き方法、デメリットとは

養育費の不払いに悩まされるケースは、離婚後に少なくありません。
公正証書を作成しておけば、万が一の未払い時に強制執行という手段が取れるため安心です。
しかし「養育費の公正証書を作るにはどれくらいの費用がかかるの?」「どんな書類が必要なの?」と不安を抱える方も多いでしょう。
養育費の公正証書作成には一定の費用が発生しますが、子どもの将来を守るための重要な投資と言えます。
この記事では、養育費の公正証書にかかる費用や作成方法について詳しく解説していきます。
専門的な内容でも分かりやすく解説していますので、これから養育費の公正証書作成を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
公正証書で養育費を残すメリットとは?
養育費の取り決めを公正証書で残しておくことは、離婚後の子どもの生活を安定させるために非常に有効な手段です。
養育費の支払いに関するトラブルは離婚後によく起こるため、きちんと法的効力のある形で取り決めを残しておく必要があります。
では、養育費の公正証書を作成するメリットについて具体的に見ていきましょう。
離婚後に問題が発生するのを防ぐことが可能
公正証書には法的な効力があるため、後から「そんな約束はしていない」などと言い逃れされるリスクを減らせます。
離婚時には円満に話し合いができていても、時間が経つと関係が悪化したり、連絡が取れなくなったりすることがあります。
公正証書があれば養育費の金額や支払い方法など、細かい条件を明確に記録できるため、後々のトラブルを未然に防げます。
また、再婚や転居といった状況変化が起きた場合の対応方法についても、あらかじめ決めておくことができます。
例えば「支払い義務者の収入が大幅に減少した場合は協議により金額を見直す」などの条件を入れておくと安心です。
さらに、公正証書は公証役場で保管されるため、原本を紛失しても謄本を取得できる点も大きな利点と言えるでしょう。
養育費未払い時に強制執行が可能
養育費の公正証書作成の最大のメリットは、支払いが滞った場合に強制執行ができる点です。
強制執行認諾文言(こうせいしっこうにんだくもんげん) が記載された公正証書があれば、裁判所を通さずに相手の財産を差し押さえることができます。
一般的な離婚協議書とは異なり、公正証書には「債務者は、この債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という文言を入れることが可能です。
この文言があると、養育費が支払われない場合に改めて裁判をする必要がなく、すぐに法的手続きに移行できます。
例えば、3か月分の養育費が未払いになった場合、この公正証書をもとに裁判所に申立てをすれば、相手の給料や預金を差し押さえる手続きが可能になります。
ただし、強制執行するには相手の勤務先や銀行口座などの情報が必要なので、これらの情報も事前に把握しておくことをおすすめします。
公正証書がない場合は、まず調停や裁判で養育費の支払いを命じる判決を得てから強制執行の手続きに進むため、時間と費用がかかってしまいます。

公正証書を作成することにはデメリットがあるか?
養育費の公正証書には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
公正証書を作成する前に、これらのデメリットについても理解しておくことで、より現実的な判断ができるでしょう。
作成には時間と費用が必要となる
公正証書を作成するには、一定の費用と時間がかかります。
公証役場に支払う手数料は養育費の金額によって変わりますが、通常1万円前後が相場です。
養育費の公正証書作成は費用面でのハードルがあり、特に離婚時は経済的に余裕がない場合が多いため負担に感じることがあります。
また、弁護士に依頼して公正証書の原案を作成してもらう場合は、別途弁護士費用が発生します。
公証役場での手続きには複数回の訪問が必要なこともあり、仕事や子育てで忙しい方にとっては時間的な負担も無視できません。
ただし、これらの費用や時間は、将来的な養育費の支払いを確保するための投資と考えるとそれほど大きなデメリットではないかもしれません。

公証役場へは夫婦で一緒に行く必要がある
公正証書を作成する際の大きなハードルとして、基本的に当事者双方が公証役場に出向く必要がある点が挙げられます。
すでに関係が悪化している元夫婦が同じ場所で顔を合わせなければならないというのは、心理的な負担となることがあります。
DV被害があったケースなど、相手と顔を合わせることが困難な場合は、別々の日時に公証役場を訪問するなどの配慮を求めることも可能です。
また、相手が遠方に住んでいる場合や、多忙で公証役場に行く時間がとれない場合も、調整が難しくなります。
このような場合は、代理人を立てることも可能ですが、委任状の作成など別の手続きが必要になってきます。
離婚協議の段階で公正証書作成についても話し合っておくと、後々のトラブルを避けられるでしょう。
なお、相手が公正証書の作成に応じない場合は、家庭裁判所での調停や審判を通じて養育費の取り決めを行う方法もあります。

養育費の公正証書作成にかかる費用と必要な書類
養育費の公正証書を作成するにあたり、どれくらいの費用がかかるのか気になる方は多いでしょう。
費用の内訳や必要書類を事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
公正証書の作成費用
養育費の公正証書作成にかかる公証人手数料は、取り決める養育費の総額によって変動します。
手数料は法律で定められた計算式に基づいて算出され、基本的には養育費総額の1,000分の4(0.4%)が目安となります。
例えば毎月5万円の養育費を子どもが20歳になるまで15年間支払う場合、総額900万円となり、手数料は約3万6,000円程度です。
ただし、最低額は5,000円と定められているため、総額が少なくても5,000円は必要です。
この他に、正本・謄本の交付手数料として1通につき250円、そして原本の保存料として2,000円程度が必要になります。
| 養育費総額 | 手数料の目安 |
|---|---|
| ~125万円 | 5,000円(最低額) |
| 125万円~500万円 | 5,000円~20,000円 |
| 500万円~1,000万円 | 20,000円~40,000円 |
| 1,000万円~ | 40,000円~ |
また、養育費以外に財産分与や慰謝料なども同時に公正証書にする場合は、それらの金額も合算して手数料が計算されます。
弁護士に依頼する際にかかる費用
公正証書の作成を弁護士に依頼すると、別途弁護士費用が発生します。
弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的には着手金と報酬金の2段階で請求されることが多いです。
養育費の公正証書作成のみの依頼であれば、着手金として3万円~10万円程度、報酬金として3万円~5万円程度が相場です。
ただし、離婚協議全体を弁護士に依頼している場合は、公正証書作成も含めた一括料金となることが多いでしょう。
弁護士に依頼するメリットは、法的な知識を活かした適切な文言での公正証書原案作成や、交渉の代行などが挙げられます。
特に相手との関係が良くない場合や、複雑な条件がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

準備すべき必要書類
養育費の公正証書を作成する際には、以下の書類を準備する必要があります。
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 印鑑(認印で可)
- 戸籍謄本または離婚届受理証明書(離婚の事実を証明するもの)
- 子どもの戸籍謄本(子どもとの関係を証明するため)
- 養育費の公正証書原案(弁護士に依頼する場合は不要)
これらの書類は原則として3か月以内に発行されたものが必要で、特に戸籍謄本は比較的新しいものを求められることが多いです。
また、代理人が公証役場に行く場合は、委任状も必要になります。
養育費の公正証書原案を自分で作成する場合は、インターネットの書式サイトや法律相談サイトで雛形を入手できます。
ただし、法的な効力を持つ文書なので、自信がない場合は専門家のアドバイスを受けるのが安心です。
公証役場によっては、事前予約が必要な場合もありますので、お近くの公証役場に確認してから訪問するとよいでしょう。
養育費の公正証書を作成するための方法
養育費の公正証書を作成するには、いくつかの手順を踏む必要があります。
公証役場での手続きをスムーズに進めるために、事前に流れを把握しておきましょう。
①離婚協議書及び公正証書原案を準備する
公正証書作成の第一歩は、離婚協議書や公正証書の原案を準備することです。
夫婦間で養育費について合意できている内容を文書化し、詳細な条件を明記します。
原案には月々の養育費の金額や支払い期間、支払い方法などの基本事項に加え、強制執行認諾文言も必ず含めるようにしましょう。
自分で原案を作成することも可能ですが、法律の専門知識がない場合は弁護士に相談するのが安心です。
また、公証役場のウェブサイトには公正証書のひな形が掲載されていることもあるので、参考にするとよいでしょう。
原案が完成したら、事前に公証役場に連絡して内容の確認や予約を取ることをおすすめします。

②公証役場で夫婦が公証人との面談を行う
原案が準備できたら、次は公証役場での面談です。
この面談には原則として夫婦双方が出席し、公証人に対して養育費の取り決め内容を説明します。
公証人は法律の専門家として、原案の内容が適法で明確かどうかをチェックし、必要に応じて修正箇所を指摘してくれます。
面談時には必要書類(本人確認書類、戸籍謄本など)を持参し、公証人からの質問に答えられるよう準備しておきましょう。
特に、養育費の金額設定の根拠や支払い終了時期の理由など、取り決めの背景も説明できるとスムーズです。
なお、どうしても相手と同席できない場合は、別々の日に面談することも可能なケースがあります。
③後日、原案を確認のあと、署名と押印を行う
面談後、公証人が原案をもとに公正証書の草案を作成します。
草案の内容に問題がなければ、再度公証役場に行き、署名と押印を行います。
この署名・押印の際も原則として夫婦双方の立会いが必要で、公証人の前で本人が直接署名することで公正証書としての効力が生まれます。
手数料を支払えば、その場で公正証書の正本や謄本を受け取ることができます。
正本は強制執行の手続きに必要となるため、大切に保管しておきましょう。
公正証書の原本は公証役場に保管されるので、万が一紛失しても再発行が可能です。
以上の手続きを経て、法的効力を持つ養育費の公正証書が完成します。
養育費の公正証書に記載すべき内容は?その書き方も紹介
養育費の公正証書を作成する際、どのような内容を記載すべきか悩む方も多いでしょう。
ここでは、後々のトラブルを防ぐために必ず盛り込むべき項目と、その書き方のポイントを解説します。
①養育費の月々の支払額
養育費の支払額は公正証書の最も重要な要素の一つです。
金額設定は子どもの年齢や人数、支払う側の収入などを考慮して決定します。
月々の具体的な金額を明確に記載し、「相当額」などの曖昧な表現は避けるようにしましょう。
例えば「毎月金50,000円」と明記することで、後から「いくら払うべきか分からなかった」という言い逃れを防げます。
また、子どもの年齢によって金額を変更する場合は「小学校入学時より月額6万円、中学校入学時より月額7万円」などと段階的に記載することも可能です。
②支払日の設定
支払日も明確に定めておくことで、いつ支払いがあるべきかの認識ずれを防げます。
一般的には「毎月15日」や「毎月末日」など、分かりやすい日にちを設定するのが良いでしょう。
支払日が休日や祝日と重なる場合の取り扱いについても「前営業日に支払う」「翌営業日に支払う」などと記載しておくとトラブル防止になります。
また、給料日に合わせて設定すると支払い義務者の負担感が減るため、「毎月25日(給料日)」などと記載することも一案です。
ただし、相手の給料日が変わることもあるため、そのような場合の対応方法も含めて記載しておくと安心です。
③支払い開始時期の明記
養育費の支払いがいつから始まるのかを明確にしておくことも重要です。
特に離婚成立日と公正証書作成日に差がある場合は、どの時点から養育費が発生するのか明記する必要があります。
「令和○年○月分から支払う」と具体的な年月を明記することで、支払い義務の始期について解釈の違いが生じるのを防げます。
また、離婚前から別居している場合は、過去の未払い分についても清算するかどうかを取り決めておくとよいでしょう。
例えば「令和○年○月から令和○年○月までの養育費として合計○○万円を令和○年○月○日までに一括で支払う」といった記載も可能です。
④支払い終了時期の設定
養育費の支払いがいつまで続くのかも明確に定めておく必要があります。
一般的には「子が満20歳に達する日の属する月まで」「子が大学を卒業する月まで」などと設定することが多いです。
終了時期は子の自立を基準に考え、高校卒業後も進学する場合は大学卒業までとするなど、子の将来を見据えた設定が望ましいでしょう。
また、子どもが就職して経済的に自立した場合の扱いについても「子が定職に就き経済的に自立した場合はその翌月から養育費の支払いを終了する」などと記載しておくと良いでしょう。
終了時期が曖昧だと、いつまで支払う義務があるのかで揉めることがあるため、できるだけ具体的な条件を設定することが大切です。
⑤養育費の支払い方法
養育費をどのような方法で支払うかも明確に決めておく必要があります。
一般的には銀行振込が最も一般的で、証拠も残りやすいため推奨されています。
振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義を公正証書に明記しておくと、支払い方法についての誤解を防げます。
振込手数料の負担についても「振込手数料は支払い義務者が負担する」と明記しておくと親切です。
また、口座変更時の対応方法についても「受取人は口座を変更する場合、変更の1か月前までに書面で支払い義務者に通知する」などと記載しておくとよいでしょう。
現金手渡しは後々トラブルの原因になりやすいため、できるだけ避けるのが無難です。
⑥養育費決定後の状況変化に対する対応方法
養育費の取り決め後、双方の状況が変化することも考えられます。
収入の増減や再婚、転居など、様々な事情変更に対する対応方法を定めておくことが重要です。
「支払い義務者の収入が著しく減少した場合」や「子の教育費が著しく増加した場合」などの状況に応じた対応策を記載しておきましょう。
例えば「双方の事情に大きな変化があった場合は、誠実に協議のうえ養育費の額を見直すことができる」といった条項を入れておくと柔軟に対応できます。
ただし、あまり抽象的な表現だと解釈の違いが生じるため、「収入が30%以上減少した場合」など具体的な基準を示すことも検討してみてください。
また、定期的な見直しの機会を設けることも有効で、「3年ごとに養育費の額を見直す協議を行う」などと記載する方法もあります。
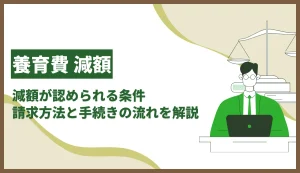
⑦強制執行認諾文言の記載
公正証書のメリットを最大限に活かすためには、強制執行認諾文言を必ず記載しましょう。
この文言がなければ、養育費が支払われなくなった場合に強制執行ができなくなってしまいます。
「債務者(支払い義務者)は、本公正証書記載の債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という文言を入れておくことが重要です。
この文言があることで、養育費が支払われない場合に裁判所を通じて相手の財産を差し押さえることが可能になります。
また、未払いが発生してから何か月経過したら強制執行の手続きを取るかについても「3か月分の養育費が未払いとなった場合、債権者は直ちに強制執行の手続きを取ることができる」などと記載しておくと明確です。
公証役場によっては、この文言の記載方法について助言してくれることもありますので、不安な場合は公証人に相談してみるとよいでしょう。
養育費の公正証書を自分で作る際に気をつけるべきこと
養育費の公正証書を自分で作成する場合、いくつか注意すべきポイントがあります。
専門知識がない状態で作成すると、思わぬトラブルを招くこともあるため、以下の点に気をつけましょう。
公正証書は法的効力を持つ重要な文書なので、曖昧な表現や解釈の余地がある書き方は避け、具体的かつ明確な表現を心がけることが大切です。
例えば「相当額」「状況に応じて」などの抽象的な表現ではなく、具体的な金額や条件を記載しましょう。
また、将来的に状況が変わることも考慮して、収入の変動や子どもの進学などに対応できる条項も盛り込むとよいでしょう。
特に前述した「強制執行認諾文言」は忘れずに記載する必要があります。
なお、公証役場では公証人が内容をチェックしてくれますが、法的な助言までは行ってくれないため、内容面での不備は指摘されないことがあります。
弁護士に作成を任すメリット
養育費の公正証書作成を弁護士に依頼することには、いくつかの大きなメリットがあります。
専門知識がなくても安心して任せられるため、多くの方が弁護士に相談しています。
弁護士は法的な知識と経験から、将来トラブルになりそうな点を事前に発見して適切な条項を設けることができます。
また、相手方との交渉も代行してくれるため、直接やり取りするストレスから解放されるというメリットもあります。
さらに、弁護士は裁判例や実務経験から適正な養育費の金額設定についてもアドバイスしてくれます。
養育費の金額が妥当かどうか判断に迷う場合は、弁護士に相談するのが確実です。
特に関係が悪化している元配偶者との間で取り決めを行う場合や、複雑な条件がある場合は、専門家のサポートを受けることで円滑に進められるでしょう。
法テラスや自治体の無料法律相談などを利用して、まずは気軽に専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

よくある質問
養育費の公正証書作成についてよく寄せられる質問をまとめました。
不安や疑問の解消にお役立てください。
- 養育費の公正証書に有効期限はありますか?
- 離婚後でも養育費の公正証書を作成できますか?
- 未婚の場合の養育費公正証書の作り方を教えてください。
- 再婚した場合、養育費の公正証書の効力はなくなりますか?
- 養育費の公正証書作成費用の補助金制度はありますか?
- 養育費の強制執行認諾文言は必ず必要ですか?
- 法テラスを利用した場合の公正証書作成費用はどのくらいですか?
- 養育費の公正証書はどこで作成できますか?
まとめ
養育費の公正証書は、子どもの将来を守るための重要な法的文書です。
作成にはいくつかの費用と手間がかかりますが、万が一の未払いに備えて強制執行ができるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
公正証書の作成費用は養育費の総額によって変わりますが、一般的に数千円から数万円程度です。
また、弁護士に依頼する場合は別途費用がかかりますが、法的な知識を持った専門家に相談することで、より確実な内容の公正証書を作成できます。
公正証書には養育費の金額や支払い方法、開始・終了時期、状況変化への対応方法などを明確に記載し、強制執行認諾文言を必ず入れておくことが重要です。
子どもの生活を守るためにも、「公正証書なんて面倒だから」と後回しにせず、きちんと法的に有効な形で養育費の取り決めを行いましょう。
将来的なトラブルを防ぎ、子どもが安心して生活できる環境を整えるための大切な一歩となります。












