養育費の支払い能力がない場合どうすればいい?収入減少時の対応

養育費の支払いが難しい状況に直面していませんか?
「収入が減って養育費が払えない」「無職で養育費の支払い能力がない」と悩んでいる方は少なくありません。
養育費は子どもの生活を支える大切なお金ですが、支払う側の経済状況によっては現実的に支払えないケースもあります。
しかし、だからといって養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、適切な対応が必要です。
当記事では、養育費の支払い能力がない場合の対処法や注意点について詳しく解説していきます。
お金の問題は繊細なテーマですが、あなたの状況に合った解決策を見つけるお手伝いをします。
まずは現状を正しく理解し、適切な対応を一緒に考えていきましょう。
養育費の支払い能力がない扶養義務者に関する基本知識
離婚後、子どもを育てるために必要なお金を「養育費」と呼びます。
通常、養育費を払う義務がある親(扶養義務者)は、自分の収入や生活状況に応じた金額を支払うことになります。
しかし「無職になった」「病気で働けない」など、さまざまな理由で養育費の支払い能力がない場合もあるでしょう。
では、支払い能力がないときは養育費をどう考えればいいのでしょうか。
無職の扶養義務者の場合、養育費の目安はおおよそ0~1万円
支払い側が無職で収入がない場合、養育費はどうなるのでしょうか。
結論からいうと、収入がゼロなら養育費も原則として0円〜1万円程度となります。
養育費は支払い義務者の「支払い能力」に応じて決まるため、本当に収入がなければ支払えない状況は認められます。
ただし、収入がなくても貯金や資産がある場合は、それらを考慮して養育費が算定されることがあります。
無職でも親から仕送りを受けている場合や、失業手当を受給している場合なども、それらを収入として養育費算定の対象になります。
また「無職だから払えない」と主張するだけでは不十分で、なぜ働けないのか、具体的な事情を証明する必要があります。
健康で就労可能な年齢であれば「働こうと思えば働ける」とみなされ、潜在的な稼働能力に基づいて養育費が決められることもあります。
潜在的な稼働能力がある場合、養育費の目安は同年齢・同性の平均賃金に基づく
「現在は収入がないが、働く能力がある」と判断された場合、裁判所はどのように養育費を算定するのでしょうか。
このケースでは、潜在的な稼働能力(働けば得られるであろう収入)を基準に養育費が決められます。
具体的には、同じ年齢・同性の平均賃金を基に、その人が得られるであろう収入額を推定して養育費が算定されます。
例えば、40代男性が「今は無職」と主張しても、同年代男性の平均年収(約500万円前後)をベースに養育費が計算されることもあります。
ただし、すべてのケースでこの基準が適用されるわけではなく、個別の事情が考慮されます。
病気やけが、介護、育児など、正当な理由で働けない場合は、潜在的稼働能力を考慮しない判断がなされることもあります。
また、就職活動を誠実に行っているが仕事が見つからない場合なども、個別の状況を考慮した判断がなされます。
養育費の支払い能力がない場合でも、将来的に収入が増えることを見込んで、支払いの開始時期を遅らせる合意をすることも一つの方法です。

扶養義務者の潜在的稼働能力を判断する基準
養育費の支払い能力を考える上で重要なのが「潜在的稼働能力」の判断です。
裁判所は単に「無職だから支払えない」という主張をそのまま認めるわけではありません。
では、潜在的な稼働能力はどのような基準で判断されるのでしょうか。
裁判所は主に「年齢」「健康状態」「学歴」「職歴」「資格」などから総合的に稼働能力を判断します。
例えば、40代で健康状態に問題がなく、これまで安定した職歴がある場合は、高い稼働能力があると判断される可能性が高いでしょう。
一方、高齢であったり、健康上の問題を抱えていたりする場合は、稼働能力が低いと判断されることもあります。
| 判断要素 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢 | 若年〜中年(20〜50代)は高い稼働能力があると判断されやすい |
| 健康状態 | 病気やけがの有無、程度、回復の見込み |
| 学歴・職歴 | 過去の収入実績、職種、勤続年数 |
| 保有資格 | 専門的な資格の有無(医師、弁護士、公認会計士など) |
| 居住地域 | 都市部か地方か(求人状況の違い) |
| 再就職の努力 | 就職活動の内容や頻度 |
また、失業の理由も重要な判断材料となります。
自己都合退職と会社都合の解雇では、裁判所の判断が異なることがあるのです。
さらに、就職活動の状況も考慮されます。
ハローワークへの通所履歴や応募書類の控えなど、真剣に再就職を目指している証拠があれば、誠実さが認められる可能性が高まります。
稼働能力の判断は個別のケースによって異なるため、養育費の支払いについて不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
養育費支払い能力がないと判断されやすいケース
養育費の支払い義務がある親でも、実際に支払い能力がないと認められるケースがあります。
ここでは、裁判所が「本当に支払い能力がない」と判断しやすい具体的な状況を見ていきましょう。
1.病気やけがにより働けない場合
重い病気やけがで働けない状況は、支払い能力がないと認められやすいケースの一つです。
特に長期入院が必要な病気や、重度の障害が残るようなけがの場合は考慮されます。
ただし、医師の診断書など客観的な証拠が必要で、自己申告だけでは認められないことが多いでしょう。
また、一時的な病気やけがの場合は、完治後の支払い再開を条件に一時的な減額や支払い猶予が認められることもあります。
うつ病などの精神疾患も、適切な診断と治療を受けていれば考慮される可能性があります。
病気やけがの状態が変わった場合は、その都度、養育費の金額について再検討することも大切です。
2.育児などにより就労が困難な場合
再婚後に新しい子どもが生まれた場合など、育児の事情で就労が難しいケースもあります。
特に乳幼児の育児や、障害のある子どもの介護が必要な場合は考慮される可能性が高いでしょう。
ただし、前婚の子どもと新しい子どもの養育費は同等に扱われるため、全額免除ではなく減額が検討されることが一般的です。
また、親の介護などで就労時間を減らさざるを得ない場合も、状況に応じて考慮されることがあります。
このようなケースでは、現在の状況だけでなく、子どもの成長や介護状況の変化に応じた見直しが必要になってきます。
将来的に就労可能になったときのことを見据えて、あらかじめ取り決めをしておくと良いでしょう。
3.生活保護を受給している場合
生活保護を受給しているケースは、支払い能力がないと判断される典型的な例です。
生活保護は最低限の生活を保障するものであり、それ以上の余裕がないと認められるからです。
生活保護受給中は原則として養育費の支払いが免除されますが、生活保護から抜けた場合は支払い義務が復活します。
ただし、生活保護を受けていても養育費の支払いを命じられるケースもあります。
例えば、わずかな就労収入がある場合や、親からの援助を受けている場合は、その範囲内で養育費の支払いが求められることもあるでしょう。
生活保護の受給状況が変わった場合は、速やかに相手方に伝え、養育費について再協議することが大切です。
養育費の支払い能力については、上記のように客観的な状況が重視されますが、個別の事情によって判断が異なることもあります。
不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

支払い能力がないため養育費を減額したい方へ3つの重要なポイント
収入が減少したり、無職になったりして養育費の支払いが難しくなった場合、どう対応すればよいのでしょうか。
ここでは、支払い能力がないために養育費を減額したい方に向けて、押さえておくべき3つのポイントを解説します。
1. 収入減少が一時的な場合には、支払い開始時期を決定する
失業や病気など一時的な理由で収入が減少した場合、養育費をどうすればよいでしょうか。
完全に支払いを免除してもらうのではなく、「支払い開始時期を遅らせる」という方法が有効です。
例えば「再就職できた月から」「退院後3か月目から」など、具体的な条件付きで養育費の支払い開始時期を設定できます。
この方法なら、現在の支払い能力がなくても将来的な子どもへの責任を放棄することなく、状況の変化に対応できます。
ただし、支払い開始の条件はできるだけ明確にしておくことが大切です。
「収入が安定したら」といった曖昧な表現では、後々トラブルの原因になりかねません。
「月収○○万円以上の仕事に就いたとき」など、具体的な数字で条件を設定しておくとよいでしょう。
2.協議が成立しない場合は調停・審判を利用する
元配偶者と話し合いをしても養育費の減額に合意が得られない場合はどうすればよいでしょうか。
そんなときは家庭裁判所の調停や審判を利用する方法があります。
調停では、裁判所が間に入り当事者同士の合意形成をサポートします。
合意に至らなければ、審判に移行して裁判官が判断を下します。
調停・審判の申立ては、自分で行うことも可能ですが、弁護士に依頼するとスムーズに進みます。
申立ての際には「養育費減額調停申立書」と「収入が減少したことを証明する書類」が必要です。
収入減少の証明としては、失業証明書、診断書、給与明細、退職証明書などが有効でしょう。
単に「支払えない」と主張するだけでは不十分です。
具体的な証拠を用意しておくことが重要です。
3.養育費の交渉に強い弁護士に相談・依頼する
養育費の減額交渉は専門知識が必要な場面が多いため、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
特に養育費問題を得意とする弁護士なら、あなたの状況に最適な対応策を提案してくれるでしょう。
弁護士に依頼すると、客観的な証拠の収集方法や説得力のある交渉術など、専門的なアドバイスを受けられます。
また、あなたの代理人として元配偶者やその弁護士と交渉してくれるため、精神的な負担も軽減されます。
弁護士費用が心配な場合は、法テラスの無料相談や弁護士費用の分割払いなどを利用する方法もあります。
まずは養育費問題に詳しい弁護士に相談し、自分の状況に合った対応を検討しましょう。
養育費の減額には正当な理由と具体的な証拠が必要です。
感情的な対応は避け、法的な手続きを踏むことで適切な解決を目指しましょう。
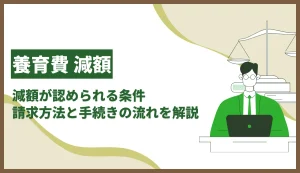
支払い能力がないのに養育費に合意するリスク
支払い能力がないのに無理に養育費の支払いに合意してしまうと、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
ここでは、現実的な支払い能力を超えた養育費に合意することで起こりうる問題点を解説します。
1.養育費の滞納が発生する
支払い能力以上の養育費に合意すると、最も直接的なリスクは滞納の発生です。
養育費を滞納すると、未払い分は借金として積み重なっていきます。
滞納が続くと、給料や財産の差し押さえなどの強制執行を受ける可能性があり、信用情報にも影響します。
また、養育費は2年で時効になるという誤解がありますが、確定した養育費債権の時効は5年です。
裁判所の調停や審判で決まった養育費は、未払いがあれば強制執行の対象になります。
支払い能力に見合った現実的な金額で合意することで、このようなリスクを避けることができるでしょう。

2.子どもとの面会交流が難しくなる
養育費の滞納は、元配偶者との関係悪化につながり、子どもとの面会交流にも悪影響を及ぼします。
法律上、養育費の支払いと面会交流は別の問題ですが、実際には関連付けて考えられがちです。
養育費を滞納すると「子どもに会う資格がない」と元配偶者に思われ、面会を拒否されるケースも少なくありません。
子どもとの関係を維持するためにも、無理のない金額で養育費を設定し、確実に支払い続けることが大切です。
もし支払いが困難になった場合は、滞納する前に元配偶者に状況を説明し、減額の協議を申し入れましょう。
誠実なコミュニケーションが、子どもとの関係を守るカギになります。
3.自分の両親に請求される恐れがある
あまり知られていませんが、養育費が支払えない場合、子どもの祖父母(扶養義務者の両親)に請求が向けられることがあります。
民法上、直系血族(親子・祖父母と孫)には扶養義務があるためです。
あなたに支払い能力がない場合、子どもの監護親はあなたの両親に対して「代襲相続的扶養請求」ができます。
特に、あなたの両親に十分な資力がある場合は、この請求が認められる可能性が高くなります。
ご両親に迷惑をかけないためにも、自分の支払い能力に見合った養育費の取り決めをすることが重要です。
また、収入状況の変化があった場合は、速やかに減額の手続きを進めることも大切でしょう。
支払い能力を超えた養育費の合意は、あなた自身だけでなく、家族にも影響を及ぼす可能性があります。
現実的な金額で合意し、必要に応じて見直すことで、長期的に子どもの養育に関わり続けられるよう心がけましょう。
離婚後、養育費の支払いが困難になった場合、減額請求を申し立てよう
離婚時に取り決めた養育費の金額も、状況の変化によって見直しが必要になるケースがあります。
特に、離婚後に収入が減少したり、病気になったりして支払い能力がなくなった場合はどうすればよいのでしょうか。
養育費の金額は「事情変更の原則」に基づいて変更が可能です。
支払い能力が著しく低下した場合は、減額請求の申立てを検討しましょう。
減額請求の手順は、まず元配偶者と話し合いを行い、合意が得られない場合は家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てます。
減額が認められるためには、離婚時と比べて「事情の変更」があったことを証明する必要があります。
例えば、失業や転職による収入減少、重い病気の発症、再婚と新しい子どもの誕生などが該当します。
| 減額が認められやすい例 | 減額が認められにくい例 |
|---|---|
| ・会社の倒産による失業 ・重大な病気やけがによる就労不能 ・災害による収入源の喪失 ・再婚による新たな扶養家族の発生 | ・自己都合による退職 ・一時的な収入減少 ・浪費による経済状況の悪化 ・意図的な収入減少(養育費逃れ) |
減額請求の際は、収入が減ったことを客観的に証明できる資料を用意することが重要です。
診断書、解雇通知書、給与明細書、失業保険受給証明書などが有効な証拠となります。
また、元配偶者との関係を考慮し、一方的な通知ではなく誠実なコミュニケーションを心がけましょう。
減額が認められるまでの間も、可能な範囲で養育費を支払い続けることで、誠意を示すことができます。
養育費の支払いが困難になった場合は、滞納する前に早めの対応を取ることが、子どもとの関係を守る上でも重要です。

よくある質問
養育費の支払い能力がない場合について、読者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
自分の状況に当てはまるものがないか確認してみてください。
- 休業補償や失業手当は養育費算定の対象になりますか?
- 養育費は借金してでも支払わなければならないのですか?
- 財産開示手続きに応じない場合のペナルティについて教えてください。
- 病気で働けなくなった場合、養育費の支払い義務は免除されますか?
- 養育費が払われない場合の強制執行の方法を教えてください。
- 無職で養育費が払えない場合の対処法はありますか?
まとめ
養育費の支払い能力がない場合でも、養育費の支払い義務自体はなくなりません。
本当に支払い能力がないと認められるのは、病気やけがで働けない場合、育児などで就労が困難な場合、生活保護を受給している場合などの限られたケースです。
支払い能力がない状況になったら、滞納する前に元配偶者に状況を説明し、減額や支払い猶予について協議しましょう。
協議が成立しない場合は、家庭裁判所に減額調停を申し立てる方法もあります。
支払い能力を超えた養育費に合意すると、滞納や関係悪化など様々なリスクがあるため、現実的な金額で合意することが大切です。
養育費問題で悩んだときは、一人で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。












