専業主婦が親権を取る方法|必要となる条件と対策とは
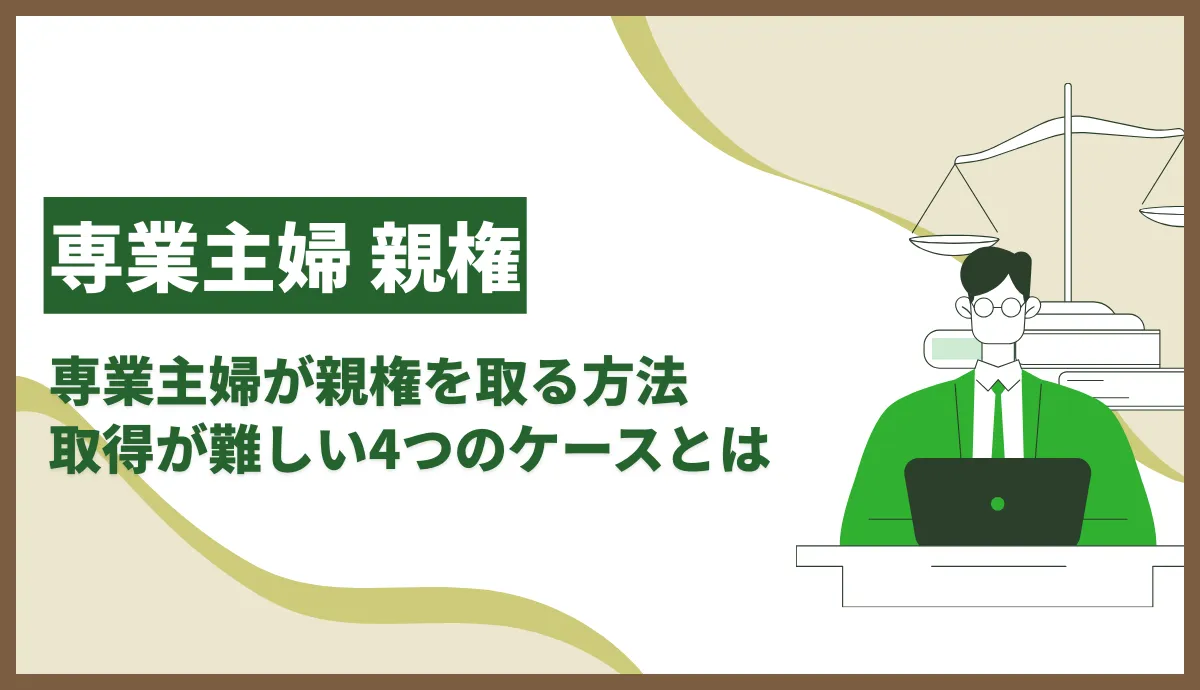
専業主婦として離婚を考える中で、最も心配なのが親権問題ではないでしょうか。
「収入がない専業主婦でも親権は取れるの?」「子どもと離れ離れになるのは絶対に避けたい」という不安を抱えている方も多いと思います。
離婚調停や裁判で専業主婦が親権者として認められるためには、いくつかの重要な基準があります。
この記事では、専業主婦が親権を獲得するための具体的なポイントや親権の基本知識について詳しく解説していきます。
専業主婦の方の不安を少しでも解消できるよう、わかりやすい言葉で一つひとつ丁寧に説明していきます。
親権とは何か?詳しく解説
親権とは、未成年の子どもに対して親が持つ法律上の権利と義務のことを指します。
離婚する際、専業主婦にとって最も気がかりなのは「子どもと一緒に暮らせるのか」という点ではないでしょうか。
実は親権には「財産管理権」と「身上監護権」という2つの重要な要素があります。
この2つを理解することで、専業主婦が親権を得るために何が必要なのかが見えてくるでしょう。
それでは、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
- 財産管理権の内容
- 身上監護権の役割
- 親権と監護権の違いと関連性
財産管理権の内容
財産管理権とは、子どもの財産を管理し、その財産に関する法律行為を行う権利のことです。
子どもが相続や贈与によって財産を取得した場合、親権者はその財産を子どもが成人するまで管理する責任があります。
例えば、祖父母から子どもへの贈与や保険金の受け取り、不動産の名義変更などの手続きは、親権者が子どもに代わって行います。
財産管理権は単なる「お金の管理」ではなく、子どもの将来に向けた資産形成や教育資金の確保という重要な役割を担っています。
専業主婦が親権者になる場合、収入がないからといって財産管理能力がないとは判断されません。
むしろ、日常的な家計管理を担ってきた経験が、子どもの財産を適切に管理できる能力として評価されることもあるのです。
ただし、借金が多いなど金銭管理に問題がある場合は、親権取得において不利になる可能性があります。
身上監護権の役割
身上監護権は、子どもの生活全般に関わる世話や教育、健康管理などを行う権利と義務です。
具体的には、子どもの居住場所の決定、学校選び、医療行為の同意など、子どもの日常生活に関わるあらゆる決断を親権者が行います。
専業主婦の場合、子育てに専念できる時間的余裕があるため、身上監護の面では有利に働くことが多いでしょう。
裁判所は「子どもの最善の利益」を最優先に考えるため、これまで主に子育てを担当してきた親に身上監護権を認めることが多い傾向があります。
例えば、幼い子どもの場合、日常的に世話をしてきた母親に親権が認められるケースが多いです。
また、子どもの精神的安定や生活環境の連続性を重視することから、これまでと同じ環境を維持できる親が有利になります。
身上監護権は子どもの心身の健全な発達に直結する重要な権利であり、専業主婦が親権を得るうえでの強みとなるポイントです。
親権と監護権の違いと関連性
親権と監護権は似ているようで異なる概念です。
親権は財産管理権と身上監護権を含む包括的な権利ですが、監護権は子どもと一緒に暮らし、日常的な世話をする権利に特化しています。
離婚時に親権と監護権が分離されるケースもあります。
例えば、父親が親権者として子どもの財産管理を担当し、母親が監護権者として子どもと同居して日常的な養育を行うという形です。
専業主婦にとって重要なのは、必ずしも親権全体ではなく「子どもと一緒に暮らせるかどうか」という監護権の部分かもしれません。
監護権のみを得た場合でも、子どもと同居して日常的な養育を行うことができます。
ただし、監護権だけでは子どもに関する重要な決定(進学、医療行為など)や財産管理に関して制限がある点に注意が必要です。
親権者と監護権者の意見が対立した場合、家庭裁判所に審判を求めることも可能です。
専業主婦が離婚を考える際は、親権と監護権のどちらを望むのか、またその理由を明確にしておくことが大切でしょう。
専業主婦でも親権者として認められる具体的なケース
専業主婦が親権を取得できるケースは意外と多いものです。
実際、日本の離婚調停や裁判では、子どもと長く一緒に過ごしてきた親に親権が認められる傾向があります。
収入がないからといって、必ずしも親権取得で不利になるわけではありません。
裁判所は「子どもの最善の利益」を最優先に考えるため、経済力だけでなく精神的な繋がりや養育環境も重視します。
下記のような状況では、専業主婦でも親権を取得できる可能性が高いでしょう。
- これまで主に育児を担当してきた実績がある場合
- 子どもが母親との同居を望んでいる場合(特に10歳以上の子どもの意思は尊重される)
- 離婚後の生活基盤(住居や養育費など)が確保されている場合
- 夫側に不利な事情(長時間労働、DV履歴、育児放棄など)がある場合
- 子どもが幼い(特に乳幼児)場合
- 兄弟姉妹がいて、分離したくない場合
また、親族のサポートがある場合や、離婚後に仕事を始める具体的な計画がある場合も有利に働きます。
ただし、養育費だけでは生活が厳しい場合は、自分の収入を得る方法も考えておくべきでしょう。
離婚調停や裁判では、いかに子どもの福祉を最優先に考えているかを示すことが重要です。
日々の育児記録や子どもとの思い出の写真、学校の先生や近所の方からの証言なども、親権取得に役立つ資料となります。
専業主婦の方は、親権を得るためにこれらの状況や資料を整えておくと良いでしょう。
専業主婦が親権者と認められるための重要な5つの基準
専業主婦が親権を獲得するためには、いくつかの重要な基準があります。
裁判所は「子どもの最善の利益」を基本として判断するため、以下の点が特に重視されます。
それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。
監護者としてのこれまでの実績
これまで子どもの世話を主に担当してきた親は、親権判断において有利になります。
専業主婦の場合、日常的に子どもの面倒を見てきた実績が高く評価されるでしょう。
例えば、子どもの送り迎えや学校行事への参加、病気の時の看病など、日々の養育の証拠があると強みになります。
裁判所は「継続性の原則」を重視するため、これまで主に育児を担当してきた親に親権を認めることが多いのです。
子どもの学校の連絡帳、通知表のサイン、予防接種の記録など、普段から子どもの生活に関わってきた証拠を集めておくと良いでしょう。
また、学校の先生や医師、近所の人など第三者からの証言も有効です。
両親の健康状態と子どもに対する愛情の深いさ
親権判断では、両親の身体的・精神的な健康状態も重要な要素となります。
子どもを適切に養育するためには、親自身が健康であることが前提です。
うつ病やアルコール依存症など、治療中の精神疾患がある場合は、治療状況や回復の見込みを示す医師の診断書が重要になります。
単に病気があるというだけで親権が否定されるわけではなく、適切に治療を受け、子どもの養育に支障がないことを示せれば問題ありません。
また、子どもへの愛情の深さも判断材料になります。
日常的に子どもとコミュニケーションを取り、子どもの気持ちに寄り添う姿勢を示すことが大切です。
例えば、子どもの誕生日や特別な行事を大切にしている、子どもの趣味や関心事に理解を示しているといった点が評価されます。
離婚後に子どもが安心して生活できるかどうか
離婚後の生活環境が子どもにとって安定したものかどうかは、親権判断の重要なポイントです。
専業主婦の場合、経済的な基盤が心配されますが、以下の点が確保できれば有利になります。
- 安定した住居環境(子どもが今までと同じ学校に通えるなど)
- 十分な養育費の取り決め
- 親族のサポート体制
- 就職の見込みや具体的な収入計画
裁判所は「子どもの生活環境の安定性」を重視するため、離婚後も子どもが安心して暮らせる環境を提供できることを示すことが大切です。
また、子どもが通っている学校や習い事、友人関係など、現在の環境をできるだけ維持できる計画を立てておくと良いでしょう。
離婚後の具体的な生活プランを示せると、専業主婦でも親権を得やすくなります。
子どもの年齢と兄弟姉妹の存在が親権に与える影響
子どもの年齢や兄弟姉妹の有無も、親権判断に影響します。
一般的に、幼い子ども(特に乳幼児)の場合は母親に親権が認められることが多いです。
これは、幼い子どもが母親との心理的な結びつきが強い傾向があるためです。
兄弟姉妹がいる場合、裁判所は兄弟姉妹の分離を避ける傾向があります。
例えば、3人の子どものうち2人が母親と暮らしたいと希望している場合、残りの1人も含めて母親に親権が認められる可能性が高くなります。
子どもの年齢が上がるにつれて、子ども自身の意見が重視されるようになります。
思春期の子どもの場合、子どもの希望がより強く考慮される傾向があるので、普段からコミュニケーションを大切にすることが重要です。
子どもの意思と親との精神的なつながり
子どもが10歳程度以上になると、子ども自身の意思が親権判断で重要な要素となります。
裁判所は子どもの希望を聞き取り、判断材料とすることが多いです。
ただし、子どもの意思だけで決まるわけではなく、その意思が子どもの福祉に沿ったものかどうかも考慮されます。
子どもとの日常的なコミュニケーションを通じて築かれた信頼関係や心の繋がりが、親権判断において重要な証拠となります。
離婚の話し合いが始まってから急に子どもに優しくするのではなく、日頃からの積み重ねが大切です。
子どもの感情を尊重し、子どもが不安なく自分の気持ちを表現できる関係を築いておくことが、専業主婦の親権獲得に役立ちます。
また、子どもが親との面会を楽しみにしている様子や、親との思い出の写真なども有力な証拠になります。
専業主婦の親権取得が難しいと考えられる4つのケース
専業主婦が親権を取得できる可能性は十分にありますが、いくつかのケースでは不利になることもあります。
以下のような状況では、専業主婦であっても親権の獲得が難しくなる可能性があるため注意が必要です。
これらの状況に心当たりがある場合でも、適切な対策を取ることで親権獲得の可能性を高めることができます。

子どもと離れて暮らしている場合
別居中に子どもと一緒に暮らしていない期間が長いと、親権取得が難しくなる可能性があります。
裁判所は「継続性の原則」を重視するため、子どもが現在安定した環境で暮らしているなら、その状況を変えたくないと考える傾向があるからです。
例えば、別居して1年以上子どもと会っていない場合や、定期的な面会を行っていない場合は不利になります。
子どもと別居中の場合でも、定期的に面会交流を行い、電話やビデオ通話などで連絡を取り続けることが非常に重要です。
別居中の面会記録や連絡の証拠(メール、LINEなど)を残しておくと、子どもとの関係を維持していた証拠になります。
また、子どもの学校行事にできる限り参加したり、子どもの誕生日やイベントを一緒に過ごしたりする努力も評価されます。
離れて暮らしている理由が夫のDVから逃れるためなど、やむを得ない事情がある場合は、その理由を明確に説明できるようにしておきましょう。
親が深刻な精神的・身体的問題を抱えている場合
重度のうつ病やアルコール依存症など、子どもの養育に支障をきたす可能性がある精神疾患がある場合、親権取得が難しくなることがあります。
同様に、入退院を繰り返すような重い身体疾患がある場合も、子どもの安定した養育環境を確保できるか疑問視されます。
ただし、疾患があるというだけで親権が否定されるわけではなく、適切な治療を受け、サポート体制が整っていることを証明できれば親権獲得の可能性はあります。
例えば、次のような対策が有効です。
- 病状が安定していることを示す医師の診断書を用意する
- 治療を継続していることの証明(通院記録など)
- 家族や親族のサポート体制を示す証拠(親族からの陳述書など)
- 精神科医や心理カウンセラーからの養育能力に関する意見書
健康上の問題がある場合は、それを隠すのではなく、きちんと治療を受け、子どもの養育に支障がないことを示す姿勢が大切です。
親が過去に虐待やDVをしていた場合
子どもへの虐待やDVの履歴がある場合、親権取得は非常に難しくなります。
裁判所は子どもの安全を最優先に考えるため、虐待やDVの事実が認められると、親権を認めない判断をすることが多いです。
虐待やDVの定義は身体的暴力だけでなく、言葉による暴力や無視などの精神的虐待も含まれます。
子どもの前で配偶者に暴力をふるうことも、子どもへの心理的虐待と判断されることがあるので注意が必要です。
もし夫から子どもやあなた自身へのDVがある場合は、以下の証拠を集めておくことが重要です。
- 診断書や怪我の写真
- 警察への相談記録
- DVシェルターの利用記録
- 暴言や脅迫のメッセージ
- 目撃者の証言
一方、もし過去に自分自身が感情的になって子どもに厳しく接したことがあるなら、カウンセリングやペアレンティング講座を受講するなど、改善の努力を示すことが大切です。
子どもを虐待する意図はなかったとしても、冷静に子どもと接することができない状態は親権判断で不利に働きます。
収入が不安定で経済的に困難な状況にある場合
専業主婦が親権を取得する際、経済的な自立の見通しは重要な要素です。
収入がなく、養育費だけでは生活が厳しい場合や、多額の借金がある場合は、子どもを養育する経済力に疑問を持たれる可能性があります。
特に養育費の未払いリスクが高い場合(元夫の収入が不安定、過去に支払い遅延があるなど)は、自分自身の収入源を確保することが重要です。
ただし、経済力だけが親権判断の決め手ではありません。収入が少なくても、生活基盤がしっかりしていれば親権を獲得できる可能性は十分にあります。
経済的な不安がある場合は、以下のような対策を取ることをおすすめおすすめ
- 具体的な就職計画や資格取得の予定を示す
- 養育費の取り決めを公正証書にする
- 親族からの援助を証明する書類を用意する
- 児童扶養手当など各種支援制度の利用計画を示す
- 住居費や生活費がどの程度必要か、具体的な家計計画を立てる
経済的に厳しい状況でも、子どもの養育に必要な最低限の生活基盤を確保できることを示すことが大切です。
場合によっては、離婚調停の段階で財産分与や慰謝料についてもしっかり話し合い、生活の基盤づくりに役立てることも検討しましょう。

よくある質問
専業主婦と親権に関して、多くの方が気になる質問に回答します。
離婚を考える中で不安に思うことや疑問点について、簡潔にお答えしていきます。
- 専業主婦でも親権を取れる確率はどのくらいですか?
- 経済力がない専業主婦は親権獲得で不利になりますか?
- 専業主婦が離婚する場合、子供の養育費はどうなりますか?
- 母親に精神疾患がある場合、親権はとれないのでしょうか?
- 専業主婦で貯金がない状態での離婚は悲惨ですか?
- 親権を父親が取るケースはどのような場合か教えてください。
- 共同親権の可能性について教えてください。
- 親権をあえて夫に渡すメリットはありますか?
- 親権問題で弁護士に相談するポイントを教えてください。
まとめ
専業主婦でも親権を獲得することは十分に可能です。
親権判断の基準は経済力だけでなく、これまでの養育実績や子どもとの精神的な繋がり、安定した生活環境を提供できるかどうかなど、多角的な視点から評価されます。
特に重要なのは「子どもの最善の利益」という点です。
裁判所は、どちらの親が子どもの健全な成長に最も適しているかを最優先に判断します。
親権獲得に向けては、日頃からの育児への関わりを大切にし、離婚の際には具体的な生活プランや経済的な見通しを立てておくことが重要です。
また、必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることも検討しましょう。
子どもとの絆を大切にしながら、冷静に親権問題に向き合うことが、専業主婦の親権獲得への近道となります。











