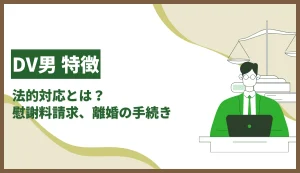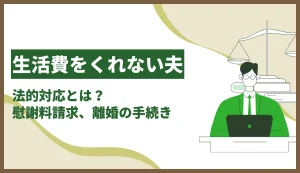DV離婚で慰謝料請求!相場と増額のために知っておくべき8つのポイント

毎日のように暴力に怯え、心身ともに傷つけられるDV被害。
離婚を決意しても、その後の生活や慰謝料について不安を抱えている方は少なくありません。
DVによる離婚での慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
この記事では、DV離婚における慰謝料の相場や請求方法について詳しく解説していきます。
DV被害に苦しむ方々の立場に寄り添い、具体的な解決策を分かりやすくお伝えします。
DVによる離婚の慰謝料の相場は50万円~300万円
DVによる離婚で請求できる慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円程度です。
この金額は、暴力の程度や頻度、結婚期間、被害者の心身への影響などによって大きく変わってきます。
特に重度のケースでは400万円以上の高額な慰謝料が認められた判例もあります。
DV慰謝料は通常の離婚慰謝料よりも高額になる傾向があります。
これは、被害者が受けた精神的、肉体的苦痛の度合いが考慮されるためです。
また、DVの証拠が明確に残っているケースほど、慰謝料の金額は高くなりやすいでしょう。
| 慰謝料の相場 | DVの特徴 |
|---|---|
| 50万円程度 | 軽度の暴言や、頻度の少ない軽い暴力 |
| 100万円程度 | 繰り返される暴言や暴力、精神的な影響がある |
| 200万円程度 | 頻繁な暴力や重度の精神的虐待、日常生活に支障 |
| 300万円以上 | 重篤な怪我を負わせるDV、長期間の虐待、後遺症が残る |
ただし、これらはあくまで目安であり、実際の慰謝料額は個々のケースによって異なります。
慰謝料を少しでも増額するためには、証拠の収集や弁護士への相談が欠かせません。

DV被害により離婚した場合の慰謝料請求に関する判例
DVによる離婚の慰謝料額は、実際の裁判例を見ることでより具体的なイメージがつかめます。
ここでは、実際の判例を金額別に紹介しながら、どのようなケースでどれくらいの慰謝料が認められるのかを見ていきましょう。
50万円の事例|東京地判平成18年8月28日
この判例では、夫から妻への暴言や軽度の身体的暴力が認められました。
暴力の頻度は比較的少なく、身体的な傷害も軽微だったことから、慰謝料は50万円と認定されています。
このケースでは、証拠が乏しかったことも慰謝料が低額になった要因の一つです。
しかし、DVの事実自体は認められたため、最低限の慰謝料が支払われることになりました。
結婚期間も比較的短く、子どもがいなかったことも考慮されています。
100万円の事例|東京地判平成18年1月17日
この事例では、週に1〜2回程度の暴力行為が約1年間続いていました。
妻は精神的ストレスから不眠や食欲不振の症状を訴え、心療内科に通院していました。
医師の診断書や、親族の証言が証拠として提出され、これらが認められました。
精神的な影響が客観的な証拠によって裏付けられたことが、慰謝料額に反映されています。
ただし、深刻な身体的傷害はなかったため、100万円という金額に落ち着きました。
200万円の事例|東京地判平成18年7月27日
この裁判例では、夫が妻に対して2年以上にわたり継続的な暴力を振るっていました。
暴力の結果、妻は全治2週間の怪我を複数回負い、警察への相談記録も証拠として提出されました。
さらに、子どもの前でDVが行われていたことも認定され、子どもへの心理的影響も考慮されています。
継続的な暴力と子どもへの影響が重視され、慰謝料は200万円と認められました。
また、夫婦の結婚期間が5年以上と比較的長かったことも要因の一つでした。
300万円の事例|東京地判平成21年8月28日
この事例では、5年以上の長期にわたって繰り返された重度の暴力がありました。
妻は複数回入院するほどの怪我を負い、うつ病を発症して長期の治療を余儀なくされました。
夫が飲酒時に暴力をふるうパターンが繰り返され、妻は常に恐怖の中で生活していました。
暴力の重篤さと長期間にわたる精神的苦痛が考慮され、300万円の慰謝料が認定されました。
診断書や写真などの明確な証拠が多数提出されたことも、高額な慰謝料認定につながりました。
400万円の事例|東京地判平成17年6月22日
この裁判例は、特に重篤なDV被害のケースでした。
10年以上の結婚期間中、夫は妻に対して悪質な身体的・精神的暴力を継続的に行っていました。
妻は複数回の骨折を含む重傷を負い、後遺症が残るほどの暴力を受けていました。
また、2人の子どもも父親の暴力を目撃したことによるPTSDと診断されていました。
暴力の重篤さ、長期間の継続、子どもへの心理的影響が総合的に考慮された結果、400万円という高額な慰謝料が認められました。
このケースでは、夫の社会的地位や収入の高さも考慮され、支払能力があると判断されています。
このように、DVによる離婚の慰謝料額は、暴力の程度や頻度、期間、被害者への影響などによって大きく変わります。
慰謝料請求を検討している方は、自分のケースに近い事例を参考にしつつ、証拠収集を徹底することが大切です。
DVによる慰謝料が増額または高額となる8つのポイント
DVによる離婚の慰謝料額は、様々な要因によって増額される可能性があります。
ここでは、慰謝料が高額になりやすい8つのポイントを詳しく解説します。
DVが度々起きている
DVの頻度は慰謝料額に大きな影響を与えます。
一度きりの暴力と比べて、繰り返し行われるDVは被害者の精神的苦痛が大きくなります。
たとえば週に複数回の暴力があった場合は、月に1回程度のケースよりも慰謝料が高くなる傾向があります。
DVの頻度を証明するためには、暴力を受けた日時や状況を日記などに記録しておくことが効果的です。
できれば写真や音声記録などの客観的な証拠も残しておくと、より説得力が増します。
DVの期間が長期にわたる
DVが長期間続いている場合も、慰謝料が増額される要因となります。
1年以上の長期にわたるDVは、短期間の暴力よりも精神的ダメージが大きいと判断されるからです。
特に3年以上続いている場合は、慰謝料が大幅に増額されるケースが多いでしょう。
長期間のDVによる日常的な恐怖や不安は、被害者の人格形成にまで影響を及ぼすことがあります。
そのような深刻な精神的被害は、裁判所でも重く受け止められます。
DV被害者の過失
被害者側にも何らかの過失があると判断された場合、慰謝料は減額される可能性があります。
ただし、DV加害者が「相手にも原因がある」と主張することは珍しくありません。
被害者の言動が暴力の理由になることはないという認識が裁判所でも広まっています。
DVは相手の言動に関わらず絶対に許されない行為であり、被害者に非があるという主張は通りにくくなっています。
とはいえ、慰謝料請求の際には、過失相殺の可能性も考慮して準備することが大切です。
DVによる怪我や障害の重篤さ
暴力によって負った怪我の程度も、慰謝料額を左右する大きな要素です。
全治2週間以上の怪我や、後遺症が残る場合は慰謝料が高額になりやすいでしょう。
特に入院が必要な重傷を負った場合や、仕事を休まざるを得なかった場合は重視されます。
怪我の証拠として、診断書や治療費の領収書、傷の写真などを保存しておくと有利になります。
また、通院記録も重要な証拠となるため、きちんと病院に行って記録を残すことをおすすめします。
DV被害が原因でうつ病を患った
精神的DVや身体的暴力の結果、うつ病などの精神疾患を発症した場合も慰謝料増額の理由になります。
精神科や心療内科での診断書があれば、DVと精神疾患の因果関係を証明しやすくなります。
特に長期の通院や薬物治療が必要な場合は、精神的苦痛の大きさが認められやすいでしょう。
精神的な症状は目に見えないため、専門医の診断書や意見書が非常に重要な証拠となります。
症状が出始めたらすぐに医療機関を受診し、DVとの関連性について医師に相談することをおすすめします。
夫婦の結婚生活が長期間にわたっている
結婚期間の長さも慰謝料額に影響します。
長年連れ添った夫婦の場合、離婚によって失われる利益が大きいと判断されることがあるためです。
10年以上の長期婚姻関係であれば、より高額な慰謝料が認められる傾向にあります。
長い結婚生活の中でDVに耐えてきた精神的苦痛は、短期婚のケースより大きいと評価されやすいでしょう。
また、高齢になってからの離婚は再婚の可能性も低くなるため、その点も考慮されることがあります。
養育を要する子どもの人数
子どもがいる家庭でのDVは、子どもへの心理的影響も考慮されます。
特に子どもの前でDVが行われていた場合、子どもの心理的ダメージも慰謝料に反映されることがあります。
また、未成年の子どもが複数いる場合は、離婚後の経済的負担も大きくなるため考慮されやすいでしょう。
子どもがDVを目撃したことによるトラウマが認められれば、慰謝料が増額される可能性が高まります。
子どもが心理カウンセリングを受けている場合は、その記録も重要な証拠となります。
DV加害者の年齢が高い
加害者の年齢や社会的地位も、慰謝料額に影響することがあります。
年齢が高く、社会的責任がある立場にある人物からのDVは、より悪質と判断される傾向があります。
また、加害者の収入が高い場合も、支払能力があると判断され高額な慰謝料が認められやすくなります。
加害者の年収や資産状況は、慰謝料の支払い能力を示す重要な要素となります。
裁判所は被害の程度だけでなく、加害者の支払能力も考慮して慰謝料額を決定することが多いのです。
これら8つのポイントは、実際の慰謝料額を決める際に総合的に判断されます。
自分のケースでどの要素が当てはまるか確認し、弁護士と相談しながら適切な金額を請求することが大切です。
DVによる離婚慰謝料を請求・増額するには証拠が欠かせない
DVによる離婚慰謝料を請求する際、最も重要なのが「証拠」です。
証拠なしでは「言った、言わない」の水掛け論になり、適切な慰謝料を得ることが難しくなります。
ここでは、効果的な証拠の集め方と保存方法について解説します。
DVを証明するための証拠
DVの証拠には様々な種類があります。
日常的にDVを受けている場合は、以下のような証拠を意識的に集めることが大切です。
DVの証拠は多ければ多いほど、慰謝料請求の際に有利に働きます。
特に客観的な第三者が関わる証拠は信頼性が高いため、積極的に収集しましょう。
可能であれば複数の種類の証拠を組み合わせることで、より説得力が増します。
| 証拠の種類 | 収集方法、注意点 |
|---|---|
| 怪我の写真 | 日付、時間が分かるように撮影し、クラウドなどに保存 |
| 診断書 | 病院で「裁判用」と伝えて作成してもらう |
| 音声、動画記録 | スマホで録音、録画(隠し撮りは証拠能力が低下する可能性あり) |
| LINEやメール | 脅迫やDVを認める内容をスクリーンショット保存 |
| 目撃者の証言 | 親族や友人など、DVを目撃した人に証言を依頼 |
| 日記 | DVの日時、内容、状況を詳細に記録 |
| 警察の相談記録 | DV相談時の受理番号や担当者名をメモ |
| 壊れた家具、物品 | 破壊行為の証拠として写真撮影して保存 |
ただし、証拠収集の際は自分の安全を最優先にしてください。
相手に証拠集めを気づかれて危険な状況になるようであれば、専門機関に相談しましょう。
DVに関する医療記録(診断書)の収集方法
医療記録は、DVの証拠として特に重要です。
DVによって怪我をした場合は、必ず医療機関を受診して記録を残しましょう。
診断書を作成してもらう際のポイントは以下の通りです。
診断書には「DV被害による怪我」と明記してもらうことが重要です。
医師に対して「離婚調停や裁判で使用する可能性がある」と伝えておくと、より詳細な記載をしてもらえるでしょう。
精神的DVの場合は、心療内科や精神科での診断も有効な証拠になります。
- 診断書作成を依頼する際は「裁判用」と伝える
- 怪我の原因がDVであることを医師に伝える
- 診断書には「全治○週間」という具体的な記載を依頼
- 通院記録も重要な証拠になるため、定期的に受診する
- 治療費の領収書も保管しておく
- 精神的症状がある場合は、精神科や心療内科も受診
また、同じ医療機関に継続して通院することで、DVの継続性を示す証拠にもなります。

警察などへの相談記録
警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関への相談記録も、有力な証拠になります。
DVを受けたら、できるだけ早く警察に相談し、記録を残しておきましょう。
相談する際のポイントは以下の通りです。
警察への相談は、暴力の証拠がなくても110番通報や相談という形で記録に残ります。
相談時に受理番号や担当者名をメモしておくと、後で証拠として活用しやすくなります。
また、警察だけでなく、以下の機関への相談記録も有効な証拠となります。
- 配偶者暴力相談支援センター
- 福祉事務所や市区町村の相談窓口
- 女性相談センター
- 全国共通のDV相談ナビ(#8008)
- 法テラス
相談の際には、できるだけ具体的にDVの状況を説明し、記録に残してもらいましょう。
警察に被害届を提出した場合は、その控えも保管しておくことが大切です。
保護命令を申し立てた記録も、DVの証拠として高い証明力を持ちます。
このように、DVによる離婚慰謝料の請求では、様々な証拠を計画的に収集することが成功への鍵となります。
証拠集めは時間がかかる場合もありますが、将来の自分を守るために必要な作業だと考えて取り組みましょう。

DVを理由に離婚して慰謝料を請求するまでの手順
DVが原因で離婚を考えている場合、具体的にどのような手順で進めれば良いのでしょうか。
ここでは、DVを理由に離婚して慰謝料を請求するまでの流れを解説します。
話し合いによる協議離婚
最も簡単な離婚方法は協議離婚です。
これは双方の話し合いで離婚条件を決め、合意すれば離婚届を提出するだけで成立します。
ただし、DV加害者との直接交渉は危険を伴うケースも多いため注意が必要です。
DVケースでの協議離婚は、必ず弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士に代理人として交渉してもらえば、直接顔を合わせる必要がありません。
協議離婚で合意する際は、以下の点を必ず書面で取り決めておきましょう。
- 慰謝料の金額と支払方法、期限
- 財産分与の内容
- 子どもがいる場合は親権、養育費、面会交流
- 将来の接触禁止事項
口頭での約束だけでは後々トラブルになりやすいため、必ず公正証書などの法的効力のある書面を作成しましょう。
民事訴訟または離婚調停
協議離婚が難しい場合は、次のステップとして調停を検討します。
離婚調停は家庭裁判所が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。
DVの場合、別室での調停や代理人出席など特別な配慮を申請できます。
調停では、DVの証拠を準備して慰謝料の根拠を明確に示すことが重要です。
離婚原因、慰謝料、親権、財産分与などを同時に協議できるのが調停のメリットです。
調停の流れは以下のようになります。
- 離婚調停の申立書を家庭裁判所に提出
- 相手方に調停期日の呼び出し通知が送付される
- 調停委員を交えた話し合いを数回行う
- 合意に至れば調停成立、できなければ不成立
調停は強制力がないため、相手が出頭しなかったり合意しなかったりする場合もあります。

離婚裁判を進める
調停でも解決しない場合は、最終手段として離婚裁判(離婚訴訟)を起こします。
裁判では裁判官が法律に基づいて判断を下すため、DVの証拠が特に重要になります。
離婚裁判の流れは以下の通りです。
DV事案の裁判では、裁判所による保護命令を同時に申し立てることも検討しましょう。
保護命令が出れば、加害者の接近が禁止され、安全に裁判を進められます。
- 訴状を裁判所に提出
- 第一回口頭弁論(双方の主張を確認)
- 証拠提出と証人尋問
- 判決(離婚の可否、慰謝料額、親権者などを決定)
裁判は一般的に半年から1年以上かかるため、精神的・経済的な負担を考慮して準備する必要があります。
裁判の際は必ず弁護士に依頼することをおすすめします。
特にDVケースでは、証拠の収集や法的主張において専門知識が必要になるからです。
裁判で離婚が認められれば、判決に基づいて慰謝料の支払いも命じられます。
判決には強制力があるため、支払いがない場合は強制執行も可能です。
DVを理由とした離婚では、どの方法を選ぶにせよ、自分の安全を最優先に考えることが大切です。
無理に自分で対応しようとせず、弁護士や支援機関の力を借りながら進めていきましょう。

DV被害者が離婚を伝える効果的な方法
DVの関係から抜け出すには、安全に離婚の意思を伝えることが重要です。
ただし、離婚を切り出すことで暴力がエスカレートするリスクもあるため、慎重な対応が必要です。
ここでは、DV被害者が安全に離婚を伝える方法について解説します。
二人だけでなく第三者を交えて話し合いをする
DV加害者と二人きりで話し合うことは危険を伴います。
信頼できる第三者を交えることで、暴力のリスクを減らせることが多いでしょう。
弁護士を代理人として立てれば、直接顔を合わせる必要もなくなります。
実際、多くのDV被害者は弁護士を通じて離婚協議を行うことで安全を確保しています。
また、以下のような第三者の同席も効果的です。
- 双方の親族(特に相手が敬意を抱く人物)
- カウンセラーや相談員
- 信頼できる共通の友人
- 宗教関係者(宗教を信仰している場合)
話し合いの場所は、公共の場所や相談支援センターなど安全な環境を選びましょう。
いざという時にすぐ助けを求められる状況を整えておくことが大切です。
裁判や調停を経て離婚を成立させる
DVケースでは、協議離婚よりも調停や裁判を利用する方が安全な場合が多いです。
調停や裁判では、裁判所という公的な場で離婚について話し合うことになります。
DVの場合、以下のような配慮を申請できることを知っておきましょう。
DV被害者は「別室調停」を申請できるため、加害者と同じ部屋にいる必要はありません。
場合によっては、調停委員が双方を行き来して話を聞く「シャトル調停」も可能です。
また、出廷時の安全対策として以下のようなサポートを受けられることもあります。
- 裁判所への別々の入退廷時間の設定
- 待合室の分離
- 警備員による見守り
- 代理人のみの出席
調停や裁判を選ぶ際は、必ず事前に弁護士に相談し、安全対策を十分に練っておきましょう。
裁判中の暴力行為を防ぐため保護命令を出してもらう
離婚手続き中も安全を確保するため、保護命令の申立てを検討しましょう。
保護命令とは、DV加害者が被害者に近づくことを禁止する裁判所の命令です。
保護命令には主に以下の種類があります。
保護命令に違反すると刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
この強制力によって、離婚手続き中の安全が確保できるでしょう。
| 保護命令の種類 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 接近禁止命令 | 被害者の身辺への接近を禁止 | 6ヶ月間 |
| 退去命令 | 共同住居からの退去を命じる | 2ヶ月間 |
| 電話等禁止命令 | 電話、メール等での連絡を禁止 | 6ヶ月間 |
| 子への接近禁止命令 | 子どもへの接近を禁止 | 6ヶ月間 |
| 親族等への接近禁止命令 | 親族等への接近を禁止 | 6ヶ月間 |
保護命令の申立てには、DVの証拠が必要です。
診断書や写真、第三者の証言など、できるだけ多くの証拠を集めておきましょう。
- 地方裁判所に保護命令申立書を提出
- 裁判所による審理(通常は書面審理)
- 保護命令発令の判断(通常は2週間程度)
- 発令された場合、加害者と警察に通知
保護命令の申立て手続きは以下の流れで行います。
保護命令が出されても油断せず、安全な住居の確保や警察への相談など、重層的な安全対策を講じることをおすすめします。
DV被害者が離婚を伝える際は、常に自分の安全を最優先に考えることが大切です。
一人で抱え込まず、弁護士や支援団体などの専門家のサポートを積極的に活用しましょう。
DVによる離婚慰謝料の未払いケースとその対処法
離婚が成立し慰謝料の支払いが決まっても、実際に支払われないケースは少なくありません。
特にDV案件では、加害者が意図的に支払いを遅らせたり、拒否したりすることがあります。
ここでは、慰謝料が支払われない場合の対処法について解説します。
裁判所から出される履行勧告と履行命令
慰謝料の支払いが滞った場合、まず検討すべきなのが「履行勧告」です。
これは、調停や審判で決まった内容の履行を裁判所が促す制度です。
履行勧告は強制力はありませんが、裁判所からの連絡という心理的プレッシャーが効果的なケースもあります。
履行勧告は費用がかからず、比較的簡単な手続きで申立てができます。
履行勧告で支払いがなければ、次のステップとして「履行命令」を申し立てることも可能です。
履行命令も強制力はありませんが、命令に従わない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
履行勧告、履行命令の申立て方法は以下の通りです。
- 家庭裁判所に「履行勧告申出書」を提出
- 裁判所から相手方に履行を促す通知が送られる
- それでも支払いがなければ「履行命令申立書」を提出
- 審問の期日が設定され、双方から事情を聴取
- 履行命令が出される(状況による)
ただし、これらの方法は間接的なものであり、確実な支払いを保証するものではありません。
強制執行を行う
履行勧告や履行命令でも支払いがない場合は、法的強制力のある「強制執行」を検討しましょう。
強制執行とは、裁判所が債務者の財産を強制的に差し押さえて債権者に支払う手続きです。
強制執行を行うには、「債務名義」と呼ばれる法的文書が必要です。
DVによる離婚慰謝料の強制執行に使える債務名義は、判決正本・調停調書・和解調書・公正証書などです。
特に公正証書は、協議離婚の場合でも作成しておけば強制執行認諾文言付きのものを作れるため便利です。
強制執行の主な種類には、以下のようなものがあります。
| 強制執行の種類 | 内容 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 預金債権差押え | 銀行口座の預金を差し押さえる | 口座情報が必要/比較的手続きが簡単 |
| 給料債権差押え | 勤務先から直接給与を差し押さえる | 安定した回収が可能/勤務先がバレる |
| 不動産差押え | 所有不動産を差し押さえる | 高額回収可能/手続きが複雑で時間がかかる |
| 動産差押え | 車や貴金属など動産を差し押さえる | 執行官が自宅訪問/費用対効果が低い場合も |
強制執行に準備すべき書類
強制執行を申し立てる際に必要な書類は以下の通りです。
これらの書類を準備して、債務者の住所地または財産所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
強制執行の手続きは複雑なため、弁護士に依頼することをおすすめします。
- 債権差押命令申立書
- 債務名義(判決正本や調停調書など)
- 送達証明書(判決や調停調書が相手に届いた証明)
- 差押対象の情報(銀行口座や勤務先など)
- 印紙代(債権額により異なる)
- 郵便切手(裁判所により金額が異なる)
強制執行は費用と時間がかかりますが、相手の資産状況が分かっている場合は効果的な方法です。
特に給料債権の差押えは、継続的な回収が期待できるため検討する価値があります。
なお、相手の資産状況が不明な場合は、「財産開示手続」を申し立てて財産情報の開示を求めることも可能です。
DVによる離婚慰謝料の未払いは、精神的にも経済的にも大きな負担となります。
そのため、離婚時には公正証書を作成するなど、支払いを確保するための対策を事前に講じておくことが大切です。
よくある質問
DVによる離婚と慰謝料に関して、多くの方が疑問に思う点について、簡潔に回答します。
- DV慰謝料の相場はどのくらいですか?
- 精神的DVでも慰謝料請求はできますか?
- DV慰謝料請求に証拠がない場合はどうすればいいですか?
- DV離婚の慰謝料と養育費は別に請求できますか?
- モラハラやDVの慰謝料請求の時効はありますか?
- 離婚せずに夫からDV慰謝料を請求する方法を教えてください。
- DVで離婚する場合の財産分与と慰謝料の違いは何ですか?
- 経済的DVも慰謝料の対象になりますか?
- 子供への暴力があった場合、離婚慰謝料はどうなりますか?
- DVの慰謝料請求で弁護士費用はいくらかかりますか?
まとめ
DVによる離婚の慰謝料相場は、一般的に50万円~300万円の範囲で、暴力の程度や頻度、結婚期間、被害者への影響などによって変わります。
慰謝料の増額ポイントとしては、DVの頻度や期間、怪我の重篤さ、精神疾患の有無などが重要です。
慰謝料請求を成功させるには、診断書や写真、相談記録などの客観的な証拠収集が欠かせません。
離婚の手続きとしては、協議離婚、調停、裁判の順に進むことが一般的ですが、DVケースでは安全確保のため弁護士を通じた交渉や保護命令の申立てを検討することも大切です。
慰謝料が支払われない場合も、履行勧告や強制執行などの法的手段によって回収を目指せます。
DVの関係から抜け出し、新しい生活を始めるためには、まず自分と子どもの安全を最優先に考え、専門家のサポートを受けながら手続きを進めることが大切です。