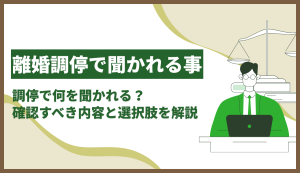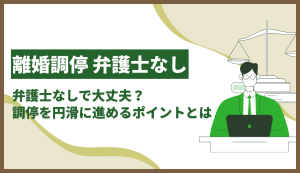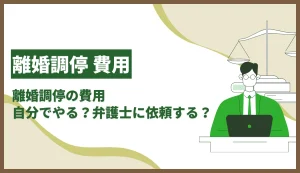「離婚したくない」場合の調停で取るべき行動と注意すべきポイント
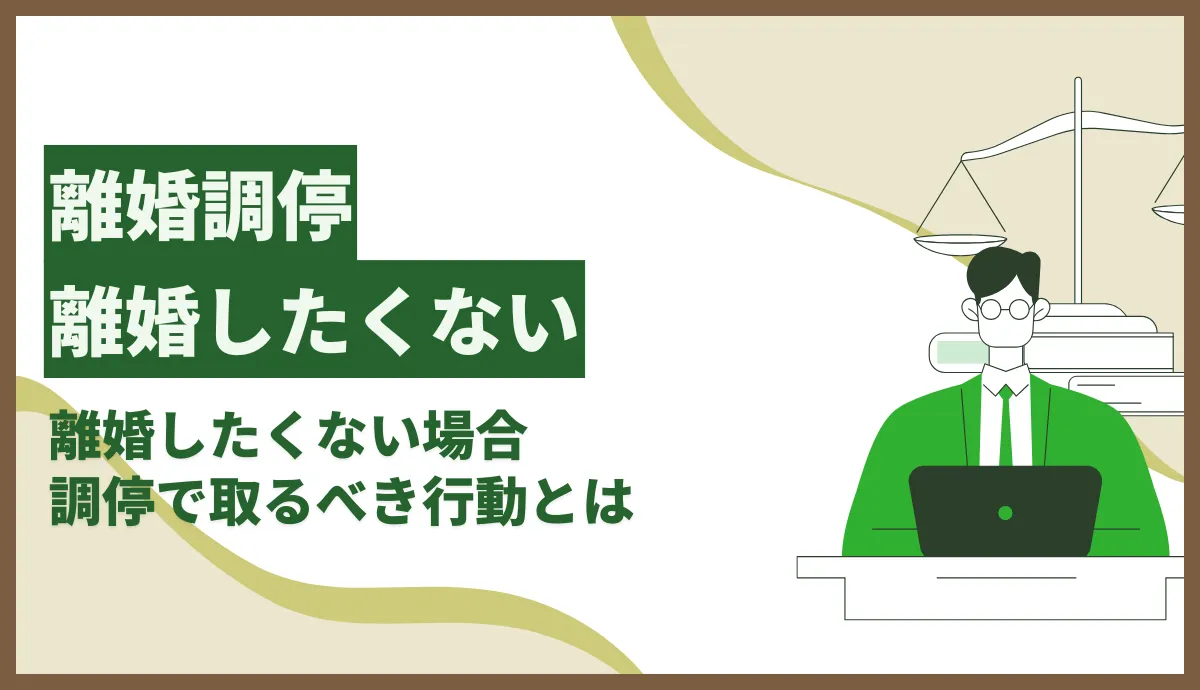
離婚調停の通知を受け取って途方に暮れていませんか?
パートナーとの関係を修復したい、どうしても離婚したくないと思うなら、あなたはまだ諦める必要はありません。
実は、離婚調停は必ずしも離婚へのカウントダウンではないのです。
離婚したくない側が適切な対応をすれば、離婚を回避できる可能性は十分にあります。
調停というプロセスを理解し、戦略的に対応することで、関係修復の糸口を見つけることができるかもしれません。
この記事では、離婚調停で離婚したくない場合の具体的な対応策や注意点について詳しく解説していきます。
不安な気持ちを抱えているあなたの力になれるよう、離婚調停での具体的な対応策を一つ一つ丁寧に解説しています。
離婚調停で離婚したくない場合は拒否の意向をはっきりと示す!
離婚調停の通知を受け取ったものの、まだパートナーとの関係を修復したいと考えていますか?大丈夫です。
離婚調停は必ずしも離婚へと進むわけではありません。
まず知っておきたいのは、日本の離婚制度では相手が離婚を望んでいても、あなたが同意しなければ協議離婚は成立しないという点です。
離婚したくない場合は、調停の場ではっきりと離婚拒否の意思表示をすることが何よりも重要になります。
調停委員に対して「夫婦関係を修復したい」「離婚に同意できない」という気持ちを率直に伝えましょう。
ただし、感情的になって相手を非難するような態度は避けるべきです。
冷静さを保ちながら、建設的な対話を心がけることが肝心です。
調停委員は中立的な立場から双方の言い分を聞き、歩み寄りの可能性を探っていきます。
離婚したくない理由が「子どものため」「経済的な不安」だけでなく、「相手への愛情」や「関係修復の可能性」についても具体的に説明できると説得力が増すでしょう。
| 離婚調停での効果的な意思表示 | 避けるべき態度 |
|---|---|
| 「関係を修復したいと強く願っています」 | 「あなたが悪いから離婚なんてありえない」 |
| 「夫婦カウンセリングを受けてみたい」 | 「子どもがかわいそうだからやめるべき」 |
| 「具体的な改善策を提案したい」 | 「離婚したら経済的に困るからダメ」 |
| 「時間をかけて話し合いたい」 | 「絶対に離婚届には判を押さない」 |
なお、離婚調停が不成立になったとしても、相手が強く離婚を望む場合は離婚裁判へと進む可能性もあります。
しかし、調停の段階できちんと自分の意思を示し、夫婦関係改善への意欲を見せることで、相手の気持ちが変わることもあるのです。
次のセクションでは、離婚したくない方が離婚調停を上手く活用するポイントについて詳しく見ていきましょう。

離婚をしたくない方が離婚調停を活用すべき2つの重要な理由
離婚調停は、離婚を希望する側が申し立てるケースが多いため、離婚したくない側にとっては「逃げ場のない状況」と感じるかもしれません。
しかし実は、離婚調停は離婚したくない側にとっても大きなメリットがあります。
離婚を回避したいと考えている方は、調停のプロセスを通じて関係修復のきっかけを見つけることも可能です。
相手が離婚を望む理由を知るから
離婚したくないと思っているのに、なぜパートナーが別れを切り出したのか疑問に思うことはありませんか?
調停の場ではお互いの言い分を述べる機会があり、相手が離婚を望む本当の理由を知ることができます。
日常生活では話し合いが難しくなっていても、調停委員という第三者が間に入ることで冷静な対話が可能になるのです。
例えば、「コミュニケーション不足」が原因と思っていたら、実は「将来のビジョンの不一致」が真の問題だったというケースもあります。
問題の本質を理解できれば、関係修復のための具体的な行動計画を立てやすくなります。
また、相手の話をしっかり聞くことで、自分自身が気づいていなかった問題点に気づく機会にもなります。
| 離婚理由として多いもの | 関係修復のためのアプローチ |
|---|---|
| 価値観の不一致 | 互いの価値観を尊重し共通点を見つける |
| コミュニケーション不足 | 定期的な対話の時間を設ける |
| 経済的な問題 | 家計管理の見直しと共有 |
| 浮気・不倫 | 関係の立て直しとカウンセリング |
| 親族との関係 | 適切な距離感の再構築 |
調停内容が後の裁判に活用できるから
離婚調停で離婚したくない意思を明確に示すことは、もし事態が裁判に発展した場合にも重要な意味を持ちます。
調停での発言や提出資料は、後の裁判の参考資料となる可能性があるからです。
調停で夫婦関係修復への真摯な姿勢を示しておくことで、裁判でも有利な立場に立てる場合があります。
例えば、離婚の法定事由に該当しないことを丁寧に主張し、証拠を提出しておけば、裁判官の心証にもプラスに働くでしょう。
また、調停の過程で相手の主張の矛盾点や不合理な要求を記録しておくことも大切です。
離婚調停での発言は「調停調書」として記録されるため、相手の言動や態度が裁判の証拠として残る場合もあります。
さらに、調停の過程で子どもの親権や養育費、財産分与などについての相手の意向を知ることができるのも大きなメリットといえるでしょう。
- 調停では相手の本音や真意を知る貴重な機会となる
- 第三者である調停委員が客観的な視点を提供してくれる
- 夫婦関係改善のための具体的な提案ができる場でもある
- 離婚回避のための時間稼ぎとしても有効な選択肢
離婚調停では、単に離婚を拒否するだけでなく、関係修復に向けた具体的な提案をすることが重要です。
次のセクションでは、離婚を避けたい場合に調停で注意すべきポイントについて詳しく解説します。
離婚を避けたい場合に調停で注意すべき5つのポイント
離婚調停において離婚を回避したいなら、ただ「離婚したくない」と主張するだけでは十分ではありません。
効果的な対応をするために、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
正当な理由がない限り、調停には必ず参加する
離婚したくないからといって調停に出席しないという選択は避けるべきです。
調停不出頭が続くと、調停不成立となり、次のステップである離婚裁判へと進んでしまう可能性が高まります。
調停は自分の意見を述べられる貴重な機会なので、健康上の理由など正当な理由がない限り必ず参加しましょう。
もし日程の都合がつかない場合は、事前に裁判所に連絡して期日変更の申請をすることが可能です。
調停に欠席するとあなたの意見が反映されず、結果的に相手側に有利な展開になりかねません。
また、調停委員に対して「誠実に話し合う姿勢がない」という悪い印象を与えてしまうことにもなります。
- 調停の日程変更が必要な場合は早めに申し出る
- やむを得ず欠席する場合は正当な理由を示す証明書を用意する
- 代理人による出席も検討する(弁護士への委任が必要)

質問への回答対策を事前に準備する
調停では、調停委員から様々な質問を受けることになります。
事前に予想される質問とその回答を用意しておくことで、冷静かつ的確に対応できるようになります。
感情に流されず論理的に答えられるよう、重要なポイントをメモにまとめておくのが効果的です。
特に「なぜ離婚したくないのか」「夫婦関係を修復するために何ができるか」といった質問には具体的な回答を準備しましょう。
また、相手側の主張に対する反論も整理しておくと良いでしょう。
離婚したくない理由が「子どものため」だけだと説得力に欠けるので、自分自身の気持ちや関係修復への展望も含めて説明できるようにしておきましょう。
| よくある質問 | 効果的な回答例 |
|---|---|
| なぜ離婚したくないのですか? | 「パートナーへの愛情があり、問題点を改善して関係を修復したいと考えています」 |
| 今後どのように関係改善する予定ですか? | 「定期的な対話の時間を設け、カウンセリングも検討しています」 |
| 相手の不満にどう対処しますか? | 「指摘された問題点を真摯に受け止め、具体的な改善策を提案したいです」 |
| 子どもへの影響はどう考えていますか? | 「両親が揃った環境が子どもの健全な成長に重要だと考えています」 |
調停委員との良好な関係を構築する
調停委員は、双方の言い分を聞いて歩み寄りを促す重要な役割を担っています。
調停委員との良好な関係を築くことで、あなたの立場や考えをより適切に理解してもらえる可能性が高まります。
礼儀正しく誠実な態度で臨み、調停委員の質問や助言に対して真摯に応答することが大切です。
怒りや不満をぶつけるのではなく、冷静に自分の考えを伝える姿勢を心がけましょう。
調停委員は中立的な立場にあるため、一方に肩入れすることはありませんが、誠実で建設的な姿勢を見せる側に好印象を持つ傾向があります。
また、調停委員からの提案には可能な限り柔軟に対応し、話し合いの意欲を示すことも重要です。
- 調停委員に対して敬意を持って接する
- 感情的にならず、落ち着いた態度で臨む
- 話を遮らず、最後まで聞く姿勢を見せる
- 調停委員の提案に対して前向きに検討する姿勢を示す
配偶者を責める発言を避ける
離婚を回避したい場合、相手を責めたり非難したりする発言は逆効果になります。
そうした否定的な態度は、相手の離婚への決意をさらに固めてしまう可能性があるのです。
「あなたが悪い」という責め立てるのではなく、「お互いの問題点を改善していきたい」という建設的な姿勢を示しましょう。
自分の非を認め、改善する意思を伝えることで、相手も心を開きやすくなります。
過去の出来事よりも、これからどう関係を修復していくかという未来志向の発言を心がけましょう。
また、相手の気持ちや立場を理解しようとする姿勢も大切です。
| 避けるべき発言 | 代わりに使うべき表現 |
|---|---|
| 「あなたのせいで家庭が壊れる」 | 「お互いに努力して家庭を守っていきたい」 |
| 「あなたは約束を守らない人だ」 | 「今後はお互いの約束を大切にしていきたい」 |
| 「子どもを不幸にするつもりか」 | 「子どもの幸せのために一緒に考えていきたい」 |
| 「親や友人も離婚に反対している」 | 「二人の問題として一緒に解決していきたい」 |

法定離婚事由に対する反論を用意する
日本の民法では、離婚裁判に至った場合、法定の離婚事由がなければ離婚は認められません。
相手が主張する離婚事由に対して、適切な反論を準備しておくことが重要です。
離婚事由としてよく挙げられる「性格の不一致」や「婚姻を継続し難い重大な事由」に対しては、具体的な反証を用意しましょう。
例えば、夫婦で楽しく過ごした写真や思い出の品、二人で立てた将来の計画など、関係が良好だった証拠を集めておくと良いでしょう。
また、相手の主張が事実と異なる場合は、それを証明できる客観的な証拠を揃えておくことも大切です。
離婚調停が不成立になった場合、次は裁判に移行する可能性があるため、法的な観点からも準備をしておくと安心です。
- 民法770条に定められた離婚事由について理解しておく
- 夫婦関係が破綻していないことを示す証拠を集める
- 相手の主張に対する具体的な反論点をまとめておく
- 必要に応じて弁護士に相談し、法的なアドバイスを得る
以上のポイントを押さえつつ、次のセクションでは離婚調停中に離婚したくない側が具体的にとるべき行動について解説します。

離婚調停中に離婚したくない側がとるべき行動
離婚調停が始まってしまっても、離婚を回避するためにとれる具体的な行動があります。
離婚したくない側が取り組むべき重要な対策を見ていきましょう。
事前に役所へ「離婚届不受理申出書」を提出しておく
離婚届は夫婦の双方が署名すれば受理されますが、あなたの知らないうちに勝手に提出されるリスクもあります。
「離婚届不受理申出書」を提出しておくと、あなたの知らないところで離婚が成立してしまうことを防げます。
この申出書は住民票のある市区町村役場で入手でき、提出すると6ヶ月間有効です。
期限が切れる前に再申請することで、さらに6ヶ月延長することも可能です。
申出書を提出しておくことで、調停や話し合いの間、不当な離婚手続きから身を守ることができます。
また、相手に不正な離婚届提出の意図がないとしても、予防策として有効です。
- 本人確認書類を持参して市区町村役場の窓口で申請する
- 申出の理由には「離婚協議中であり合意に至っていない」など記載する
- 6ヶ月ごとの更新を忘れないようカレンダーに記録しておく
離婚したくない側が家庭裁判所に円満調停を申し立てる
相手から離婚調停を申し立てられた場合、あなたも「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てることができます。
これは離婚ではなく、夫婦関係の修復を目的とした調停です。
円満調停の申立てにより、関係修復への積極的な姿勢を示すことができます。
両方の調停が並行して進むことになりますが、裁判所は通常、これらを一緒に取り扱います。
離婚調停が「相手の非を指摘する場」になりがちなのに対し、円満調停では建設的な解決策を模索する雰囲気が作りやすくなります。
申立ての際には、具体的な夫婦関係修復のプランやあなたが変われる点について明確に記載すると効果的です。
| 離婚調停と円満調停の違い | 申立て費用 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 離婚調停 | 1,200円 | 離婚条件の取り決め |
| 円満調停 | 1,200円 | 夫婦関係の修復 |
夫婦関係修復のためにカウンセリングを受ける
離婚の危機に直面している夫婦は、専門家によるカウンセリングを受けることで関係を立て直せる可能性があります。
実際に離婚調停の場で「カウンセリングの提案」をすることは、関係修復への真剣な姿勢を示すことにもなります。
カウンセリングは夫婦間の根本的な問題を専門家の視点から解決するための有効な手段です。
まずは一人でカウンセリングを受け、自分自身の課題に向き合うことから始めるのも良いでしょう。
その姿勢を見て、相手も一緒にカウンセリングを受ける気持ちになるかもしれません。
カウンセリングには「夫婦カウンセリング」「家族療法」「メディエーション」など様々な種類があるので、状況に合わせて選びましょう。
- 地域の家庭支援センターでは無料・低額で相談できる場合もある
- オンラインカウンセリングサービスも増えているので活用を検討する
- カウンセリングの効果を高めるために自分の気持ちを整理しておく
- 複数回のセッションを継続して受けることが重要

別居中の場合は可能な限り早期に同居を再開させる
別居状態が長く続くと、夫婦の心理的距離がさらに広がってしまう傾向があります。
可能であれば、同居の再開を目指すことが関係修復の第一歩となります。
別居期間が長期化すると裁判所が「婚姻関係の破綻」と判断する可能性が高まります。
同居再開を申し出る際は、一方的に押し付けるのではなく、相手の意見や感情に配慮した提案をすることが大切です。
いきなり完全同居は難しい場合は、週末だけ一緒に過ごすなど段階的なアプローチも検討してみましょう。
別居を余儀なくされている理由を理解し、その問題点を解決する具体的な提案をすることも効果的です。
たとえ相手が同居を望まない場合でも、定期的な面会や連絡を続けることで関係改善のチャンスを維持できます。
| 同居再開のステップ | ポイント |
|---|---|
| 1. 面会の再開 | 中立的な場所で短時間から始める |
| 2. 定期的な交流 | 食事や趣味の時間を共有する |
| 3. 部分的な同居 | 週末だけ一緒に過ごすなど |
| 4. 完全同居の再開 | お互いの変化を認め合う |
次のセクションでは、離婚したくない側が弁護士に依頼するメリットについて解説します。
離婚したくない側が弁護士に依頼するメリット
離婚したくない場合、自分一人で調停に臨むのは精神的にも負担が大きく、法的な知識も必要となります。
ここでは離婚したくない側が弁護士に依頼するメリットについて解説します。
離婚成立を防ぐ確率が上がる
離婚問題を専門とする弁護士は、離婚を防ぐための法的戦略を熟知しています。
特に法律の専門知識がない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。
弁護士は法定離婚事由に対する効果的な反論方法や、相手側の主張の矛盾点を指摘する技術を持っています。
例えば「性格の不一致」という曖昧な理由での離婚を認めさせないための具体的な対策を提案してくれます。
また、弁護士は多くの離婚事例を見ているため、どのようなケースで離婚が認められにくいかを経験的に知っています。
その経験に基づいたアドバイスは、離婚回避の可能性を高める重要な要素となるでしょう。
- 離婚事由への法的な反論ポイントを整理してくれる
- 調停や裁判での効果的な主張方法をアドバイスしてくれる
- 有利な証拠の収集方法を指南してくれる
- 法的な専門用語を分かりやすく説明してくれる
本人が仕事を休まずに調停を進めることができる
離婚調停は平日の日中に行われることが多く、仕事を持っている方にとっては大きな負担となります。
弁護士に依頼すれば、代理人として調停に出席してもらうことが可能です。
仕事の都合で調停に参加できない場合でも、弁護士があなたの意向を正確に代弁してくれます。
調停の内容や進行状況については、弁護士から詳細な報告を受けることができるので安心です。
特に重要な調停日には本人が出席し、それ以外は弁護士に任せるという柔軟な対応も可能です。
これにより、仕事と調停の両立がしやすくなり、経済的な基盤を維持しながら離婚問題に対応できます。
| 弁護士の代理出席が可能な場面 | 本人の出席が望ましい場面 |
|---|---|
| 通常の調停期日 | 初回の調停期日 |
| 事務的な協議 | 調停委員との信頼関係構築が必要な場面 |
| 相手の主張を聞く場面 | 和解案の最終確認 |
| 書類の提出や受け取り | 重要な証言が必要な場面 |
調停同席による精神的な安心感を得られる
離婚調停は感情的に大きな負担がかかる場面です。
特に離婚したくない側にとっては、精神的なプレッシャーも大きいでしょう。
弁護士が同席することで、一人で対応する不安や緊張が軽減されます。
専門家がそばにいることで冷静さを保ちやすくなり、感情的な発言を抑えて建設的な話し合いができます。
相手側の弁護士が同席している場合は特に、法的知識のバランスを保つためにも自分側の弁護士がいることは重要です。
調停委員にも「専門家のサポートを受けている」という印象を与えることができ、より真剣に対応してもらえる可能性が高まります。
また、弁護士は法的な観点だけでなく、離婚問題の経験が豊富なため、心理的なサポートも期待できるでしょう。
- 不安や疑問点をその場で弁護士に相談できる
- 相手からの圧力や脅しから守ってもらえる
- 適切なタイミングでの発言をアドバイスしてもらえる
- 調停後の振り返りや次回への対策を一緒に考えられる
弁護士費用は確かに負担になりますが、離婚回避という目的を考えれば、価値ある投資といえるでしょう。
次のセクションでは、離婚したくない場合に避けるべき行動について解説します。
離婚したくない場合の避けるべき行動
離婚を回避したいと思うあまり、かえって状況を悪化させてしまう行動があります。
ここでは、離婚したくない場合に絶対に避けるべき行動を具体的に解説します。
配偶者以外の異性と関係を持たないようにする
離婚を避けたいなら、配偶者以外の異性との親密な関係は絶対に避けるべきです。
たとえ精神的な支えを求めているだけでも、誤解を招く行動は慎みましょう。
不貞行為は離婚の法定事由に該当するため、裁判でも不利に働く決定的な要素となります。
SNSでの異性とのやり取りも、スクリーンショットなどで証拠として残る可能性があるので注意が必要です。
「ただの友人」であっても、第三者から見て誤解されるような行動は避けるべきでしょう。
もし以前に不貞行為があった場合でも、誠実に反省し、信頼回復のための具体的な行動を示すことが大切です。
- SNSなどでの異性との私的なやり取りも控える
- 仕事上の付き合いでも必要以上に親密にならない
- 配偶者に疑念を抱かせるような言動や行動を避ける
- 過去の不信行為については誠実に謝罪し、繰り返さない姿勢を示す
離婚を阻止する目的での暴力や暴言もしてはいけない
離婚を回避したいという思いから、感情的になって暴力や暴言に頼ってしまうケースがあります。
しかし、こうした行為は離婚回避どころか、相手の離婚への決意を固める結果になるでしょう。
DVや暴言は離婚の法定事由となるだけでなく、刑事罰の対象にもなり得る深刻な問題です。
また「離婚届に判を押さなければ離婚はできない」と思い込み、脅迫めいた言動をとることも絶対に避けるべきです。
感情的になりそうな場合は、一旦その場を離れ、冷静になってから対話することを心がけましょう。
怒りのコントロールが難しい場合は、カウンセリングを受けるなど専門的なサポートを検討することも重要です。
| 避けるべき行動 | 代わりに取るべき行動 |
|---|---|
| 身体的な暴力 | 冷静な対話や話し合い |
| 脅迫や恐怖を与える言動 | 相手の意見に耳を傾ける姿勢 |
| 子どもを利用した駆け引き | 子どもの福祉を最優先に考える |
| 相手の友人・家族への誹謗中傷 | 互いの人間関係を尊重する |
| 相手のプライバシー侵害 | 適切な距離を保つ |
離婚したくない場合でも、相手の人格や尊厳を尊重することが最も重要です。
暴力や暴言は関係修復の可能性を完全に断ち切ってしまう行為なので、どんな状況でも慎むべきでしょう。
ストレスや感情をコントロールするための健全な対処法を身につけることが、離婚回避への第一歩となります。
続いて、離婚調停に関するよくある質問とその回答を見ていきましょう。
よくある質問
離婚調停で離婚したくない場合について、多くの方が抱える疑問にお答えします。
実際の調停でどのように対応すべきか、参考にしてください。
- 離婚調停で離婚したくない場合、成功する確率はどのくらいですか?
- 離婚したくない側が取るべき最終手段について教えてください。
- 離婚調停で効果的な陳述書の書き方を教えてください。
- 離婚したくないのに相手が離婚を申し立てた場合の対処法は?
- 離婚を拒否し続けることのデメリットはありますか?
- 離婚調停で離婚したくない理由を効果的に伝える方法はありますか?
- 離婚調停不成立後に復縁を目指す方法はありますか?
- 弁護士に依頼すると離婚調停でより有利になりますか?
- 離婚したくない場合でも、自分に非がある場合はどうすればよいですか?
まとめ
離婚調停で離婚したくない場合、単に拒否するだけでなく、戦略的な対応が必要です。
調停の場では冷静さを保ちながらも、はっきりと離婚拒否の意思表示をすること、そして相手の離婚理由を理解し、具体的な関係修復プランを提示することが重要です。
また「離婚届不受理申出書」の提出や「円満調停」の申立てなど、法的手段も効果的に活用しましょう。
カウンセリングの受講や弁護士への依頼も、離婚回避に向けた有効な選択肢となります。
ただし、感情的な対応や暴言・暴力、不貞行為など相手の離婚意思を固めてしまう行動は絶対に避けるべきです。
離婚したくないという気持ちは尊重されるべきですが、同時に相手の気持ちも尊重する姿勢を持ち、建設的な対話を心がけることが、関係修復への第一歩となります。