別居中の生活費どうする?婚姻費用の請求方法と相場を解説!
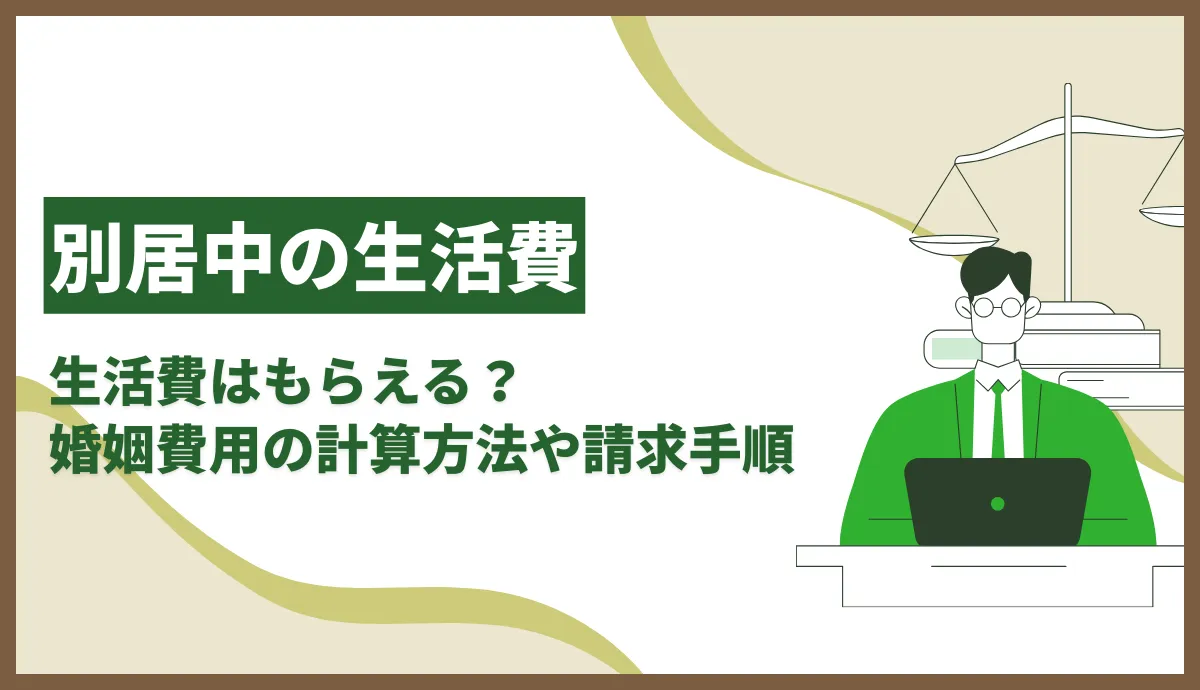
夫婦間で別居することになった場合、生活費についての問題は避けて通れません。
特に収入が少ない側や子どもと同居している側にとって、別居中の生活費はとても切実な問題です。
あなたは「別居したら相手に生活費を請求できるの?」「別居中にもらえる生活費の相場はいくら?」と不安を感じていませんか?
法律上、別居中でも配偶者に対して「婚姻費用」として生活費を請求することが可能です。
この記事では、別居中に請求できる生活費(婚姻費用)について詳しく解説していきます。
別居中の生活費についてお悩みの方に、具体的な金額や請求方法をわかりやすく解説します。
この記事を参考に、あなたの権利を正しく理解して適切な生活費を確保しましょう。
別居中でも配偶者に婚姻費用を請求できる
夫婦が別居するとき、多くの方が「生活費はどうなるの?」と不安を感じます。
実は法律上、別居中であっても配偶者に対して「婚姻費用」として生活費を請求する権利があります。
婚姻費用とは、夫婦が共同生活を送るために必要な費用のことで、食費や住居費、光熱費などの基本的な生活費を含みます。
民法第760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。
この規定は夫婦が別居している場合でも適用されるため、収入が少ない方や子どもと同居している方は、もう一方の配偶者に対して生活費を請求できるのです。

別居期間中に請求可能な婚姻費用の内訳
別居中に請求できる婚姻費用には、どのような項目が含まれるのでしょうか。
婚姻費用には基本的な生活費だけでなく、生活水準を維持するために必要な様々な費用が含まれます。
まず基本となるのは、食費・住居費・光熱費といった日常生活に欠かせない費用です。
さらに、医療費や保険料などの健康維持に関わる費用も婚姻費用に含まれます。
子どもがいる場合は、教育費や習い事の費用なども請求の対象になるでしょう。
また、それまでの生活水準に応じた娯楽費や交際費なども、場合によっては認められることがあります。
| 項目 | 内容 | 請求可否 |
|---|---|---|
| 基本生活費 | 食費、住居費、光熱費など | ◯ |
| 医療関連費用 | 医療費、保険料など | ◯ |
| 子どもの費用 | 教育費、習い事、衣服費など | ◯ |
| 娯楽・交際費 | 外食、旅行、交際費など | △(生活水準による) |
| 贅沢品の費用 | 高級品、ブランド品など | ×(原則対象外) |
ただし、贅沢品や趣味に関する高額な費用は、一般的に婚姻費用として認められないことが多いです。
婚姻費用を請求可能な期間
婚姻費用はいつからいつまで請求できるのか、その期間についても押さえておきましょう。
基本的に婚姻費用は別居開始時から離婚が成立するまでの間、請求することができます。
別居を始めた日から請求する権利が発生しますが、実際に請求があった日以降の分しか認められないのが一般的です。
ただし、請求を行う前の分についても、特別な事情がある場合には遡って認められることもあります。
例えば、別居直後から話し合いを続けていたが合意に至らなかった場合などです。
婚姻費用の請求権は離婚が成立した時点で終了し、その後は「離婚後の子の養育費」という別の制度に移行します。
また、別居中でも復縁すれば婚姻費用の請求権はなくなりますし、再度別居すれば再び請求権が発生します。
| 期間 | 婚姻費用請求の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 別居開始前 | × | 同居中は共同生活費として負担 |
| 別居開始〜請求前 | △ | 原則請求できないが特別な事情があれば可能 |
| 請求日〜離婚成立 | ◯ | 請求すれば期間中ずっと受け取れる |
| 離婚成立後 | × | 養育費制度に移行 |
過去の分の婚姻費用を請求する場合、別居開始日や交渉の経緯を証明する証拠が重要になります。
婚姻費用の額は原則として夫婦の協議で決定する
別居中の生活費(婚姻費用)の金額は、どのように決まるのでしょうか。
婚姻費用の金額は、まず当事者同士の話し合い(協議)によって決めるのが原則です。
夫婦がお互いの収入や生活状況を考慮しながら、適切な金額を決めることが望ましいとされています。
しかし、別居に至る夫婦の場合、冷静な話し合いが難しいことも少なくありません。
そのような場合は、「婚姻費用算定表」と呼ばれる裁判所の基準を参考に金額を決めることが多いです。
この算定表では、夫婦それぞれの収入や子どもの有無、子どもの年齢などを考慮して、標準的な婚姻費用の目安が示されています。
もし協議で合意できない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることになります。
裁判所では、以下のような要素を考慮して婚姻費用の金額を決定します。
- 双方の収入と資産状況
- 別居に至った経緯と責任
- 子どもの有無と年齢
- それまでの生活水準
- 特別な出費(医療費や教育費など)の有無
- その他の個別事情
一般的に、収入が多い側が少ない側に対して婚姻費用を支払うことになりますが、別居の原因が一方にある場合は、金額が調整されることもあります。
婚姻費用の合意は口頭だけでなく、書面で残しておくことが重要です。

別居期間中に受け取れる婚姻費用の一般的な金額
「別居したら実際にいくらもらえるの?」と気になる方も多いでしょう。
別居中に請求できる婚姻費用の相場は、夫婦の収入差や子どもの有無・年齢によって大きく変わります。
裁判所では「婚姻費用算定表」という基準表を参考に金額を決めるのが一般的です。
この算定表は定期的に見直されるため、最新の情報を確認することをおすすめします。
ここでは、一般的な状況別の婚姻費用相場を紹介しましょう。
子どもがいない夫婦の場合
子どものいない夫婦の婚姻費用はどのように計算されるのでしょうか。
子どもがいない場合の婚姻費用は、主に夫婦の収入差に基づいて計算されます。
例えば、夫の手取り収入が月30万円、妻の収入が月10万円の場合、婚姻費用は月5〜8万円程度になるケースが多いです。
もし妻が専業主婦で収入がない場合、月8〜12万円程度が一般的な相場となります。
逆に、妻の収入が夫より多い場合は、妻から夫へ婚姻費用が支払われることもあります。
収入が同程度の場合は、婚姻費用がほとんど発生しないか、少額になることが多いでしょう。
| 収入が多い配偶者 | 収入が少ない配偶者 | 婚姻費用の目安 |
|---|---|---|
| 30万円/月 | 0円/月(専業主婦/主夫) | 8〜12万円/月 |
| 30万円/月 | 10万円/月 | 5〜8万円/月 |
| 30万円/月 | 20万円/月 | 2〜5万円/月 |
| 50万円/月 | 0円/月(専業主婦/主夫) | 12〜18万円/月 |
ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は個別の事情により変動します。
子どもが1人いる夫婦の場合
子どもが1人いる場合の婚姻費用はどのように変わるのでしょうか。
子どもが1人いる場合は、子どもの年齢や同居している親の状況によって婚姻費用が増額されます。
一般的に、子どもが同居している親の側に、子どもの養育費分が加算される形になります。
例えば、妻が子ども(小学生)と同居し、夫の収入が月30万円、妻の収入が月10万円の場合、婚姻費用は月10〜15万円程度になることが多いです。
子どもの年齢によっても金額は変わり、年齢が上がるほど教育費などが増えるため、婚姻費用も高くなる傾向があります。
特に中学生・高校生になると学費や塾代などの教育費がかさむため、増額されるケースが多いでしょう。
| 子どもの年齢 | 夫の収入 | 妻の収入 | 婚姻費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 0〜5歳 | 30万円/月 | 10万円/月 | 9〜13万円/月 |
| 小学生 | 30万円/月 | 10万円/月 | 10〜15万円/月 |
| 中学生 | 30万円/月 | 10万円/月 | 12〜17万円/月 |
| 高校生 | 30万円/月 | 10万円/月 | 13〜18万円/月 |
子どもの医療費や習い事など特別な費用がかかる場合は、別途請求できることもあります。
子どもが2人いる夫婦の場合
子どもが2人以上いる場合は、さらに婚姻費用はどう変わるのでしょうか。
子どもが2人いる場合は、1人目よりも2人目の加算額が若干少なくなる傾向がありますが、全体としては大幅に増額されます。
例えば、妻が2人の子ども(小学生と幼児)と同居し、夫の収入が月30万円、妻の収入が月10万円の場合、婚姻費用は月15〜20万円程度になるケースが多いです。
子どもの年齢の組み合わせによっても金額は変動します。
高校生と中学生のように教育費がかさむ年齢の子どもが2人いる場合は、さらに高額になる傾向があります。
また、住居費も考慮され、子どもが2人以上いる場合は広い住居が必要になるため、その分の費用も加味されます。
| 子どもの年齢 | 夫の収入 | 妻の収入 | 婚姻費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 幼児2人 | 30万円/月 | 10万円/月 | 13〜18万円/月 |
| 小学生と幼児 | 30万円/月 | 10万円/月 | 15〜20万円/月 |
| 中学生と小学生 | 30万円/月 | 10万円/月 | 17〜22万円/月 |
| 高校生と中学生 | 30万円/月 | 10万円/月 | 20〜25万円/月 |
子どもが3人以上いる場合も、基本的な考え方は同じですが、スケールメリットにより1人あたりの加算額は徐々に減少する傾向にあります。
婚姻費用の金額は、あくまで一般的な目安であり、実際の金額は家庭裁判所の判断や当事者の合意によって決まります。
婚姻費用を別居中に請求する際の流れ
別居中の生活費について知ったところで、実際にどのように請求すればよいのでしょうか。
婚姻費用を請求するには、いくつかの段階があります。
まずは話し合いから始め、それでうまくいかない場合は法的手続きへと進むのが一般的です。
ここでは、婚姻費用を請求する際の具体的な流れを見ていきましょう。
直接交渉して婚姻費用を請求する
婚姻費用の請求は、まず当事者同士の話し合いから始めるのが基本です。
別居中の生活費について、できるだけ冷静に話し合い、お互いが納得できる金額を決めることが望ましいでしょう。
話し合いの際は、自分の収入や支出を明確にし、相手にも同様の情報を提示してもらうとスムーズです。
また、婚姻費用算定表を参考に、一般的な相場を伝えることも効果的かもしれません。
直接会って話し合うのが難しい場合は、手紙やメールで交渉することも可能です。
その際は、感情的な表現を避け、事実と必要な金額を淡々と伝えるよう心がけましょう。
話し合いで合意ができたら、合意内容を書面にしておくことが重要です。
後々のトラブル防止のため、日付や金額、支払方法などを明記し、双方で署名しておきましょう。
婚姻費用の請求を弁護士に代理してもらう
感情的になりがちな別居中の配偶者との交渉は、うまくいかないことも少なくありません。
直接交渉が難しい場合は、弁護士に依頼して代理交渉してもらうのも一つの選択肢です。
弁護士に依頼することで、法的な専門知識に基づいた適切な金額を提示してもらえます。
また、感情的なしこりを残さず、冷静に交渉を進められるというメリットもあります。
弁護士への依頼は、初回相談無料のところも多いので、まずは相談してみるとよいでしょう。
弁護士費用は一般的に着手金と成功報酬の組み合わせで、20〜30万円程度かかることが多いです。
弁護士に依頼する際は、事前に費用体系をしっかり確認しておくことが大切です。

相手が支払わない場合は婚姻費用分担請求調停を申し立てる
話し合いでも弁護士を通じた交渉でも合意に至らない場合はどうすればよいでしょうか。
相手が婚姻費用の支払いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。
調停では、調停委員が間に入って双方の言い分を聞きながら、適切な解決策を探っていきます。
申立ては相手の住所地を管轄する家庭裁判所に行い、申立手数料は収入印紙代1,200円程度です。
調停の申立てに必要な書類は主に以下の通りです。
- 調停申立書(裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
- 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
- 収入を証明する書類(給与明細や源泉徴収票など)
- 支出を証明する書類(家賃の領収書や各種請求書など)
- その他の資料(必要に応じて)
調停は通常1〜3か月程度かかり、その間に3〜5回程度の期日が設けられます。
調停が成立すれば、その内容に法的拘束力が生じ、合意した金額が支払われることになります。
調停では必ずしも自分の希望通りの金額になるとは限らないため、柔軟な姿勢で臨むことが大切です。
調停が成立しない場合は審判へ移行する
調停で合意に至らなかった場合は、次のステップに進むことになります。
調停が不成立となった場合、自動的に審判手続きへと移行し、裁判官が婚姻費用の金額を決定します。
審判では、裁判所が双方から提出された資料や調停での発言内容などを踏まえ、総合的に判断します。
基本的には婚姻費用算定表を参考にしながら、個別の事情を考慮して金額が決められます。
審判までの期間は約1〜2か月程度ですが、事案によってはさらに時間がかかることもあります。
審判の結果、婚姻費用の支払いが命じられた場合、相手はその命令に従わなければなりません。
もし相手が審判で決まった婚姻費用を支払わない場合は、強制執行の手続きをとることができます。
審判は裁判官の判断によるため、必ずしも自分の希望通りの結果になるとは限りません。
審判結果に納得できなければ即時抗告を申し立てる
審判の結果に不服がある場合は、さらなる手続きをとることができます。
審判の結果に納得できない場合は、審判書の送達を受けた日から2週間以内に「即時抗告」を申し立てることができます。
即時抗告は、審判を行った家庭裁判所を通じて高等裁判所に申し立てます。
申立ての際には、審判のどの部分にどのような不服があるのかを明確に記載する必要があります。
即時抗告の手数料は1,000円程度ですが、弁護士に依頼する場合は別途費用がかかります。
高等裁判所での審理は基本的に書面審理で、新たな事実や証拠の提出は制限されることがあります。
即時抗告の審理期間は約2〜3か月程度ですが、事案によって異なります。
高等裁判所の決定に対してさらに不服がある場合は、特別抗告や許可抗告という手段もありますが、認められるケースは限られています。
即時抗告は時間と費用がかかるため、審判内容と抗告の見込みをよく検討してから決断することをお勧めします。
別居中に婚姻費用を請求する際に押さえるべきポイント
婚姻費用の請求手続きについて理解したところで、実際に請求する際に気をつけるべきポイントを見ていきましょう。
適切な準備と対応をすることで、スムーズに婚姻費用を受け取れる可能性が高まります。
ここでは、別居中の生活費を請求する際に押さえておくべき重要な点を解説します。
別居中に生活費を請求した証拠を適切に保管する
別居中に生活費を請求する際、その経緯や合意内容を記録に残すことが非常に重要です。
別居中の婚姻費用請求に関するやり取りは、必ず証拠として残しておきましょう。
話し合いの日時や内容をメモしておくだけでなく、可能な限り書面やメールなどの形で記録を残すことが大切です。
特に、相手に送った請求書や受け取った返答、振込記録などは必ず保管しておきましょう。
これらの証拠は、後に調停や審判になった場合に自分の主張を裏付ける重要な資料となります。
もし電話やLINEでやり取りする場合も、後から「そんな話はしていない」と言われないよう、重要な点は必ず文書で確認するクセをつけましょう。
- 請求書や合意書の写し
- メールやLINEなどのメッセージ
- 振込記録や領収書
- 話し合いの議事録や録音(相手の同意がある場合)
- 生活費に関する相手とのやり取りの履歴
証拠は最低でも5年間は保管しておくことをお勧めします。
別居期間の生活費に関する取り決めを公正証書で確定させる
当事者間で婚姻費用について合意できた場合、その内容を法的に確実なものにしておくことが大切です。
別居中の生活費に関する合意内容は、公正証書にして法的効力を持たせることで安心です。
公正証書とは、公証人が作成する公文書で、強制執行認諾文言を入れることで、相手が支払いを怠った場合に財産の差し押さえなどの強制執行が可能になります。
公正証書の作成費用は内容によって異なりますが、一般的に1〜3万円程度です。
公正証書に記載すべき主な内容は以下の通りです。
- 支払う婚姻費用の金額
- 支払日(毎月○日など)
- 支払方法(振込先口座など)
- 支払期間
- 特別な出費が生じた場合の負担方法
- 将来の見直し条件
- 強制執行認諾文言
公正証書の作成には双方の合意が必要ですが、相手が同意しない場合は調停や審判の手続きを検討することになります。
公正証書があれば、相手が支払いを怠った際の手続きが格段に簡単になります。
別居中の生活費が支払われない場合は強制執行を申し立てる
合意や審判で決まった婚姻費用が支払われない場合、法的な強制力で回収する方法があります。
婚姻費用の不払いが続く場合は、強制執行の手続きをとることで支払いを強制できます。
強制執行の方法には、主に以下の三つがあります。
- 給与などの債権差押え:相手の給与や預金を差し押さえる
- 動産差押え:相手の自動車やブランド品などの財産を差し押さえる
- 不動産差押え:相手の土地や建物を差し押さえる
強制執行を申し立てるには、「債務名義」と呼ばれる法的な根拠が必要です。
債務名義となるのは、強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書、審判書などです。
強制執行の申立ては、相手の住所地や財産所在地を管轄する地方裁判所に行います。
手続きは複雑なため、弁護士に依頼することをお勧めします。
強制執行は相手との関係を決定的に悪化させる可能性があるため、最終手段として検討しましょう。
自分の不貞行為で別居した場合は生活費の請求ができない
別居の原因によっては、婚姻費用の請求が制限されることがあります。
自分の不貞行為や暴力など「有責配偶者」と認められる場合、婚姻費用の請求が認められないこともあります。
「有責配偶者」とは、婚姻関係が破綻した主な原因を作った配偶者のことです。
例えば、浮気や不倫、DV(家庭内暴力)、生活費を渡さないなどの行為が該当します。
有責配偶者からの婚姻費用請求は、「クリーンハンドの原則」により制限されることがあります。
ただし、子どもが同居している場合は、子どもの福祉のために必要最低限の婚姻費用が認められる傾向にあります。
また、別居の原因が自分にあっても、相手も同様に有責性がある場合(双方に非がある場合)は、婚姻費用の請求が認められることが多いです。
| 別居の原因 | 婚姻費用請求の可否 |
|---|---|
| 自分の不貞行為(一方的な有責) | 原則として請求困難 |
| 相手の不貞行為 | 請求可能 |
| 双方に非がある場合 | 請求可能(金額が調整されることも) |
| 性格の不一致など責任の所在が明確でない | 請求可能 |
婚姻費用請求の際には、別居の経緯や原因を客観的に説明できるように準備しておくことが重要です。
別居に必要な費用を確保できないときの対処法
別居を考えていても、経済的な不安から踏み出せない方は少なくありません。
特に収入が少ない方や専業主婦(主夫)の場合、別居後の生活費をどう確保するかは大きな問題です。
ここでは、別居に必要な費用を十分に確保できない場合の対処法をいくつか紹介します。

婚姻費用分担の仮処分を申請する
婚姻費用の支払いが始まるまでに時間がかかる場合の緊急措置があります。
別居直後の生活費を早急に確保するには、「婚姻費用分担の仮処分」という制度を利用できます。
通常の婚姻費用分担請求調停や審判は手続きに時間がかかりますが、仮処分なら比較的短期間で決定が出ます。
仮処分の申立ては、家庭裁判所ではなく地方裁判所に行います。
申立ての際には、「生活に困窮している」という緊急性を証明する必要があります。
家賃の滞納通知や光熱費の未払い警告など、経済的に困っていることを示す資料を用意しましょう。
仮処分決定までの期間は約1〜2週間程度と短く、一時的な生活費を確保するのに有効です。
仮処分はあくまで暫定的な措置なので、並行して正式な婚姻費用分担請求調停も申し立てることをお勧めします。
実家で別居生活を送る
経済的に自立が難しい場合、家族の協力を得るという選択肢もあります。
経済的な余裕がない場合、一時的に実家に身を寄せて別居生活を始めるのも現実的な対処法です。
実家暮らしなら家賃や光熱費などの基本的な生活費を大幅に抑えられます。
特に子どもがいる場合は、親に育児の協力を得られるというメリットもあるでしょう。
実家に頼る際は、あらかじめ滞在期間や生活費の負担方法などについて話し合っておくことが大切です。
また、実家が遠方にある場合は、子どもの転校や自分の仕事の継続などについても検討が必要です。
実家暮らしをしながら、婚姻費用の請求手続きを進め、経済的な基盤を整えてから独立するという段階的なプランも考えられます。
一時的に実家に頼ることで精神的にも安心でき、今後の生活再建のための時間と余裕を得られるでしょう。
マンスリーマンションを利用する
すぐに住居が必要でも、初期費用が用意できない場合の選択肢があります。
初期費用を抑えて別居するなら、マンスリーマンションやウィークリーマンションの利用も検討できます。
通常の賃貸物件は敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用がかかりますが、マンスリーマンションなら月額料金だけで入居できることが多いです。
家具や家電が備え付けられているため、新たに購入する必要もありません。
短期契約から始められるので、状況に応じて住居を変更しやすいという柔軟性もあります。
ただし、一般的な賃貸物件より家賃は割高なため、長期間の利用は経済的負担が大きくなる点に注意が必要です。
マンスリーマンションは、婚姻費用が確定するまでの一時的な住まいとして、または次の住居を探す間の仮住まいとして活用するのがおすすめです。
利用前に複数の物件を比較し、立地や設備、料金体系をしっかり確認することが大切です。
ひとり親支援制度を活用する
子どもと一緒に別居する場合は、公的な支援制度を利用できる可能性があります。
子どもと別居する場合は、ひとり親家庭向けの各種支援制度を積極的に活用しましょう。
法律上はまだ離婚していなくても、別居中であれば利用できる支援制度があります。
例えば、児童扶養手当は、離婚前でも事実上の単身世帯となっていれば受給できる可能性があります。
また、自治体によっては、ひとり親家庭への医療費助成や住宅支援、就労支援なども行っています。
まずは住んでいる(または住む予定の)自治体の福祉窓口や母子・父子自立支援員に相談してみましょう。
| 支援制度 | 内容 | 申請窓口 |
|---|---|---|
| 児童扶養手当 | 月額約4〜5万円(子ども1人の場合) | 住所地の市区町村役場 |
| ひとり親家庭医療費助成 | 医療費の一部または全額助成 | 住所地の市区町村役場 |
| 母子・父子福祉資金貸付 | 生活資金や住宅資金などの低利貸付 | 都道府県・政令指定都市 |
| 就労支援(高等職業訓練促進給付金など) | 資格取得のための支援金 | 住所地の市区町村役場 |
支援制度は自治体によって内容や条件が異なるため、早めに情報収集することをお勧めします。
児童手当の受給者変更を行う
子どもと同居している場合、児童手当の受給者を変更することができます。
子どもと別居する場合は、児童手当の受給者を子どもと同居する親に変更する手続きを行いましょう。
児童手当は原則として、子どもと同居している親が受給者となります。
別居前に配偶者が受給者だった場合は、市区町村役場で受給者変更の手続きをすることで、子どもと同居する親が受給できるようになります。
必要な書類は、「児童手当認定請求書」「受給者変更届」「別居の事実を証明する書類」などです。
別居の証明には、住民票や公共料金の領収書、賃貸契約書などが使えます。
児童手当の金額は子どもの年齢や人数によって異なりますが、0〜3歳未満は月額15,000円、3歳以上小学校修了前は月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は月額10,000円です。
所得制限があるため、高所得者は特例給付(月額5,000円)となる点に注意が必要です。
受給者変更の手続きは別居後すぐに行うことをお勧めします。遡っての支給はされないためです。
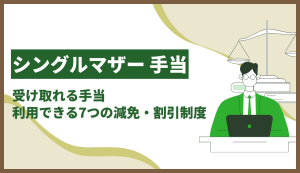
自宅のリースバックの活用を検討する
住宅ローンの支払いが困難な場合に検討できる方法もあります。
自宅を所有している場合は、リースバック制度を利用して資金を調達する方法も選択肢の一つです。
リースバックとは、自宅を不動産会社に売却した後、同じ物件を賃貸として借りて住み続ける仕組みです。
別居によって住宅ローンの支払いが困難になった場合や、まとまった資金が必要な場合に検討する価値があります。
売却代金からローンの残債を返済し、残ったお金を別居生活の資金に充てることができます。
ただし、売却価格は市場価格より低くなる傾向があり、家賃支払いが新たな負担になる点には注意が必要です。
また、リースバック契約の条件(契約期間や家賃、将来の買い戻し条件など)をよく確認することが重要です。
リースバックは最終手段として検討し、必ず専門家(弁護士や不動産コンサルタント)に相談してから判断することをお勧めします。
よくある質問
別居中の生活費について、読者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
ご自身の状況に近い質問があれば、参考にしてみてください。
- 別居中の生活費相場は子供の人数によって変わりますか?
- 別居中に夫が生活費をくれない場合どうすればいいですか?
- 別居中の専業主婦が請求できる生活費の金額を教えてください。
- 共働き夫婦の別居中の生活費はどう計算されますか?
- 婚姻費用算定表とは何ですか?
- 実家に帰って別居する場合も生活費は請求できますか?
- 離婚せずに別居を続ける場合、生活費請求の期間に制限はありますか?
- DV・モラハラが原因で別居した場合、特別な法的保護はありますか?
- 別居中の家賃も婚姻費用の対象になりますか?
- 別居中の生活費請求で弁護士に依頼する費用を教えてください。
まとめ
別居中でも、法律上は配偶者に対して「婚姻費用」として生活費を請求する権利があります。
婚姻費用の金額は、夫婦の収入差や子どもの有無・年齢によって変わり、一般的には収入が多い側が少ない側へ支払います。
請求方法は、まず当事者間の話し合いから始め、合意できなければ家庭裁判所の調停・審判という流れになります。
別居中の生活費請求で大切なのは、すべての交渉内容を記録に残し、合意内容は書面化することです。
経済的に厳しい状況では、婚姻費用分担の仮処分申請や、実家での一時的な別居、各種支援制度の活用なども検討しましょう。
別居中の生活費問題は心理的にも経済的にも負担が大きいものですが、適切な知識と準備で自分と子どもの生活を守ることができます。
必要に応じて弁護士や専門家に相談し、自分の権利を適切に主張していきましょう。





