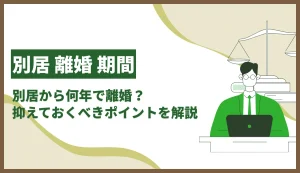離婚したいと思ったらどうする?よくある離婚理由・必要となる準備
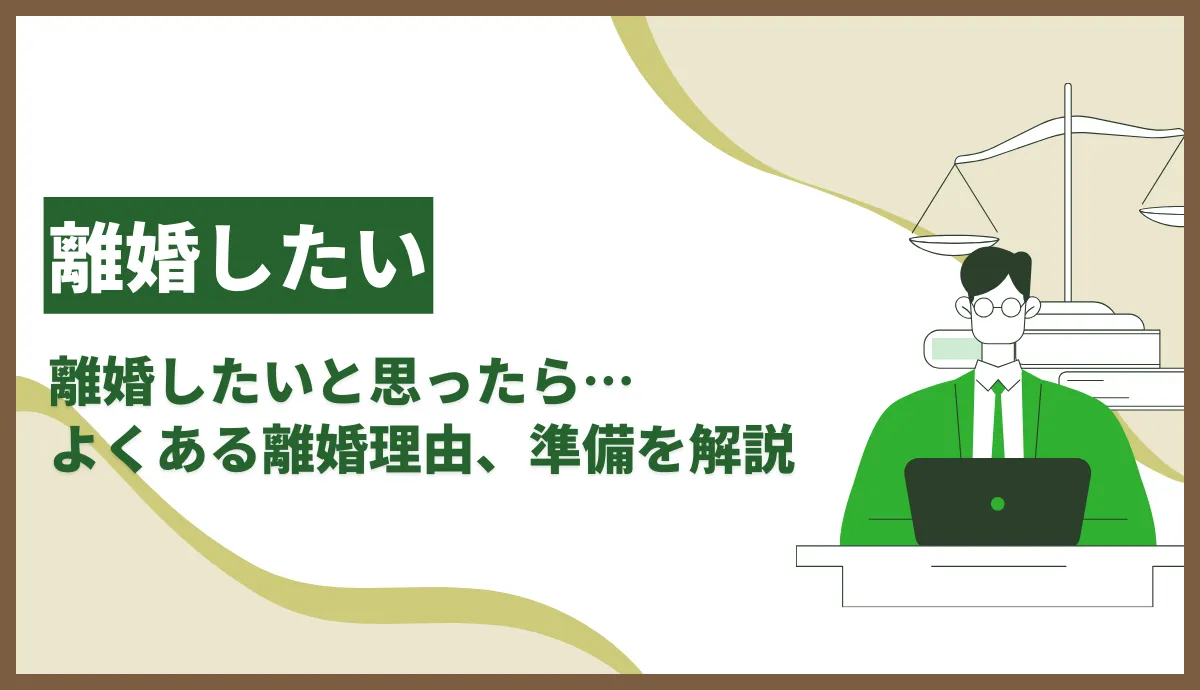
「もう一緒にいられない」「このままの関係を続けられない」と思った時、離婚を考え始める方は少なくありません。
離婚したいと思っても、どこから手をつければいいのか分からず悩んでいる方も多いでしょう。
特に子どもがいる場合や財産分与が複雑な場合は、さらに不安が大きくなります。
離婚には協議離婚や調停離婚など複数の方法があり、それぞれの進め方や必要な手続きが異なります。
また、離婚したい理由によっては慰謝料請求が可能なケースもあるため、正しい知識を持つことが重要です。
この記事では、離婚したいと思ったときに知っておくべき情報や手続きの流れについて解説していきます。
一人で悩まずに専門家のアドバイスを受けることで、未来への不安を軽減できます。ご自身の状況に合った離婚の進め方を見つけるための情報をしっかりとお伝えします。
離婚したい理由を整理してみる
離婚を考え始めたとき、まず自分の気持ちや状況を整理することが大切です。
なぜ離婚したいと思うのか、具体的な理由を明確にすることで、今後の進め方が見えてきます。
離婚したい理由を明確にする
離婚したいと思ったとき、まず自分自身の気持ちと向き合いましょう。
離婚を考える理由は人それぞれですが、自分の中で整理しておくことが重要です。
「最近喧嘩が増えた」など一時的な感情なのか、「価値観の違いが大きい」など根本的な問題なのかを区別しましょう。
理由が明確になれば、その後の対応策や離婚の進め方も変わってきます。
例えば、浮気や暴力など法律的に「有責配偶者」と認められる理由であれば、慰謝料請求が可能な場合もあります。
また、離婚したい理由を明確にすることで、調停や裁判になった際の主張もしやすくなるでしょう。
| 離婚の法定事由 | 説明 |
| 不貞行為 | 配偶者の浮気や不倫 |
| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく同居や生活費の負担を拒否 |
| 3年以上の生死不明 | 行方不明や音信不通の状態が3年以上続いている |
| 重度の精神疾患 | 回復の見込みがない精神疾患 |
| その他婚姻を継続し難い重大な事由 | DV、アルコール依存症、ギャンブル依存症など |
理由を書き出してみると、本当に離婚すべきなのか、あるいは別の解決策があるのかも見えてくるかもしれません。

離婚後に必要となる手続き
離婚を考える際には、離婚後の生活や必要な手続きについても事前に知っておくことが大切です。
離婚後には様々な行政手続きが必要となり、これらを把握しておくことで離婚後の生活をスムーズに始められます。
まず、離婚届を提出した後は住民票や健康保険、年金などの変更手続きが必要です。
子どもがいる場合は、児童手当や児童扶養手当の申請も検討しましょう。
また、姓を変更する場合は、銀行口座や免許証、パスポートなどの名義変更も必要となります。
こうした手続きは意外と時間がかかるため、事前に準備しておくと安心です。
- 住民票の変更(別居する場合は転出・転入届)
- 健康保険の切り替え(国民健康保険への加入など)
- 年金分割の請求(必要な場合)
- 子どもの氏の変更届(子どもの姓を変える場合)
- 児童手当・児童扶養手当の申請
- 各種名義変更(銀行口座、クレジットカード、免許証など)
離婚後の生活設計も重要な検討事項です。
収入や住居、子どもの養育費など、具体的にイメージしておくことで、離婚後の不安を軽減できるでしょう。
離婚したい理由として最も多いのは
離婚を考える理由は人それぞれですが、統計的に見ると一定の傾向があります。
厚生労働省の人口動態統計によると、離婚の主な理由には以下のようなものがあります。
性格の不一致は離婚理由の中で最も高い割合を占めており、夫婦間のコミュニケーション不足や価値観の相違が根底にあることが多いです。
次いで多いのが、配偶者の浮気や不倫による精神的苦痛です。
また、経済的な問題も重要な理由の一つで、生活費の問題やギャンブル依存などが挙げられます。
近年では、DV (ドメスティック・バイオレンス) や精神的虐待を理由とする離婚も増加傾向にあります。
| 離婚理由 | 割合 | 特徴 |
| 性格の不一致 | 約50% | 価値観の違い、コミュニケーション不足など |
| 浮気・不倫 | 約20% | 精神的信頼関係の破綻 |
| 経済的問題 | 約15% | 浪費、借金、生活費の問題など |
| 暴力・DV | 約10% | 身体的・精神的暴力 |
| その他 | 約5% | 親族との不和、依存症問題など |
「性格の不一致」は幅広い意味を持ち、日常生活での小さな意見の食い違いから、人生観や子育て方針の根本的な違いまで含まれます。
家事や育児の分担についての認識の違いも、最近では大きな問題として取り上げられることが増えています。
あなたが離婚を考えている理由が何であれ、その悩みは決して珍しいものではありません。
自分の置かれている状況を客観的に見つめ、必要に応じて専門家に相談することで、より良い決断ができるでしょう。
離婚が成立するまでの手続きの流れ
離婚したいと考えたとき、実際にどのような手続きが必要なのかを知っておくことは重要です。
離婚の手続きには主に4つの方法があり、それぞれ特徴や進め方が異なります。

日本の離婚の大半は協議離婚で行われている
日本では離婚の約90%が協議離婚という方法で成立しています。
協議離婚とは、夫婦間の話し合いのみで離婚が成立する制度で、裁判所を介さずに手続きできる点が大きな特徴です。
手続きはシンプルで、必要事項を記入した離婚届を市区町村の役所に提出するだけです。
ただし、離婚届には夫婦双方の署名と実印による押印が必要なため、両者の合意がなければ成立しません。
合意形成が難しい場合は、調停離婚や審判離婚、裁判離婚といった他の方法を検討する必要があります。
| 離婚の種類 | 特徴 | 手続きの流れ |
| 協議離婚 | 夫婦の合意のみで成立 | 話し合い→離婚届提出 |
| 調停離婚 | 裁判所の調停委員が仲介 | 調停申立→調停→調停成立→離婚届提出 |
| 審判離婚 | 調停不成立後、家庭裁判所が審判 | 調停不成立→審判→離婚届提出 |
| 裁判離婚 | 地方裁判所での訴訟 | 訴状提出→裁判→判決確定→離婚届提出 |
相手に非がなくても合意があれば協議離婚が可能
日本の離婚制度の特徴として、協議離婚では「法定の離婚事由」がなくても離婚できる点が挙げられます。
つまり、相手に特に非がなくても、お互いが離婚に合意すれば離婚が成立します。
これは諸外国と比較しても珍しい制度で、夫婦の自由意思を尊重する仕組みといえるでしょう。
ただし、調停離婚や裁判離婚では、民法に定められた離婚事由が必要となります。
「性格の不一致」のような抽象的な理由でも、日常生活が破綻している実態があれば離婚事由と認められる場合もあります。
離婚したい場合、まずは話し合いによる解決を試みることが一般的ですが、暴力や深刻な問題がある場合は直接調停を申し立てることも検討しましょう。
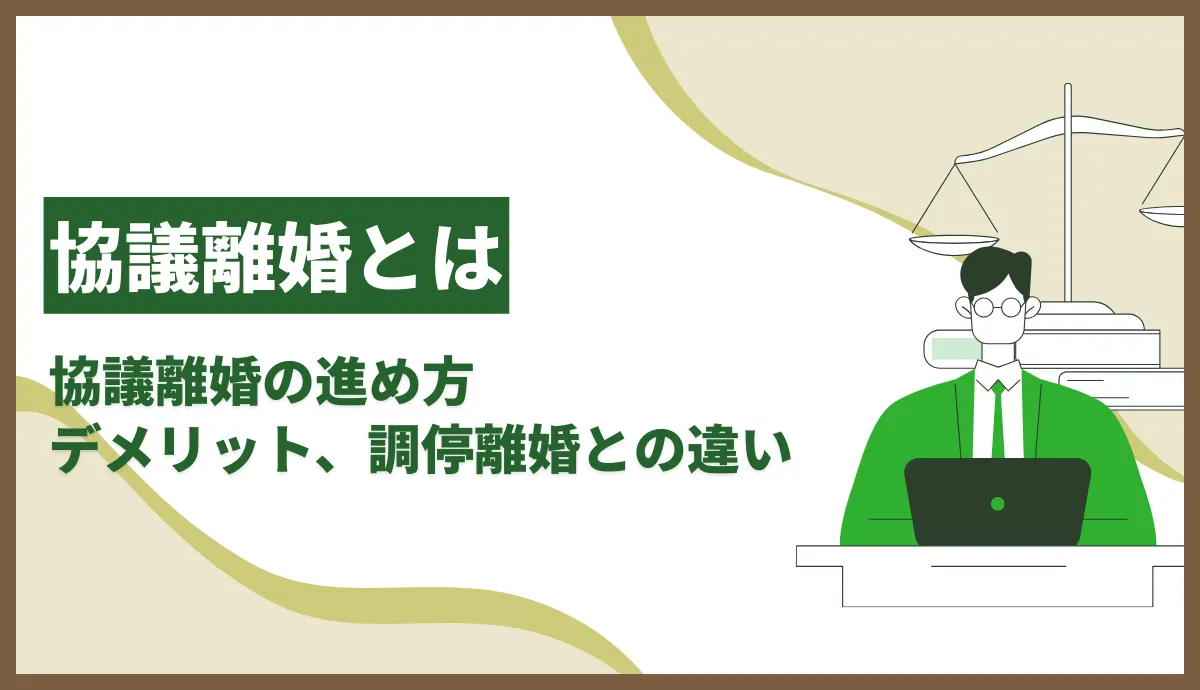
離婚に必要な費用について
離婚手続きにかかる費用は、選択する離婚方法によって大きく異なります。
協議離婚は最も費用が抑えられ、離婚届の提出自体は無料ですが、公正証書の作成など追加で発生する費用もあります。
合意形成が難しく調停や裁判になると、弁護士費用や申立費用などが必要となるため、費用は高額になる傾向があります。
弁護士に依頼する場合、初回相談料は5,000円〜10,000円程度が一般的です。
離婚全般の手続きを依頼する場合は、着手金と成功報酬を合わせて30万円〜50万円程度かかることが多いでしょう。
ただし、財産分与や慰謝料請求など複雑な事情がある場合は、さらに高額になることもあります。
| 手続き内容 | 費用の目安 | 備考 |
| 離婚届の提出 | 無料 | 戸籍謄本など書類取得費用は別途必要 |
| 公正証書作成 | 5万円前後 | 内容によって変動 |
| 調停申立費用 | 1,200円程度 | 収入印紙・郵便切手代 |
| 離婚訴訟提起 | 1万円前後 | 収入印紙・郵便切手代 |
| 弁護士相談料 | 5,000円〜1万円 | 30分〜1時間程度 |
| 弁護士依頼(協議) | 20万円〜30万円 | 着手金と成功報酬の合計 |
| 弁護士依頼(裁判) | 30万円〜50万円以上 | 内容によって大きく変動 |
費用面で不安がある場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談や、自治体が提供する無料相談サービスを利用することも検討しましょう。
また、収入が少ない場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性もあります。

夫の不倫が理由で離婚したい場合
配偶者の不倫は精神的な苦痛を伴い、離婚を考える大きなきっかけとなることが少なくありません。
夫の不倫が原因で離婚を考える場合、まず証拠の確保と今後の生活設計を整理することが重要です。
不倫を理由に離婚する場合、証拠があれば慰謝料請求や有利な条件での財産分与が可能となるケースが多いです。
証拠は、メールやLINEのやり取り、ホテルの領収書、目撃情報など客観的なものが有効です。
ただし、証拠集めは違法行為にならないよう注意が必要で、盗聴や無断での携帯電話チェックは避けるべきでしょう。
不倫の事実が確認できたら、冷静に今後の対応を検討します。
すぐに離婚を切り出すのではなく、まずは自分の気持ちを整理し、必要に応じて弁護士に相談するのも一つの方法です。
| 不倫による離婚での確認事項 | 内容 |
| 証拠の確保 | メール、LINE、写真、ホテルの領収書など |
| 慰謝料請求の可能性 | 相場は100万円〜300万円程度 |
| 時効 | 不倫を知ってから3年、行為から20年 |
| 弁護士への相談 | 証拠の評価や今後の対応について |
| 婚姻関係の修復 | カウンセリングなど第三者の介入も検討 |
不倫相手への慰謝料請求も可能ですが、相手が既婚者の場合はその家族への影響も考慮する必要があります。
また、不倫が原因でも修復を選ぶケースもあるため、すぐに離婚を決断せず、夫婦カウンセリングなどの選択肢も検討してみるとよいでしょう。
離婚を選択する場合は、財産分与や養育費、親権などについて冷静に話し合いをすることが大切です。
感情的になりすぎると、自分にとって不利な条件で合意してしまう可能性もあるため注意しましょう。
特に子どもがいる場合は、子どもの将来を第一に考えた判断が求められます。
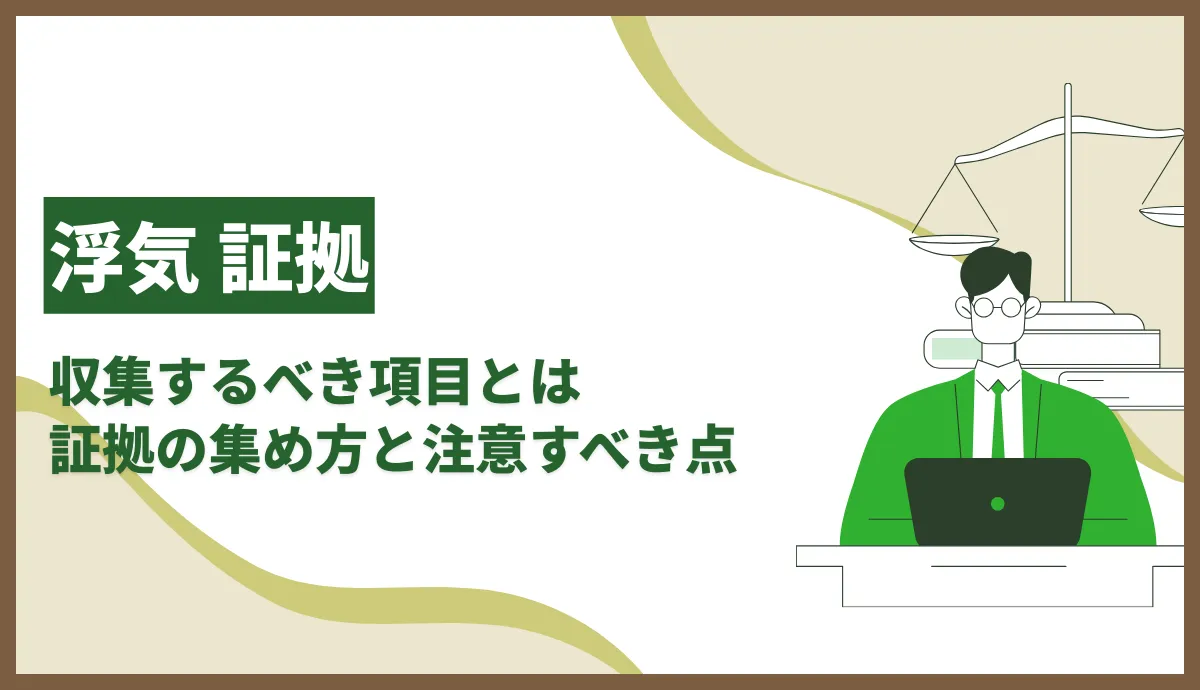
離婚したいけれど子どものことが心配な方へ
子どもがいる場合、離婚を考える際に最も心配なのは子どもへの影響ではないでしょうか。
親としては子どもの幸せを第一に考えたいものの、自分自身の幸せも大切にしなければなりません。
子どもがいる場合の離婚では、親権や養育費、面会交流など子どもの将来に関わる重要な取り決めが必要です。
まず親権については、どちらが子どもの親権者になるのかをしっかり話し合うことが大切です。
日本では未だに母親が親権者になるケースが多いですが、父親が親権者になるケースも増えています。
裁判所は子どもの利益を最優先に考え、養育能力や生活環境などを総合的に判断して親権者を決めます。
次に養育費については、子どもが成人するまでの経済的負担をどう分担するかを取り決めます。
「養育費算定表」を参考に、非監護親の収入や子どもの年齢などから算出するのが一般的です。
| 取り決め事項 | 内容 | 注意点 |
| 親権 | 子どもの法的な監護者を決める | 子どもの意思も尊重(年齢による) |
| 養育費 | 子どもの生活費や教育費の負担 | 公正証書での取り決めが望ましい |
| 面会交流 | 別居親と子どもの交流方法 | 頻度や方法を具体的に決める |
| 学校や病院の連絡先 | 緊急時の連絡体制 | 両親の連絡先を登録しておく |
| 子どもの氏の変更 | 必要に応じて家庭裁判所に申立 | 子どもの同意が必要な場合も |
面会交流は、離婚後も非監護親と子どもが定期的に会える機会を確保するものです。
子どもにとって両親との関係を継続することは健全な成長のためにも重要といわれています。
離婚が子どもに与える影響を最小限にするためには、両親が協力して子育てを続ける「共同養育」の姿勢が大切です。
子どもの前でお互いの悪口を言わない、子どもを取り合いの駒にしないなど、配慮すべき点は多くあります。
どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や弁護士の介入も検討しましょう。
また、子どもの年齢に合わせた説明も必要です。嘘をついたり、詳細を隠したりするより、子どもの理解力に合わせて誠実に向き合うことが信頼関係を築きます。
離婚前に別居するメリットについて解説
離婚を考えている場合、いきなり離婚手続きに進む前に別居を選択する方も少なくありません。
別居には様々なメリットがあり、冷静な判断をするための時間を確保できます。
別居は離婚前の冷却期間として機能し、感情的な対立を避けながら互いの気持ちを整理する時間を持てるメリットがあります。
日常的な摩擦から解放されることで、本当に離婚すべきか冷静に考えることができるでしょう。
また、別居期間中に一人暮らしを経験することで、離婚後の生活をシミュレーションすることもできます。
経済的な自立が可能か、一人での生活に適応できるかなど、実際に試してみることで具体的な課題が見えてきます。
離婚調停や裁判になった場合、別居の事実は「婚姻関係が破綻している」ことの証拠として扱われることもあります。
| 別居のメリット | 具体的な内容 |
| 冷静な判断が可能 | 日常的な摩擦から離れて考える時間が持てる |
| 離婚後の生活を試せる | 一人暮らしや経済的自立の実現性を確認できる |
| 子どもへの影響を確認 | 親の別居が子どもに与える影響を見極められる |
| 法的な証拠となる | 婚姻関係の破綻を示す証拠として活用できる |
| 新しい環境での気分転換 | 精神的なストレスから解放される可能性がある |
一方で、別居にはデメリットもあることを理解しておく必要があります。
二重生活による経済的負担の増加や、別居中に相手が財産を処分してしまうリスクなどです。
また、子どもがいる場合は、別居によって親子関係に影響が出る可能性もあります。
別居を選択する場合は、事前に以下のポイントを整理しておくと安心です。
- 別居期間の生活費や住居費の分担方法
- 子どもがいる場合の面会交流のルール
- 別居中の連絡手段や頻度
- 共有財産の管理方法
- 別居の目的と期間の目安
別居前に公正証書などで取り決めを交わしておくと、後のトラブルを防ぐことができるでしょう。
また、別居中でも法的には夫婦のままなので、相手に対する扶養義務や貞操義務は継続することも覚えておく必要があります。
離婚したいが話し合いが進まないときは弁護士に相談を
相手と離婚について話し合いを始めても、なかなか折り合いがつかないことは珍しくありません。
そんなとき、一人で抱え込まずに専門家である弁護士に相談することで道が開けることがあります。
弁護士は離婚問題の専門家として法的アドバイスだけでなく、交渉の代理人となって客観的な立場から話し合いを進めることができます。
特に以下のような状況では、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- 相手が離婚に応じず、話し合いが平行線になっている
- DVや浮気など深刻な問題を抱えている
- 財産分与や養育費の金額で折り合いがつかない
- 親権や面会交流について意見が対立している
- 相手が高額な財産を隠している疑いがある
弁護士に依頼するメリットは、法的な知識や経験に基づいたアドバイスが得られるだけではありません。
感情的になりがちな当事者同士の代わりに、冷静な第三者として交渉を進めることで合意に至りやすくなります。
また、相手との直接対話が精神的に負担になる場合も、弁護士が間に入ることでストレスを軽減できるでしょう。
| 弁護士に相談するタイミング | 具体的な状況 |
| 離婚を考え始めた時点 | 今後の進め方や法的権利の確認 |
| 話し合いが難航している時 | 交渉が平行線、感情的になっている |
| 相手からDVを受けている時 | 安全確保や保護命令の申立が必要 |
| 財産分与に不安がある時 | 財産の隠匿疑いや複雑な資産がある |
| 調停を申し立てる前 | 調停の進め方や必要書類の確認 |
弁護士を選ぶ際は、離婚問題を得意とする弁護士を探すことが大切です。
初回相談は無料や数千円で対応している法律事務所も多いので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。
相性も重要なポイントです。信頼できる弁護士と出会えれば、精神的な支えにもなります。
また、費用面で不安がある場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することも検討してみてください。
収入が一定基準以下であれば、弁護士費用の立替制度が利用できる場合があります。
弁護士に依頼する際は、依頼内容と費用について事前に明確に確認しておくことが重要です。

よくある質問
離婚を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。具体的な状況によって対応が異なる場合もありますので、必要に応じて専門家にご相談ください。
離婚したいと思ったら最初に何をすべきですか?
まず自分の気持ちや離婚理由を整理し、必要な証拠を集めましょう。その上で今後の生活設計を考え、必要に応じて専門家(弁護士や行政の相談窓口)に相談することをおすすめします。
相手に非がない場合でも離婚できますか?
はい、可能です。協議離婚では双方の合意があれば法定の離婚事由がなくても離婚できます。ただし調停や裁判では、婚姻関係が破綻していることを示す必要があります。
夫婦関係を修復する方法はありますか?
夫婦カウンセリングや家族療法などの専門的サポートを受けることで関係改善の可能性があります。また、コミュニケーションの取り方を見直したり、一時的な別居で冷却期間を設けるのも効果的です。
子供がいる場合の親権について教えてください。
日本では一方が単独で親権を持つのが一般的です。親権者は子どもの監護権と財産管理権を持ちます。決定の際は子どもの福祉が最優先され、年齢や生活環境、養育能力などが考慮されます。
性格の不一致を理由に離婚したい場合の進め方は?
まずは冷静に話し合いを進め、協議離婚を目指します。合意が得られない場合は調停を申し立て、それでも解決しない場合は裁判離婚となります。具体的な事例を挙げて婚姻関係の破綻を示すとよいでしょう。
離婚前に別居するメリットとデメリットは何ですか?
メリットは冷静な判断ができることや離婚後の生活をシミュレーションできる点です。デメリットは経済的負担の増加や別居中の財産管理リスク、子どもとの関係への影響などが挙げられます。
男性が離婚したいと思った時の準備について教えてください。
財産状況の把握、必要書類の準備、住居の確保が重要です。特に子どもがいる場合は親権や養育費について前もって検討し、必要に応じて公正証書を作成しておくとよいでしょう。
夫の浮気の証拠を集めるにはどうすべきですか?
メールやSNSのやり取り、ホテルの領収書、第三者の証言などが有効です。ただし、盗聴や無断での携帯確認など違法な手段は避け、必要に応じて探偵事務所への依頼も検討しましょう。
離婚について弁護士に相談するタイミングはいつですか?
話し合いが進まない、DVや財産隠しが疑われる、複雑な財産分与がある、親権争いがあるなどの場合は早めに相談すべきです。初期段階での相談が後々のトラブル防止にも役立ちます。
離婚に関わる費用の相場はどれくらいですか?
協議離婚なら離婚届のみで基本的に費用はかかりません。弁護士に依頼する場合は初回相談料5,000円〜1万円程度、全般的な依頼で20万円〜50万円程度が一般的です。内容により大きく変動します。
まとめ
離婚したいと思ったとき、まずは冷静に自分の気持ちと状況を整理することが大切です。
離婚の手続きには協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、できるだけ話し合いで解決することがスムーズな離婚への近道となります。
不倫や性格の不一致など、離婚理由はさまざまですが、特に子どもがいる場合は、親権や養育費、面会交流などについてしっかりと話し合うことが重要です。
話し合いがうまく進まない場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することで、より良い解決策を見つけることができるでしょう。
離婚は人生の大きな決断ですが、きちんと準備をして臨むことで、新たな人生のスタートを切るきっかけにもなります。