養育費はあとから請求できる!離婚後の請求方法と金額の相場を解説
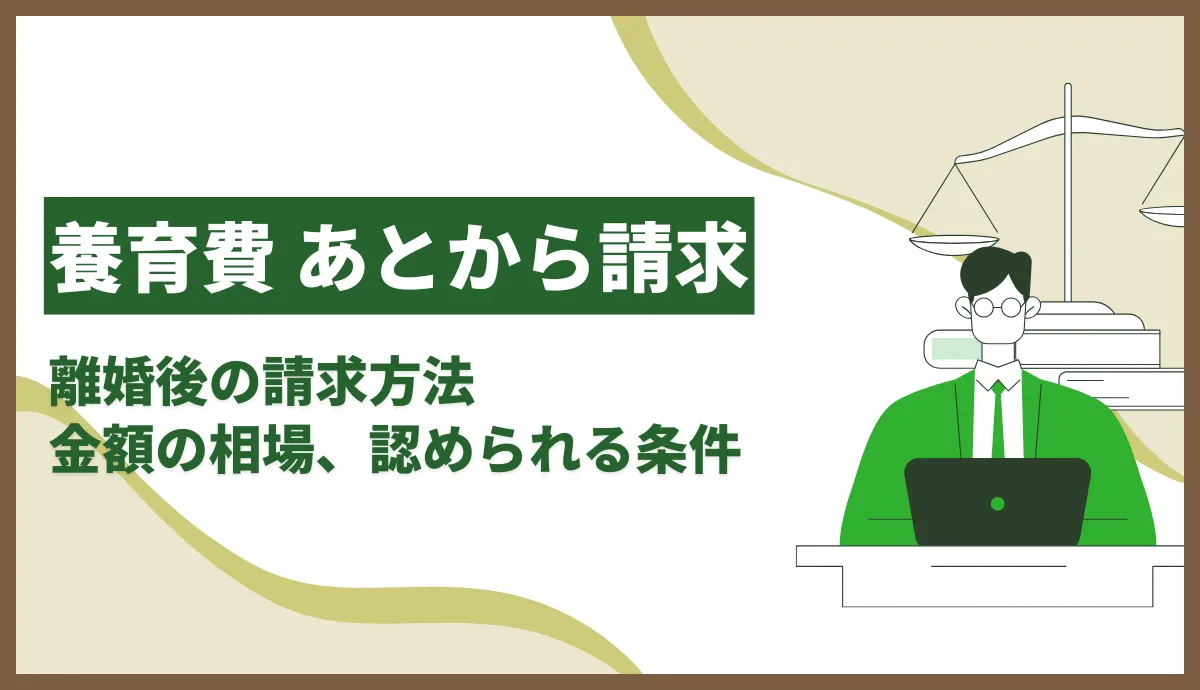
離婚後に「養育費はいらない」と言ったものの、生活が苦しくなってきて後悔していませんか?
子どもの教育費や生活費が予想以上にかかり、元配偶者に養育費を請求したいと考える方は少なくありません。
実は、離婚時に養育費を請求しなかったり、不要だと言ったりしても、あとから養育費を請求できる可能性があるんです。
ただし、養育費をあとから請求するには一定の条件があり、手続きも必要となります。
当記事では、養育費をあとから請求する方法や注意点について詳しく解説していきます。
法律の知識がなくても理解できるよう、養育費をあとから請求する具体的な手順をわかりやすく解説します。
養育費は後からでも請求すれば支払ってもらえる
離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、あとから請求することは可能です。
親権者には子どもを育てるために必要な養育費を元配偶者に求める権利があります。
経済的に余裕があったり、「子どもは自分一人で育てる」と思って養育費の取り決めをしなかったりするケースは少なくありません。
しかし、生活状況の変化や予想外の出費により、後になって「やっぱり養育費が必要」と感じることもあるでしょう。
養育費をあとから請求するには、いくつかの方法や注意点があるので確認していきましょう。
- 養育費を不要だと言った場合でも、請求は可能
- 子どもからの養育費請求も認められている
養育費を不要だと言った場合でも、請求は可能
「養育費はいらない」と一度言ったとしても、法的には請求する権利は消滅しません。
養育費は本来、子どもが親から受け取る権利です。
そのため、親権者が「不要」と言ったとしても、子どものための養育費を請求する権利は残ります。
離婚時に「養育費はいらない」と言った理由はさまざまでしょう。
元配偶者との関わりを絶ちたい、早く離婚を成立させたい、当時は経済的に困っていなかったなど、その時の状況に合わせた判断だったはずです。
しかし生活環境が変わり、子どもの教育費が増えるなど、状況が変化することは珍しくありません。
そのような場合には、離婚時の言葉に関わらず、養育費をあとから請求できます。
ただし、離婚時の約束や取り決めがある場合は、それを覆す合理的な理由が必要となることもあります。
子どもからの養育費請求も認められている
養育費は親権者だけでなく、子ども自身が請求することも法律上認められています。
未成年の子どもの場合は、通常、親権者が代理人として養育費請求を行いますが、成人した子どもは自分自身で請求できます。
子どもが成人した後でも、未払いの養育費を請求する権利は残ります。
例えば、親権者が「養育費はいらない」と言ったために受け取れなかった養育費でも、子ども自身が成人後に請求できる可能性があるのです。
ただし、この場合も時効の問題があるため、養育費が発生した時点から一定期間が経過すると請求が難しくなります。
子どもが自ら養育費を請求するケースは増えており、裁判所も子どもの権利を重視する傾向にあります。
親権者が様々な事情で養育費を請求してこなかった場合でも、子どもには別途請求する権利があることを覚えておきましょう。
養育費の相場はいくら?
養育費をあとから請求する際に、まず気になるのはいくら請求できるかという点でしょう。
養育費の金額は、子どもの年齢や人数、親の収入によって大きく変わります。
一般的には、裁判所が定めた「養育費算定表」を参考に金額が決められることが多いです。
養育費の相場は子ども1人あたり月額3〜8万円程度が目安となっています。
ただし、これはあくまで平均的な金額であり、実際には様々な要素によって変動します。
例えば、支払い義務者の年収が1,000万円以上の場合、子ども1人に対して月10万円以上の養育費が認められるケースもあります。
反対に、支払い義務者の年収が200万円程度だと、月額2〜3万円程度になることもあるでしょう。
| 子どもの年齢 | 支払義務者の年収300万円の場合 | 支払義務者の年収500万円の場合 | 支払義務者の年収800万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 0〜5歳 | 3〜4万円 | 4〜5万円 | 5〜7万円 |
| 6〜14歳 | 4〜5万円 | 5〜6万円 | 6〜8万円 |
| 15〜19歳 | 4〜6万円 | 5〜7万円 | 7〜9万円 |
上記の表はあくまで目安であり、実際の金額は個別の事情によって異なります。
子どもが私立学校に通っている場合や特別な教育費・医療費がかかる場合には、基本の養育費に加えて特別費用が認められることもあります。
養育費の金額について合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決められることになります。
裁判所は両親の収入や子どもの年齢、生活状況などを考慮して、適正な金額を判断します。
養育費をあとから請求する場合も、この養育費算定表が基準となることが多いので、参考にしておくといいでしょう。

養育費を後から請求するために満たすべき条件
養育費をあとから請求するには、いくつかの条件や前提があります。
これらの条件を把握しておくことで、スムーズに養育費請求を進めることができるでしょう。
離婚時に養育費の支払いは明確なルールを設けること
養育費をスムーズに受け取るためには、離婚時に明確なルールを決めておくことが理想的です。
具体的には、毎月の支払額、支払方法、支払日、支払期間などを細かく取り決めておく必要があります。
このルールは離婚協議書や公正証書などの書面にしておくと、後々のトラブルを防げます。
書面による養育費の取り決めがあれば、あとから請求する際の根拠になります。
例えば「月5万円を毎月15日までに指定口座に振り込む」といった具体的な内容を記載しておくと良いでしょう。
また、子どもの成長に合わせて増額する条件(中学・高校進学時など) や、物価上昇に応じた見直し条件なども盛り込んでおくと安心です。
離婚届とは別に、養育費に関する公正証書を作成しておくと、万が一支払いが滞った場合に強制執行もできます。
将来の生活状況を考慮し、できるだけ詳細に養育費の条件を決めておくことが大切です。

養育費を決めないまま離婚した場合は相手の同意が必要
養育費を取り決めないまま離婚した場合、あとから請求する際には基本的に相手の同意が必要です。
離婚時に養育費について何も決めなかった場合、法的な合意がない状態になります。
相手が任意で支払いに応じてくれれば問題ありませんが、拒否された場合は調停や審判などの法的手続きが必要になります。
養育費の請求権自体は消滅していないため、子どもが成人するまでの間は請求可能です。
ただし、過去の分については時効の問題があるため、請求できる期間に制限があることを覚えておきましょう。
離婚時に「養育費はいらない」と明確に言った場合でも、その後の事情変更があれば請求できる可能性はあります。
例えば、親権者の収入が大幅に減った、子どもの教育費が増えたなどの事情があると、請求が認められやすくなるでしょう。
養育費を決めずに離婚した場合でも、子どもの権利を守るために請求を諦める必要はありません。
相手との話し合いから始め、合意が得られない場合は法的手続きに進むことを検討しましょう。
養育費をあとから請求する方法とその手続き
養育費をあとから請求するには、いくつかの方法があります。
状況に応じて最適な方法を選ぶことで、スムーズに養育費を請求できるでしょう。
相手方との話し合いを行う
養育費をあとから請求する最初のステップは、元配偶者と直接話し合うことです。
まずは電話やメールで連絡を取り、養育費が必要になった事情を説明しましょう。
感情的にならず、子どものために必要だという点を冷静に伝えることが大切です。
話し合いの際には、具体的な金額や支払方法などの条件を明確にしておくと良いでしょう。
例えば「月々5万円を毎月末日までに振り込んでほしい」といった形で提案します。
相手が養育費の支払いに同意してくれた場合は、必ず書面にして双方で保管しておきましょう。
口約束だけでは後々トラブルになる可能性があるので、合意書や念書などの形で残しておくことが重要です。
できれば公正証書にしておくと、万が一支払いが滞った場合に強制執行できるので安心です。
裁判外での解決手続きを選択する
直接の話し合いがうまくいかない場合は、裁判外での解決手続きを検討しましょう。
弁護士に依頼して内容証明郵便を送ったり、ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用したりする方法があります。
弁護士に相談すると専門的なアドバイスが得られ、交渉もスムーズに進みやすくなります。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の通知を送ったかが証明できる公的な文書です。
養育費の請求意思を明確に伝えるとともに、法的手続きに移行する可能性があることを示す効果があります。
弁護士会のADRを利用する方法もあります。
第三者である弁護士が間に入って話し合いを進めることで、感情的対立を避けながら合意形成を目指せます。
ADRは裁判よりも費用が安く、迅速に解決できる可能性が高いというメリットがあります。
養育費請求の調停や審判を申し立てる
話し合いや裁判外での解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停は裁判所が間に入って話し合いによる解決を目指す手続きです。
調停の申立ては費用が安く(収入印紙1,200円程度)、弁護士がいなくても自分で行えます。
調停の流れは以下のとおりです。
| ① | 家庭裁判所に調停を申し立てる |
|---|---|
| ② | 調停期日の通知 |
| ③ | 調停委員を交えて話し合いを行う |
| ④ | 合意できれば調停調書が作成される |
| ⑤ | 合意できなければ審判に移行することもある |
調停で合意に至れば調停調書が作成され、これは裁判所の判決と同じ効力を持ちます。
調停で合意できない場合は、審判という裁判所が判断を下す手続きに移行することがあります。
審判では両親の収入や子どもの年齢などから、裁判所が適正な養育費を決定します。
審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告という不服申立てができます。
調停や審判の手続きは複雑なため、可能であれば弁護士に相談することをおすすめします。

養育費を後から請求する際の留意点
養育費をあとから請求する際には、いくつかの重要な留意点があります。
これらのポイントを理解しておくことで、トラブルを避け、円滑に養育費を受け取れるようになります。
養育費請求権には時効があることに注意
養育費の請求権には時効があるため、いつまでも請求できるわけではありません。
未払いの養育費を請求できる期間には制限があるので注意が必要です。
養育費の請求権の時効は、各支払日から5年とされています。
例えば、3年前に支払われるべきだった養育費は請求できますが、6年前のものは時効により請求できない可能性が高いです。
ただし、時効は援用(相手が時効を主張すること)があって初めて成立するものです。
相手が時効を主張しなければ、6年以上前の養育費でも請求できる場合があります。
また、時効の中断方法もあります。
内容証明郵便で請求したり、調停を申し立てたりすることで、時効の進行を止めることができます。

養育費の合意がある場合
離婚時に養育費について合意していた場合、その合意内容に基づいて請求することができます。
合意があるケースでは、比較的スムーズに養育費を請求できる可能性が高いでしょう。
合意内容が書面化されていれば、それを根拠に支払いを求めることができます。
特に公正証書などの法的効力のある文書があれば、支払いが滞った場合にも強制執行ができます。
ただし、合意後に事情変更があった場合は、養育費の増額や減額の調停を申し立てることもできます。
例えば、子どもが高校や大学に進学して教育費が増えた場合や、逆に支払い義務者の収入が大幅に減少した場合などが該当します。
事情変更の調停では、現在の状況に合わせた養育費の見直しが行われます。
養育費の合意がない場合
離婚時に養育費について何も決めていなかった場合は、あとから新たに請求することになります。
この場合、まずは相手方との話し合いから始めるのが基本です。
話し合いがうまくいかなければ、調停や審判などの法的手続きに進むことになります。
養育費の金額は、両親の収入や子どもの年齢、生活状況などを考慮して決められます。
裁判所は一般的に「養育費算定表」を参考に判断することが多いです。
「養育費はいらない」と言った場合でも、子どものための権利なので請求は可能です。
ただし、明確な放棄の意思表示があった場合は、その後の事情変更(収入減少や教育費増加など)を説明する必要があるでしょう。
再婚や養子縁組があると、養育費が減額される可能性がある
親権者が再婚した場合、養育費が減額される可能性があります。
特に、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は注意が必要です。
養子縁組が成立すると、法律上の親子関係が生じるため、元配偶者の養育費支払い義務が減額または消滅する可能性があります。
ただし、養子縁組をしても自動的に養育費が不要になるわけではありません。
裁判所は個別のケースごとに、子どもの利益を最優先に判断します。
再婚しても養子縁組をしていない場合は、基本的に養育費支払い義務に変更はありません。
ただし、再婚相手の収入が高く、親権者の生活水準が大幅に向上した場合などは、減額が認められることもあります。
いずれにしても、養育費の変更を希望する場合は、調停などの手続きを経る必要があります。

養育費に関する合意は公正証書にしておく
養育費の取り決めは、できるだけ公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書には特別な法的効力があり、支払いが滞った場合に強制執行できるメリットがあります。
公正証書があれば、裁判を経ずに差し押さえなどの手続きができるため、未払い養育費の回収がスムーズになります。
公正証書の作成は公証役場で行います。
作成費用は金額や内容によって異なりますが、一般的に数万円程度です。
公正証書に記載すべき主な内容は以下の通りです。
- 毎月の養育費の金額
- 支払期日(毎月何日まで)
- 支払方法(込先口座など)
- 支払期間(子どもが何歳まで)
- 増額・減額の条件(進学時など)
- 不払いの場合の措置(強制執行に関する文言)
あとから請求した養育費についても、合意が得られたら必ず公正証書にしておくと安心です。
養育費は長期間にわたって支払われるものなので、法的に強制力のある形で合意しておくことが重要です。
よくある質問
養育費をあとから請求する方法について、読者の皆さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
具体的な不安や疑問の解消にお役立てください。
- 養育費は後から増額することができますか?
- 養育費に関するルールはどのように決めておくべきですか?
- 養育費の消滅時効が近い場合の対処法を教えてください。
- 相手が養育費を支払わない場合の対応方法はありますか?
- 離婚後の養育費請求を弁護士に依頼する場合の費用はいくらかかりますか?
- 養育費はいらないと言ってしまった場合でも後から請求できますか?
- 子供が成人した後でも未払いの養育費を請求する方法はありますか?
- 養育費の口約束だけでも法的効果はありますか?
まとめ
養育費は、離婚時に「不要」と言った場合でも、あとから請求することが可能です。
子どもの健全な成長のためには適切な養育費が必要であり、それを請求する権利は親権者だけでなく子ども自身にもあります。
養育費をあとから請求する方法としては、まず相手方との話し合いを試み、それがうまくいかない場合は調停や審判などの法的手続きに進むことになります。
ただし、養育費の請求権には時効があるため、各支払日から5年以内に請求する必要があることを忘れないでください。
また、養育費に関する合意は必ず書面化し、できれば公正証書にしておくと安心です。
養育費は子どもの権利であることを念頭に置き、必要な場合は躊躇せず請求しましょう。
子どもの将来のために、親として責任を果たすことが大切です。











