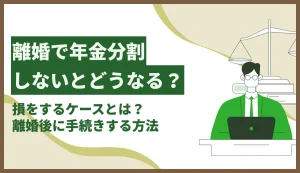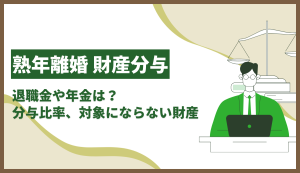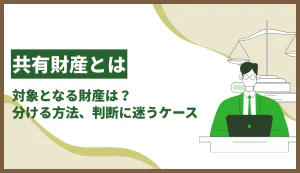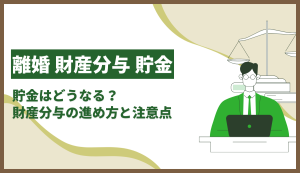扶養的財産分与とは?離婚後の生活費が認められる条件と相場

離婚を考えていると、財産分与のことが頭を悩ませますよね。
特に「扶養的財産分与」という言葉を初めて聞いた方は、一体どんな制度なのか気になるところでしょう。
扶養的財産分与とは、離婚後の生活を支えるための財産分与の一種です。
清算的財産分与とは異なり、将来の生活保障を目的としているため、経済的に不安がある方には重要な権利となります。
特に専業主婦(夫)だった方や収入の少ない方にとって、扶養的財産分与は離婚後の生活を立て直すための大切な支えになるのです。
この記事では、扶養的財産分与について詳しく解説していきます。
専門的な内容もわかりやすく丁寧に説明しますので、ご自身の状況に当てはめながら参考にしてください。
扶養的財産分与の定義とは
離婚する際には財産分与が発生しますが、その種類のひとつに「扶養的財産分与」があります。
財産分与は一般的に、結婚中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける制度として知られています。
しかし扶養的財産分与は、単に財産を分けるだけでなく、離婚後の生活保障という目的を持っているのです。
扶養的財産分与と清算的財産分与の違い
財産分与には主に「清算的財産分与」と「扶養的財産分与」の2種類があります。
清算的財産分与は、結婚期間中に夫婦が共同で築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分け合うものです。
一方で扶養的財産分与は、経済力の乏しい配偶者の将来の生活を保障するための分与となります。
つまり、清算的財産分与が「過去の清算」なのに対し、扶養的財産分与は「将来の生活保障」という違いがあるのです。
| 清算的財産分与 | ・結婚期間中に形成した財産を分ける ・過去の貢献度に応じて分配 ・一般的に折半が基本 |
|---|---|
| 扶養的財産分与 | ・離婚後の生活保障が目的 ・経済力の少ない配偶者を支援 ・生活レベルや年齢などを考慮 |
例えば、専業主婦だった妻が離婚後すぐに十分な収入を得ることが難しい場合、扶養的財産分与として夫から一定期間、生活費相当額を受け取るケースがあります。
また、清算的財産分与は婚姻期間中の財産のみが対象ですが、扶養的財産分与では将来の収入も考慮されるのが特徴です。

扶養的財産分与が必要とされる背景
なぜ扶養的財産分与という制度が存在するのでしょうか。
結婚生活の中で、家事や育児に専念して働くことができなかった配偶者は、離婚後に経済的に不利な立場に置かれがちです。
扶養的財産分与は、このような経済的格差を是正し、離婚後も人間らしい生活を送れるようにするための制度なのです。
特に専業主婦(夫)や、結婚生活のためにキャリアを中断した配偶者にとって重要な権利といえます。
年齢が高く再就職が難しい場合や、病気や障害があって十分な収入を得ることが難しい場合にも、扶養的財産分与が認められやすくなります。
また離婚する時点でまだ幼い子供がいる場合など、家事、育児をしながら働かなければならない状況も考慮されます。
- 長期間専業主婦(夫)だった
- 年齢が高く再就職が困難
- 子育てや親の介護で働けない
- 病気や障害がある
- 職業訓練や資格取得に時間がかかる
こうした背景から、日本の民法では、配偶者の一方が離婚後に生活に困る場合の保障として、扶養的財産分与が認められているのです。

扶養的財産分与の相場と支払期間の目安
「扶養的財産分与はいくらもらえるのか」「どのくらいの期間支払われるのか」と気になる方も多いでしょう。
結論からいうと、扶養的財産分与の金額や期間には明確な基準がなく、ケースバイケースで決まります。
それでも大まかな相場や目安を知っておくことで、離婚協議の際の参考になるはずです。
相場はどれくらい?
扶養的財産分与の金額は、さまざまな要素によって変動します。
相手の収入や支払能力、受け取る側の年齢や就労能力、婚姻期間の長さなどが総合的に考慮されます。
一般的な目安としては、相手の収入の15〜30%程度が扶養的財産分与として認められるケースが多いでしょう。
例えば、相手の月収が40万円の場合、月に6万円〜12万円程度が相場と考えられます。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は個別の事情によって大きく変わることを覚えておきましょう。
| 考慮される要素 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 長期間の結婚ほど金額が高くなる傾向 |
| 年齢 | 高齢であるほど再就職が難しく金額が増える |
| 職歴、スキル | 就労経験が少ないほど金額が増える |
| 健康状態 | 持病や障害があれば金額が増える |
| 相手の収入 | 高収入であるほど支払額が増える |
裁判所が扶養的財産分与を認める際には、「相当性」という基準を用います。
これは支払う側に過度な負担にならず、かつ受け取る側の生活を支えるのに十分な金額かどうかを判断するものです。
扶養財産分与にかかる税金
扶養的財産分与を受け取る際、税金について知っておくことも大切です。
基本的に、扶養的財産分与として受け取る金額には所得税がかかる可能性があるので注意が必要です。
これは清算的財産分与と大きく異なる点です。
清算的財産分与は過去の財産の分配なので非課税ですが、扶養的財産分与は「将来の生活費」という性質上、一時所得または雑所得として課税対象になります。
税務上の取り扱いについては、税理士に相談するのがベストでしょう。
期間はいつまで続くか?
扶養的財産分与の支払期間も、状況によって大きく異なります。
一般的には3年から5年程度の期間が多いですが、婚姻期間や年齢によっては10年以上続くケースもあります。
期間を決める際に考慮される主な要素は以下の通りです。
- 受け取る側の年齢と再就職の可能性
- 婚姻期間の長さ
- 子どもの年齢や状況
- 資格取得や職業訓練に必要な期間
- 健康状態や障害の有無
例えば、結婚期間が長く高齢で再就職が難しい場合は、より長期間の支払いが認められる傾向にあります。
一方、若く再就職の可能性が高い場合は、比較的短期間で自立できるとみなされることが多いでしょう。
また、扶養的財産分与は一括払いではなく、月々の分割払いが一般的です。
これは受け取る側の生活を継続的に支えるという目的に沿った形といえるでしょう。
ただし、諸事情により一括払いで合意するケースもあります。
扶養的財産分与が認められやすい事例
扶養的財産分与は全ての離婚ケースで認められるわけではありません。
「自分のケースでは認められるのだろうか」と疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、扶養的財産分与が認められやすい具体的な事例を紹介します。
自分の状況と照らし合わせながら確認してみましょう。
- 長期間の専業主婦(夫)で職歴が少ない場合
- 高齢で再就職が難しい場合
- 病気や障害があり働くことが困難な場合
- 幼い子どもがいて就労に制限がある場合
- 結婚のために退職した場合
特に結婚生活が長く、その間に働く機会を失ってスキルが低下していた場合は、扶養的財産分与が認められる可能性が高いでしょう。
例えば、20年間専業主婦として家庭を支え、45歳で離婚するケースでは、再就職の困難さを考慮して扶養的財産分与が認められやすくなります。
また、婚姻中に病気や怪我をして働く能力が低下した場合も、将来の生活保障として扶養的財産分与が認められるケースが多いようです。
扶養目的の財産分与が裁判で認められた判例
実際の裁判例を見てみると、扶養的財産分与が認められるパターンがより明確になります。
過去の判例から、どのようなケースで扶養的財産分与が認められているのか確認してみましょう。
| 判例 | 事例の概要 | 認められた内容 |
|---|---|---|
| 最高裁昭和46年7月23日 | 長年専業主婦だった50代女性の離婚ケース | 月額7万円の扶養的財産分与を5年間 |
| 東京高裁平成18年3月29日 | 25年の婚姻後に離婚した専業主婦 | 月額10万円を3年間の支払い |
| 名古屋高裁平成22年6月9日 | 病気を抱える妻の離婚ケース | 一時金300万円の支払い |
これらの判例から見えてくるのは、長期の婚姻関係や健康上の問題、年齢による再就職の困難さなどを裁判所が重視しているということです。
特に有名な判例としては、最高裁昭和46年7月23日判決があります。
この判決では「離婚によって生活の困窮するおそれのある配偶者に対して相当額の財産を与える」という扶養的財産分与の考え方が明確に示されました。
また、近年の判例では、単に経済的な面だけでなく、精神的な負担や社会的な不利益なども考慮されるようになってきています。
例えば、夫の暴力や不貞行為によって離婚に至った場合、慰謝料とは別に扶養的財産分与が認められるケースもあります。
扶養的財産分与が認められるかどうかは個別の事情によって異なりますが、これらの判例を参考にすることで、自分のケースでの可能性を探ることができるでしょう。
扶養的財産分与の手続き方法
扶養的財産分与を請求するためには、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。
離婚の方法によって手続きが異なるため、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
ここでは、協議離婚と調停、裁判での扶養的財産分与の手続き方法について解説します。
協議離婚での扶養的財産分与の決め方
協議離婚は当事者同士の話し合いで離婚条件を決める方法です。
扶養的財産分与についても、双方の合意で自由に金額や期間を決めることができます。
協議離婚での扶養的財産分与を決める際は、必ず書面で残すことが重要です。
口頭だけの約束は後々トラブルの原因になりやすいため、離婚協議書に詳細を記載しましょう。
離婚協議書には以下の内容を明記することをおすすめします。
- 支払う金額(月額または総額)
- 支払い期間
- 支払い方法(振込先口座など)
- 支払い日
- 不払いの場合の対応
- 支払いが終了する条件(再婚時など)
より法的な効力を持たせるには、公正証書にすることも検討しましょう。
公正証書にしておくと、もし相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに強制執行することができます。
協議の際は、相手に対して一方的な要求をするのではなく、自分の状況や将来の見通しを冷静に説明することが大切です。

調停・裁判での扶養的財産分与を主張する方法
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や裁判で扶養的財産分与を請求することになります。
調停や裁判で扶養的財産分与を認めてもらうには、自分がなぜ扶養的財産分与を必要としているのか、具体的な事情を説明する資料を準備することが重要です。
主に以下のような資料を用意しておくと良いでしょう。
- 現在の収入を証明する書類(給与明細など)
- 今後の収入見込みに関する資料
- 生活費の見積もり
- 健康状態に関する診断書(病気や障害がある場合)
- 就労が困難な事情を説明する資料
- 相手の収入に関する資料(分かる範囲で)
調停では、調停委員を介して話し合いが進められます。
その過程で裁判官から扶養的財産分与の金額や期間について提案がなされることもあります。
調停でも合意に至らない場合は、審判や訴訟に移行することになりますが、この場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
裁判では、より専門的な法律知識が必要となるからです。
なお、調停や裁判では感情的な主張よりも、客観的な事実や数字に基づいた主張のほうが説得力を持ちます。
感情的にならず、冷静に自分の状況を説明することを心がけましょう。

離婚後の金銭的な準備をしておくこと
扶養的財産分与をもらえたとしても、将来的には自立した生活を送ることが大切です。
離婚後の金銭的な準備を整えておくことで、より安定した生活を目指せるでしょう。
ここでは、扶養的財産分与をもらいながら、将来に向けてどのような準備をすべきかを解説します。
離婚後の生活設計を考える
扶養的財産分与は永続的なものではなく、いずれは終了します。
そのため、離婚後の生活設計をきちんと立てておくことが、将来の安心につながります。
まずは、現在の収入と支出を把握し、今後の生活費をどのように賄っていくか計画しましょう。
扶養的財産分与を受け取る間に、以下のような準備をしておくことをおすすめします。
- 月々の生活費と収入のバランスを確認する
- 将来的な収入源を確保するための計画を立てる
- 無理なく貯金できる金額を設定する
- 必要最低限の生活費を算出しておく
- 突発的な出費に備えた緊急資金を確保する
特に子どもがいる場合は、教育費なども考慮した長期的な資金計画が必要です。
養育費とは別に、教育費の負担についても元配偶者と取り決めておくと安心でしょう。
また、扶養的財産分与の支払い期間中に、できるだけ貯蓄を増やしておくことも大切です。
このような準備をしておくことで、支払いが終了した後も安定した生活を送ることができます。
再就職や資格取得の準備
長期的な経済的自立のためには、就労による収入確保が重要です。
扶養的財産分与を受け取りながら、再就職のための準備や資格取得にチャレンジすることをおすすめします。
特に専業主婦(夫)だった方は、すぐに正社員として働くのが難しい場合もあるでしょう。
そんな時は、まずはパートやアルバイトから始めて、徐々に働く時間を増やしていくという方法も検討できます。
また、以下のような就労支援サービスも積極的に活用しましょう。
- ハローワークの就職支援プログラム
- 自治体の就労支援サービス
- 母子家庭向けの就労支援
- 職業訓練校の活用
- キャリアカウンセリングの利用
資格取得も収入アップの有効な手段です。
自分の興味や適性に合った資格を選び、計画的に勉強を進めていきましょう。
中には、資格取得のための費用を扶養的財産分与として請求できるケースもあります。
離婚協議の際に、就職や資格取得のための費用についても話し合っておくとよいでしょう。
焦らず着実に自立への道を進むことが大切です。
一度に全てを解決しようとせず、ステップを踏みながら、徐々に経済的自立を目指していきましょう。

離婚後2年以内なら扶養的財産分与を請求可能
「もう離婚してしまったけど、扶養的財産分与を請求できるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
結論から言うと、離婚後でも2年以内であれば、扶養的財産分与を請求することができます。
民法768条では、財産分与の請求期限を「離婚の時から2年」と定めています。
この期限を過ぎると原則として請求権が消滅するため、早めの行動が大切です。
離婚後の請求に必要な手続き
離婚後に扶養的財産分与を請求するには、まず元配偶者と話し合いをすることから始めます。
しかし離婚後は関係が悪化していることも多く、直接の交渉が難しいケースがほとんどです。
そんな場合は、以下のような手続きを取ることになります。
- 弁護士に相談し、内容証明郵便で請求の意思を伝える
- 相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる
- 調停でも合意に至らない場合は、審判または訴訟へ移行する
離婚後の請求では、なぜ離婚時に財産分与を請求しなかったのか理由を説明できることが重要です。
例えば、「離婚時は感情的になっていて冷静な判断ができなかった」「元配偶者から威圧されて請求できなかった」などの事情があれば説明しましょう。
また、離婚後の扶養的財産分与請求では、経済状況の変化なども考慮されます。
離婚後に病気になったり、予想以上に再就職が難しかったりした場合は、その状況も詳しく説明する必要があります。
離婚後の請求は離婚時よりもハードルが高くなるため、弁護士に相談して進めることをおすすめします。
時効を過ぎた場合の対応方法
離婚から2年以上が経過すると、原則として財産分与を請求する権利は時効によって消滅します。
しかし特別な事情がある場合には、2年の時効を過ぎても請求が認められる可能性があります。
例えば、以下のような場合です。
- 元配偶者から脅迫や暴力を受けていて請求できなかった
- 元配偶者が財産を隠していて、後から発覚した
- 重い病気や怪我で請求行為ができない状態だった
こうした事情がある場合は、弁護士に相談して「時効の援用に対する信義則違反」や「権利の濫用」として争う方法があります。
ただし、時効を過ぎてからの請求は非常に難しいのが現実です。
離婚を考えている段階や離婚直後から、扶養的財産分与について検討し、早めに行動することが大切です。
もし時効が迫っている場合は、まず内容証明郵便で請求することで、時効の進行を一時的に止めることができます。
このように、離婚後であっても2年以内であれば扶養的財産分与を請求する権利がありますので、必要性を感じたらためらわずに専門家に相談しましょう。

よくある質問
扶養的財産分与について、読者からよく寄せられる質問をまとめました。
具体的な疑問点の解消にお役立てください。
- 扶養的財産分与の相場はいくらですか?
- 扶養的財産分与は専業主婦にとってどのような意味がありますか?
- 扶養的財産分与の支払い期間はいつまで続くのですか?
- 扶養的財産分与に関する代表的な裁判例を教えてください。
- 扶養的財産分与と養育費の違いは何ですか?
- 扶養的財産分与を一括で支払うことは可能ですか?
- 扶養的財産分与に税金はかかりますか?
- 病気や障害がある場合、扶養的財産分与はどうなりますか?
- 扶養的財産分与の金額が高すぎると感じる場合の対応策を教えてください。
- 離婚協議書での扶養的財産分与の書き方を教えてください。
まとめ
扶養的財産分与は、離婚後の生活を支えるための重要な制度です。
清算的財産分与とは異なり、将来の生活保障を目的としており、特に専業主婦(夫)や年齢が高い方、健康上の問題がある方には大きな意味を持ちます。
金額や期間の相場はケースバイケースですが、相手の収入の15〜30%程度が目安となり、期間は3〜5年程度が一般的です。
請求するためには、協議離婚の場合は離婚協議書に詳細を記載し、話し合いがつかない場合は調停や裁判で主張することになります。
離婚後でも2年以内であれば請求が可能ですが、早めに行動することが大切です。
また、扶養的財産分与はあくまで一時的な支援であり、将来的には自立した生活を目指して再就職や資格取得の準備を進めることも重要です。
どのようなケースでも、専門家のアドバイスを受けながら、自分の状況に合った扶養的財産分与を請求していきましょう。