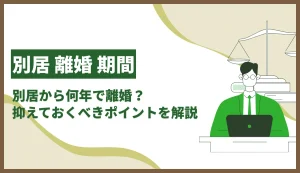離婚時に決めること|トラブルを避けるための6つの重要な条件

離婚を決意するのは人生の大きな岐路です。
感情的になりがちな離婚協議の場で、冷静に何を決めなければならないのか把握していますか?
離婚時に決めることを見落としてしまうと、将来的に大きなトラブルや金銭的な損失につながることもあります。
この記事では、離婚する際に必ず決めておくべき6つの重要な項目について解説していきます。
離婚の手続きにおける不安を少しでも和らげられるよう、専門用語をなるべく使わずに分かりやすく説明します。
将来の安心につながる大切な決断をサポートするため、ぜひ最後までご覧ください。
離婚の際に決定することは?6つの重要な条件
離婚を決めたとき、多くの人は感情的になりがちです。
しかし冷静に考えるべき重要な事項があり、これらを適切に決めておかないと将来トラブルの原因になります。
離婚手続きは単に婚姻関係を解消するだけでなく、これまでの生活や今後の人生設計に関わる様々な条件を決める大切なプロセスなのです。
離婚時に決めるべき重要な項目は「財産分与」「慰謝料」「年金分割」「親権者」「面会交流」「養育費と婚姻費用」の6つです。
これらの条件は離婚協議の中心となり、将来の生活や子どものためにも丁寧に取り決めておく必要があります。

離婚の際に決定する項目のリスト
離婚を進める前に、どのような項目について話し合い、決定する必要があるのか理解しておきましょう。
以下に離婚時に決めるべき主な項目をリストアップします。
| 決定項目 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 財産分与 | 結婚中に築いた財産をどう分けるか | ★★★★★ |
| 慰謝料 | 有責配偶者から支払われる精神的損害の賠償 | ★★★☆☆ |
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金の分割方法 | ★★★★☆ |
| 親権者 | 未成年の子どもの親権をどちらが持つか | ★★★★★ |
| 面会交流 | 親権を持たない親と子どもの交流方法 | ★★★★☆ |
| 養育費 | 子どもの成長に必要な費用の分担 | ★★★★★ |
| 婚姻費用 | 離婚成立前の別居期間中の生活費 | ★★★☆☆ |
これらの項目はそれぞれ密接に関連しています。
たとえば、財産分与の額が大きければ慰謝料が減額されるケースもあります。
また、子どもがいる場合は特に親権者と面会交流、養育費の取り決めが重要になるでしょう。
これらの項目について合意したら、離婚協議書を作成して双方が署名することで、将来のトラブルを防ぐことができます。
特に子どもがいる場合や財産が多い場合は、弁護士に相談しながら進めるのも一つの方法です。
これから各項目について詳しく見ていきましょう。
離婚の際に決定する① 財産分与
離婚を決めたとき、まず直面するのが財産分与の問題です。
結婚生活で夫婦が築き上げた財産をどのように分けるかは、将来の生活基盤に大きく影響します。
財産分与の取り決めは、離婚後の金銭的な安定と公平性を確保するために欠かせません。

共有財産を離婚後にどう分けるかを財産分与で決定する
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に公平に分配する制度です。
民法上では夫婦の共有財産を「清算的財産分与」として分けることが定められています。
結婚生活では、仕事をする人と家庭を守る人といった役割分担がある場合も多いでしょう。
財産分与の基本的な考え方は、それぞれの貢献度に応じて公平に分配することにあります。
例えば、専業主婦として家庭を支えてきた場合でも、家事や育児による貢献が認められます。
そのため、収入を得ていなくても財産分与の権利は発生するのです。
財産分与の請求権は離婚成立後2年以内に行使する必要があるため、離婚時に必ず取り決めておきましょう。
財産分与で離婚時に決定すべき内容
財産分与を円滑に進めるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
特に「対象となる財産」「分配割合」「分与の方法」の3点は離婚時に必ず決めておくべき事項です。
財産分与の対象となるもの
まず、どの財産が分与の対象になるのかを明確にしておきましょう。
基本的に婚姻期間中に夫婦で協力して得た財産が対象となります。
具体的には下記のような資産が財産分与の対象です。
| 分類 | 対象となる財産の例 |
|---|---|
| 不動産 | 自宅、投資用不動産、別荘など |
| 預貯金 | 普通預金、定期預金、積立預金など |
| 有価証券 | 株式、投資信託、国債、社債など |
| 保険 | 生命保険の解約返戻金など |
| 動産 | 自動車、貴金属、美術品、家具家電など |
| 退職金 | すでに受け取った退職金や退職金の期待権 |
一方で、以下のものは原則として財産分与の対象外となります。
- 結婚前から所有していた財産
- 相続や贈与によって単独で取得した財産
- 個人的な使用目的の衣類や身の回り品
- 特別な事情で単独で取得した財産(例:障害補償金など)
財産分与の対象を明確にするには、結婚前からの財産と婚姻中に形成した財産を区別できる記録を残しておくことが重要です。
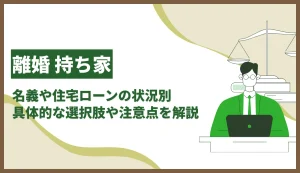
財産分与時の分配割合
財産分与の分配割合は、原則として夫婦の貢献度に応じて決められます。
一般的には「2分の1ずつ」が基本とされていますが、様々な要素で変動することがあります。
分配割合に影響する要素として、婚姻期間の長さ、各自の収入、家事・育児への貢献度などが考慮されます。
例えば、結婚生活が短い場合や、一方が浪費や借金を重ねていた場合は、均等分割から外れるケースもあるでしょう。
裁判所の判例では、専業主婦の場合でも家事や育児の貢献が認められ、多くの場合で2分の1の分与が認められています。
ただし、婚姻期間が極端に短いケースや特殊な事情がある場合は、割合が変わることもあります。

財産分与を行う方法
財産分与の方法には、主に以下の3つがあります。
- 現物分与:財産そのものを分ける方法(不動産や自動車など)
- 代償分与:財産評価額の一方の取り分を金銭で支払う方法
- 換価分与:財産を売却して現金化し、その代金を分ける方法
例えば、住宅ローン付きの自宅がある場合、次のような選択肢が考えられます。
一方が自宅に住み続け、その評価額の半分を相手に支払う(代償分与)。
自宅を売却して得た利益を分け合う(換価分与)。
財産分与の方法を決める際は、税金や手数料などのコストも考慮することが大切です。
特に不動産の名義変更には登録免許税や不動産取得税がかかる場合があります。
離婚時の財産分与は、将来の生活基盤を左右する重要な決断です。
感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが大切ですが、どうしても合意できない場合は専門家に相談しましょう。
離婚の際に決定する② 慰謝料
離婚を考える際、「慰謝料」という言葉をよく耳にするでしょう。
これは離婚の原因を作った配偶者から支払われる精神的損害の賠償金です。
ただし、慰謝料は離婚時に必ず発生するものではないため、正しい知識を持っておくことが大切です。
慰謝料について正しく理解し、離婚協議の際に適切な判断ができるようにしましょう。
離婚しても必ずもらえるとは言えない慰謝料
慰謝料は、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金です。
しかし、すべての離婚ケースで慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料が認められるのは、一方配偶者に「有責性」があると認められる場合に限られます。
具体的には、以下のような行為が慰謝料発生の原因となります。
- 不倫や浮気などの不貞行為
- 暴力やDV(ドメスティックバイオレンス)
- 生活費を渡さないなどの悪意ある遺棄
- アルコールや薬物依存などによる生活妨害
- 親族に対する虐待や暴言
一方で、性格の不一致や価値観の相違、すれ違いなどが原因の場合は、慰謝料は発生しないことが多いです。
また、双方に非がある場合や、有責性が明確でない場合も慰謝料は認められにくくなります。
離婚慰謝料を請求する際は、相手の有責行為と自分の精神的苦痛の因果関係を立証する必要があるため、証拠集めが重要です。
例えば、不貞行為の場合は、相手と不倫相手が会っていた証拠や交換したメッセージなどが有効でしょう。
DVや暴力の場合は、診断書や写真、音声録音などが証拠として活用できます。

離婚慰謝料が決まる基準と要素
慰謝料の金額は、法律で明確に定められているわけではありません。
一般的には以下の要素を考慮して個別に決められます。
| 考慮される要素 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 有責行為の内容と程度 | 不貞行為、暴力、生活費不払いなど | 行為が深刻なほど高額に |
| 婚姻期間 | 結婚していた年数 | 期間が長いほど高額になる傾向 |
| 当事者の社会的地位 | 職業や収入、社会的評価 | 地位が高いほど高額になる場合も |
| 子どもへの影響 | 子どもの有無や年齢、精神的影響 | 子どもへの悪影響が大きいと高額に |
| 慰謝料支払い能力 | 加害者の収入や資産状況 | 支払能力に応じて現実的な金額に |
慰謝料の相場は、不貞行為の場合で100万円〜300万円程度、DVの場合で200万円〜500万円程度とされています。
ただし、これはあくまで目安であり、個々のケースによって大きく異なることを理解しておきましょう。
相場より高額な慰謝料を請求するには、相手の行為が特に悪質であることや、精神的苦痛が通常より大きいことを証明する必要があります。
例えば、長期間にわたる不貞行為や、重大な健康被害を伴うDVなどが該当するでしょう。
慰謝料の支払方法は一括払いが原則ですが、支払能力などの事情により分割払いも可能です。
分割払いにする場合は、支払期間や各回の金額、遅延した場合の対応なども明確に取り決めておくことが重要です。
慰謝料請求権は、相手の不法行為を知った時から3年、または行為の時から20年で時効となるため、離婚時に一緒に決めておくことをおすすめします。
ただし、離婚時に取り決めがなくても、後から請求することは可能です。
慰謝料の話し合いは感情的になりやすい話題ですが、冷静に証拠や状況を整理し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが解決への近道です。

離婚の際に決定する③ 年金分割
離婚時に見落としがちだが将来の生活に大きな影響を与えるのが「年金分割」です。
年金は老後の重要な収入源となるため、適切な分割方法を決めておくことが大切です。
特に専業主婦(夫)だった方にとって、年金分割は老後の生活を左右する重要な問題です。

離婚後の経済基盤を支える年金分割とは
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金保険料を、離婚時に分け合う制度です。
2007年4月から施行されたこの制度は、特に収入の少なかった配偶者の老後を支える重要な仕組みとなっています。
年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)のみで、国民年金(基礎年金)は分割対象外です。
具体的には、会社員や公務員として働いていた期間に支払った厚生年金保険料に基づく年金受給権が分割の対象となります。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
| 種類 | 内容 | 分割割合 | 請求期限 |
|---|---|---|---|
| 合意分割 | 当事者間の合意や裁判所の決定に基づく分割 | 上限50%で自由に決定可能 | 離婚から2年以内 |
| 3号分割 | 第3号被保険者期間(専業主婦等)の自動分割 | 固定50% | 離婚から2年以内 |
合意分割では、夫婦の話し合いによって分割割合を決めることができます。
一方、3号分割は第3号被保険者(主に専業主婦・主夫)だった期間について、自動的に50%の分割が行われる制度です。
年金分割の手続きは日本年金機構で行いますが、離婚から2年以内に請求する必要があるため注意が必要です。
手続きに必要な書類は主に以下の通りです。
- 年金分割のための情報通知書
- 戸籍謄本(離婚の事実が記載されたもの)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 合意分割の場合は合意書または審判書・調停調書など
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
一度年金分割が行われると、将来受け取る年金額に反映されます。
つまり、分割を受けた側は将来もらえる年金が増え、分割した側は減ることになります。
年金分割の割合を離婚時に決める重要性
年金分割の割合は離婚時に正しく決めておくことが非常に重要です。
なぜなら、これが将来の老後生活を左右する大きな要素となるからです。
特に次のようなケースでは、年金分割について特に慎重に検討する必要があります。
- 長期間専業主婦(夫)だった場合
- 収入格差が大きかった夫婦の場合
- 結婚期間が長い場合
- 離婚時の年齢が高い場合
年金分割の請求権は離婚から2年で消滅するため、この期間内に必ず手続きを完了させる必要があります。
年金分割の割合を決める際は、まず「年金分割のための情報通知書」を入手しましょう。
これは日本年金機構に請求でき、婚姻期間中の双方の厚生年金記録が確認できる重要な資料です。
年金分割の割合は、財産分与や慰謝料などと合わせて総合的に検討するのが一般的です。
例えば、財産分与で多くを取得する代わりに年金分割の割合を低くするなどの調整が可能です。
また、年金分割は将来の年金受給権に影響するものであり、即時に現金が手に入るわけではないことも理解しておきましょう。
離婚時に50代以上の場合は特に、老後の生活設計を考えて年金分割を検討することが重要です。
年金分割は複雑な制度であるため、不明点がある場合は年金事務所や弁護士、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
適切な年金分割を行うことで、離婚後も安定した老後生活を送るための基盤を確保できるでしょう。
離婚の際に決定する④ 親権者
子どもがいる夫婦が離婚する場合、最も慎重に決めなければならないのが親権者です。
親権者の決定は子どもの将来に大きく影響するため、感情的にならず子どもの利益を第一に考える必要があります。
親権は単なる子どもの居住場所だけでなく、教育や医療、財産管理など広範囲に影響する重要な権利です。

親権者を決定するのは不可欠な離婚条件
親権とは、未成年の子どもを養育し保護するための法的な権利と責任を指します。
日本の民法では、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、必ず親権者を決めなければなりません。
親権には「身上監護権」と「財産管理権」の2つの権利が含まれています。
身上監護権は、子どもの居住場所の決定や教育方針、医療行為の同意など日常的な養育に関する権限です。
一方、財産管理権は子どもの財産を管理し、必要な法律行為を子どもに代わって行う権限を指します。
親権者は以下のような重要な決定を行う権限を持ちます。
- 子どもの住む場所の決定
- 教育機関の選択や教育方針の決定
- 医療行為への同意
- 子どもの財産の管理
- 子どもを代理しての契約や法律行為
- 子どもの国籍や姓に関する決定
日本の離婚届には親権者欄があり、ここに記入がないと離婚届は受理されません。
そのため、子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者の決定は避けて通れない問題です。
親権者の決定は、原則として夫婦の話し合いで決めますが、合意できない場合は家庭裁判所の調停や審判で決められます。
親権者を決める際には、子どもの年齢や性別、これまでの養育状況、両親の仕事や生活環境などが考慮されます。
単独親権か共同親権か離婚の際に決定しなければならない
日本の現行法では離婚後は単独親権しか認められていません。
つまり、どちらか一方だけが親権者になり、もう一方は親権を持たない「非親権者」となります。
単独親権制度での主な親権者の選定基準は以下の通りです。
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 継続性の原則 | これまで主に子育てをしてきた親が有利 |
| 子どもの意思 | 一定年齢以上(概ね10歳以上)の子どもの希望も考慮 |
| 経済的安定性 | 子どもを養育する経済力があるか |
| 養育環境 | 住居や時間的余裕、サポート体制など |
| 親としての適格性 | 精神的安定性や子どもへの愛情 |
日本では現在、法制審議会で共同親権制度の導入が検討されていますが、2025年3月現在はまだ実現していません。
一方、欧米諸国では離婚後の共同親権が一般的で、両親が協力して子育てする仕組みが整っています。
共同親権と単独親権のメリット・デメリットを比較してみましょう。
| 親権形態 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 単独親権 | ・決定が迅速にできる ・両親間の対立が少ない ・子どもの生活が安定する | ・非親権者との関係が希薄になりやすい ・片方の親の意見が反映されない ・子どもが罪悪感を持つことがある |
| 共同親権 | ・両親の意見が反映される ・子どもが両親との関係を維持できる ・親としての責任を共有できる | ・両親の対立が続くと子どもが板挟みになる ・決定に時間がかかる ・親同士のコミュニケーションが必須 |
現在の日本では法律上は単独親権しか選択できませんが、実質的に共同で子育てする「共同監護」の形を取ることは可能です。
例えば、親権は一方が持ちつつも、重要な決定は両親で話し合う取り決めを離婚協議書に明記するといった方法があります。
ただし、これには両親の協力関係が必要不可欠です。
親権争いは感情的になりやすい問題ですが、常に「子どもの最善の利益」を第一に考えて決定することが重要です。
必要に応じて家族問題に詳しい弁護士や家庭裁判所の調停制度を利用し、冷静な話し合いを心がけましょう。

離婚の際に決定する⑤ 面会交流
親権者が決まった後、次に取り決めるべき重要事項が「面会交流」です。
子どもが親権者と暮らすことになっても、もう一方の親との関係を継続することは子どもの健全な成長にとって大切です。
面会交流は離婚後の親子関係を維持するための重要な制度であり、子どもの福祉を考える上で欠かせない要素です。

面会交流は同居していない親と子どもが定期的に会える権利
面会交流とは、離婚後に子どもと別居することになった親が、定期的に子どもと会って交流する権利のことです。
この制度は子どもの健全な成長のために設けられたもので、単に親の希望を満たすためだけのものではありません。
面会交流は親の権利であると同時に子どもの権利でもあり、親子双方にとって重要な意味を持っています。
最高裁判所も「子どもの健全な成長のためには、別居している親との交流が重要」という立場を示しています。
面会交流には次のような重要な意義があります。
- 子どもが両親から愛されていると実感できる
- 子どもの「見捨てられ感」を軽減する
- 親子の絆を維持、強化できる
- 子どもの情緒の安定や自己肯定感の形成に寄与する
- 非監護親が養育費を支払う意欲を維持しやすい
ただし、DVや児童虐待があった場合など、子どもの福祉に反する事情がある場合は、面会交流が制限されたり禁止されたりすることもあります。
面会交流は直接会うだけでなく、電話やビデオ通話、手紙やメールなど様々な方法で行うことができます。
特に遠距離の場合は、オンラインでのコミュニケーションを活用することも効果的でしょう。
面会交流の頻度は子どもの年齢や生活環境などに応じて柔軟に設定するのが理想的です。
乳幼児期は短時間でも頻繁に、学齢期になれば長期の宿泊も含めた交流など、子どもの発達段階に合わせた対応が重要となります。
面会交流を離婚時に取り決めるべき事項
面会交流を円滑に進めるためには、離婚時に具体的な条件を取り決めておくことが大切です。
曖昧な取り決めは後のトラブルの原因となるため、できるだけ詳細に決めておきましょう。
| 取り決め項目 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 頻度と時間 | 月2回、第1・3土曜日の10時~17時など |
| 場所 | 自宅、公園、ファミリーレストラン、面会交流支援施設など |
| 送迎方法 | 誰がどこで子どもを引き渡し・受け取りするか |
| 宿泊の有無 | 宿泊の頻度、条件(年齢制限など) |
| 長期休暇の扱い | 夏休み、冬休みなどの特別な期間の面会交流 |
| 連絡方法 | 面会交流の日程調整や緊急時の連絡手段 |
| キャンセル時の対応 | 事前連絡の期限、代替日の設定方法 |
面会交流の取り決めは、必ず書面(離婚協議書や公正証書など)に残しておくことが重要です。
口頭での約束だけでは後に「言った・言わない」のトラブルになりかねません。
面会交流を実施する上で生じる費用(交通費、食事代、レジャー費用など)の負担についても明確にしておくと良いでしょう。
一般的には面会交流を希望する非監護親が負担するケースが多いですが、状況に応じて話し合いで決めます。
面会交流がうまくいかないケースでは、第三者の支援を利用する方法もあります。
- 家庭裁判所の調停、審判
- 面会交流支援団体の利用
- 弁護士や家族問題の専門家への相談
面会交流は子どもの権利を守るための制度ですが、実際には親同士の感情的対立が障害となることも少なくありません。
しかし、「子どもの最善の利益」を第一に考え、親としての責任を果たす姿勢が大切です。
子どもは両親の離婚によって心に傷を負うことが多いですが、両親との良好な関係を維持できれば、その傷を癒やし健全な成長を促すことができます。
面会交流は単なる「会う権利」ではなく、離婚後も親としての責任を果たし続ける重要な機会と捉えましょう。

離婚で決めること⑥ 養育費と婚姻費用
離婚時に子どもの将来に関わる重要な経済的取り決めとして「養育費」と「婚姻費用」があります。
これらは子どもの生活基盤を支える大切な要素であり、親としての責任を果たすために欠かせない項目です。
養育費と婚姻費用は似ているようで性質が異なります。
それぞれの特徴と取り決め方を見ていきましょう。

養育費について離婚時に決めておくべき事項
養育費とは、離婚後に子どもと同居しない親が、子どもの生活費や教育費として支払うお金のことです。
民法上、親は子どもが経済的に自立するまで養育の義務を負うとされています。
養育費は子どもの権利であり、親の都合で放棄したり免除したりすることはできません。
離婚時に養育費について取り決めるべき主な項目は以下の通りです。
| 取り決め項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月々いくら支払うか(基本月額) |
| 支払期間 | いつからいつまで支払うか(通常は成人まで) |
| 支払方法 | 振込先、支払日、振込手数料の負担者など |
| 増額事由 | 入学金や受験費用など特別な出費の扱い |
| 見直し条件 | 物価上昇や収入変化があった場合の対応 |
| 不払い対策 | 支払いが滞った場合の対応策 |
養育費の金額は、支払う側(非監護親)の収入と子どもの人数・年齢を基準に決められることが多いです。
裁判所が示す「養育費算定表」が参考になりますが、子どもの特別な事情(持病や障害など)がある場合は考慮する必要があります。
養育費の支払期間は、原則として子どもが経済的に自立するまでです。
一般的には「子どもが満20歳になるまで」としますが、大学進学の場合は卒業まで延長するケースも増えています。
養育費の不払いを防ぐためには、公正証書の作成や履行勧告制度、強制執行などの対策を講じておくことが重要です。
特に強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、不払いの際に裁判なしで差し押さえができるため有効です。
2021年に創設された「養育費不払い解消支援事業」も活用できます。
これは国が民間保証会社と連携し、養育費の立替払いと回収を行う制度で、経済的な安定につながります。
また、養育費は物価上昇や収入の変化に応じて見直せることも知っておきましょう。
子どもの成長に伴い教育費などが増える場合は、増額の交渉や調停申立てができます。

婚姻費用|離婚前に別居中の生活費をどうするか決める
婚姻費用とは、法律上の夫婦が別居している期間中に、経済力のある配偶者が相手の生活費として支払うべき費用です。
養育費と異なり、婚姻費用は離婚前(婚姻関係継続中)の期間だけに発生します。
別居中の生活は経済的に不安定になりがちですが、婚姻費用の請求権は民法第760条に定められている夫婦の権利です。
婚姻費用の額は主に以下の要素で決まります。
- 双方の収入と収入格差
- 婚姻中の生活水準
- 子どもの有無と人数
- 別居の原因(有責性の有無)
- 特別な出費(医療費など)の有無
婚姻費用の算定には裁判所の「婚姻費用算定表」が参考になりますが、具体的な金額は当事者の話し合いで決めるのが基本です。
例えば月収30万円の夫と収入のない妻、小学生の子ども1人の場合、婚姻費用は月額8〜10万円程度が目安となります。
婚姻費用と養育費の大きな違いは、婚姻費用には配偶者の生活費が含まれる点です。
離婚が成立したと同時に婚姻費用の支払義務は終了し、子どもがいる場合は養育費の支払いが始まります。
婚姻費用の取り決めには以下の項目が含まれるべきです。
| 取り決め項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月々の支払額 |
| 開始時期 | 別居日や請求した日から |
| 支払方法 | 振込先や支払日 |
| 臨時支出 | 医療費や教育費など特別な出費の扱い |
| 見直し条件 | 収入変化などがあった場合の対応 |
婚姻費用の支払いが滞った場合、調停や審判を申し立てることができます。
審判で決まった場合は、履行勧告や強制執行などの法的手段も利用可能です。
なお、婚姻費用と養育費は同時に受け取ることはできません。
離婚成立と同時に婚姻費用は終了し、子どもがいる場合は養育費に切り替わります。
別居から離婚までの期間が長期化する場合は、婚姻費用の取り決めは特に重要です。
経済的に困窮することなく離婚協議を進めるためにも、早めに婚姻費用について話し合いましょう。

よくある質問
離婚時に決めることについて、読者からよく寄せられる質問に回答します。
離婚の手続きや取り決めに関して不安や疑問を感じている方は、以下の内容を参考にしてください。
- 離婚する際、子ありの場合と子なしの場合で決めることに違いはありますか?
- 離婚前に準備しておくべき項目リストを教えてください。
- 協議離婚で決めることと調停離婚で決めることの違いはありますか?
- 離婚を決めた時に妻と話し合うべき内容は何ですか?
- 離婚の取り決めを公正証書にする際の注意点を教えてください。
- 離婚後の生活で困らないために事前にやるべきことは何ですか?
- 離婚する前に絶対にやってはいけないことはありますか?
まとめ
離婚時に決めることは多岐にわたりますが、主に6つの重要な条件があります。
「財産分与」では婚姻中に築いた財産の分配方法や割合を決めます。
「慰謝料」は離婚原因に有責性がある場合に発生する精神的損害の賠償です。
「年金分割」では老後の経済基盤となる厚生年金の分割割合を決定します。
子どもがいる場合は「親権者」「面会交流」「養育費」の3つが特に重要で、子どもの福祉を最優先に考える必要があります。
また別居中の生活を支える「婚姻費用」についても適切に取り決めておくことが大切です。
これらの条件は、口頭での約束だけでなく、書面に残して明確にしておくべきでしょう。
特に子どもがいる場合は、感情的にならず「子どもの最善の利益」を第一に考えた冷静な話し合いを心がけましょう。
離婚は新しい人生のスタートです。
将来に禍根を残さないよう、これらの重要事項をしっかりと決めておくことで、お互いが前向きに歩み出せる環境を整えましょう。