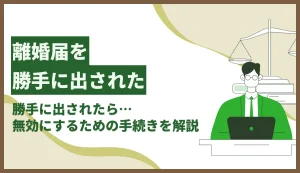離婚届の書き方|押さえておくべきポイント、注意点を解説

離婚届の書き方で悩んでいませんか?人生の大きな転機となる離婚手続きは、書類の記入ミスによって受理されないケースも少なくありません。
実際に窓口で「書き直してください」と言われてしまうと、精神的にも時間的にも大きな負担になってしまいます。
離婚届の書き方には、いくつかの重要なポイントがあります。
記入欄ごとの正しい書き方や注意点を知っておくことで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
離婚届の記入で特に気をつけたいのは、筆記用具の選び方から証人の署名まで、細かいルールが多い点です。
この記事では、離婚届の書き方について基本事項から実際の記入方法、よくある質問まで詳しく解説していきます。
初めて離婚届を書く方でも安心できるよう、各項目の記入例を交えながらわかりやすく説明します。
手続きがスムーズに進むよう、ぜひ最後までお読みください。
離婚届の書き方は?押さえておくべき基本事項
離婚届を提出する際には、いくつかの基本事項を押さえておく必要があります。
記入ミスがあると受理されないため、正しい書き方を知っておきましょう。
離婚届の書き方①:見やすくためしっかりと色が出る筆記用具を使用
離婚届を記入する際は、黒または青のボールペンを使いましょう。
鉛筆やシャープペンシルは消えやすいため使用できません。
役所で長期保存される重要書類なので、耐久性のある筆記用具で、はっきりと見やすい字で記入することが大切です。
特に記名・押印の部分は、公的な文書として証明力が求められるため、鮮明に記入しなければなりません。
万年筆やサインペンなども使用できますが、インクが滲まないように注意しましょう。
また、離婚届を記入する前に下書きを用意しておくと、本番で慌てずに済みます。
離婚届の書き方②:訂正する場合は二重線を引く
離婚届の記入中に間違えてしまった場合は、修正液や修正テープは使用できません。
訂正箇所には、間違えた部分に二重線を引き、その上または横に訂正印を押す方法で修正します。
訂正印は認印で構いませんが、シャチハタなどのスタンプ式印鑑は使用できないため注意が必要です。
特に氏名や生年月日などの重要事項は、正確に記入することを心がけましょう。
記入ミスが多いと書類の信頼性が下がり、審査に時間がかかる場合もあります。
離婚届の書き方③:協議離婚の際に当事者二人で記入する
協議離婚の場合、離婚届は夫婦二人で記入する必要があります。
代理人による記入や一方だけの記入では受理されないため、必ず夫婦揃って記入しましょう。
もし片方が入院中や遠方にいる場合でも、基本的には両者が記入・捺印する必要があります。
ただし、裁判離婚や調停離婚の場合は、確定判決や調停調書があれば、当事者の一方のみで届出が可能です。
どうしても二人で記入できない特別な事情がある場合は、事前に役所に相談することをおすすめします。

離婚届の書き方④:シャチハタ印はNGなので注意
離婚届に押す印鑑は、朱肉を使用する実印や認印を使わなければなりません。
シャチハタなどのスタンプ式印鑑は公的書類では使用できないので、必ず朱肉を使う印鑑を用意しましょう。
印鑑は夫婦それぞれが押印する箇所と、証人が押印する箇所があります。
実印でなくても構いませんが、印影がはっきりと出るものを選びましょう。
また、離婚届提出時に本人確認書類が必要になるため、運転免許証やパスポートなども忘れずに持参してください。
離婚届の書き方⑤:協議離婚の際には証人2名の署名捺印が求められる
協議離婚の場合、成人の証人2名の署名と捺印が必要です。
証人は両家の親族や友人など、夫婦の協議離婚の意思を証明できる人であれば誰でも構いません。
証人の条件としては、20歳以上であることのみが定められています。
ただし、証人は離婚の事実を第三者として証明する役割があるため、信頼できる人を選ぶことが望ましいでしょう。
証人欄には、証人の氏名と住所を記入し、それぞれが捺印する必要があります。
離婚届の提出前に、証人への依頼と署名捺印をもらう段取りも忘れずに行いましょう。
実際に離婚届を作成する際の注意点
離婚届には様々な記入欄がありますが、それぞれに正しい書き方があります。
ここでは、各項目ごとの正確な記入方法を解説していきます。
- 【令和〇年〇月〇日届出】届出日付は実際に提出した日を記入する
- 【○○長殿】夫婦の本籍地の市区村長宛に書く
- 【氏名】戸籍に登録されている氏名を書く
- 【生年月日】年号でも西暦でも記入可能
- 【住所】戸籍に記載されている通りの住所を記入する
- 【本籍】本籍と住所が異なる場合があるため確認を忘れずに
- 「父母の氏名」親が亡くなっていても必ず記入する必要がある
- 【続き柄】父母との関係を正確に書く
- 【離婚の種別】話し合いによる離婚は「協議離婚」にチェック
- 【婚姻前の氏にもどる者の本籍】旧姓に戻る人は記入を忘れずに
- 【未成年の子の氏名】親権を持つ方が子の名前を記入する
- 【同居の期間】覚えていない場合は大体の期間で問題ない
- 【別居する前の住所】別居している人だけ記入が必要
- 【別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業】国勢調査の年度だけ書く
- 【その他】養父母が父母の場合に記入
- 【届出人】夫婦の氏名を記入して捺印する
【令和〇年〇月〇日届出】届出日付は実際に提出した日を記入する
離婚届の日付欄には、実際に役所へ提出する日を記入します。
離婚が成立するのは役所に提出した日であり、記入した日ではありません。
事前に記入して持参する場合は、日付欄を空欄にしておき、窓口で記入するのがベストです。
もし日付を記入してから提出日が変わってしまった場合は、二重線で訂正し訂正印を押す必要があります。
年号は現在の「令和」を使用しますが、西暦で記入しても問題ありません。
【○○長殿】夫婦の本籍地の市区村長宛に書く
離婚届の宛先となる「○○長殿」の欄には、夫婦の本籍地がある市区町村の長の名前を記入します。
例えば東京都新宿区に本籍がある場合は「新宿区長殿」と記入します。
市区町村名だけで、個人の名前を書く必要はありません。
本籍地と現住所が異なる場合でも、必ず本籍地の市区町村長宛にします。
どこに提出するかわからない場合は、お住まいの市区町村役場で相談するとよいでしょう。
【氏名】戸籍に登録されている氏名を書く
氏名欄には、戸籍に記載されている通りの氏名を正確に記入します。
通称名やペンネームではなく、必ず戸籍上の正式な氏名を書きましょう。
旧字体(旧漢字)で登録されている場合は、そのまま旧字体で書く必要があります。
自分の戸籍上の正確な氏名がわからない場合は、事前に戸籍謄本を取得して確認しておくと安心です。
氏名の下には押印も必要になりますので、朱肉を使う印鑑も忘れずに用意しましょう。
【生年月日】年号でも西暦でも記入可能
生年月日は年号(明治、大正、昭和、平成、令和)でも西暦でも記入できます。
自分の生まれた年号を正確に把握していない場合は、西暦で記入するのが確実です。
年号と西暦の対応は以下の通りです。
| 明治 | 1868年〜1912年 |
|---|---|
| 大正 | 1912年〜1926年 |
| 昭和 | 1926年〜1989年 |
| 平成 | 1989年〜2019年 |
| 令和 | 2019年〜 |
月日は1桁の場合でも、「01月09日」のように0を付ける必要はなく「1月9日」と記入して構いません。
【住所】戸籍に記載されている通りの住所を記入する
住所欄には、現在実際に住んでいる住所を記入します。
住民票に記載されている住所を正確に書き、マンション名や部屋番号まで省略せずに記入してください。
「東京都」「大阪府」などの都道府県名から始めて、番地まで正確に記載しましょう。
引っ越したばかりで住民票の住所変更がまだの場合は、変更手続きを先に済ませるのが望ましいです。
ただし、DV被害などで住所を明かせない特別な事情がある場合は、事前に役所に相談することをおすすめします。
【本籍】本籍と住所が異なる場合があるため確認を忘れずに
本籍欄には、戸籍謄本に記載されている本籍地を記入します。
本籍と現住所は異なることが多いので、必ず戸籍謄本で確認してから記入しましょう。
都道府県名から始まり、市区町村名、番地までを正確に記載します。
特に引っ越しを何度もしている場合は、古い戸籍謄本では本籍地が現在と異なる可能性があるので注意が必要です。
最新の本籍地を確認したい場合は、本籍地のある市区町村役場で戸籍謄本を取得するとよいでしょう。
「父母の氏名」親が亡くなっていても必ず記入する必要がある
父母の氏名欄には、たとえ両親が既に亡くなっていても、必ず記入する必要があります。
亡くなった親の名前の横に「故」や「亡」などと書く必要はありません。
実の親だけでなく、養子縁組をしている場合は養父母の名前を記入します。
父母の名前がわからない場合は、戸籍謄本で確認しましょう。
特別な事情で父母の名前が戸籍に記載されていない場合は、その旨を記載するか窓口で相談するとよいでしょう。
【続き柄】父母との関係を正確に書く
続柄欄には、父母との関係を「長男」「長女」「二男」「二女」などと記入します。
養子縁組している場合は「養子」「養女」と記入するのが一般的です。
複雑な家族関係の場合は、戸籍謄本に記載されている続柄をそのまま転記すると確実です。
父母との続柄がわからない場合は、事前に戸籍謄本で確認しておきましょう。
正確な続柄を記入することで、戸籍の整合性が保たれます。
【離婚の種別】話し合いによる離婚は「協議離婚」にチェック
離婚の種別欄では、離婚に至った方法によって適切な項目にチェックを入れます。
夫婦間の話し合いで合意した離婚の場合は「協議離婚」にチェックを入れます。
他にも、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の選択肢があります。
調停や裁判所の判決による離婚の場合は、それに応じた書類の添付が必要になります。
チェックする欄を間違えると受理されないことがあるので、自分の離婚がどの種別に当たるか確認しておきましょう。

【婚姻前の氏にもどる者の本籍】旧姓に戻る人は記入を忘れずに
結婚で姓が変わった方が離婚後に婚姻前の姓に戻りたい場合、この欄の記入が必要です。
婚姻前の姓に戻る場合は、新しく作る戸籍の本籍地を記入します。
現在の姓を維持したい場合は、この欄は空欄のままで構いません。
婚姻前の姓に戻る手続きは離婚届と同時に行えるため、希望する場合は忘れずに記入しましょう。
本籍地は結婚前と同じ場所でも、新しい場所でも自由に設定できます。
【未成年の子の氏名】親権を持つ方が子の名前を記入する
未成年の子がいる場合、離婚届の該当欄に子どもの氏名と親権者を記入します。
子の氏名は戸籍に記載されている通りに正確に書き、親権者を決めて記入する必要があります。
子どもが複数いる場合は、それぞれについて記入欄を設け、すべての子について親権者を決めなければなりません。
親権者欄には「父」または「母」のいずれかを記入します。
共同親権が認められていない日本では、どちらか一方を親権者として選択する必要があることを覚えておきましょう。

【同居の期間】覚えていない場合は大体の期間で問題ない
同居期間の欄には、婚姻してから別居するまでの期間を記入します。
正確な日付がわからなくても、おおよその年数や期間を記入すれば問題ありません。
例えば「約5年」「3年6か月」などの書き方で構いません。
別居せずに離婚する場合は、婚姻期間をそのまま記入します。
この項目は統計調査のためのものなので、受理に影響するわけではないため、あまり神経質になる必要はありません。
【別居する前の住所】別居している人だけ記入が必要
離婚前に既に別居している場合、別居前に一緒に住んでいた住所を記入します。
別居していない場合は、この欄は記入不要です。
住所は都道府県名から始めて、できるだけ正確に記入しましょう。
ただし、マンション名や部屋番号までは必須ではありません。
この情報も統計調査のためのものなので、多少あいまいでも手続き自体には影響しません。
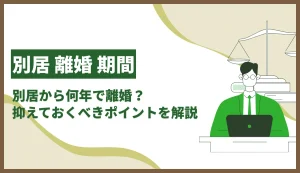
【別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業】国勢調査の年度だけ書く
この欄は国勢調査が行われる年(西暦末尾が0か5の年)に離婚する場合のみ記入します。
国勢調査の年でない場合は空欄でかまいません。
記入する場合は、世帯の主な収入源となる仕事と、夫婦それぞれの職業を具体的に書きます。
例えば「会社員」「公務員」「自営業(具体的な業種)」などと記入します。
特に正確さを求められる項目ではないので、一般的な職業名で記入して構いません。
【その他】養父母が父母の場合に記入
その他の欄は、特殊なケースにのみ記入が必要です。
主に養子縁組をしている場合や、特別な事情がある場合に使用します。
養父母がいる場合は、その旨を記載します。
通常は空欄で問題ありませんが、記入すべきか迷う場合は窓口で相談するのが確実です。
離婚に関して特記すべき事項がある場合も、この欄に記入することができます。
【届出人】夫婦の氏名を記入して捺印する
届出人欄には、離婚する夫婦の氏名を記入し、それぞれが捺印します。
協議離婚の場合は、必ず夫婦両方の署名と捺印が必要です。
印鑑は認印で構いませんが、シャチハタは使用できません。
裁判離婚や調停離婚の場合は、申立人のみの署名捺印でも受理されることがあります。
署名は自筆で行い、代筆は認められていないことに注意しましょう。
よくある質問
離婚届の書き方についてよく寄せられる質問をまとめました。
手続きをスムーズに進めるために参考にしてください。
- 離婚届の書き方の見本はどこで確認できますか?
- 離婚届に証人として署名する条件を教えてください。
- 女性が離婚届を書く際の注意点はありますか?
- 離婚後に新しい戸籍を作る方法を教えてください。
- 子供が2人いる場合の離婚届の書き方はどうなりますか?
- 離婚届はどこでダウンロードできますか?
- 離婚届の本人が記入するところはどこですか?
- 離婚届はどこまで書いて相手に渡せばいいですか?
- 同居の期間の書き方について教えてください。
- 外国人と離婚する場合の離婚届の書き方を教えてください。
まとめ
離婚届の書き方は、いくつかの基本ルールを押さえておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
記入には黒または青のボールペンを使用し、訂正する場合は二重線と訂正印が必要なことを忘れないようにしましょう。
協議離婚の場合は夫婦二人の署名捺印と成人の証人2名の署名捺印が必須です。
また、シャチハタ印は使用できないので注意が必要です。
各記入欄については、届出日や氏名、住所、本籍地など、戸籍に記載されている通りに正確に記入することが大切です。
特に子どもがいる場合は親権者の記入を忘れずに、また婚姻前の姓に戻りたい場合は該当欄への記入を必ず行いましょう。
離婚届の提出前に一度記入内容を確認し、不明点があれば役所の窓口で相談することをおすすめします。
正確な記入で、新しい生活への第一歩をスムーズに踏み出しましょう。