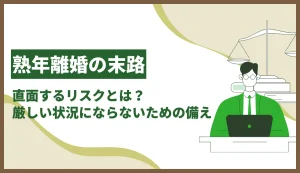熟年離婚の真実|増加する理由とメリット・デメリットを解説

「これからは自分らしく生きたい」「毎日顔を合わせるのが苦痛」……定年退職後の夫婦生活に不安を抱えていませんか?
最近では熟年離婚を選択するカップルが増加しており、この傾向は今後も続くと予想されています。
夫婦関係の悩みを抱えた方が熟年離婚について考える際、その原因や特徴、メリット・デメリットを理解することが重要です。
離婚は人生の大きな決断であり、特に長年連れ添った夫婦にとっては様々な問題が伴います。
熟年離婚の手続きや必要な準備、相談先についても知っておくことで、将来への不安を軽減できるでしょう。
熟年離婚について判断に迷っている方へ、客観的な情報と実用的なアドバイスをご提供します。
あなたの人生の次のステージを考える参考にしてください。
熟年離婚を引き起こす10の主な原因とは
熟年離婚は、長年連れ添った夫婦が人生の後半で別れを選択する現象です。
近年、その件数は増加傾向にあり、多くの中高年夫婦が直面する問題となっています。
なぜこれほど熟年離婚が増えているのでしょうか。
その背景には社会的要因から個人的な事情まで、様々な原因が絡み合っています。
団塊世代が定年退職の時期を迎えたから
熟年離婚の増加要因として、まず挙げられるのが団塊世代の定年退職です。
長い間、仕事中心の生活を送ってきた夫が突然家にいる時間が増えると、夫婦間の問題が表面化しやすくなります。
「定年退職後の夫在宅ストレス症候群」と呼ばれる現象が、熟年離婚の引き金になるケースも少なくありません。
妻からすれば「突然、知らない人が家にいる」という感覚で、長年築いてきた自分の生活リズムが乱されることに不満を抱くのです。
一方、夫も社会との接点を失い、家庭内での居場所を見つけられずにイライラを募らせることがあります。
こうした互いのストレスが蓄積され、最終的に別々の道を選ぶカップルが増えているのです。
2007年の年金制度改正が影響しているから
熟年離婚の増加には、2007年に施行された「年金分割制度」の影響も見逃せません。
この制度改正により、離婚時に夫の厚生年金を最大2分の1まで分け合うことが可能になりました。
それまでは経済的不安から離婚に踏み切れなかった専業主婦も、この制度によって離婚後の生活に一定の経済的保障を得られるようになったのです。
特に結婚期間が長い夫婦の場合、分割される年金額も相応のものとなり、離婚を現実的な選択肢として考える女性が増えました。
実際、この制度が導入された2007年以降、熟年離婚の件数は顕著に増加しています。
経済的自立の道が開かれたことで、不満を抱えながらも我慢して続けていた結婚生活に終止符を打つ決断をする人が増えたのです。
熟年離婚の認知度が以前より上がったから
熟年離婚という言葉自体の認知度向上も、離婚増加の一因となっています。
かつては「年を取ってから離婚するなんて」と否定的な見方が強かった社会の風潮が、徐々に変化してきました。
テレビドラマや新聞、雑誌などのメディアで熟年離婚がテーマとして取り上げられる機会が増え、「人生100年時代」において後半の人生を自分らしく生きる選択肢として認知されるようになったのです。
また、SNSの普及により離婚経験者のリアルな声に触れる機会も増えました。
「離婚後に新しい趣味を見つけて充実している」「精神的に楽になった」といったポジティブな体験談が共有されることで、離婚への心理的なハードルが下がっているのです。
社会全体が多様な生き方を認める方向に変化していることも、熟年離婚を後押しする要因となっています。
子どもの自立によって夫婦の役割が変化するから
子育てが終わり、子どもが独立すると、夫婦の関係性に大きな変化が訪れます。
それまで「親」としての役割に重きを置いていた関係から、再び「夫婦」としての関係が問われるようになるのです。
「子どものため」という共通目標を失った夫婦は、改めて二人の関係性と向き合うことになります。
そこで、長年抑え込んできた不満や違和感が表面化しやすくなるのです。
特に子育てに全精力を注いできた女性の場合、子どもの独立後に「これから何のために生きるのか」という喪失感や空虚感を抱くことがあります。
そんな時、夫との関係に満足できない場合、「残りの人生は自分のために生きたい」という思いから離婚を決断するケースもあるのです。
長年の結婚生活で価値観の相違が目立つようになるから
結婚当初は気にならなかった価値観の違いが、長い結婚生活の中で徐々に大きな溝となることがあります。
特に定年退職後は、一緒に過ごす時間が増えるため、その差異がより明確に表れやすくなります。
「老後の過ごし方」「お金の使い方」「家族との関わり方」など、さまざまな場面で価値観の不一致が表面化し、それが日常的な衝突につながるのです。
例えば、退職後の夫が「のんびり家で過ごしたい」と考える一方、妻は「旅行や趣味を充実させたい」と思っているケース。
また、親の介護に対する考え方の違いが夫婦間の亀裂を深めることもあります。
若い頃は仕事や子育てに追われて気づかなかった互いの本質的な価値観の違いが、時間的余裕ができた熟年期に表面化し、離婚の引き金になるのです。

退職金を離婚後の生活資金として考えるから
経済的な側面から熟年離婚を考える夫婦も少なくありません。
特に、夫の定年退職時に支給される退職金は、離婚を検討するタイミングに影響を与えることがあります。
退職金は夫婦の共有財産とみなされるため、離婚時の財産分与の対象となります。
そのため、「退職金が入ったタイミングで離婚すれば、まとまった資金を得られる」と考える配偶者もいるのです。
実際、熟年離婚の相談が増える時期は、ボーナスシーズンや退職金が支給される3月頃に集中する傾向があります。
また、退職金を元手に新生活をスタートさせたいという思いから、長年我慢してきた不満を爆発させ、離婚に踏み切るケースもあるのです。

離婚時の年金分割を期待しているから
先述した年金分割制度の導入は、熟年離婚の増加に大きく影響しています。
特に専業主婦として夫を支えてきた女性にとって、この制度は離婚後の生活を支える重要な経済的基盤となります。
年金分割制度により、最長20年間の婚姻期間中に夫が得た厚生年金の受給権の最大2分の1を妻が受け取れるようになりました。
長年家庭を支えてきた貢献が経済的に評価される仕組みができたことで、不満を抱えながらも経済的理由から我慢していた妻たちが離婚に踏み切りやすくなったのです。
「この制度がなければ離婚はできなかった」と語る女性は少なくありません。
熟年世代の女性の多くは、自身の年金受給額が少ないケースが多いため、年金分割制度の存在は離婚後の生活設計において大きな安心材料となっているのです。

介護負担が重く感じるから
高齢化社会において、親の介護問題が熟年夫婦の関係を悪化させるケースが増えています。
特に妻が夫の親の介護を担うケースでは、その負担から解放されたいという思いが離婚の動機になることがあります。
「介護離婚」と呼ばれるこの現象は、介護の長期化や負担の偏りによって引き起こされることが多いのです。
例えば、夫が親の介護に無関心で協力的でない場合、妻の疲労やストレスは蓄積される一方です。
また、義父母との同居によるストレスや、介護と自分の生活のバランスが取れないことへの不満も、離婚を考えるきっかけになります。
中には「自分の親の介護は自分でするべき」という考えから、パートナーの親の介護から解放されるために離婚を選択する人もいるのです。
配偶者の自己中心的な言動に耐えられなくなるから
長年の結婚生活で積み重なった小さな不満や傷つきが、ある時点で限界を迎えることがあります。
特に配偶者の自己中心的な言動は、熟年離婚の大きな引き金となっています。
「家事を一切しない」「自分の趣味にばかりお金を使う」「妻の意見を無視する」といった夫の態度に、長年我慢してきた妻が堪忍袋の緒を切らすケースは少なくありません。
子育て期間中は「子どものため」と我慢していた不満も、子どもの独立と共に表面化しやすくなります。
また、定年後に家にいる時間が増えた夫の命令口調や支配的な態度に反発する妻も多いのです。
「このままでは残りの人生が台無しになる」という危機感から、熟年になって初めて離婚を真剣に考え始める女性は増加傾向にあります。
配偶者の不貞行為が発覚するから
熟年離婚の決定的な引き金として、配偶者の浮気や不倫の発覚が挙げられます。
長年連れ添った夫婦であっても、パートナーの裏切りは関係修復が難しいダメージとなりえます。
特に熟年期における不貞行為は「これまでの人生を否定された」という深い傷つきを与えることが多く、離婚の直接的な原因となるケースが少なくありません。
また、定年後に時間的・経済的余裕ができたことで、それまで隠されていた浮気や二重生活が発覚するケースもあります。
携帯電話やSNSの普及により、以前より不貞行為が発覚しやすくなったことも、熟年離婚の増加につながっている一因です。
「老後は穏やかに過ごしたい」と考えていた矢先の裏切りは、取り返しのつかない亀裂を夫婦関係にもたらすことがあるのです。

熟年離婚が起こりやすい夫婦の6つの特徴
熟年離婚に至る夫婦には、いくつかの共通する特徴があります。
これらの特徴を知ることで、自分たちの関係を見つめ直すきっかけになるかもしれません。
また、離婚を考えている方にとっては、現在の状況を客観的に評価する手助けになるでしょう。
夫婦間での話し合いが少ない
熟年離婚に至りやすい夫婦の最も顕著な特徴は、コミュニケーション不足です。
長年の結婚生活の中で、次第に会話が減っていき、お互いの気持ちや考えを共有する機会が失われていきます。
「言わなくても分かるだろう」という思い込みが、実は夫婦間の大きな溝を作り出しているのです。
特に男性は感情表現が苦手な傾向があり、妻から「無口になった」「何を考えているか分からない」と指摘されるケースが多いようです。
また、日常的な会話が「今日の夕食は何?」「ゴミ出しした?」といった事務的なやりとりだけになっている夫婦も要注意です。
お互いの気持ちや考え、悩みを共有し合う時間を意識的に設けることが、熟年離婚を防ぐ第一歩となります。
お互いへの感謝の気持ちを表現しない
長年連れ添った夫婦ほど、相手への感謝の気持ちを口に出して伝えることが少なくなりがちです。
当たり前の日常が続く中で、パートナーの存在や行動に対する感謝の気持ちが薄れてしまうのです。
「ありがとう」「助かるよ」などの言葉を伝え合うことが、実は熟年夫婦の絆を強める重要な要素になります。
感謝の言葉が飛び交う家庭と、それが全くない家庭では、夫婦関係の満足度に大きな差が生じるでしょう。
特に家事や介護などの目に見えない労力に対する感謝の言葉が欠けると、「自分の存在が認められていない」という不満が積み重なります。
日々の小さなことでも感謝を伝え合うことで、長年の関係を再構築するきっかけになることもあるのです。
子どもが独立して親の介護が不要になった
子育てという共通の目標がなくなり、親の介護も終わると、夫婦だけの時間が急に増えます。
それまで「子どものため」「親のため」と我慢してきた不満が表面化しやすくなるのです。
熟年離婚の多くは、子どもの独立や親の看取りといった人生の節目に訪れることが統計からも明らかになっています。
「子育て」や「親の介護」という共通の目的がなくなった後、夫婦二人だけの関係を再構築できるかどうかが離婚の分かれ道となります。
特に子育てに全エネルギーを注いできた女性は、子どもの独立後に「夫との関係性の希薄さ」に気づくことが多いのです。
パートナーと新たな共通の趣味や目標を見つけることが、この時期の夫婦関係を守るカギとなるでしょう。
育児・家事・介護の負担を一方だけが抱えている
家庭内の負担が極端に偏っている夫婦は、熟年離婚のリスクが高まります。
特に妻が家事や育児、介護のほとんどを担い、夫がそれに無関心な場合、長年の不満が蓄積されやすいのです。
「自分ばかりが頑張っている」という不公平感は、熟年期に爆発するケースが少なくありません。
働き盛りの時期は、夫の仕事の忙しさを理解し我慢していた妻も、定年後に「家にいるのに家事を手伝わない」状況に強い不満を抱くことがあります。
また、親の介護負担が一方に集中することも、夫婦関係を悪化させる大きな要因です。
家庭内の仕事を公平に分担し、お互いの負担を理解し合える関係が、熟年期の夫婦関係を健全に保つための重要なポイントとなります。
配偶者に対して悪口を言うことが頻繁
パートナーの悪口を友人や家族に頻繁に話す夫婦は、離婚リスクが高いと言われています。
不満を直接相手に伝えず、第三者に愚痴をこぼす習慣は、夫婦関係をさらに悪化させる要因となります。
配偶者の悪口を言うことで、自分の中でもパートナーへの否定的なイメージが強化され、修復不可能な心理的距離が生まれてしまいます。
「夫は何もしない」「妻は文句ばかり」といった批判的な表現が日常化すると、お互いの良い面を見る余裕がなくなっていくのです。
また、子どもに親の悪口を聞かせることも、家庭環境を悪化させる原因となります。
不満があっても、まずは直接パートナーと建設的な対話を心がけることが、熟年離婚を防ぐためには大切です。

妻が経済的に自立している
女性の社会進出が進み、経済的に自立している妻が増えたことも、熟年離婚の増加要因となっています。
かつては経済的理由から離婚を諦めていた女性も、自身の収入や年金があれば、不満のある結婚生活に終止符を打つ選択ができるようになったのです。
「経済的な理由で我慢する必要がない」という状況は、女性にとって離婚という選択肢をより現実的なものにしています。
特に、子育てが終わり仕事に復帰した女性や、定年を迎えず働き続ける女性は、経済的自立度が高く、夫への依存度が低い傾向にあります。
また、前述した年金分割制度により、専業主婦であっても離婚後の経済的基盤が確保できるようになったことも影響しています。
経済的に対等な関係になった夫婦は、感情面での満足度がより重視されるようになり、その結果として不満足な関係に終止符を打つケースが増えているのです。
熟年離婚で得られるメリットとデメリット
熟年離婚を考える際には、その後の人生にどのような影響があるのかを冷静に考える必要があります。
離婚によって得られるメリットと失うものを天秤にかけることで、より賢明な判断ができるでしょう。
ここでは熟年離婚のメリットとデメリットを詳しく解説していきます。
- 熟年離婚のメリット
- 熟年離婚のデメリット
熟年離婚のメリット
長年の不満から解放されることで、新たな人生を歩み始める人も少なくありません。
熟年離婚にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
精神的な解放感を得られる
不満の多い結婚生活から抜け出すことで、多くの人が精神的な解放感を得ています。
「毎日顔を合わせるのがストレス」「言動に常に気を遣う」といった状況から解放されることで、心の余裕が生まれるのです。
特に夫婦関係が険悪な状態が長く続いていた場合、離婚後に「こんなに心が軽くなるとは思わなかった」と感じる人が多いようです。
自分の感情を抑え込む必要がなくなり、本来の自分を取り戻せるという点は大きなメリットと言えるでしょう。
また、離婚を決断すること自体が自分の人生を主体的に選び取る行為であり、自尊心の回復につながるケースも少なくありません。
「我慢」が当たり前だった日々から解放され、自分らしさを取り戻せることが熟年離婚の大きな魅力です。
自分の思い通りの生活が実現できる
熟年離婚のもう一つの大きなメリットは、自分のペースで生活できるようになることです。
食事の時間や内容、睡眠のリズム、家の掃除や整理の方法など、すべてを自分の好みで決められるようになります。
「もっと早くこうしていれば良かった」と、離婚後に自由な生活を満喫している人は意外と多いものです。
特に趣味や交友関係においても、パートナーの目を気にせず自分の好きなように過ごせるようになるのは大きな変化です。
旅行や習い事、ボランティア活動など、興味はあってもパートナーの理解が得られなかった活動にも自由に参加できるようになります。
「私のやりたいことを優先できる」という自由は、熟年期の新たな生きがいにつながることがあるのです。
配偶者の親族関係からも解放される
結婚生活では、パートナーの親族との付き合いが義務的になることがあります。
特に義父母との関係に悩んできた方にとって、その関係からの解放は大きなメリットになり得ます。
盆や正月などの親族行事への参加義務がなくなり、気を遣う相手が減ることで精神的な負担が軽減されます。
また、配偶者の親の介護問題から解放されることも、特に女性にとっては大きなメリットと感じる場合があります。
「嫁」としての役割から解放され、自分の親との関係に集中できるようになるのは、人生後半の大きな変化と言えるでしょう。
自分の時間やエネルギーを自分自身や実の家族のために使えるようになることは、多くの人にとって新たな人生の始まりとなります。
熟年離婚のデメリット
熟年離婚には多くのメリットがある一方で、見過ごせないデメリットも存在します。
決断する前に、以下のような問題点についても十分に検討する必要があるでしょう。
ひとりの生活で孤独を感じることがある
長年連れ添った相手と別れた後、一人暮らしの寂しさに直面する人は少なくありません。
特に定年退職後で社会との接点が減っている場合、その孤独感はより強まる傾向にあります。
「話し相手がいない」「体調が悪い時に誰も助けてくれない」といった不安を感じる人が多く、これが熟年離婚後の大きな課題となります。
夫婦関係に不満があっても、「誰かがそばにいる安心感」は意外と大きなものです。
また、家族や親族の集まりに一人で参加することへの心理的ハードルの高さも、多くの人が経験するデメリットです。
孤独対策として新たなコミュニティや趣味を見つけることが重要になりますが、高齢になるほどその難易度は上がります。
成人した子どもにも影響を与える
子どもが成人していても、両親の離婚は大きな心理的影響を与えることがあります。
特に結婚式や孫の誕生など、家族の行事の際に両親の不仲が表面化すると、子どもは板挟みになることがあります。
「どちらの親を優先すべきか」「両親を同時に招待できない」といった悩みを子どもに背負わせることになるのです。
また、熟年離婚の場合、子どもたち自身が親の介護や看取りについて考えなければならない時期と重なることもあります。
離婚によって両親がそれぞれ別々に住むようになれば、子どもの介護負担が倍増する可能性もあるでしょう。
子どもの立場や感情にも配慮した上で、離婚を検討することが大切です。
交友関係が狭まる可能性がある
熟年離婚後に予想外に直面するのが、交友関係の変化です。
長年夫婦で付き合ってきた共通の友人関係は、離婚によって変化することが少なくありません。
夫婦の友人は離婚後に「どちらと付き合うべきか」という選択を迫られ、自然と距離を置くようになるケースも多いのです。
特に男性は、家族を通じた地域コミュニティとのつながりを失いやすく、社会的に孤立するリスクが高まります。
一方、女性も「夫婦で招待される」行事から自然と外れていくことで社交の機会が減ることがあります。
離婚後の新たな人間関係構築は若い世代より難しい面があり、それが生活の質に大きく影響することを考慮する必要があるでしょう。
熟年離婚を決断する前に検討すべきポイント
熟年離婚を考える際には、感情だけでなく現実的な問題についても冷静に検討する必要があります。
特に経済面や住まい、将来の生活設計など、様々な角度から考えることが大切です。
ここでは、熟年離婚を決断する前に確認しておくべき重要なポイントを解説します。
- 離婚後の生活設計について考える
- 相手の財産状況を把握しておく
- 慰謝料請求の可能性を確認する
- 相手への感情を明らかに見つめ直す
離婚後の生活設計について考える
熟年離婚後の生活をどのように送るかは、決断の前に最も重要な検討事項です。
特に経済面、住居、健康管理について具体的なプランを立てておく必要があります。
離婚後の収入源(年金、就労収入、財産分与など)と支出のバランスを詳細に計算し、老後の生活が成り立つかどうかを確認しましょう。
住居については、現在の住まいに残るのか、新たに住まいを探すのかも大きな問題です。
家賃や住宅ローンの支払い能力、一人暮らしに適した環境かどうかも考慮する必要があります。
また、高齢になるにつれて健康面の不安も大きくなるため、一人で生活するための体力や健康状態も冷静に評価しておきましょう。
相手の財産状況を把握しておく
熟年離婚では、長年の結婚生活で築いた財産の分与が重要な問題となります。
離婚を考える前に、相手の財産状況を正確に把握しておくことが賢明です。
不動産、預貯金、保険、株式、退職金、年金など、すべての財産について情報を集め、財産分与の対象となるものを整理しておきましょう。
特に夫が家計を管理しているケースでは、妻が財産状況を正確に把握していないことも少なくありません。
銀行の通帳や不動産の権利書、保険証券などの確認が必要です。
また、配偶者が隠し財産を持っている可能性も考慮し、弁護士や専門家のアドバイスを受けることも検討すべきでしょう。
慰謝料請求の可能性を確認する
離婚に際して慰謝料請求が可能かどうかも確認しておくべき重要なポイントです。
特に配偶者に不貞行為や暴力などの明らかな落ち度がある場合は、慰謝料請求の権利が発生します。
慰謝料は単なる罰金ではなく、精神的苦痛に対する賠償という性質を持ちます。
そのため、証拠の収集と保管が非常に重要になります。
例えば不貞行為の場合、写真やメール、LINEのスクリーンショットなどの証拠が必要です。
DVやモラハラの場合は、診断書や日記、録音などが証拠になり得ます。
慰謝料請求を検討する場合は、早い段階で弁護士に相談し、適切な証拠収集の方法について助言を受けることをおすすめします。

相手への感情を明らかに見つめ直す
熟年離婚を考える際、一時的な感情ではなく本当に離婚が最善の選択なのかを冷静に見極めることが大切です。
長年の不満や怒りが蓄積している場合でも、パートナーに対する気持ちを改めて見つめ直してみましょう。
「本当に一緒にいることが苦痛なのか」「修復の可能性はないのか」「離婚後の人生をどう描いているのか」といった問いかけを自分自身にすることが重要です。
場合によっては、一時的な別居や夫婦カウンセリングを試してみるのも一つの方法です。
また、離婚の決断が感情的なものではなく、冷静な判断によるものであることを確認するため、友人や専門家に相談することも有益でしょう。
熟年期の離婚は人生の大きな転機となるため、後悔のない決断をするための十分な自己分析と冷静な判断が求められます。
熟年離婚を行う際の具体的な流れ
熟年離婚を決意した場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
離婚に至るまでの道のりは一つではなく、状況によって異なる選択肢があります。
ここでは、熟年離婚を進める際の一般的な流れと各ステップでの注意点を解説します。
まずは夫婦が話し合って協議離婚を進める
熟年離婚を考える場合、まず試みるべきなのは夫婦間での話し合い、すなわち協議離婚です。
これは最も円満で費用と時間がかからない離婚方法といえるでしょう。
協議離婚では、離婚の意思確認に加えて、財産分与、年金分割、慰謝料などの条件についても双方が合意する必要があります。
特に熟年期の場合、長年の結婚生活で築いた財産や将来の年金受給に関わる事項が多いため、慎重な協議が求められます。
話し合いがスムーズに進むよう、あらかじめ財産リストを作成したり、お互いの希望や条件を明確にしておくことが大切です。
合意に達した場合は「離婚届」と「離婚協議書」を作成します。
特に離婚協議書は将来のトラブル防止のため、公正証書にしておくことをおすすめします。
双方が納得した内容で離婚協議書を作成し、離婚届に署名・捺印して役所に提出すれば、協議離婚の手続きは完了です。

協議がまとまらない場合は離婚調停を申し立てる
夫婦間の話し合いでは合意に至らない場合、次の段階として家庭裁判所での離婚調停を検討します。
調停は裁判所という公的な場で第三者のサポートを受けながら話し合いを進める制度です。
離婚調停申立のやり方
離婚調停を申し立てるには、まず家庭裁判所に必要書類を提出します。
申立書の作成は自分で行うことも可能ですが、初めての場合は弁護士に相談することをおすすめします。
必要書類には「調停申立書」「戸籍謄本」「収入に関する資料」などがあり、申立手数料として収入印紙1,200円が必要です。
申立書には離婚を希望する理由や財産分与、年金分割などの希望条件を具体的に記載します。
特に熟年離婚の場合、年金分割や退職金、住居の問題など複雑な要素が多いため、弁護士のサポートを受けると安心です。
申立先は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、双方の合意があれば自分の住所地の裁判所でも可能です。
離婚調停の基本的な進め方
調停は通常、月に1回程度のペースで進められます。
調停委員2名と裁判官1名が中立的な立場から夫婦の話し合いを仲介し、合意形成を支援します。
調停の場では、申立人と相手方が別々の部屋で調停委員と話し、直接対面することはほとんどありません。
これは感情的な対立を避け、冷静な話し合いを促すためです。
調停委員は双方の主張を聞いた上で、妥当な解決策を提案してくれます。
熟年夫婦の場合、長年の結婚生活で蓄積された感情もあるため、第三者の客観的な視点が役立つことが多いでしょう。
離婚調停にかかる期間の目安
離婚調停の期間は、ケースによって大きく異なります。
比較的早く合意に達する場合もあれば、何ヶ月も続くケースもあるでしょう。
一般的には3〜6ヶ月程度かかることが多く、複雑な財産分与や年金分割の問題がある熟年離婚では、さらに長期化する傾向があります。
調停で双方が合意に達した場合は「調停調書」が作成され、これは裁判の判決と同等の効力を持ちます。
しかし、話し合いが平行線をたどり、合意が困難と判断された場合は「調停不成立」となります。
調停不成立の場合、次のステップとして離婚裁判を検討することになるでしょう。

調停不成立の場合は離婚裁判を申し立てる
調停でも合意に至らなかった場合、最終手段として離婚裁判(離婚訴訟)の提起を検討します。
裁判は法律に基づいた判断が下される場であり、当事者の合意がなくても裁判所の判決によって離婚が成立することがあります。
離婚裁判を起こすための条件
離婚裁判を提起するには、民法で定められた「離婚原因」が必要です。
単に「性格の不一致」という理由だけでは裁判で離婚が認められない場合があります。
法定の離婚原因には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、重度の精神疾患、その他婚姻を継続しがたい重大な事由などがあります。
熟年夫婦の場合、特に「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかが焦点になることが多いでしょう。
裁判所は夫婦関係が破綻しているかどうかを総合的に判断し、修復不可能と認められれば離婚が認められる可能性があります。
長期間の別居や夫婦間の会話の欠如、共同生活の実態がないことなどが破綻の証拠として重視されます。
離婚裁判の具体的な申立手続き
離婚裁判を起こすには、「訴状」の作成が必要です。
訴状には離婚を求める理由や財産分与、年金分割などの条件を詳細に記載します。
離婚裁判は専門的な法律知識が必要になるため、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
特に熟年離婚の場合、長年の結婚生活で蓄積された財産や年金の問題が複雑であることが多いため、専門家のサポートが不可欠です。
訴状の提出先は相手の住所地を管轄する家庭裁判所で、訴訟費用として収入印紙(訴額によって異なる)と郵便切手が必要です。
提出後、裁判所から相手方に訴状が送達され、審理日程が決まります。
離婚裁判の一般的な審理期間
離婚裁判にかかる期間は事案の複雑さによって大きく異なります。
単純な事案でも半年以上、複雑な財産分与や親権問題がある場合は1年以上かかることも珍しくありません。
熟年離婚の場合、長期間の結婚生活における財産形成や年金分割の問題が複雑なため、裁判が長期化する傾向があります。
裁判の過程では、証人尋問や本人尋問などが行われ、必要に応じて証拠書類の提出が求められます。
審理の結果、裁判所が離婚を認める場合は判決が下され、判決確定後に離婚が成立します。
なお、裁判中でも当事者間で合意に達した場合は「和解」により離婚が成立する可能性もあるため、柔軟な姿勢を持つことも大切です。

熟年離婚で悩んだ時の相談先
熟年離婚を考える際、一人で悩みを抱え込まずに専門家に相談することで、より適切な判断ができるようになります。
特に長年連れ添った夫婦の離婚は、法律的な問題だけでなく感情面でも複雑な側面を持つため、適切なサポートを受けることが大切です。
ここでは、熟年離婚で悩んだ時に頼れる主な相談先とその特徴を紹介します。
- 専門的なアドバイスが受けられる離婚カウンセラー
- 離婚問題の対応経験が豊富な弁護士
専門的なアドバイスが受けられる離婚カウンセラー
離婚カウンセラーは、離婚に関する心理面のサポートを専門とする相談相手です。
特に熟年期の離婚は感情的な葛藤が大きいため、カウンセリングを受けることで心の整理がつくことがあります。
カウンセラーは中立的な立場から話を聞き、冷静な判断ができるようサポートしてくれるため、感情的になりがちな時期に客観的な視点を得られる点が大きなメリットです。
「本当に離婚すべきか迷っている」「離婚後の生活に不安がある」といった悩みを抱えている方におすすめの相談先といえるでしょう。
カウンセリングは個別セッションだけでなく、夫婦カウンセリングという形で受けることも可能です。
第三者の介入によって冷静な話し合いができ、関係修復のきっかけになることもあります。
料金は一般的に1回5,000円〜10,000円程度で、完全予約制の場合が多いため、事前に電話やメールで問い合わせることをおすすめします。

離婚問題の対応経験が豊富な弁護士
熟年離婚では、長年の結婚生活で形成された財産分与や年金分割など、法律的に複雑な問題が多く発生します。
こうした問題を適切に解決するには、離婚問題に詳しい弁護士への相談が効果的です。
特に熟年離婚に強い弁護士は、年金分割制度や退職金の扱い、住宅ローンの問題など、高齢者特有の法律問題に詳しいため、より的確なアドバイスが期待できます。
弁護士に相談することで得られるメリットは多岐にわたります。
離婚条件の交渉、必要書類の作成サポート、離婚調停や裁判での代理人としての活動など、専門的な支援を受けられるのです。
特に相手方と対立関係にある場合や、DV・モラハラなどの問題がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士への相談料は初回無料の事務所もありますが、一般的には30分5,000円〜10,000円程度が相場です。
依頼する場合の着手金は20万円〜30万円程度、成功報酬として解決金額の10〜20%程度が一般的な費用となります。
費用面で心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談や、自治体が提供する無料法律相談などの公的サービスを利用するという選択肢もあります。
熟年離婚は人生の大きな転機となるため、専門家のサポートを受けながら、後悔のない選択をすることが大切です。

よくある質問
熟年離婚について、多くの方が疑問に思われることをQ&A形式でまとめました。
離婚を検討する際の参考にしてください。
- 熟年離婚の主な原因は何ですか?
- 熟年離婚とは具体的に何歳くらいの離婚を指すのですか?
- 熟年離婚における財産分与の割合はどのくらいですか?
- 熟年離婚をする場合、弁護士に相談するべきですか?
- 熟年離婚の準備として何をしておくべきですか?
- 熟年離婚をされる妻の特徴を教えてください。
- 熟年離婚後の女性の生活はどのようになりますか?
- 熟年離婚における年金分割について教えてください。
- 子供が独立している場合の熟年離婚の問題点は何ですか?
- 夫から突然熟年離婚を切り出された場合の対処法を教えてください。
- 熟年離婚後の老後の生活費はどうなりますか?
- 別居中でも熟年離婚は成立しますか?
- 熟年離婚にかかる費用やお金の問題について教えてください。
まとめ
熟年離婚は、長年連れ添った夫婦が人生の後半で新たな選択をする重要な決断です。
その背景には、定年退職による夫婦関係の変化、子どもの独立、年金制度の改正など、様々な社会的・個人的要因があります。
熟年離婚を考える際には、精神的な解放感や自分らしい生活の実現というメリットと、孤独感や経済的不安などのデメリットを冷静に比較することが大切です。
特に経済面では、財産分与や年金分割など、将来の生活に直結する問題について十分な知識を持ち、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
離婚の手続きは協議離婚から始まり、合意できない場合は調停、さらには裁判へと進みますが、どの段階でも冷静な判断と適切な準備が必要です。
熟年離婚は単なる結婚生活の終わりではなく、人生の新たなスタートと捉えることができます。
自分らしく充実した後半生を送るための選択として、十分な情報収集と準備をした上で決断することが、後悔のない未来につながるでしょう。