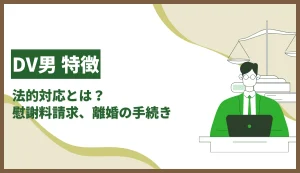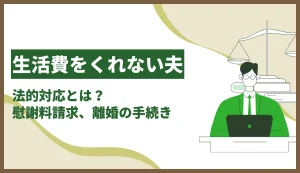接近禁止命令とは?警察に相談する方法と申立ての流れを解説

身近な人からの度重なる嫌がらせや脅迫に悩まされていませんか?
接近禁止命令は、あなたの安全を守るための重要な法的手段です。
警察に相談して接近禁止命令を申し立てることで、加害者が接近することを法的に禁止できます。
しかし、「具体的にどうやって警察に相談すればいいの?」「接近禁止命令を出すための条件は?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、接近禁止命令の仕組みから警察への相談方法、申立ての流れまで詳しく解説していきます。
不安な状況にある方でも理解しやすいよう、一つひとつ丁寧に説明しています。
あなたの安全を守るために必要な情報を、ぜひ最後までご覧ください。
接近禁止命令とは?その具体的な内容と効果
接近禁止命令は、あなたを脅かす相手からの危害を防ぐための法的手段です。
DV (ドメスティックバイオレンス) やストーカー行為に悩まされている方を守るために、裁判所が相手に対して出す命令になります。
警察に相談することで接近禁止命令の申立てへとつながり、あなたの安全を法的に守ることができるのです。
接近禁止命令が発令されると、加害者はあなたに近づくことが法律で禁じられ、違反した場合は刑事罰の対象となります。
禁止対象となる2つの行為
接近禁止命令で禁止される行為は主に2つあります。
1つ目は「被害者への接近の禁止」で、加害者があなたに物理的に近づくことを禁じるものです。
一般的に指定される距離は100メートル以内とされており、この距離内に加害者が入ることは違法行為となります。
これにより、自宅や職場、よく行く場所でも安心して過ごせるようになります。
2つ目は「つきまとい等の禁止」で、電話やメール、SNSなどを通じた接触も禁止されます。
加害者からの連絡や監視行為、贈り物の送付なども禁止対象となるため、精神的な嫌がらせからも解放されます。
| 禁止される行為 | 具体例 |
|---|---|
| 被害者への接近 | 自宅、職場、通学路などへの訪問や待ち伏せ |
| つきまとい等 | 電話、メール、SNS、手紙などでの連絡、監視行為、贈り物の送付 |
警察への相談時に、どのような行為に悩まされているのかを具体的に伝えることで、適切な対応策を講じてもらえます。
接近禁止命令では十分に対応できない場合(他に取るべき手段)
接近禁止命令だけでは安全を確保できないケースもあります。
例えば、加害者が命令を無視する可能性が高い場合や、すでに深刻な暴力を振るっている場合は追加措置が必要でしょう。
接近禁止命令と併せて検討すべき対策としては、警察への「身辺警戒」の依頼が挙げられます。
これにより、警察がパトロールの頻度を増やしたり、緊急時の対応を迅速化したりする体制を整えてくれます。
また、安全な避難所や緊急時の連絡先を確保しておくことも大切です。
- DV被害者支援センターへの相談
- シェルターなどの一時避難施設の利用
- 弁護士への相談による法的保護の強化
- 住民基本台帳の閲覧制限申請
- 引っ越しや転職などの生活環境の変更
警察に相談する際には、これらの追加措置についても相談してみるといいでしょう。
万が一の事態に備えて、複数の対策を組み合わせることが安全確保には欠かせません。
期待される効果
接近禁止命令を申し立てると、どのような効果が期待できるのでしょうか。
まず、最も大きな効果は「物理的な安全の確保」です。
加害者があなたに近づくことが法的に禁止されるため、直接的な危害を防ぐことができます。
また、警察への通報がしやすくなるという心理的な安心感も得られます。
接近禁止命令がある状態で加害者が接近してきた場合、迷わず警察に通報できますよね。
さらに、加害者に対して「被害者を守る法的枠組みが存在する」という強いメッセージを送ることになります。
これにより、多くの場合、加害者は接触を諦めて行動を改めることが期待できるのです。
| 期待される効果 | 内容 |
|---|---|
| 物理的安全の確保 | 加害者からの直接的な危害を防止できる |
| 精神的安心感 | 連絡や監視行為からの解放、警察に通報しやすくなる |
| 加害者への抑止効果 | 法的措置があることで行動を自制するようになる |
| 社会的サポートの獲得 | 職場や学校などでの理解と協力を得やすくなる |
接近禁止命令は単なる紙切れではなく、あなたの安全を守るための強力な道具になります。
違反した場合に課せられる罰則
接近禁止命令に違反した場合、加害者には厳しい罰則が待っています。
接近禁止命令違反は刑事罰の対象となり、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。
これは軽い罪ではなく、前科がつく深刻な犯罪として扱われます。
また、違反行為があった場合は逮捕される可能性も高く、警察は積極的に介入します。
繰り返し違反する場合はさらに重い処罰を受けることもあるでしょう。
こうした厳しい罰則があることで、多くの加害者は接近禁止命令を遵守するようになります。
もし接近禁止命令に違反する行為を見つけたら、すぐに警察に通報しましょう。
- 証拠(写真や動画、メッセージなど) があれば保存しておく
- 違反の日時や場所を記録しておく
- 目撃者がいれば連絡先を確認しておく
- 安全を確保した上で警察に通報する
ただし、違反を発見しても自分で対応せず、必ず警察に通報することが最も安全な方法です。

接近禁止命令を申し立てができる対象者
接近禁止命令を申し立てられるのは、誰に対してでも可能というわけではありません。
申立ての対象となるのは主に以下の関係性にある人物です。
最も一般的なのは「配偶者からの暴力」に関するケースで、現在の配偶者や元配偶者が対象となります。
法律婚だけでなく、事実婚(内縁関係)のパートナーに対しても申立ては可能です。
また、生活の本拠を共にする交際相手 (同棲している恋人など) も対象になります。
さらに、ストーカー規制法に基づく場合は、交際相手や元交際相手、知人、同僚なども対象になり得ます。
| 対象者 | 法的根拠 |
|---|---|
| 配偶者(現在・元) | DV防止法 |
| 事実婚パートナー(現在・元) | DV防止法 |
| 同居中の交際相手 | DV防止法 |
| 恋人・元恋人(同居なし) | ストーカー規制法 |
| 知人・同僚・他人 | ストーカー規制法 |
ただし、親子間や兄弟姉妹間のトラブルには、原則としてDV防止法に基づく接近禁止命令は適用されません。
これらの関係性の場合は、別の法的手段(例:保護命令など) を検討する必要があるでしょう。
警察に相談する際は、加害者との関係性を明確に伝え、どの法律に基づいて保護を求めるべきか相談するといいでしょう。
なお、未成年者が被害者の場合でも、親権者などを通じて申立てが可能です。
自分が対象者に該当するか迷ったら、まずは警察や配偶者暴力相談支援センターに相談してみましょう。

接近禁止命令を行う4つのステップ
接近禁止命令を取得するには、順を追って手続きを進める必要があります。
ここでは警察への相談から発令までの流れを4つのステップで解説します。
これから各ステップについて詳しく見ていきましょう。
1.配偶者暴力相談支援センター又は警察に連絡(DVの場合)
接近禁止命令の最初のステップは、専門機関への相談です。
DV被害の場合、まずは「配偶者暴力相談支援センター」または「警察」に連絡しましょう。
ストーカー被害の場合は、直接警察に相談するのが一般的です。
相談の際は、被害の内容をできるだけ具体的に伝えることが大切です。
いつ、どこで、どのような暴力や嫌がらせを受けたのか、時系列でメモしておくとスムーズです。
また、証拠となる写真や録音、メッセージなどがあれば、それらも準備しておきましょう。
- 配偶者暴力相談支援センター:各都道府県に設置 (無料相談可能)
- 警察:最寄りの警察署または「#9110」(警察相談専用電話)
- DV相談ナビ:「#8008」(最寄りの相談窓口に繋がる)
相談を受けた機関では、あなたの状況を確認し、接近禁止命令が適切かどうかを判断します。
緊急性が高い場合は、ためらわずに110番通報してください。あなたの安全が最優先です。

2.接近禁止命令を申立てる
相談後、接近禁止命令が必要と判断されれば、裁判所への申立てを行います。
申立ては、加害者の住所地または申立人(被害者)の住所地を管轄する地方裁判所で行います。
裁判所に行く前に、必要書類を準備しておくことが重要です。
警察や配偶者暴力相談支援センターでは、申立ての際の助言や必要書類の説明をしてくれます。
また、弁護士に相談するとよりスムーズに手続きを進められることも多いでしょう。
申立てに必要書類
接近禁止命令の申立てに必要な書類は以下の通りです。
- 保護命令申立書(裁判所で入手可能)
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 申立書付属書類(被害の状況を記載)
- 配偶者暴力相談支援センターや警察での相談証明書
- 戸籍謄本または配偶者関係を証明する書類
- その他証拠資料(診断書、写真、メッセージのスクリーンショットなど)
書類の準備は大変かもしれませんが、充実した証拠資料があると申立ての成功率が高まります。
申立てにかかる費用
接近禁止命令の申立てにかかる費用は以下のとおりです。
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 1,000円 |
| 郵便切手代 | 数百円程度(裁判所により異なる) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 450円程度/通 |
| 弁護士に依頼する場合の費用 | 10万円~30万円程度 |
経済的に困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。
また、DV被害者支援団体などでも費用面での相談に乗ってくれる場合があります。
3.口頭弁論・審問を行う
申立てが受理されると、裁判所で審問が行われます。
審問では、裁判官があなた(申立人)から直接話を聞き、提出された証拠を検討します。
基本的に、加害者(相手方)も呼び出され、反論の機会が与えられます。
ただし、緊急性が高い場合は、相手方を呼ばずに審問が行われることもあります。
審問では、被害の内容や危険性について具体的に説明することが求められます。
感情的になりすぎず、事実に基づいて冷静に話すことが大切です。
弁護士がいれば、適切なサポートを受けながら審問に臨めるでしょう。
相手方と同じ場所で顔を合わせたくない場合は、事前に裁判所に伝えると配慮してもらえる場合があります。
4.接近禁止命令が発令される
審問の結果、裁判所が接近禁止命令の必要性を認めると、命令が発令されます。
発令されると「保護命令書」が作成され、申立人と相手方の双方に送達されます。
また、命令の内容は警察にも通知され、警察は命令の履行を確保するために必要な措置を取ります。
接近禁止命令は、相手方に命令が伝達された時点から効力を発します。
有効期間は原則として6ヶ月間ですが、状況によっては延長することも可能です。
接近禁止命令が発令されたら、命令書のコピーを常に携帯しておくと良いでしょう。
もし相手が命令に違反して接近してきた場合は、すぐに警察に通報してください。
| 手続きの流れ | 所要期間の目安 |
|---|---|
| 相談から申立てまで | 数日~数週間 |
| 申立てから審問まで | 1週間~1ヶ月程度 |
| 審問から発令まで | 数日~1週間程度 |
| 発令から効力発生まで | 相手方への送達時(即時) |
なお、緊急性が特に高い場合は、審問を経ずに「緊急保護命令」が発令されることもあります。
接近禁止命令に関して押さえておくべき4つのポイント
接近禁止命令は万能ではなく、いくつか知っておくべき重要なポイントがあります。
これから、実際に申立てを検討している方が押さえておくべき4つの注意点を解説します。
1.接近禁止命令が出されないケースがある
すべての申立てが認められるわけではありません。
接近禁止命令が出されないケースとして多いのは、「危険性の証明が不十分」な場合です。
裁判所は、あなたが身体的暴力や生命の危険にさらされる恐れがあるかを重視します。
単なる口論や一度きりの軽微なトラブルでは、命令が出されないことが多いでしょう。
また、暴力やストーカー行為の証拠が乏しい場合も、命令が認められにくくなります。
そのため、警察への相談記録や診断書、メッセージの記録など、できるだけ多くの証拠を集めることが大切です。
- 発生した暴力やストーカー行為の日時と内容を記録しておく
- 写真や録音、メッセージなどの証拠を保存する
- 医師の診断書や警察への相談記録を取得する
- 目撃者がいれば証言を依頼する
証拠集めが難しい場合は、専門家(弁護士やDV支援団体)に相談するのがおすすめです。
2.相手が命令に従わない場合もある
残念ながら、接近禁止命令が出されても相手が従わないケースも存在します。
命令違反には罰則があるものの、それが完全な抑止力になるとは限りません。
特に精神的に不安定な相手や、強い執着心を持つ相手は命令を無視する可能性があります。
そのため、接近禁止命令を取得した後も、自分の安全を守るための対策を継続することが重要です。
日常の行動パターンを変える、信頼できる人に状況を伝えておく、防犯カメラを設置するなどの対策も検討しましょう。
また、スマートフォンには緊急時にすぐ通報できるアプリをインストールしておくのも良い方法です。
命令違反を発見したら、自分で対応せず、すぐに警察に通報してください。
3.街中で偶然会っただけでは罪にならない
接近禁止命令があっても、街中での偶然の遭遇が全て違反になるわけではありません。
命令違反と認められるのは、相手が「意図的に」接近した場合に限られます。
例えば、スーパーで偶然鉢合わせした程度では違反にならないことがほとんどです。
ただし、相手がその後もあなたを追いかけたり、接触を試みたりすれば明らかな違反となります。
偶然の遭遇か意図的な接近かの判断は、状況や前後関係によって大きく変わります。
不安な場合は、その場を離れて安全な場所に移動し、必要に応じて警察に相談しましょう。
| 状況 | 命令違反になるか |
|---|---|
| 駅やスーパーで偶然鉢合わせした | 通常は違反にならない |
| 偶然会った後、追いかけられた | 違反になる可能性が高い |
| 相手が頻繁に利用するとわかっている場所に行った | 被害者側の責任は問われない |
| 同じイベントに相手がいた | 意図的でなければ違反にならない |
偶然の遭遇が繰り返される場合は、パターンを記録しておくと良いでしょう。
4.発令後に時間を要する場合がある
接近禁止命令が発令されても、すぐに効力が生じるわけではない場合があります。
命令の効力は「相手方に命令が送達された時点」から発生します。
相手の所在が不明だったり、送達を意図的に避けたりする場合、効力発生までに時間がかかることも。
送達までの間は法的な保護が完全ではないため、この期間も自己防衛を怠らないようにしましょう。
また、命令の内容が警察に通知されるまでにも若干の時間差が生じることがあります。
発令後は、最寄りの警察署に自分から命令の内容を伝えておくと安心です。
命令書のコピーを携帯しておくと、緊急時に警察への説明がスムーズになります。
発令から送達までの期間は特に注意が必要です。
警察と連絡を密にしておきましょう。
接近禁止命令を延長するためにはもう一度申立てをしなければならない
接近禁止命令は一度発令されても、効力が永続するわけではありません。
通常、命令の有効期間は6ヶ月とされており、それ以降も保護が必要な場合は延長手続きが必要です。
接近禁止命令の延長は、自動的に行われるものではなく、被害者側から再度申立てを行う必要があります。
延長が認められるには、引き続き危険性が存在することを証明しなければなりません。
申立てが可能なケース
接近禁止命令の延長が認められるケースには、いくつかのパターンがあります。
最も一般的なのは、「相手が依然として危険な行動を示している」または「再び危害を加える可能性が高い」と判断できる場合です。
例えば、相手が第三者を通じてあなたに接触を試みている場合や、あなたの周辺をうろついているという情報がある場合などが当てはまります。
また、命令期間中に違反行為があった場合は、延長が認められる可能性が高くなります。
さらに、相手が反省の態度を示さず、むしろ敵意を強めているような発言をしている場合も延長の理由となるでしょう。
ただし、単に「不安だから」という理由だけでは、延長が認められない可能性があります。
- 命令期間中に相手が違反行為を行った
- 第三者を通じて接触を試みている
- SNSなどであなたに関する投稿をしている
- 周囲の人にあなたについて執拗に質問している
- 以前の暴力やストーカー行為が特に重大だった
延長を検討する際は、期間満了の1ヶ月前くらいから準備を始めるのが理想的です。
延長申立てを行う方法
延長申立ての手続きは、基本的に初回の申立てと同様です。
延長申立ては、現在の命令が失効する前に行うことが重要です。
理想的には、期間満了の2週間〜1ヶ月前には申立てを済ませておくべきでしょう。
申立ては、最初の命令を出した裁判所で行います。
- 裁判所に延長申立ての意向を伝える
- 必要書類を準備する
- 裁判所に申立て書類を提出する
- 審問に出席する
- 延長の決定を待つ
延長申立ても、初回と同様に裁判所での審問が行われます。
延長が必要な理由や、現在も危険が続いていることを具体的に説明できるよう準備しておきましょう。
もし期限切れ間際になって申立てを行う場合は、その旨を裁判所に伝え、対応を急いでもらえるよう相談しましょう。
延長申立てに必要な書類
延長申立てに必要な書類は、初回の申立てとほぼ同じですが、いくつか追加される項目もあります。
延長申立ての際に特に重要なのは、「延長が必要な理由を示す証拠」です。
- 保護命令延長申立書(裁判所で入手可能)
- 現在の保護命令書のコピー
- 延長が必要な理由を記載した陳述書
- 命令期間中の出来事を記録した日記やメモ
- 警察への相談記録(命令期間中にあれば)
- 相手からの接触の証拠(存在する場合)
- 収入印紙(1,000円)と郵便切手
特に重要なのは、命令期間中の相手の行動を記録しておくことです。
例えば、不審な電話がかかってきた、知人から相手があなたのことを聞いていたと報告があったなど、小さなことでも記録しておきましょう。
| 記録しておくべき事項 | 記録の方法 |
|---|---|
| 不審な接触の試み | 日時、場所、状況を詳細に記録 |
| 第三者を介した接触 | 誰を通じて、どのような接触があったか |
| SNSでの言及 | スクリーンショットを保存 |
| 周辺での目撃情報 | 目撃者の証言を書面にしてもらう |
| 脅迫的な言動 | 具体的な内容と日時を記録 |
延長申立ては、最初の申立てよりも証拠集めが難しい場合もあります。
そのため、命令期間中からこまめに記録を取っておくことが大切です。
延長が認められた場合も、通常は6ヶ月間の効力となります。
さらに延長が必要な場合は同様の手続きが必要です。
接近禁止命令は取り消すことができる
接近禁止命令は一度発令されたら必ず期間満了まで続くわけではありません。
状況の変化により、命令を取り消すことも可能です。
取消しの申立ては、申立人(被害者)側からも、相手方(加害者)側からも行うことができます。
ただし、それぞれのケースで申立ての理由や手続きが異なります。
相手側が取消しを申立てる場合
接近禁止命令を受けた相手方が取消しを申し立てるケースは少なくありません。
相手方が取消しを申し立てる場合、「命令の必要性がなくなった」ことを証明する必要があります。
例えば、暴力的な行動が反省されたこと、カウンセリングを受けていること、生活環境や状況が大きく変わったことなどが挙げられます。
ただし、裁判所は被害者の安全を第一に考えるため、相手方からの取消申立てが認められるハードルは高いです。
裁判所は申立人(被害者)の意見も聞き、取消しによって危険が生じないかを慎重に判断します。
そのため、被害者が取消しに反対している場合、特に強い理由がない限り認められないことが多いです。
- 相手方が暴力について反省し、カウンセリングを受けている
- 転勤や転居により、物理的に遠く離れることになった
- 被害者との関係が解消され、接触する必要がなくなった
- 当初の命令の原因となった問題が解決された
相手方から取消しの申立てがあった場合、裁判所から連絡があります。
取消しに同意するかどうかは慎重に判断し、必要に応じて警察や弁護士に相談することをおすすめします。
取り消すために必要な費用
接近禁止命令の取消しには、申立てる側によって必要な費用が異なります。
申立人が取消しを申立てる場合
申立人(被害者)が自ら取消しを申し立てる場合の費用は比較的シンプルです。
被害者側からの取消申立ての場合、収入印紙代として1,000円程度の費用がかかります。
また、裁判所によっては郵便切手が必要な場合もあります。
申立人側が取消しを望む理由としては、和解した、状況が改善した、別の保護手段を講じたなどが挙げられます。
ただし、相手からの圧力や脅迫によって取消しを申し立てるケースもあるため、裁判所は慎重に事情を確認します。
もし圧力を感じているなら、警察や支援団体に相談することが大切です。
取消しを検討する際は、あなたの安全が本当に確保されるのか十分に考慮してください。
相手方が取消しを申立てる場合
相手方(加害者)が取消しを申し立てる場合は、より多くの費用がかかる傾向にあります。
相手方の取消申立ての場合、収入印紙代の他に、証拠書類の準備費用や弁護士費用がかかることが多いです。
取消しを認めてもらうために、カウンセリングを受けた証明や反省文、第三者の証言などを用意する必要があるからです。
弁護士に依頼する場合は、10万円前後の費用がかかることもあります。
相手方からの取消申立てに対して、あなたは意見を述べる権利があります。
審問の際には、取消しに反対する理由を明確に説明できるよう準備しておくと良いでしょう。
| 申立て主体 | 必要な費用 | 認められやすさ |
|---|---|---|
| 申立人(被害者) | 収入印紙代 約1,000円 | 比較的容易 |
| 相手方(加害者) | 収入印紙代+証拠書類準備費用+弁護士費用 | 難しい(特に被害者が反対する場合) |
取消しが認められると、接近禁止命令は即時に効力を失います。
しかし、状況が再び悪化した場合は、新たに接近禁止命令を申し立てることが可能です。
よくある質問
接近禁止命令について読者からよく寄せられる疑問にお答えします。
申立ての条件や期間、流れなど、気になる点を簡潔にまとめました。
- 接近禁止命令は配偶者以外にも申し立てることができますか?
- 接近禁止命令を出すための具体的な条件を教えてください。
- 接近禁止命令の期間はどれくらい続くのですか?
- 元彼氏からのストーカー行為に対して接近禁止命令を申し立てる方法はありますか?
- 接近禁止命令違反があった場合、警察はすぐに逮捕してくれますか?
- 親子間でも接近禁止命令は申立てできますか?
- DV被害を受けている場合の接近禁止命令申し立ての流れを教えてください。
- 接近禁止命令は実際に効果がないという話を聞きましたが本当ですか?
まとめ
接近禁止命令は、あなたの安全を守るための重要な法的手段です。
DV被害やストーカー行為に悩まされている方が、警察に相談し適切な保護を受けるための第一歩となります。
接近禁止命令では、加害者があなたに近づくことや連絡を取ることが禁止され、違反した場合は刑事罰の対象となります。
申立ての手続きは、相談から始まり、裁判所への申立て、審問を経て発令という流れになります。
ただし、命令は万能ではないため、警察との連携や生活環境の見直しなど、複数の安全対策を組み合わせることが大切です。
また、6ヶ月の有効期間後も保護が必要な場合は延長申立てができ、状況が改善されれば取消しも可能です。
あなたの命や安全を守ることが最優先です。一人で抱え込まず、警察や専門機関に相談することから始めましょう。