養育費調停の流れ|手続きと有利に進めるためのポイントを解説

離婚後の養育費について元配偶者と話し合いがまとまらず、困っていませんか?
養育費の問題は子どもの将来に関わる大切な問題ですが、当事者同士では感情的になって解決が難しいケースがよくあります。
そんなとき頼りになるのが「養育費調停」という制度です。
養育費調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して養育費の取り決めを行う手続きのことで、話し合いがこじれたときの強い味方になってくれます。
当記事では養育費調停の基本的な知識から申立て方法、有利に進めるコツまで詳しく解説していきます。
養育費問題でお悩みの方にとって、一歩を踏み出すきっかけとなる情報をわかりやすくまとめました。
お子さんの将来のために、養育費調停を上手に活用する方法をぜひ参考にしてください。
養育費調停とは?
養育費調停とは、離婚後の子どもの養育費について、当事者同士で話し合いがつかない場合に家庭裁判所を通じて解決を図る手続きです。
子どもの成長に必要なお金をどのように負担するか、元配偶者との間で意見が合わないケースは少なくありません。
このような場合、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行うことで、公平な立場から適切な養育費の金額や支払い方法を決めていきます。
調停は裁判とは異なり、お互いの主張を調整しながら合意点を見つけ出す手続きなので、比較的負担が少ないのが特徴です。
- 離婚時の養育費は「離婚調停」で話し合う
- 養育費調停でよく確認されること

離婚時の養育費は「離婚調停」で話し合う
離婚する際に養育費について話し合う場合は、通常「離婚調停」の中で一緒に取り決めていきます。
離婚調停では、離婚自体の可否と共に、親権や面会交流、財産分与、そして子どもの生活に必要な養育費も重要な協議事項として扱われます。
ただし、離婚が既に成立していて養育費だけが未解決の場合や、一度決めた養育費の増額、減額を求める場合は「養育費調停」として単独で申し立てることになります。
また未婚のカップルで子どもがいる場合でも、養育費については同様の調停を申し立てることが可能です。
どちらのケースでも、調停委員が双方の話を聞きながら、子どもの福祉を最優先に考えた解決策を探っていきます。
養育費調停でよく確認されること
養育費調停では、主に以下のような事項について確認、協議が行われます。
- 双方の収入や資産状況
- 子どもの年齢や人数
- 子どもに特別な事情(病気や障害など)があるか
- 子どもの教育費や医療費などの特別な支出
- 支払い方法や期間
- 養育費の増減についての条件
特に、双方の収入状況は養育費の金額を決める重要な要素となるため、給与明細や確定申告書などの提出を求められることがあります。
子どもの生活水準や教育環境についても細かく確認され、両親の離婚後も子どもの生活に大きな変化が生じないよう配慮されます。
養育費は月々いくらという形で決めるのが一般的ですが、子どもの年齢やライフステージに応じて金額を段階的に変更することもあります。
| 確認事項 | 具体的な内容 | 必要な書類例 |
|---|---|---|
| 収入状況 | 月収、年収、賞与、副収入など | 給与明細、確定申告書、源泉徴収票 |
| 子どもの状況 | 年齢、学年、健康状態 | 戸籍謄本、健康保険証 |
| 特別な支出 | 習い事、医療費、教育費 | 領収書、通知書 |
| 資産状況 | 預貯金、不動産、負債 | 預金通帳、ローン契約書 |
調停では、これらの情報をもとに「養育費算定表」という目安を参考にしながら、個別の事情に応じた適切な金額が検討されていきます。
養育費調停のメリットとデメリット
養育費調停には、当事者間の話し合いだけでは解決できない問題を第三者の介入によって解決できるメリットがある一方で、時間や手間がかかるデメリットもあります。
これから養育費調停の申立てを検討している方は、以下のメリットとデメリットをよく理解した上で判断しましょう。
養育費調停のメリット
養育費調停には、当事者だけでは解決が難しい問題を解決に導く様々な利点があります。
まず、調停は裁判所という公的機関での手続きなので、成立した合意には法的な拘束力があるという大きなメリットがあります。
これにより、後から「言った、言わない」のトラブルを防ぎ、合意内容が守られない場合も強制執行の手続きが可能になります。
また、専門知識を持った調停委員が間に入ることで、感情的になりがちな話し合いを冷静に進められます。
さらに、裁判と比べて費用が安く、手続きも比較的シンプルなため、経済的・精神的な負担が少ないのも大きな利点です。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 法的拘束力がある | 調停成立後は裁判所の調停調書として記録され、法的効力を持つ |
| 専門家の介入 | 調停委員や裁判官が公平な立場から適切なアドバイスをしてくれる |
| 強制執行が可能 | 支払いが滞った場合に、財産の差し押さえなどの法的手段を取れる |
| 費用が安い | 裁判と比べて申立費用が安く、弁護士がいなくても手続き可能 |
| 非公開 | 調停内容は公開されないため、プライバシーが守られる |
このように養育費調停は、子どもの将来に関わる重要な取り決めを、安定的かつ公正に行うための効果的な手段となります。
養育費調停のデメリット
養育費調停には様々なメリットがある一方で、いくつかの注意点やデメリットも存在します。
まず、調停は両当事者の合意が必要なため、相手が非協力的だと長期化したり不成立になったりする可能性がある点が挙げられます。
調停委員は強制力を持たないため、一方が頑なに譲らない場合は解決が難しくなることもあります。
また、複数回の出廷が必要となるため、時間的な拘束があり、仕事を休む必要が生じるかもしれません。
さらに、相手と直接対面する可能性もあるため、DV被害などの特別な事情がある場合は事前に裁判所に相談しておくことが重要です。
- 手続きが長期化する可能性がある(平均3〜6ヶ月)
- 調停不成立の場合は審判や訴訟へ移行しなければならない
- 相手が調停に応じないケースもある
- 複数回の出廷による時間的拘束がある
- 相手との対面によるストレスがかかる場合がある
これらのデメリットを踏まえた上で、ご自身の状況に適した解決方法を選ぶことが大切です。
相手との関係性が著しく悪い場合や、DV被害がある場合は、最初から弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、直接対面せずに調停を進められる場合もあり、精神的な負担を軽減できます。
養育費調停の進め方
養育費調停を申し立てる際の具体的な流れと必要な準備について解説します。
調停は複数のステップから成る手続きで、適切に準備を整えることでスムーズに進めることができます。
養育費調停の申立てに必要な書類
養育費調停を申し立てるには、いくつかの書類を準備する必要があります。
必要な書類をすべて揃えた上で申立てをすることで、調停手続きがスムーズに進みます。
主な必要書類は以下の通りです。
- 調停申立書(裁判所で入手可能、またはウェブサイトからダウンロード可)
- 申立人と相手方の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
- 子どもの戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
- 収入を証明する書類(給与明細や確定申告書など)
- 申立人の身分証明書のコピー
特に収入証明書類は、養育費の金額を算定する重要な資料となるため、直近の情報を提出することが望ましいでしょう。
また、申立書には相手方の現住所を正確に記載する必要があるため、事前に確認しておくことが大切です。
これらの書類を準備したら、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
養育費調停にかかる費用
養育費調停にかかる費用は比較的低額で済むのが特徴です。
申立てに必要な費用は主に以下の通りです。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 1,200円 | 申立書に貼付 |
| 連絡用の郵便切手 | 約3,000円程度 | 裁判所によって金額が異なる |
| 戸籍謄本取得費用 | 1通450円程度 | 必要枚数分 |
| 交通費 | 実費 | 調停の出席回数分 |
弁護士に依頼せず自分で手続きを行う場合、調停にかかる基本的な費用は5,000円程度で済みます。
一方、弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が発生します。
弁護士費用の相場は、着手金が10〜30万円程度、成功報酬が解決金額の10〜20%程度が一般的です。
ただし、法律扶助制度を利用すれば、一時的に弁護士費用の立替えを受けられる可能性もあるため、経済的に厳しい場合は法テラスに相談するとよいでしょう。

養育費調停を行うのにかかる期間
養育費調停にかかる期間は、ケースにより異なりますが、一般的には3〜6ヶ月程度です。
調停の所要期間は当事者の協力度合いや主張の隔たりによって大きく変わります。
話し合いがスムーズに進めば早期解決も可能ですが、対立が激しい場合は長期化することもあります。
調停の流れは大まかに以下のようになります。
- 申立て(書類提出)
- 第1回調停期日の指定(約1ヶ月後)
- 第1回調停(申立人と相手方が別々に事情を説明)
- 第2回以降の調停(双方の主張を調整)
- 合意成立または不成立
調停は通常1回につき1〜2時間程度で、2〜3週間おきに開かれることが多いです。
早期解決を望む場合は、必要書類を事前に準備しておくことと、柔軟な姿勢で話し合いに臨むことが重要です。

調停不成立の場合は審判手続きへ移行
養育費調停で合意に至らなかった場合は、審判手続きへと移行します。
審判とは裁判官が法的な判断を下す手続きで、当事者の合意がなくても解決できる点が調停との大きな違いです。
調停が不成立になると、原則として自動的に審判手続きに移行するため、新たに申立てを行う必要はありません。
審判では、裁判官が当事者から提出された資料や調停での経緯をもとに、養育費の金額や支払い方法を決定します。
審判手続きの流れは以下のようになります。
- 審判手続きの開始(調停不成立後、自動的に移行)
- 審問(必要に応じて行われる)
- 裁判官による審判
- 審判書の送達
- 2週間以内に不服申立てがなければ確定
審判に不服がある場合は、審判書の送達を受けてから2週間以内に即時抗告という手続きで不服を申し立てることができます。
審判は調停に比べて拘束力が強く、従わない場合は法的制裁の対象となる可能性があります。
審判手続きは調停よりも形式的で厳格なため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

養育費調停に相手が出席しない場合はどうなる?
養育費調停において、相手方が出席しないケースは少なくありません。
元配偶者との関係が悪化していたり、そもそも連絡が取れない状況だったりすると、調停への出席を拒否されることがあります。
では、相手が調停に出席しない場合、どのような対応が可能なのでしょうか。
相手が調停に出席しない場合、裁判所は最大3回程度の呼出しを行いますが、それでも応じない場合は「調停不成立」となり、審判手続きへ移行します。
このように、相手の非協力的な態度によって調停が不成立になったとしても、養育費の問題を解決する道は閉ざされません。
審判では裁判官が法的な判断を下すため、相手の出席がなくても手続きを進めることができます。
具体的には、以下のような流れで対応が進みます。
- 相手方に調停期日の通知が送られる
- 相手方が欠席した場合、裁判所から再度の呼出し
- 再三の呼出しにも応じない場合、調停不成立の判断
- 自動的に審判手続きへ移行
- 裁判官による審理と判断
なお、調停の呼出状が相手に届いていない場合(住所不明など)は、調停自体が開始できないこともあります。
相手の住所が不明の場合は、住民票の写しの交付請求や弁護士会照会制度を利用して住所を特定する方法もあります。
また、調停が不成立となった後の審判でも相手が非協力的な場合、「欠席判決」に近い形で養育費が決定されることもあります。
このような状況では、自分側の主張や証拠をしっかり準備しておくことが重要です。
収入証明書や子どもの養育状況を示す資料など、養育費算定の基礎となる資料を十分に用意しておきましょう。
相手が非協力的な場合こそ、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
養育費調停を有利に進めるためのコツ
養育費調停では、適切な準備と戦略が結果を大きく左右します。
子どもの将来のために適正な養育費を獲得するため、調停を有利に進めるためのポイントを押さえておきましょう。
養育費算定表で相場金額を把握する
養育費調停に臨む前に、まずは養育費の相場を知っておくことが大切です。
裁判所が実際の判断基準として使用している「養育費算定表」を確認し、自分のケースでの目安額を事前に把握しておきましょう。
養育費算定表は、両親の収入と子どもの年齢・人数から養育費の標準的な金額を導き出すものです。
例えば、父親の年収500万円、母親の年収300万円、子ども1人(小学生)の場合、養育費の目安は月額約5万円程度となります。
この算定表は裁判所のウェブサイトや法律関連のサイトで確認でき、最新版を参照することが重要です。
ただし、算定表はあくまで目安であり、特別な事情(子どもの習い事や医療費など)がある場合は金額が調整されることもあります。
この相場感を持った上で調停に臨むことで、非現実的な要求や不当に低い提案に対して適切に対応できるようになります。

調停委員との良好な関係を築く
養育費調停では、調停委員が双方の意見を聞きながら合意形成を促す重要な役割を担っています。
調停委員からの信頼を得ることで、自分の主張が適切に相手方に伝わりやすくなります。
調停委員との良好な関係を築くためのポイントは以下の通りです。
- 時間厳守で調停に臨む
- 丁寧な言葉遣いと態度を心がける
- 感情的にならず、冷静に事実を説明する
- 質問には簡潔かつ誠実に答える
- 相手を非難するのではなく、子どもの利益を中心に話を進める
調停委員は法律の専門家とは限らず、元教員や地域の名士など様々な背景を持つ方々がなっていることも多いです。
そのため、専門用語を避け、誰にでも分かりやすい言葉で説明することも重要です。
また、自分の主張を押し通そうとするのではなく、柔軟な姿勢で話し合いに臨む姿勢も好印象を与えるでしょう。
必要な証拠書類と陳述書を準備する
養育費調停では、主張を裏付ける証拠が重要な役割を果たします。
自分の主張を客観的に証明できる資料をしっかり準備することで、調停の説得力が大幅に高まります。
特に重要な証拠書類としては以下のものが挙げられます。
| 目的 | 必要な書類 |
|---|---|
| 収入の証明 | 源泉徴収票、給与明細書、確定申告書 |
| 子どもの状況 | 学校の領収書、医療費の領収書、習い事の費用 |
| 生活状況 | 家賃の領収書、ローン返済証明、公共料金の明細 |
| 相手の収入把握 | 以前の給与明細、勤務先情報 |
また、陳述書(自分の主張をまとめた書面)も効果的です。
陳述書では、子どもの養育状況や特別な支出、相手方との関係性などを客観的かつ具体的に記載します。
ただし、相手を必要以上に非難するような内容は避け、事実に基づいた冷静な記述を心がけるべきです。
証拠書類は複数部用意しておき、調停委員や相手方に提示できるよう整理しておくことが重要です。
審判申立ての可能性も視野に入れる
養育費調停に臨む際は、調停不成立の可能性も視野に入れておく必要があります。
調停で合意に至らなかった場合は審判手続きに移行するため、その場合の対応も事前に検討しておくことが重要です。
審判では裁判官が法的な判断を下すことになるため、より客観的な証拠や法的根拠が重視されます。
そのため、調停の段階から証拠書類をしっかり揃えておくと同時に、審判に向けた準備も並行して進めておくとよいでしょう。
例えば、相手の収入を証明する資料が手元にない場合は、調停で裁判所から相手方に収入証明の提出を求めてもらうなどの対応も検討できます。
また、相手方が調停に非協力的な態度を示す場合は、早い段階から審判への移行を見据えて、より詳細な証拠収集を進めることも大切です。
審判に備えて、弁護士のサポートを受けることも効果的な選択肢の一つとなります。
養育費問題に強い弁護士に相談する
養育費調停は自分で行うことも可能ですが、法的な知識や交渉経験がないと不利になることもあります。
特に相手が弁護士を立てている場合や複雑な事情がある場合は、養育費問題に精通した弁護士に相談することで成功率が高まります。
弁護士に依頼するメリットは以下のような点です。
- 法的な知識に基づいた適切なアドバイスが受けられる
- 感情的にならず冷静に交渉を進められる
- 必要な証拠の収集方法を助言してもらえる
- 調停への同席も可能で心強い
- 相手との直接対面を避けられる場合もある
弁護士費用の目安としては、着手金が10〜30万円程度、成功報酬が獲得した養育費の数ヶ月分程度が一般的です。
費用面で心配がある場合は、法テラスの民事法律扶助制度や自治体の無料法律相談なども活用できます。
弁護士選びでは、家事事件や養育費問題の実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。
初回無料相談を実施している事務所も多いので、複数の弁護士に相談して相性の良い弁護士を見つけるとよいでしょう。

一度決められた養育費を増減することは可能か?
養育費は一度決まったら永久に変更できないというわけではありません。
家庭や経済状況の変化に応じて、すでに決まっている養育費の金額を見直すことは可能です。
養育費の増額や減額を希望する場合は、「養育費増額調停」または「養育費減額調停」として、改めて家庭裁判所に申し立てることができます。
ただし、単に「もっと欲しい」「払いたくない」といった理由だけでは認められません。
養育費の変更が認められるためには、当初の取り決め時から「事情の変更」があったことを証明する必要があります。
以下では、増額・減額それぞれが認められやすいケースについて解説します。
養育費の増額を認められやすいケース
養育費の増額が必要になるケースは様々ですが、以下のような事情変更があれば増額が認められる可能性が高まります。
子どもの成長に伴う教育費の増加や、支払い義務者の収入が大幅に増えた場合などは、養育費増額の正当な理由として認められやすいでしょう。
具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 子どもが小学校から中学校、高校へと進学した
- 子どもが病気や障害により特別な医療費や療養費が必要になった
- 養育費を支払う側の収入が大幅に増加した(昇進や転職など)
- 物価の上昇により生活費が著しく増加した
- 当初の養育費額が養育費算定表の金額より著しく低かった
増額調停を申し立てる際は、これらの事情変更を証明する資料を用意することが重要です。
例えば、学校の納付金の領収書や医療費の証明、相手方の昇進や収入増加を示す資料などを準備しましょう。
特に子どもの進学に伴う増額は認められやすいケースですが、進学が決まる前の早めの準備が大切です。
養育費の減額を認められやすいケース
一方、養育費の支払いが経済的に厳しくなったケースでは、減額調停を申し立てることができます。
減額が認められるのは、支払い義務者に明らかな経済状況の悪化があり、それが本人の責任ではない場合が多いです。
以下は減額が認められやすい具体的なケースです。
- 失業や転職により収入が大幅に減少した
- 病気やケガにより働けなくなった(または収入が減った)
- 再婚して新たな子どもが生まれた
- 親の介護などで新たな出費が生じた
- 自然災害などで資産に大きな損害を受けた
減額調停を申し立てる場合も、これらの事情を客観的に証明する資料が必要です。
例えば、退職証明書や雇用保険の受給証明、医師の診断書、新たな家族構成を示す戸籍謄本などを準備します。
ただし、自己都合による退職や、生活水準を下げずに新たな出費を増やしただけのケースでは認められにくい点に注意が必要です。
また、減額調停を申し立てたからといって、すぐに養育費の支払いを停止してよいわけではありません。
調停や審判で正式に決定するまでは、従来通りの養育費を支払い続ける義務があります。
もし支払いが困難な場合は、相手方に事情を説明して一時的な減額について合意を得るか、弁護士に相談するとよいでしょう。
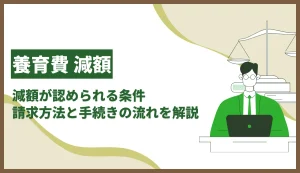
調停で取り決めた養育費が未払いの場合の対処法
養育費の取り決めをしても、実際に支払いが滞るケースは残念ながら少なくありません。
厚生労働省の調査によれば、離婚後に養育費を継続的に受け取っている割合は約3割程度といわれています。
しかし、調停や審判で決まった養育費には法的な効力があるため、未払いの場合にはいくつかの対処方法があります。
調停や審判で決まった養育費の支払いが滞った場合、法的な強制力をもって支払いを求めることができます。
以下では、未払い養育費の回収方法について解説します。
履行勧告や履行命令を行う
養育費の支払いが滞っている場合、まず試すべき方法が「履行勧告」と「履行命令」です。
履行勧告とは、家庭裁判所が支払い義務者に対して養育費を支払うよう促す制度で、比較的簡易な手続きで申し立てができます。
履行勧告は強制力はありませんが、裁判所からの通知が届くことで心理的なプレッシャーとなり、支払いを再開するケースも少なくありません。
履行勧告の申立ては無料で、必要な書類も少ないため、まずはこの方法を試すことをおすすめします。
履行勧告で支払いが再開されない場合は、次のステップとして「履行命令」を申し立てることができます。
履行命令は、裁判所が相手方に対して養育費の支払いを命じるもので、従わない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、過料は国庫に納められるもので、未払い養育費が直接支払われるわけではありません。
履行命令の申立ては印紙代800円程度で行うことができ、申立書は家庭裁判所に用意されています。
強制執行による財産の差し押さえ
履行勧告や履行命令でも効果がない場合は、「強制執行」という方法があります。
強制執行とは、相手の財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押さえて、未払いの養育費に充てる手続きです。
強制執行は裁判所の執行官や執行裁判所を通じて行います。
強制執行を行うためには、「債務名義」と呼ばれる法的な根拠が必要です。
調停調書、審判書、和解調書、公正証書などが債務名義となります。
よくある強制執行の方法としては以下があります。
| 執行方法 | 内容 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 給与差押え | 勤務先に対して給与の一部を差し押さえる | 継続的に回収できるが、相手の勤務先に知られる |
| 預貯金差押え | 銀行口座の預金を差し押さえる | 手続きが比較的簡単だが、一度に全額回収できるとは限らない |
| 不動産差押え | 所有する不動産を差し押さえる | 高額な回収が可能だが、手続きが複雑で時間がかかる |
| 動産差押え | 自動車などの財産を差し押さえる | 執行官が相手方宅に訪問するため心理的効果が高い |
強制執行を行う際は、相手方の財産情報を事前に把握しておくことが重要です。
しかし、相手の資産状況を調べるのは個人では難しいケースも多いため、「財産開示手続」という制度を利用したり、弁護士に依頼したりするとよいでしょう。
強制執行は手続きが複雑で専門知識が必要になるため、可能であれば弁護士に相談することをおすすめします。
また、2021年の民事執行法改正により、相手方の勤務先情報を裁判所が調査する制度も始まり、給与差押えがしやすくなっています。
養育費の未払いに悩んでいる方は、一人で抱え込まず、法テラスや自治体の無料法律相談なども活用して専門家に相談することが解決への近道です。

よくある質問
養育費調停に関して読者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
自分の状況に当てはまる質問があれば、参考にしてみてください。
- 養育費調停で決まった金額が支払われない場合のペナルティはありますか?
- 養育費調停で支払い義務なしと判断されることはありますか?
- 養育費調停の申立て中に養育費を受け取ることは可能ですか?
- 養育費調停を弁護士なしで行うことはできますか?
- 養育費調停が不成立になった後の審判の流れを教えてください。
- 養育費調停に相手が欠席した場合の対処方法を教えてください。
- 離婚後に養育費調停を申し立てる際の時効はありますか?
- 養育費調停を有利に進めるために必要な書類は何ですか?
- 養育費調停と裁判所での審判の違いは何ですか?
- 未婚の場合でも養育費調停を申し立てることはできますか?
まとめ
養育費調停は、子どもの将来のために重要な養育費を適切に決めるための有効な手段です。
当事者同士で話し合いが難しい場合でも、家庭裁判所の調停委員を介して冷静に協議を進められます。
調停は比較的費用が安く手続きも簡便ですが、相手が非協力的だと時間がかかることもあります。
調停が不成立になっても審判手続きへ移行するため、必ず解決への道があることを覚えておきましょう。
養育費の金額は養育費算定表を基準に、両親の収入や子どもの状況などを考慮して決められます。
一度決まった養育費も、状況の変化に応じて増額・減額の調停を申し立てることが可能です。
もし養育費が未払いになった場合は、履行勧告や強制執行などの手段で回収を求めることができます。
子どもの健やかな成長のためには適切な養育費が必要です。
この記事が養育費調停の理解と適切な対応の一助となれば幸いです。












