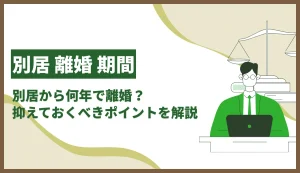離婚費用の相場はいくら?協議・調停・裁判の手続き別に徹底解説

離婚を考え始めると、「一体どのくらいの費用がかかるの?」という不安が頭をよぎりませんか?
離婚にかかる費用は、手続きの方法によって大きく異なり、協議離婚なら数千円程度、調停・裁判になると数十万円から100万円以上かかることもあります。
また手続き費用だけでなく、慰謝料や養育費、財産分与、さらには離婚後の新生活費用なども考慮する必要があります。
この記事では、離婚費用の相場や必要な手続きについて詳しく解説していきます。
離婚費用についての知識を得ることで、将来の不安を軽減し、より良い決断ができるようになります。
あなたの状況に合った情報を見つけるために、ぜひ最後までご覧ください。
離婚方法別の手続き費用
まず、離婚の手続き自体にかかる費用を確認しておきましょう。
協議離婚の場合:基本的に0円
夫婦の話し合いで離婚が成立する協議離婚の場合、手続き自体に費用はかかりません。
ただし、公正証書を作成する場合は手数料が必要で、取り決め金額によって5,000円~23,000円程度かかります。
調停離婚の場合:約2,600円
離婚調停の申立てに必要な費用は約2,600円で、内訳は以下の通りです。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 1,200円 |
| 郵便切手代 | 約1,000円 |
| 戸籍謄本 | 450円 |
裁判離婚の場合:約18,000円
離婚裁判の場合、離婚のみを求めるケースで約18,000円の費用がかかります。
慰謝料や財産分与を併せて請求する場合は、追加で印紙代が必要になります。
協議離婚での慰謝料の相場はいくらなのか?
離婚を考えたとき、まず気になるのは費用面ではないでしょうか。
協議離婚は裁判所を通さず当事者同士で話し合いをする方法で、離婚費用を最小限に抑えられます。
ただし慰謝料や財産分与などの金銭面での取り決めは、しっかりと話し合っておく必要があります。
この項目では、協議離婚での慰謝料の相場について詳しく説明します。

離婚時に発生する慰謝料の一般的な相場
慰謝料とは、離婚の原因を作った側が相手に対して支払う精神的苦痛への賠償金です。
一般的な離婚慰謝料の相場は100万円〜300万円程度と言われています。
しかし実際の金額は、離婚の原因や婚姻期間、相手の収入などによって大きく変わります。
例えば、不倫が原因の場合は300万円前後が相場となりますが、暴力やモラハラなど悪質なケースでは500万円以上になることもあります。
逆に、原因が比較的軽微なものであれば、50万円程度で合意するケースも少なくありません。
| 離婚原因 | 慰謝料相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 不倫・浮気 | 200万円〜300万円 | 証拠の有無や期間によって変動 |
| DV・モラハラ | 300万円〜500万円 | 証拠があると高額になりやすい |
| 性格の不一致 | 0円〜100万円 | 有責配偶者がいない場合は 発生しないことも |
| 借金・浪費 | 100万円〜200万円 | 金額の大きさに比例する傾向 |
協議離婚の場合、慰謝料は当事者同士の合意で決まります。
ただし、あまりにも常識を逸脱した金額を要求すると、後々トラブルになる可能性があるため注意が必要です。
また、慰謝料の支払い方法も重要なポイントです。
一括払いだけでなく、分割払いという選択肢もありますが、その場合は公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書がないと、支払いが途中で滞った場合に強制執行ができませんので、必ず作成しておきましょう。
なお、弁護士に依頼せずに協議離婚を進める場合でも、一度専門家に相談することで適切な金額設定ができます。
初回相談無料の弁護士事務所も多いので、不安な場合は気軽に相談してみてください。
離婚調停にかかる費用の相場
協議離婚で話し合いがまとまらない場合、次の選択肢として考えられるのが「離婚調停」です。
調停では、裁判所の調停委員を介して話し合いを進めていくため、一定の費用が発生します。
ここでは、離婚調停を行う際にかかる費用の相場について詳しく見ていきましょう。
離婚調停にかかる費用は、主に「申立費用」と「弁護士費用」の2つに分けられます。
申立費用は1,200円程度と比較的安価ですが、弁護士に依頼する場合は別途費用が発生します。
弁護士費用の相場は20万円~50万円が一般的で、着手金と成功報酬に分かれるケースが多いです。
ただし、事案の複雑さや争点の数によって費用は大きく変動するため、事前に弁護士と確認しておくことが大切です。
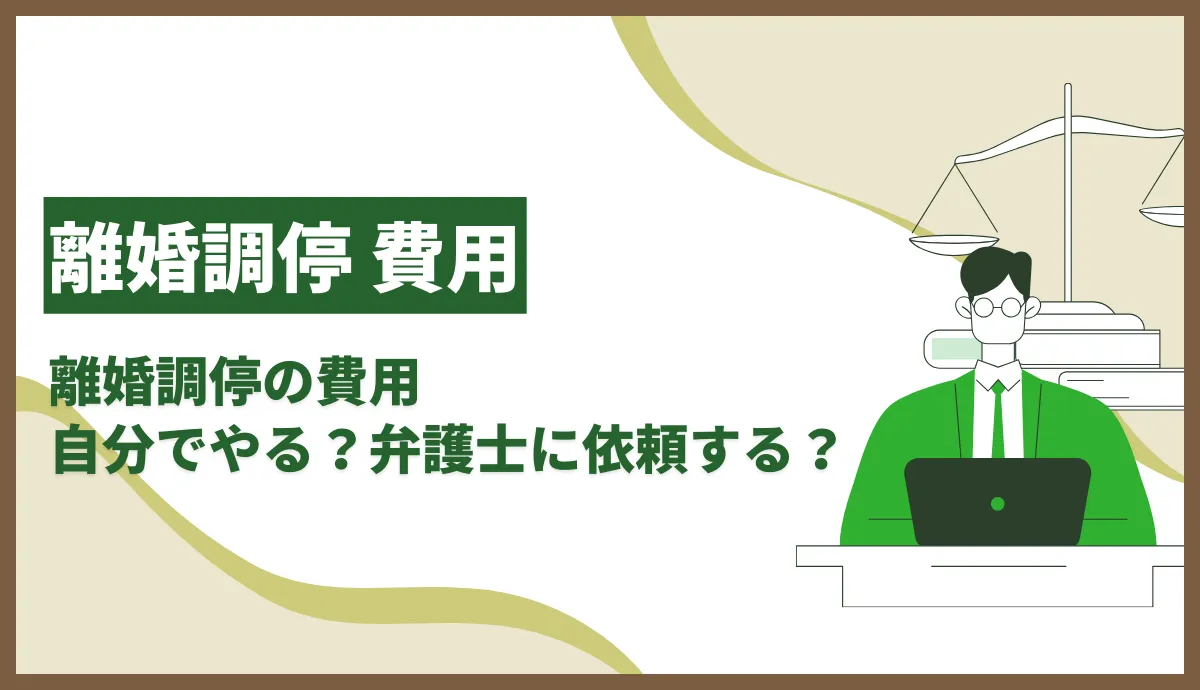
離婚調停に必要な書類と経費(各手続きにかかる費用)
離婚調停を申し立てるには、いくつかの書類と手数料が必要になります。
離婚調停の申立てに必要な費用は、収入印紙代1,200円と切手代約800円程度です。
これに加えて、調停の過程で追加の書類や証拠の準備が必要になる場合があります。
例えば、住民票や戸籍謄本の取得費用として1通300円~450円程度がかかります。
また、財産分与の対象となる不動産の登記簿謄本は1通600円程度です。
| 必要書類・手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 調停申立費用 (収入印紙) | 1,200円 | 裁判所に納付 |
| 郵便切手代 | 約800円 | 裁判所によって金額が異なる |
| 住民票 | 300円/通 | 市区町村役場で取得 |
| 戸籍謄本 | 450円/通 | 本籍地の市区町村役場で取得 |
| 不動産登記簿謄本 | 600円/通 | 法務局で取得 |
| 弁護士相談料 | 5,000円~10,000円/回 | 初回無料の事務所も多い |
弁護士に依頼する場合の費用体系は事務所によって異なりますが、一般的な費用目安は以下の通りです。
着手金は20万円~30万円程度で、これに加えて成功報酬が20万円~30万円程度発生します。
弁護士費用については、次の項目で詳しく解説します。
なお、経済的に余裕がない場合は「法テラス」の民事法律扶助制度を利用することも可能です。
この制度を利用すると、弁護士費用の立て替えや分割払いなどのサポートを受けられます。
離婚調停は平均3~6回程度行われ、解決までに3~6ヶ月かかることが一般的なので、時間的・金銭的なコストを考慮しておきましょう。
調停委員は法律の専門家と一般市民で構成されており、中立的な立場から双方の主張を聞いて解決策を提案してくれます。
離婚調停では感情的になりがちですが、冷静に対応することで早期解決につながり、結果的に費用を抑えることができます。
離婚裁判にかかる費用の相場
協議離婚も調停も不成立となった場合、最終的な選択肢として「離婚裁判」があります。
裁判は法的拘束力のある判決によって離婚問題を解決する手段ですが、それなりの費用と時間がかかります。
離婚裁判にかかる費用は大きく分けて「裁判所に納める費用」と「弁護士費用」の二つです。
裁判所に納める費用としては、訴状に貼る収入印紙代が1万円程度、郵便切手代が2,000円~3,000円程度必要です。
しかし、離婚裁判の本当のコストは弁護士費用であり、これが大部分を占めています。
弁護士費用の相場は着手金が30万円~50万円、成功報酬が30万円~50万円程度で、合計すると60万円~100万円になるケースが多いです。
これに加えて、証人尋問の準備や証拠収集のための費用も別途発生することがあります。
離婚裁判の平均的な期間は1年~1年半程度で、回数は5回~10回ほどと言われています。
この間のやりとりや書類作成などすべてを自分で行うのは非常に困難なため、弁護士への依頼を検討する人が多いのが実情です。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 1万円程度 | 請求内容によって変動 |
| 郵便切手代 | 2,000円~3,000円 | 裁判所により異なる |
| 弁護士着手金 | 30万円~50万円 | 事案の複雑さで変動 |
| 弁護士成功報酬 | 30万円~50万円 | 交渉結果によって変動 |
| 証拠収集費用 | 5万円~20万円 | 必要な証拠により変動 |
弁護士費用が用意できない場合は成功報酬型の契約がおすすめ
離婚裁判を進めたいけれど、高額な弁護士費用が準備できない場合もあるでしょう。
そんなときは「成功報酬型」の契約を結んでいる弁護士事務所を探すという選択肢があります。
成功報酬型の契約では、着手金を低く抑えてもらい、離婚や財産分与で得られた金額に応じて成功報酬を支払う形になります。
例えば、着手金10万円程度で契約し、財産分与や慰謝料で得られた金額の20%~30%を成功報酬として支払うという方式です。
また、公的な制度として「法テラス」を利用する方法もあります。
法テラスの仕組みと活用法
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない方を対象に法律サービスを提供する公的な機関です。
収入や資産が一定基準以下であれば、弁護士費用の立て替えを受けることができます。
立て替えられた費用は、月々数千円程度の分割払いで返済することが可能なので、一度に大きな出費をしなくて済みます。
法テラスを利用するには、まず最寄りの事務所に問い合わせ、収入証明書などの必要書類を提出します。
審査に通れば、法テラスが紹介する弁護士に依頼できるシステムになっています。
法テラスの利用条件は厳格で、単身者の場合は月収20万円以下が目安となっているため、事前に確認しておきましょう。
成功報酬型契約を選ぶ際の注意点
成功報酬型の契約は費用の心配が少ない反面、いくつか注意点もあります。
まず、成功報酬の料率が高めに設定されている場合が多く、最終的な総額は通常の契約より高くなることもあります。
また、弁護士事務所によって料率や条件が大きく異なるため、複数の事務所に相談し、比較検討することをおすすめします。
契約の際には、どのような場合に成功報酬が発生するのか、具体的な計算方法はどうなっているのかなど、詳細を確認しておくことが重要です。
さらに、離婚訴訟が長期化した場合の追加費用についても事前に確認しておきましょう。
弁護士との信頼関係は非常に重要なので、費用面だけでなく相性も考慮して選ぶことをおすすめします。
弁護士選びで迷ったら専門家に相談を
法テラスは経済的に困っている方にとって有用な制度ですが、利用条件が厳しく、弁護士を自由に選べないというデメリットもあります。
また、離婚問題の経験が豊富な弁護士に依頼したい場合は、専門性を重視して弁護士を選ぶことも重要です。
初回相談無料の弁護士事務所も多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
弁護士費用の詳細と相場
弁護士に依頼する場合の費用は、離婚の方法や事案の複雑さによって大きく異なります。
弁護士費用の内訳
| 費用項目 | 協議離婚 | 調停・裁判 |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回無料~1万円/時間 | 初回無料~1万円/時間 |
| 着手金 | 20万円~40万円 | 30万円~60万円 |
| 成功報酬 | 20万円~40万円 | 30万円~60万円 |
| 日当 | 不要 | 1万円~3万円/回 |
成功報酬は依頼内容の成功の程度に応じて決まり、獲得した金額の10%~16%が一般的です。
離婚費用や弁護士選びでお悩みの方は、離婚問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士事務所も多く、費用面の不安についても気軽に相談できます。
離婚慰謝料の相場と慰謝料を増やすためのポイント
離婚時の慰謝料は、相手の不法行為によって被った精神的苦痛に対する賠償金です。
金額は状況によって大きく変わりますが、適切な慰謝料を得るためのポイントを押さえておきましょう。
離婚慰謝料の一般的な相場は100万円~300万円程度で、不倫やDVなどの場合はより高額になる傾向があります。
慰謝料の金額は、主に以下の要素によって決まります。
まず「離婚原因の深刻さ」が重要で、不貞行為やDVなど相手の責任が重いほど高額になります。
また「婚姻期間」も考慮され、長期間の結婚生活であるほど慰謝料が高くなる傾向があります。
さらに「相手の収入」も重要な要素で、高収入であるほど支払い能力が高いとみなされ、慰謝料も増える可能性があります。
| 離婚原因 | 慰謝料相場 | 増額のポイント |
|---|---|---|
| 不倫・浮気 | 200万円~300万円 | 証拠の明確さ、期間の長さ、複数回の不貞 |
| DV・暴力 | 300万円~500万円 | 暴力の程度、頻度、診断書の有無 |
| モラハラ | 100万円~300万円 | 精神的苦痛の証明、第三者の証言 |
| アルコール・ ギャンブル依存 | 100万円~200万円 | 治療拒否の有無、家計への影響度 |
| 性格の不一致 | 0円~100万円 | 相手の明確な有責行為の証明 |
慰謝料を増やすためには、以下のポイントを意識しましょう。
まず「客観的な証拠の収集」が最も重要です。
例えば、不倫の場合はメールやLINEのスクリーンショット、ホテルの領収書などが有効な証拠になります。
DVの場合は診断書や通院記録、警察への相談記録などを残しておくことが大切です。
また「第三者の証言」も有効で、友人や親族、近隣住民などの証言が慰謝料増額の根拠になることもあります。
さらに、弁護士に依頼することで専門的な交渉が可能になり、適切な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
慰謝料の請求は離婚から3年以内に行う必要がありますので、時効には十分注意しましょう。
なお、慰謝料の支払い方法は一括払いが理想ですが、相手の経済状況によっては分割払いになることも少なくありません。
分割払いの場合は必ず公正証書を作成し、支払いが滞った際に強制執行できるようにしておくことが重要です。
具体的な費用計算例
実際のケースで離婚費用がどのくらいになるか、具体例で見てみましょう。
ケース1:協議離婚(弁護士あり)
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 手続き費用 | 0円 | 協議離婚のため |
| 公正証書作成費用 | 17,000円 | 慰謝料300万円の場合 |
| 弁護士着手金 | 300,000円 | – |
| 弁護士成功報酬 | 300,000円 | – |
| 合計 | 617,000円 | 受け取り:慰謝料200万円+財産分与300万円 |
ケース2:調停から裁判まで進行
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調停申立費用 | 2,600円 | 印紙代+切手代+戸籍謄本 |
| 裁判申立費用 | 18,000円 | 離婚+慰謝料請求の場合 |
| 弁護士着手金(調停) | 300,000円 | – |
| 弁護士着手金(裁判追加) | 200,000円 | 調停から裁判移行 |
| 弁護士成功報酬 | 500,000円 | – |
| 弁護士日当 | 50,000円 | 調停5回+裁判3回出廷 |
| 合計 | 1,070,600円 | 受け取り:慰謝料300万円+財産分与500万円 |
ケース3:協議離婚(弁護士なし)
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 手続き費用 | 0円 | 協議離婚のため |
| 公正証書作成費用 | 11,000円 | 慰謝料200万円の場合 |
| 戸籍謄本等 | 900円 | 戸籍謄本450円×2通 |
| 合計 | 11,900円 | 最も費用を抑えられるパターン |
ケース4:法テラス利用(調停)
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調停申立費用 | 2,600円 | 印紙代+切手代+戸籍謄本 |
| 弁護士着手金 (法テラス) | 108,000円 | 立替制度利用 |
| 弁護士成功報酬 (法テラス) | 152,000円 | 立替制度利用 |
| 合計 | 262,600円 | 分割返済可能 |
これらの計算例からわかるように、弁護士に依頼するかどうか、どの手続きまで進むかによって費用は大きく変わります。
ただし、弁護士に依頼することで獲得できる慰謝料や財産分与が増額される可能性もあるため、費用対効果を考慮して判断することが重要です。
慰謝料の金額は離婚原因や証拠の有無によって大きく変わります。
適正な慰謝料を獲得するためには、専門家のサポートが重要です。
離婚問題に詳しい弁護士なら、あなたのケースに応じた適切な慰謝料額の算定や交渉をサポートできます。
離婚前の婚姻費用としていくら請求できる?
別居中でも法的には夫婦関係が継続している期間には、お互いに生活を支え合う義務があります。
この義務に基づいて支払われるのが「婚姻費用」です。
特に収入の少ない配偶者は、別居期間中の生活を維持するために婚姻費用の請求が必要になるケースが多いでしょう。
婚姻費用の相場は、収入の差や子どもの有無によって変わりますが、一般的には収入の多い配偶者の手取り収入の20%~30%程度と言われています。
例えば、夫の手取り収入が月30万円で妻に収入がない場合、婚姻費用は月6万円~9万円程度になることが多いです。
子どもがいる場合は、子ども一人につき月3万円~5万円程度が加算されるのが一般的です。
ただし、これはあくまで目安であり、裁判所では「婚姻費用算定表」という基準表を参考に金額が決められます。
| 夫の年収(手取り) | 妻の年収(手取り) | 子どもなし | 子ども1人 | 子ども2人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 5~7万円/月 | 8~10万円/月 | 10~13万円/月 |
| 400万円 | 0円 | 7~9万円/月 | 10~13万円/月 | 13~16万円/月 |
| 500万円 | 0円 | 9~11万円/月 | 13~16万円/月 | 16~19万円/月 |
| 600万円 | 0円 | 11~14万円/月 | 15~18万円/月 | 19~22万円/月 |
| 400万円 | 200万円 | 3~5万円/月 | 6~8万円/月 | 8~11万円/月 |
婚姻費用の請求方法は主に3つあります。
まずは「話し合い」による解決が最も簡単で、双方が合意すれば書面にまとめるだけで済みます。
話し合いがまとまらない場合は「調停」を申し立て、裁判所の調停委員を介して金額を決めることができます。
調停でも解決しない場合は「審判」に移行し、最終的に裁判官が金額を決定します。
婚姻費用の請求は離婚が成立するまで可能であり、さかのぼって請求することもできますが、通常は別居開始時からが基本となります。
なお、婚姻費用の支払いが滞る場合は、給与の差し押さえなど強制執行の手続きも可能です。
そのためには、調停や審判の結果を記載した調書が必要になるので、必ず正式な手続きを踏んでおくことをおすすめします。
離婚後の財産分与ではいくら受け取れる?
離婚する際の大きな関心事の一つが「財産分与」です。
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で形成した財産を離婚時に分配する制度のことを指します。
基本的な考え方として、婚姻期間中に夫婦で築いた財産は原則として半分ずつ(50%:50%)に分けるのが一般的です。
ただし、実際には様々な要素が考慮され、必ずしも完全に半分になるとは限りません。
財産分与の対象となるのは主に以下のような資産です。
預貯金、不動産(マイホームなど)、自動車、株式・投資信託などの金融商品、退職金(既に受け取ったもの)などが代表的です。
これらの資産を合計し、そこから住宅ローンなどの債務を差し引いた「純資産」が分与の対象となります。
一方、以下のものは原則として財産分与の対象外です。
結婚前から持っていた財産、相続や贈与で個人的に得た財産などは「特有財産」として分与対象にはなりません。
| 分与対象となる財産 | 分与対象外の財産 |
|---|---|
| 夫婦共有の預貯金 | 結婚前からの預貯金 |
| 婚姻中に購入した不動産 | 相続や贈与で取得した不動産 |
| 婚姻中に購入した車や家具 | 個人的に使用する衣類や装飾品 |
| 婚姻中に積み立てた保険 | 一方の親族からの贈与品 |
| 退職金(婚姻期間分) | 慰謝料や損害賠償金 |
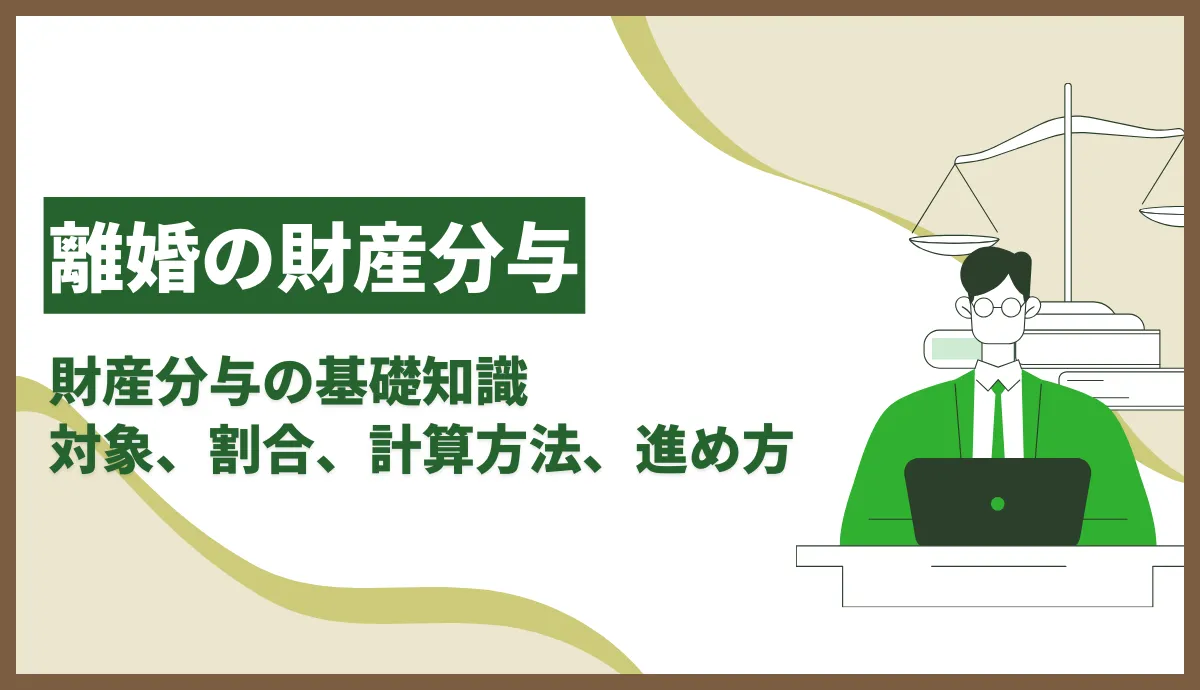
財産分与が半分にならないケース
基本的には50:50が原則ですが、様々な理由で比率が変わることがあります。
たとえば、「婚姻期間の長さ」によって分与率が変わることがあり、短期間の結婚では少なくなる傾向があります。
また「財産形成への貢献度」も重要な要素で、一方が専業主婦(夫)として家事や育児を担当していた場合でも、原則として貢献度は同等と評価されます。
しかし、特殊な事情があればこの比率は変動します。
例えば、一方が浪費や借金を繰り返していた場合や、離婚原因において大きな責任がある場合などは、分与率が下がることがあります。
財産分与の請求権は離婚成立から2年で時効となるため、離婚後すぐに手続きを始める必要があります。
財産分与の具体的な計算方法は以下の通りです。
まず、婚姻中に形成された財産の総額を確定します。
次に、双方の貢献度を考慮して分与の割合を決定します(通常は50:50)。
そして、すでに双方が保有している財産を差し引いて、最終的な支払い額を算出します。
例えば、婚姻中の財産総額が2,000万円で夫が1,800万円、妻が200万円を保有している場合、均等分配なら夫から妻へ800万円の支払いが必要になります。
財産分与は話し合いで決めるのが基本ですが、合意できない場合は調停や裁判で解決することになります。
特に財産が多い場合や複雑な資産がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
財産分与は夫婦で築いた財産を公平に分ける重要な手続きですが、何が対象になるか、どう評価するかなど複雑な問題が多くあります。
特に不動産や株式、退職金などがある場合は、専門知識を持った弁護士のサポートが不可欠です。
適切な財産分与を受けるためにも、まずは専門家に相談することをおすすめします。
離婚後に子どもの養育費として受け取れる金額
子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者が非親権者から受け取る「養育費」は重要な問題です。
養育費は子どもが成人するまでの生活費や教育費をカバーするもので、親としての責任から支払う義務があります。
養育費の相場は、支払う側の年収や子どもの人数・年齢によって変わりますが、一般的には月額3万円~5万円程度が子ども一人あたりの目安となっています。
例えば、父親の年収が500万円で子ども1人(小学生)の場合、月額4万円~5万円程度が標準的な養育費です。
子どもが2人になると、それぞれに対して若干減額されるものの、総額では増加します。
また、子どもの年齢が上がるにつれて教育費などがかさむため、中学生や高校生になると増額されるケースも多いです。
養育費の決め方は「養育費算定表」という裁判所の基準表を参考にするのが一般的です。
| 支払側の年収 | 子ども1人(0~14歳) | 子ども1人(15~19歳) | 子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 2万円~3万円 | 3万円~4万円 | 4万円~6万円 |
| 400万円 | 3万円~4万円 | 4万円~5万円 | 5万円~7万円 |
| 500万円 | 4万円~5万円 | 5万円~6万円 | 7万円~9万円 |
| 600万円 | 5万円~6万円 | 6万円~7万円 | 8万円~10万円 |
| 800万円 | 6万円~8万円 | 8万円~9万円 | 10万円~13万円 |
養育費の取り決め方法には主に「協議」「調停」「審判」の3つがあります。
できるだけ話し合いで決めるのが理想的ですが、合意できない場合は調停や審判で決めることになります。
養育費は通常「子どもが成人するまで」または「大学を卒業するまで」支払われるものです。
金額の変更が必要な場合(収入の増減や子どもの進学など)は、再度話し合いや調停で見直すことができます。
養育費の不払いは深刻な問題で、約6割が滞っているというデータもあります。
不払いを防ぐためには、離婚時に「公正証書」を作成しておくことが重要です。
公正証書があれば、支払いが滞った際に裁判所を通さずに強制執行ができるため、確実に養育費を受け取る助けになります。
なお、2020年の民事執行法改正により、養育費の不払いに対する強制執行がしやすくなりました。
支払いが滞った場合は、法テラスや弁護士に相談して対応することをおすすめします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に決められるのが一般的です。
2019年12月に算定表が改定され、ほぼ全ての年収帯で養育費が月額1~2万円程度増額されました。
算定表は裁判所のウェブサイトで確認できます。
養育費は子どもの将来にかかわる重要な問題です。
適正な金額の設定や、支払いが滞った場合の対処法など、専門的な知識が必要になることも多くあります。
養育費の問題は一人で悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。
離婚後の生活費と引越し費用を準備しておこう
離婚が成立した後、新しい生活をスタートさせるためには一定の資金が必要です。
離婚後に必要な資金は、引越し費用が10万円~30万円、新居の初期費用が家賃の4~6ヶ月分程度、さらに当面の生活費として最低でも3ヶ月分は確保しておくことが理想的です。
新居取得費用の内訳
| 費用項目 | 家賃8万円の場合 | 備考 |
|---|---|---|
| 敷金 | 8万円~16万円 | 家賃の1~2ヶ月分 |
| 礼金 | 8万円~16万円 | 家賃の1~2ヶ月分 |
| 仲介手数料 | 8.8万円 | 家賃の1.1ヶ月分(上限) |
| 前家賃 | 8万円~16万円 | 入居日による |
| 火災保険料 | 1万円~3万円 | 2年分一括 |
| 保証会社利用料 | 4万円~8万円 | 家賃の0.5~1ヶ月分 |
これらを合計すると、家賃8万円の物件でも約38万円~67万円の初期費用が必要になります。
公的融資を活用し、生活に必要費用を借りる
十分な貯蓄がない場合でも、公的な融資制度を利用して離婚後の生活資金を借りることが可能です。
代表的なものとして「生活福祉資金貸付制度」と「母子父子寡婦福祉資金貸付金」があります。
これらは民間の金融機関よりも低金利で借りられるため、資金が足りない場合の有力な選択肢となります。
生活福祉資金貸付の利用方法
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者などを対象にした制度です。
離婚によって生活が困窮する場合にも利用できることがあります。
この制度には「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類があり、目的に応じて利用できます。
例えば、総合支援資金であれば、生活再建に必要な資金として最大で200万円まで借りることが可能です。
借入の申し込みは、各市区町村の社会福祉協議会で行います。
必要書類は住民票や所得証明書、借入の使途がわかる見積書などで、審査には1~2ヶ月程度かかります。
緊急小口資金貸付を申請
急いでお金が必要な場合は「緊急小口資金」の利用も検討できます。
これは生活福祉資金貸付制度の一つで、緊急かつ一時的に生計が困難になった場合に少額の資金を借りられる制度です。
貸付上限額は10万円(特別な事情がある場合は20万円)で、無利子・保証人不要という好条件があります。
申し込みから貸付までの期間も比較的短く、1週間程度で手続きが完了することも多いです。
この制度も社会福祉協議会で申し込みができますので、急な出費に備えて知っておくと良いでしょう。
離婚後の職探し
離婚後の経済的な安定のためには、安定した収入源を確保することが何よりも重要です。
特に専業主婦(夫)だった場合は、新たに就職先を見つける必要があります。
ハローワークでは、ひとり親家庭を対象にした就労支援サービスがあり、専門の相談員が就職活動をサポートしてくれます。
また、「母子家庭等就業・自立支援センター」では、就業相談からスキルアップのための講習会、職業紹介まで一貫したサポートを受けられます。
子育てと仕事の両立が難しい場合は、在宅ワークなどの柔軟な働き方も選択肢の一つです。
クラウドソーシングサイトを利用すれば、自宅にいながら仕事を受注することも可能です。
さらに資格取得を目指す場合は、「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」という制度もあります。
これは看護師や介護福祉士、保育士などの資格取得を目指すひとり親に対して、修学期間中の生活費を支援する制度です。
離婚は大きな環境変化ですが、これを機に新たなキャリアをスタートさせる良い機会と捉えることもできます。
自分の適性や希望に合った仕事を見つけることで、精神的にも経済的にも自立した生活を送ることができるでしょう。
よくある質問
離婚費用について、読者の皆さんからよく寄せられる質問に回答します。
- 離婚費用は男性と女性でいくら違いますか?
- 離婚にかかる弁護士費用の相場を教えてください。
- お金がない状態で離婚手続きを進めることはできますか?
- 離婚の弁護士費用は誰が払うものですか?
- 養育費の相場はいくらくらいですか?
- 弁護士費用を準備できない場合、法テラスを利用できますか?
- モラハラや浮気が原因の離婚で慰謝料はいくら請求できますか?
- 離婚後の引っ越し費用をローンで借りることはできますか?
- 離婚調停から裁判に移行するとどれくらい費用がかかりますか?
まとめ
離婚にかかる費用は、手続きの方法や弁護士への依頼有無によって大きく変わります。
協議離婚なら数千円程度、調停・裁判で弁護士に依頼すると100万円~200万円程度が目安となります。
また、離婚後の新生活には引越し費用や新居の初期費用として50万円~100万円程度、当面の生活費も必要です。
経済的な準備をしっかりと行い、必要に応じて法テラスや公的融資制度も活用しながら、安心して新たなスタートを切りましょう。
離婚は人生の一大イベントです。
費用面での不安を解消し、新しい生活のためにしっかりと準備をすることが大切です。
離婚に関するお金の問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。
離婚費用や手続きについて不安をお持ちの方は、まず専門家に相談してみませんか?
経験豊富な弁護士があなたの状況に応じて、最適な解決策をご提案いたします。
初回相談無料の事務所も多数ございますので、お気軽にご相談ください。